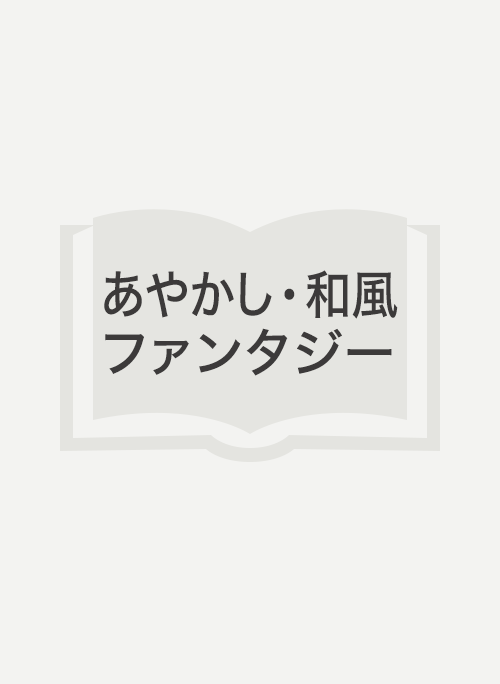千冬がお風呂に入っている間、書斎では灯璃と蓮司が書類の処理をしていた。
花嫁が見つかったと分家に連絡するためだ。
両親だけでなく一族中にすぐさま伝達するのがしきたりで、作業をしている文机には灯璃の婚約者である鬼川薫子宛ての書もある。
年内の内に花嫁が見つからなければ薫子と結婚をする予定だったが千冬が見つかった今、その必要はなくなった。
薫子は女性の鬼の中で灯璃の母親に次いで霊力が高い。
そのため妻に相応しいのは薫子だと誰もが納得し婚約というかたちになった。
政略結婚を決められても薫子は嫌がるそぶりなど見せず、むしろ明らかな好意を灯璃に向けていた。
しかし灯璃は生まれてから一度も恋という感情を憶えたことはない。
千冬と出逢うまでは。
そんな千冬のことがよほど気になるのか珍しく身が入らず手が動いていない。
「灯璃さま、どうかされましたか?」
「……お前は千冬が嶺木家について話すと思うか?」
「難しいでしょうね。嶺木家は帝都に名を轟かせる名家ですが娘でありながらあのお姿は何か事情を抱えているのかもしれません」
「蓮司、嶺木家の内情を探れ」
「かしこまりました」
(千冬が風呂から出る前に済ませてしまおう)
灯璃は息を吐いて作業に集中しなおした。
千冬が入浴を済ませると詩乃に居間とはまた別の一室へ案内される。
鬼城家は実家とは比べものにならないほどの広さなので一人で歩くと迷子になりそうだ。
左右を見て道順を覚えながらついていく。
先を歩いていた詩乃が足を止める。
「失礼致します」と声をかけ襖を開けると畳一面にいくつもの反物が置かれていた。
淡い色から鮮やかな色、撫子柄、牡丹柄といった様々な反物が所狭しと並べてあり目を奪われる。
部屋に入ると灯璃と白髪を綺麗に結った女性が座っていた。
使用人用のお仕着せ服を来ていないので一体誰なのだろうと入口付近で戸惑う。
もし客人だったら、こんな風呂上がりの長襦袢姿はまずいのではと、とっさに詩乃の後ろに隠れる。
「千冬さま?どうかされましたか?」
「お、お客さまですよね?わたしこんな格好で……」
恥ずかしさでだんだんと声がしぼんでいく。
先ほどまで着ていたお仕着せ服を着るわけにはいかないし、かといって代わりの着物もない。
「そんなに恥ずかしがることはない。この者は呉服店の店主で事情は説明してある」
(呉服店の方……。もしかしてわたしの着物がないからこんな遅い時間に呼んでくださったのかしら)
見るからに上等な反物が並んでいて、自分のためにと自意識過剰な考えはしたくないがそれしか思い浮かばなかった。
千冬が隠れていた詩乃の背中から顔を出すと「こちらへおいで」と灯璃が自分が座っている隣の座布団を示す。
勧められるまま灯璃の隣に座ると女性は恭しく頭を垂れる。
「私、狐森呉服店の狐森麻子と申します。花嫁さまがお召しになる着物を仕立てたいと鬼城さまからご連絡をいただきまして参りました所存でございます」
「こんな夜遅くにありがとうございます」
おそらく店の営業は終了しているはずなのにわざわざ出向いてくれたなんて申し訳なくなる。
しかし就寝時は良くても明日に着る着物がないと困るのでありがたさもある。
お仕着せ服でも構わないのだが、灯璃たちにとってはそうもいかないのだろう。
「いつも鬼城さまにはご贔屓にしていただいておりますから。それに私にとっても花嫁さまが見つかられたことは喜ばしいです。本日は当店選りすぐりの反物を御用意しました」
「好きな物をいくつでも選ぶといい。千冬はどれが好みだ?」
「で、でもこのような上等な反物をいただくのは……」
値段を聞くのが気が引けるほど高価だというのが分かるし継母達でもここまでの着物は着ていなかった。
その上、物欲なんてないしこんなにも素敵な着物は地味な自分には到底似合うはずがない。
「遠慮はするな。私からの贈り物だ、受け取ってほしい」
「もしかして、この中にお気に召す反物はありませんでしたか?それでしたら店からまた別の物を……」
「い、いえ!決してそのようなわけでは……!どの反物もとても素敵ですっ」
「まぁ、お褒めいただいて嬉しいですわ。千冬さまは特にどちらがお好みですか?」
「ええと……」
何だか策にはまってしまったような気がして助けを求めるように灯璃を見る。
「千冬には淡い色が似合うと思うぞ」
まだ灯璃からの贈り物を受け取る決心ができておらず戸惑う千冬に一つの反物を手に取り差し出す。
「素敵……」
春らしさを感じさせる白と桃色の生地に、桜模様が可憐ですぐに目を奪われた。
ここまで勧めてくれているのにこれ以上断るのはそれこそ失礼なような気がして。
「本当にいただいてよろしいのですか?」
「ああ。もちろんだ」
「……ありがとうございます、鬼城さま」
初めての贈り物、それも男性から。
まるで心に暖かな風が吹いたようだった。
そうして千冬は桜柄の反物の他にいくつかの反物を灯璃と共に選んだ。
選んだ反物は早急に仕立てると呉服店の店主である麻子は、はりきっていた。
何でも妖狐の一族である狐森家は昔、先代である灯璃の父親に助けてもらった恩があるらしい。
そして仕立てている間に着る着物を数着、頂いてしまった。
麻子の娘が昔、少しだけ着ていた着物らしく新品と変わらない良い状態だ。
千冬と麻子の娘は背丈もほとんど同じで、着ても何の問題はない。
お下がりで申し訳ないが、もしよかったらと譲ってくれたのだ。
「それでは、仕立て終わりましたらご連絡致します」
「ああ。頼んだ」
「よろしくお願い致します」
玄関で灯璃、詩乃と共に見送りをする。
麻子は反物が入った箱を抱えながら門の前に止めてある自動車に乗り込んで去っていった。
「千冬さま、本日はもうお疲れでしょう。お部屋にご案内しますね」
「ありがとうございます」
たくさん詰め込まれた長い一日が終わろうとしていて身体が重い。
そして食事と入浴を済ませたことに加え、日頃から睡眠もろくにとれていないせいか余計に眠かった。
眠気を払うように一度、頭を横に数回振る。
「千冬、顔色が悪いぞ。部屋まで歩けるか?」
「は、はい」
少しだけ、ぼうっとしてしまったがこれ以上心配させないように笑顔をつくった。
すると灯璃はこちらに腕を伸ばし、千冬を抱き上げた。
「きゃっ」
突然の浮遊感に一瞬何が起きたのか分からなかった。
すぐ近くにある端正な顔立ち、胸元に触れた耳から聞こえる心臓の音、細くも男らしい鍛えられた腕。
身体に伝わる体温、音、目線が千冬の鼓動を急激に高まらせる。
抱き上げられているのだと理解したときには眠気など吹き飛んでしまった。
「あ、の……。わたし一人で歩けます」
この状態で抵抗するのは危険だと察した千冬は顔を真っ赤にさせ必死に訴える。
「いや、倒れたら危ない。このまま部屋まで連れて行く」
千冬の頼みも虚しく散っていき、灯璃はしっかりした足取りで廊下を歩いていく。
下から見る灯璃の真剣な表情にきっと降ろしてくれないと諦めた千冬は何も言わずに身を任せた。
しばらく歩き、案内されたのは屋敷の奥にある部屋だった。
詩乃が襖を開けると、そこは一人で使うには広すぎるほどの部屋で、鏡台や箪笥、文机などが置かれている。
実家の部屋はところどころ破れている障子でへたれた布団以外、何もなかった。
整えられた空間に瞳を瞬かせ驚いているところでやっと灯璃が降ろしてくれた。
「布団は押し入れに入っております。何か他にも必要なものがありましたらお申しつけください。こちらお着物です」
「ありがとうございます」
着物が入った箱を受け取ると詩乃は「おやすみなさいませ」と言って一礼するとその場をあとにした。
鬼城家で働く使用人たちは、自宅からの通いで夜には千冬と灯璃の二人きりになる。
急遽千冬が住むことが決まって準備をするのに忙しかっただろうに皆、疲れた顔を一切見せなかった。
それなのにここまでしっかりと用意してくれて感謝しかない。
「鬼城さま、本日はありがとうございました」
もし、あのとき灯璃が乗った自動車が近くを通らなかったら自分はここにはいない。
感謝を伝えるために頭を下げるがこのお辞儀だけでは足りないくらいだ。
「私の方こそ千冬に礼を言いたいくらいだ」
「えっ?なぜですか?」
(わたし、何かしたかしら?)
自分の行動を振り返ってみるが何も思い当たる節がない。
不思議に思っていると腰に手を回され、優しく抱き寄せられた。
彼の胸元に顔をうずめる形になり灯璃の匂いに包まれる。
トクンと鼓動が跳ねて、身体中に熱が集まった。
「言っただろう?私は千冬に会えて幸せなのだと。こんな感情は初めてだ」
心の底から溢れ出すような声色。
存在意義が認められるのが泣きそうになるくらい嬉しい。
灯璃の胸元に顔をうずめているおかげでまた泣き顔が見られなくて済むと少しだけ安堵した。
ただ一つだけ胸に引っかかるものがあって。
(こんなにも想いを伝えてくださるのにわたしは……)
普通の恋仲ならこのような場合、女性も背に腕を回すだろう。
ただ千冬は恋という感情を知らない。
灯璃は自分を助けてくれた恩人。
想いに応えたいのに、はっきりしないままただじっと腕の中にいていいのか。
僅かにできた隙間から灯璃をそっと見上げる。
「でもわたしは恋というものを知りませんし、おそらく今も感じていないのです。それでもここにいて良いのですか?」
きっと悲しませてしまう。
恋に気づくまで一方的に想いを伝えられても何も返せないし、気づくどころかもしかしたらずっと……。
「ああ。私は千冬に傍にいてほしいんだ。嫌か?」
千冬は首を横に振る。
灯璃はくすりと小さく笑って千冬の白く細い手を優しく握った。
包み込むほど大きな手から熱が伝わる。
「私たちは出逢ったばかり。ゆっくりお互いを知っていけば良い」
気持ちが焦っていたのかもしれないと灯璃の言葉に気づかされる。
きっとどんなに進むのが遅くても彼なら先に行かず待ってくれる。
「はい」
千冬がこくりと頷くと灯璃はそっと手を離す。
「おやすみ、千冬」
「おやすみなさいませ」
灯璃が背を向け廊下を歩き出したのを見届けて千冬も部屋に入った。
箱から着物と帯を取り出して箪笥にしまう。
やはり何度見ても美しくてとてもお下がりには見えない。
ここに仕立て終わった着物も入るのだと思うと気持ちが弾んだ。
収納が終わると押し入れを開けて布団を取り出す。
触り心地も良く厚みもあって上等な布団だとわかる。
(よく眠れそう)
敷き終わりさっそく入ってみると身体を覆う温かさに再度、睡魔が襲う。
(起きたら朝食作りやお掃除をして皆さんの、鬼城さまのお役に立たないと)
できることといったらそれくらいだが命を救ってくれたのだから恩人のために働くのは当然だ。
そう考えていると次第に瞼が開かなくなって千冬は眠りについた。
花嫁が見つかったと分家に連絡するためだ。
両親だけでなく一族中にすぐさま伝達するのがしきたりで、作業をしている文机には灯璃の婚約者である鬼川薫子宛ての書もある。
年内の内に花嫁が見つからなければ薫子と結婚をする予定だったが千冬が見つかった今、その必要はなくなった。
薫子は女性の鬼の中で灯璃の母親に次いで霊力が高い。
そのため妻に相応しいのは薫子だと誰もが納得し婚約というかたちになった。
政略結婚を決められても薫子は嫌がるそぶりなど見せず、むしろ明らかな好意を灯璃に向けていた。
しかし灯璃は生まれてから一度も恋という感情を憶えたことはない。
千冬と出逢うまでは。
そんな千冬のことがよほど気になるのか珍しく身が入らず手が動いていない。
「灯璃さま、どうかされましたか?」
「……お前は千冬が嶺木家について話すと思うか?」
「難しいでしょうね。嶺木家は帝都に名を轟かせる名家ですが娘でありながらあのお姿は何か事情を抱えているのかもしれません」
「蓮司、嶺木家の内情を探れ」
「かしこまりました」
(千冬が風呂から出る前に済ませてしまおう)
灯璃は息を吐いて作業に集中しなおした。
千冬が入浴を済ませると詩乃に居間とはまた別の一室へ案内される。
鬼城家は実家とは比べものにならないほどの広さなので一人で歩くと迷子になりそうだ。
左右を見て道順を覚えながらついていく。
先を歩いていた詩乃が足を止める。
「失礼致します」と声をかけ襖を開けると畳一面にいくつもの反物が置かれていた。
淡い色から鮮やかな色、撫子柄、牡丹柄といった様々な反物が所狭しと並べてあり目を奪われる。
部屋に入ると灯璃と白髪を綺麗に結った女性が座っていた。
使用人用のお仕着せ服を来ていないので一体誰なのだろうと入口付近で戸惑う。
もし客人だったら、こんな風呂上がりの長襦袢姿はまずいのではと、とっさに詩乃の後ろに隠れる。
「千冬さま?どうかされましたか?」
「お、お客さまですよね?わたしこんな格好で……」
恥ずかしさでだんだんと声がしぼんでいく。
先ほどまで着ていたお仕着せ服を着るわけにはいかないし、かといって代わりの着物もない。
「そんなに恥ずかしがることはない。この者は呉服店の店主で事情は説明してある」
(呉服店の方……。もしかしてわたしの着物がないからこんな遅い時間に呼んでくださったのかしら)
見るからに上等な反物が並んでいて、自分のためにと自意識過剰な考えはしたくないがそれしか思い浮かばなかった。
千冬が隠れていた詩乃の背中から顔を出すと「こちらへおいで」と灯璃が自分が座っている隣の座布団を示す。
勧められるまま灯璃の隣に座ると女性は恭しく頭を垂れる。
「私、狐森呉服店の狐森麻子と申します。花嫁さまがお召しになる着物を仕立てたいと鬼城さまからご連絡をいただきまして参りました所存でございます」
「こんな夜遅くにありがとうございます」
おそらく店の営業は終了しているはずなのにわざわざ出向いてくれたなんて申し訳なくなる。
しかし就寝時は良くても明日に着る着物がないと困るのでありがたさもある。
お仕着せ服でも構わないのだが、灯璃たちにとってはそうもいかないのだろう。
「いつも鬼城さまにはご贔屓にしていただいておりますから。それに私にとっても花嫁さまが見つかられたことは喜ばしいです。本日は当店選りすぐりの反物を御用意しました」
「好きな物をいくつでも選ぶといい。千冬はどれが好みだ?」
「で、でもこのような上等な反物をいただくのは……」
値段を聞くのが気が引けるほど高価だというのが分かるし継母達でもここまでの着物は着ていなかった。
その上、物欲なんてないしこんなにも素敵な着物は地味な自分には到底似合うはずがない。
「遠慮はするな。私からの贈り物だ、受け取ってほしい」
「もしかして、この中にお気に召す反物はありませんでしたか?それでしたら店からまた別の物を……」
「い、いえ!決してそのようなわけでは……!どの反物もとても素敵ですっ」
「まぁ、お褒めいただいて嬉しいですわ。千冬さまは特にどちらがお好みですか?」
「ええと……」
何だか策にはまってしまったような気がして助けを求めるように灯璃を見る。
「千冬には淡い色が似合うと思うぞ」
まだ灯璃からの贈り物を受け取る決心ができておらず戸惑う千冬に一つの反物を手に取り差し出す。
「素敵……」
春らしさを感じさせる白と桃色の生地に、桜模様が可憐ですぐに目を奪われた。
ここまで勧めてくれているのにこれ以上断るのはそれこそ失礼なような気がして。
「本当にいただいてよろしいのですか?」
「ああ。もちろんだ」
「……ありがとうございます、鬼城さま」
初めての贈り物、それも男性から。
まるで心に暖かな風が吹いたようだった。
そうして千冬は桜柄の反物の他にいくつかの反物を灯璃と共に選んだ。
選んだ反物は早急に仕立てると呉服店の店主である麻子は、はりきっていた。
何でも妖狐の一族である狐森家は昔、先代である灯璃の父親に助けてもらった恩があるらしい。
そして仕立てている間に着る着物を数着、頂いてしまった。
麻子の娘が昔、少しだけ着ていた着物らしく新品と変わらない良い状態だ。
千冬と麻子の娘は背丈もほとんど同じで、着ても何の問題はない。
お下がりで申し訳ないが、もしよかったらと譲ってくれたのだ。
「それでは、仕立て終わりましたらご連絡致します」
「ああ。頼んだ」
「よろしくお願い致します」
玄関で灯璃、詩乃と共に見送りをする。
麻子は反物が入った箱を抱えながら門の前に止めてある自動車に乗り込んで去っていった。
「千冬さま、本日はもうお疲れでしょう。お部屋にご案内しますね」
「ありがとうございます」
たくさん詰め込まれた長い一日が終わろうとしていて身体が重い。
そして食事と入浴を済ませたことに加え、日頃から睡眠もろくにとれていないせいか余計に眠かった。
眠気を払うように一度、頭を横に数回振る。
「千冬、顔色が悪いぞ。部屋まで歩けるか?」
「は、はい」
少しだけ、ぼうっとしてしまったがこれ以上心配させないように笑顔をつくった。
すると灯璃はこちらに腕を伸ばし、千冬を抱き上げた。
「きゃっ」
突然の浮遊感に一瞬何が起きたのか分からなかった。
すぐ近くにある端正な顔立ち、胸元に触れた耳から聞こえる心臓の音、細くも男らしい鍛えられた腕。
身体に伝わる体温、音、目線が千冬の鼓動を急激に高まらせる。
抱き上げられているのだと理解したときには眠気など吹き飛んでしまった。
「あ、の……。わたし一人で歩けます」
この状態で抵抗するのは危険だと察した千冬は顔を真っ赤にさせ必死に訴える。
「いや、倒れたら危ない。このまま部屋まで連れて行く」
千冬の頼みも虚しく散っていき、灯璃はしっかりした足取りで廊下を歩いていく。
下から見る灯璃の真剣な表情にきっと降ろしてくれないと諦めた千冬は何も言わずに身を任せた。
しばらく歩き、案内されたのは屋敷の奥にある部屋だった。
詩乃が襖を開けると、そこは一人で使うには広すぎるほどの部屋で、鏡台や箪笥、文机などが置かれている。
実家の部屋はところどころ破れている障子でへたれた布団以外、何もなかった。
整えられた空間に瞳を瞬かせ驚いているところでやっと灯璃が降ろしてくれた。
「布団は押し入れに入っております。何か他にも必要なものがありましたらお申しつけください。こちらお着物です」
「ありがとうございます」
着物が入った箱を受け取ると詩乃は「おやすみなさいませ」と言って一礼するとその場をあとにした。
鬼城家で働く使用人たちは、自宅からの通いで夜には千冬と灯璃の二人きりになる。
急遽千冬が住むことが決まって準備をするのに忙しかっただろうに皆、疲れた顔を一切見せなかった。
それなのにここまでしっかりと用意してくれて感謝しかない。
「鬼城さま、本日はありがとうございました」
もし、あのとき灯璃が乗った自動車が近くを通らなかったら自分はここにはいない。
感謝を伝えるために頭を下げるがこのお辞儀だけでは足りないくらいだ。
「私の方こそ千冬に礼を言いたいくらいだ」
「えっ?なぜですか?」
(わたし、何かしたかしら?)
自分の行動を振り返ってみるが何も思い当たる節がない。
不思議に思っていると腰に手を回され、優しく抱き寄せられた。
彼の胸元に顔をうずめる形になり灯璃の匂いに包まれる。
トクンと鼓動が跳ねて、身体中に熱が集まった。
「言っただろう?私は千冬に会えて幸せなのだと。こんな感情は初めてだ」
心の底から溢れ出すような声色。
存在意義が認められるのが泣きそうになるくらい嬉しい。
灯璃の胸元に顔をうずめているおかげでまた泣き顔が見られなくて済むと少しだけ安堵した。
ただ一つだけ胸に引っかかるものがあって。
(こんなにも想いを伝えてくださるのにわたしは……)
普通の恋仲ならこのような場合、女性も背に腕を回すだろう。
ただ千冬は恋という感情を知らない。
灯璃は自分を助けてくれた恩人。
想いに応えたいのに、はっきりしないままただじっと腕の中にいていいのか。
僅かにできた隙間から灯璃をそっと見上げる。
「でもわたしは恋というものを知りませんし、おそらく今も感じていないのです。それでもここにいて良いのですか?」
きっと悲しませてしまう。
恋に気づくまで一方的に想いを伝えられても何も返せないし、気づくどころかもしかしたらずっと……。
「ああ。私は千冬に傍にいてほしいんだ。嫌か?」
千冬は首を横に振る。
灯璃はくすりと小さく笑って千冬の白く細い手を優しく握った。
包み込むほど大きな手から熱が伝わる。
「私たちは出逢ったばかり。ゆっくりお互いを知っていけば良い」
気持ちが焦っていたのかもしれないと灯璃の言葉に気づかされる。
きっとどんなに進むのが遅くても彼なら先に行かず待ってくれる。
「はい」
千冬がこくりと頷くと灯璃はそっと手を離す。
「おやすみ、千冬」
「おやすみなさいませ」
灯璃が背を向け廊下を歩き出したのを見届けて千冬も部屋に入った。
箱から着物と帯を取り出して箪笥にしまう。
やはり何度見ても美しくてとてもお下がりには見えない。
ここに仕立て終わった着物も入るのだと思うと気持ちが弾んだ。
収納が終わると押し入れを開けて布団を取り出す。
触り心地も良く厚みもあって上等な布団だとわかる。
(よく眠れそう)
敷き終わりさっそく入ってみると身体を覆う温かさに再度、睡魔が襲う。
(起きたら朝食作りやお掃除をして皆さんの、鬼城さまのお役に立たないと)
できることといったらそれくらいだが命を救ってくれたのだから恩人のために働くのは当然だ。
そう考えていると次第に瞼が開かなくなって千冬は眠りについた。