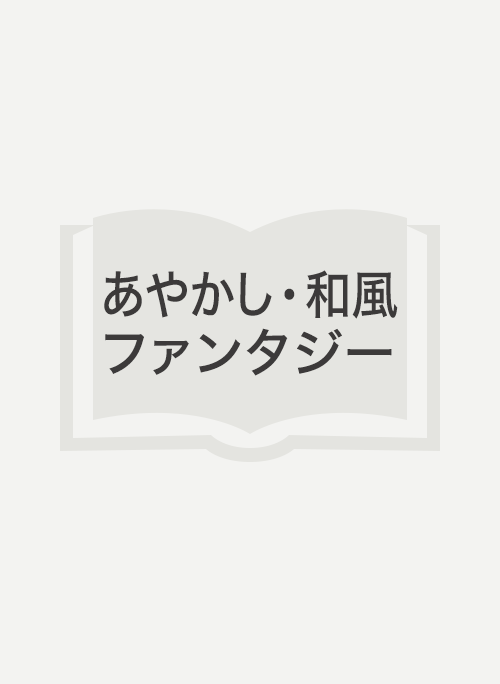板張りの長い廊下を歩いていると千冬の手を引きながら案内していた灯璃が襖の前で足を止めた。
「ここが居間だ」
襖が開けられるとそこは居間とは思えないほど広い部屋で入っていくと爽やかな藺草の香りがした。
「失礼致します」
そこに使用人が千冬と灯璃の分であるお茶が入った湯呑みを盆に載せ、運んできた。
灯璃に勧められ席に座ると座卓にそっと湯呑みが置かれた。
いつも自分がお茶を淹れる立場だったので丁寧なもてなしをされると変な感じがする。
「間もなくお食事の準備が出来ますので少々お待ちください」
「ありがとうございます……」
千冬が頭を下げると使用人は「失礼致します」と言って居間から出て行った。
灯璃と二人きりになり急に訪れた静けさにどうしたら良いか分からず視線を彷徨わせていると。
「身体が冷えただろう。茶を飲むといい」
「は、はい。いただきます」
湯呑みを持ち一口飲む。
(美味しい……)
運ばれたときにも感じていたがまず香りが良い。
鼻腔をくすぐるような香りで口に含んだときの茶葉の旨味が広がり余韻も残る。
嶺木家でも上等な茶葉を使用していたがそれをはるかに上回る高級な茶葉だと確信できる。
冷えていた身体も芯から温まり、頬の血色が戻ってきた千冬を見て灯璃も安堵していた。
緊張がほぐれてきたのかふと千冬の頭の中に疑問が浮かぶ。
座卓をはさんだ目の前の席に座っている灯璃にそっと視線を移し口を開いた。
「あの、ここで働かれている皆さんは鬼なのですか?」
お世話係の詩乃をはじめとした使用人達の瞳は灯璃と同じ赤い瞳だった。
しかもあやかしは皆、容姿端麗だという噂もある。
まさにその通りで美しいその姿に釘付けになってしまうほどだ。
詩乃も老女とはいえ、一挙一動に気品があり惚れ惚れする。
千冬の質問に灯璃は頷いた。
「ここで働く使用人は鬼城家の分家の者だ。蓮司と同じで代々、本家に仕えている」
灯璃によると鬼の一族だけではなく、どのあやかしにも本家に選ばれし分家の者が仕えるというしきたりがあるそう。
使命が与えられることは名誉で誇られるものらしい。
そしてあやかしが人間の花嫁を迎えるとよりその家は繁栄すると言われており、花嫁のお世話をすることが使用人にとって何よりの喜びだという。
(知らないことばかり。外に出られなかったとはいえ恥ずかしいわ)
もしかしたら帝都に出ればその話自体有名だったかもしれない。
小学校止まりな千冬は名家の令嬢らしい教養すらない。
無知な自分が少し恥ずかしくなる。
本当にこんな自分が鬼帝の花嫁になって良いのかと今になって思案に暮れてしまう。
千冬の顔に影が落ちたのを灯璃は見逃さなかった。
「どうした?」
「あ……。えっと……」
一瞬言うのを躊躇ったが隠してもきっと見透かされる。
それに黙っているのも親切にしてくれた灯璃に失礼だ。
千冬は膝の上に置いてある手のひらをぎゅっと握りしめ想いを伝えた。
「わたし、あやかしの方達のこと何も知らなくて……。それに教養もないのです。こんな自分が鬼城さまの花嫁で本当に良いのか考えてしまって……」
自分より花嫁に相応しいのは、たいそう美しく要領や器量が良い妹の依鈴と誰もが言うだろう。
何の知識も作法も身に付いていないのに、瞳で花嫁を選ぶあやかしの本能のまま、この立場にいて良いのか。
隣にいることでお荷物になることが目に見えている。
「私の花嫁は千冬しか考えられない」
凛とした声と眼差しが千冬を射抜く。
強い決意をも感じさせる瞳になぜか視線を逸らせなかった。
「その想いが決して揺るがることはない。花嫁修業もゆっくりしていけば良い。私が傍にいるから不安になる必要はない」
鬼の花嫁に選ばれて気持ちが焦っていたのかもしれない。
世の中をほとんど知らない、教養もなく貧しい庶民の娘のような自分に重要な役目を担っていけるのか。
弱く、すぐ不安になる自分が嫌いで。
もし迷惑をかけたら。
もしまた孤独になったら。
父にも裏切られ誰かを信じることが不可能だと思っていた。
けれど灯璃の優しい声が、瞳が、まるで閉ざされた心に触れてくれたようだった。
「弱音ばかり言って申し訳ありません……」
「謝ることない。悲しかったら悲しいと、つらかったらつらいと伝えてほしい」
今まではどんなに虐げられても感情を押し殺してきた。
紫紺色の瞳をもつ運命だと何度も言い聞かせ毎日を過ごしてきた。
だが今は違う。
声にして伝えられる。
助けを求めるのは悪いことではない。
高い壁が立ちはだかって歩みを止めても灯璃が一緒に前へ進んでくれる。
出逢ったばかりで千冬にとってはまだ距離が感じるが少しでも委ねて良いのかもしれない。
「はい。ありがとうございます……」
こうして想いを伝えられる人がいるのは何て幸せなのだろう。
微笑み合いながら温かな玉露のお茶を飲む。
その時間が千冬が抱えていた心労を癒してくれた。
「ここが居間だ」
襖が開けられるとそこは居間とは思えないほど広い部屋で入っていくと爽やかな藺草の香りがした。
「失礼致します」
そこに使用人が千冬と灯璃の分であるお茶が入った湯呑みを盆に載せ、運んできた。
灯璃に勧められ席に座ると座卓にそっと湯呑みが置かれた。
いつも自分がお茶を淹れる立場だったので丁寧なもてなしをされると変な感じがする。
「間もなくお食事の準備が出来ますので少々お待ちください」
「ありがとうございます……」
千冬が頭を下げると使用人は「失礼致します」と言って居間から出て行った。
灯璃と二人きりになり急に訪れた静けさにどうしたら良いか分からず視線を彷徨わせていると。
「身体が冷えただろう。茶を飲むといい」
「は、はい。いただきます」
湯呑みを持ち一口飲む。
(美味しい……)
運ばれたときにも感じていたがまず香りが良い。
鼻腔をくすぐるような香りで口に含んだときの茶葉の旨味が広がり余韻も残る。
嶺木家でも上等な茶葉を使用していたがそれをはるかに上回る高級な茶葉だと確信できる。
冷えていた身体も芯から温まり、頬の血色が戻ってきた千冬を見て灯璃も安堵していた。
緊張がほぐれてきたのかふと千冬の頭の中に疑問が浮かぶ。
座卓をはさんだ目の前の席に座っている灯璃にそっと視線を移し口を開いた。
「あの、ここで働かれている皆さんは鬼なのですか?」
お世話係の詩乃をはじめとした使用人達の瞳は灯璃と同じ赤い瞳だった。
しかもあやかしは皆、容姿端麗だという噂もある。
まさにその通りで美しいその姿に釘付けになってしまうほどだ。
詩乃も老女とはいえ、一挙一動に気品があり惚れ惚れする。
千冬の質問に灯璃は頷いた。
「ここで働く使用人は鬼城家の分家の者だ。蓮司と同じで代々、本家に仕えている」
灯璃によると鬼の一族だけではなく、どのあやかしにも本家に選ばれし分家の者が仕えるというしきたりがあるそう。
使命が与えられることは名誉で誇られるものらしい。
そしてあやかしが人間の花嫁を迎えるとよりその家は繁栄すると言われており、花嫁のお世話をすることが使用人にとって何よりの喜びだという。
(知らないことばかり。外に出られなかったとはいえ恥ずかしいわ)
もしかしたら帝都に出ればその話自体有名だったかもしれない。
小学校止まりな千冬は名家の令嬢らしい教養すらない。
無知な自分が少し恥ずかしくなる。
本当にこんな自分が鬼帝の花嫁になって良いのかと今になって思案に暮れてしまう。
千冬の顔に影が落ちたのを灯璃は見逃さなかった。
「どうした?」
「あ……。えっと……」
一瞬言うのを躊躇ったが隠してもきっと見透かされる。
それに黙っているのも親切にしてくれた灯璃に失礼だ。
千冬は膝の上に置いてある手のひらをぎゅっと握りしめ想いを伝えた。
「わたし、あやかしの方達のこと何も知らなくて……。それに教養もないのです。こんな自分が鬼城さまの花嫁で本当に良いのか考えてしまって……」
自分より花嫁に相応しいのは、たいそう美しく要領や器量が良い妹の依鈴と誰もが言うだろう。
何の知識も作法も身に付いていないのに、瞳で花嫁を選ぶあやかしの本能のまま、この立場にいて良いのか。
隣にいることでお荷物になることが目に見えている。
「私の花嫁は千冬しか考えられない」
凛とした声と眼差しが千冬を射抜く。
強い決意をも感じさせる瞳になぜか視線を逸らせなかった。
「その想いが決して揺るがることはない。花嫁修業もゆっくりしていけば良い。私が傍にいるから不安になる必要はない」
鬼の花嫁に選ばれて気持ちが焦っていたのかもしれない。
世の中をほとんど知らない、教養もなく貧しい庶民の娘のような自分に重要な役目を担っていけるのか。
弱く、すぐ不安になる自分が嫌いで。
もし迷惑をかけたら。
もしまた孤独になったら。
父にも裏切られ誰かを信じることが不可能だと思っていた。
けれど灯璃の優しい声が、瞳が、まるで閉ざされた心に触れてくれたようだった。
「弱音ばかり言って申し訳ありません……」
「謝ることない。悲しかったら悲しいと、つらかったらつらいと伝えてほしい」
今まではどんなに虐げられても感情を押し殺してきた。
紫紺色の瞳をもつ運命だと何度も言い聞かせ毎日を過ごしてきた。
だが今は違う。
声にして伝えられる。
助けを求めるのは悪いことではない。
高い壁が立ちはだかって歩みを止めても灯璃が一緒に前へ進んでくれる。
出逢ったばかりで千冬にとってはまだ距離が感じるが少しでも委ねて良いのかもしれない。
「はい。ありがとうございます……」
こうして想いを伝えられる人がいるのは何て幸せなのだろう。
微笑み合いながら温かな玉露のお茶を飲む。
その時間が千冬が抱えていた心労を癒してくれた。