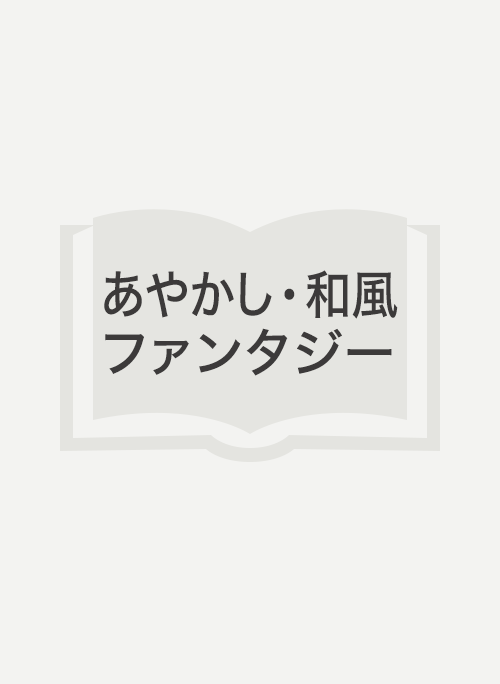「千冬にこの者を紹介しておきたい」
灯璃の視線を追うと赤い瞳の男性と目が合う。
ほっそりとした体格に、灯璃と比べると少し低い背がどこか幼い印象を与える。
「私、灯璃さまの秘書兼、妖特務部隊の副隊長の鬼崎蓮司と申します」
「は、はじめまして。嶺木千冬と申します」
恭しく洗練された美しい所作に千冬は見入ってしまうがふと我に返り、慌ててお辞儀をした。
先ほどの千冬と灯璃のやり取りを見ていた蓮司も次第に落ち着きを取り戻したようでお互いに自己紹介を交わした。
「蓮司も私と同じ、鬼の一族だ」
灯璃の言葉にすぐ腑に落ちた。
血のような赤い瞳を見ておそらく鬼なのだろうと勘づいてはいたから。
継母達も見た目は美しい人だったが二人はそれ以上。
適当に結っていた髪に古びた着物姿が今になって恥ずかしくなってくる。
来客があっても人前に出ることを禁じられていた千冬は当然ながらめかしこんだことはない。
灯璃と共に暮らす以上、恥ずかしくないくらい身なりは整えておきたいが、死ぬつもりだったのでお金なんて持ち合わせていない。
元々、新しい着物など買うお金など千冬はないのだが少しでもあれば何かしら買えたかもしれない。
(住む場所が決まったのはいいけれど、わたし何も持っていないわ……)
みすぼらしい格好から感じる羞恥心に加えこれから先どうしたら良いのか思い悩んでしまう。
「どうした?」
俯いて黙っている千冬を見て灯璃は気遣うように声をかけた。
「あ……えっと……」
(もし正直に言ったらまるで物をねだっているように聞こえるかもしれない……)
そんな風に聞こえてしまったらとてつもなく失礼だ。
どうしても遠慮してしまって話すことを躊躇してしまう。
「千冬の気持ちを聞かせてくれないか。その方が私も嬉しい」
背中に触れられる手からまるで一歩踏み出していいのだと教えられているよう。
両手を胸の前でぎゅっと握り、千冬は悩んでいることを言葉にした。
「こんな貧相な格好が恥ずかしくなってしまって……。わたし、新しい物を買うお金すら持っていないのです」
言葉にすると想像以上に悲しくなる。
着ているお下がりのお仕着せ服は貰った時点でかなり古かった。
頻繁に繋ぎ目が破れて自分で繕うことも多々あり、薄い生地と僅かな隙間から入る冷気で余計、精神的に追いつめる。
視界が涙で滲んだとき、握りしめていた手の上に灯璃が自らの手を重ねた。
「不安になることはない。新しい着物も他に必要な物も全てこちらで揃える」
「それは出来ません……!働き口を見つけたら、そのお給料で買いますから」
住む場所まで用意してくれたのに花嫁だからといってそこまでしてもらうわけにはいかない。
慌てて首を横に振ると灯璃が急に真剣な表情になる。
「駄目だ。千冬の願いでもそれは叶えられない」
「え……!どうしてですか?」
共に暮らすといいという提案に最大限、甘えたつもりだがなぜ町で働くことが駄目になるのか千冬には分からない。
「人間の中には花嫁を狙った誘拐事件などを企てる者もいる。そのため、あやかし達は花嫁を働きに出すこと、ましてや一人で外出させることさえ許さない」
「そんな……」
住む場所以外はせめて自立した生活を送ろうと思ったのだが、それも儚く消えてゆく。
肩を落とした千冬を見て灯璃は何か考えを巡らせた後、口を開いた。
「気に病む必要はない。千冬には頼みたいことがあるからな」
その言葉に千冬は俯かせていた顔を上げ、今日一番の笑顔を浮かべた。
「本当ですか……!わたし、何でもします」
嬉しそうにしている千冬に気づかれぬよう蓮司は灯璃にひっそりと耳打ちをする。
「灯璃さま、まさか本当に花嫁さまを働かせるおつもりですか?」
「そんなわけないだろう。私にも考えがある」
「は、はぁ……」
余裕のある表情と言葉に蓮司はそれ以上問いかける勇気は出なかった。
その考えとやらは教えてはくれなかったが、幼い頃から彼の傍にいて見ていればきっと大丈夫なのだろうと蓮司は思う。
灯璃はそっと千冬に視線を移す。
頼られることがよほど嬉しいのか目を細めて微笑む千冬を見て愛おしさが増していく。
そんなにも想われていることに灯璃と出逢って間もない千冬はまだ気づかない。
吹いた風が三人の間を通り抜けたとき、灯璃は細く小さな千冬の手をとった。
「そろそろ車へ戻って屋敷へ帰ろう」
「は、はい」
近くに止めてあった自動車まで行くと待機していた運転手がドアを開ける。
高価な自動車は多額の資産を所有している者しか買えない。
帝都で知らぬ人はいない有名な嶺木家にも当然あるが勿論、千冬は乗ったことがない。
全員が乗り込むのを確認すると「出せ」と灯璃が運転手に伝える。
自動車が走り出し橋を越えるとかくりよ國に入っていく。
(緊張してきたわ……)
千冬はそんな思いを隠すように窓から外を見る。
鬼城家はかくりよ國の一番奥にあるそうで自動車だと十分程度で到着するようだ。
遅い時間だからか、ほとんどの屋敷の明かりは点いていない。
しかし少ない明かりでもどの構えている屋敷も広大であることがわかる。
純和風の屋敷以外にも洋館のような建物もあって、そのモダンさは人間が住む帝都とさほど変わりはない。
改めてあやかし達の凄さをひしひしと感じていると辺り一帯の雰囲気が変わった。
白い外壁がどこまでも長く続き、その上から僅かに瓦屋根が見える。
「もしかしてここが……」
「ああ。鬼城家だ」
鬼帝の住まいはきっと、とてつもない広さなのだろうと思っていたがそんな想像をはるかに超えている。
門の前に自動車が着くと、内側からゆっくりと開けられ敷地内に進んでいくと玄関の近くに並んで立っている人の姿が見えた。
自動車が止まると先に降りた灯璃に手を差し伸べられる。
一切の無駄なく動く紳士な姿に胸が高鳴りながらそっとその手をとった。
千冬が降りると玄関の前に立っていた数名の中から一人の老女が前に出てくる。
「お帰りなさいませ、灯璃さま。そちらのご令嬢が花嫁さまでいらっしゃいますか?」
穏やかに微笑みながら視線を千冬に向ける。
「ああ。念話で伝えた通り今日からこの屋敷で暮らすことになった」
念話とは離れていても脳内から語りかけることで会話ができ、あやかしなら誰でも使える術。
どうやら鬼城家まで向かう道中で屋敷の使用人達に伝えていたようだ。
「初めまして、嶺木千冬と申します。よろしくお願いします」
千冬が丁寧に頭を下げると使用人達が慌てふためく。
「は、花嫁さま!どうかお顔をお上げくださいませ!この屋敷の女主人となる御方が我々などに頭など下げなくてよろしいのですよ……!」
「そんな女主人だなんて……。お世話になる身なのですから当然のことです」
それに頭を下げることが身体に染みついてしまって今すぐ変えるのは難しいだろう。
堂々としていることなど控えめな自分の性格からして出来ないと諦めている。
「奥ゆかしいところも千冬の魅力だ。無理して変える必要はない」
謙遜している千冬の背に灯璃の手が優しく触れる。
継母達から虐げられていても何も言い返すことが出来ず、ずっと黙っていた。
黙っていることでまた苛つかせるのも事実で「こんな自分なんて大嫌い」とも思った。
しかしあまり好きではなかったこの性格も灯璃は肯定してくれる。
それが何より嬉しくて初めて自分を好きになれたかもしれない。
「鬼城さま……。ありがとうございます」
礼を言うと灯璃は微笑みながら頷いてくれた。
二人のやり取りを見ていた使用人達も理解してくれたようで「今後、花嫁さまが我々に頭を下げられても動揺しないようにしよう」とその場で決めていた。
「この者は使用人頭の詩乃。千冬のお世話係も兼任することになった。何か困ったことがあれば詩乃に言ってくれ。勿論、他の使用人でも構わない」
「改めまして、詩乃と申します。千冬さま、よろしくお願い致します」
「よろしくお願いします……!」
まさか自分にお世話係がつくとは思ってもおらず驚き、申し訳なくなったがあまり自分の意見を言いすぎても良くないと思い、何も言わずにそのまま受け入れた。
「では詩乃を中心に使用人達は食事と風呂の準備、あと千冬の着物を仕立てたい。反物をいくつか用意してくれ」
「かしこまりました」
灯璃からの指示を受け使用人達は動き始める。
決してうろたえることはなく、素早く冷静な行動。
無駄のない動きに思わず圧倒されていると灯璃が口を開く。
「私達も中へ入ろう」
「は、はい」
今日からこの広大な屋敷で暮らすかと思うとかなり緊張してしまう。
ゆっくりと深呼吸をして気持ちを落ち着かせる。
庭にある草花のにおいも鼻に抜けて少しだけほぐれた。
千冬は灯璃に手を引かれながら鬼城家の屋敷の中へ足を踏み入れた。
灯璃の視線を追うと赤い瞳の男性と目が合う。
ほっそりとした体格に、灯璃と比べると少し低い背がどこか幼い印象を与える。
「私、灯璃さまの秘書兼、妖特務部隊の副隊長の鬼崎蓮司と申します」
「は、はじめまして。嶺木千冬と申します」
恭しく洗練された美しい所作に千冬は見入ってしまうがふと我に返り、慌ててお辞儀をした。
先ほどの千冬と灯璃のやり取りを見ていた蓮司も次第に落ち着きを取り戻したようでお互いに自己紹介を交わした。
「蓮司も私と同じ、鬼の一族だ」
灯璃の言葉にすぐ腑に落ちた。
血のような赤い瞳を見ておそらく鬼なのだろうと勘づいてはいたから。
継母達も見た目は美しい人だったが二人はそれ以上。
適当に結っていた髪に古びた着物姿が今になって恥ずかしくなってくる。
来客があっても人前に出ることを禁じられていた千冬は当然ながらめかしこんだことはない。
灯璃と共に暮らす以上、恥ずかしくないくらい身なりは整えておきたいが、死ぬつもりだったのでお金なんて持ち合わせていない。
元々、新しい着物など買うお金など千冬はないのだが少しでもあれば何かしら買えたかもしれない。
(住む場所が決まったのはいいけれど、わたし何も持っていないわ……)
みすぼらしい格好から感じる羞恥心に加えこれから先どうしたら良いのか思い悩んでしまう。
「どうした?」
俯いて黙っている千冬を見て灯璃は気遣うように声をかけた。
「あ……えっと……」
(もし正直に言ったらまるで物をねだっているように聞こえるかもしれない……)
そんな風に聞こえてしまったらとてつもなく失礼だ。
どうしても遠慮してしまって話すことを躊躇してしまう。
「千冬の気持ちを聞かせてくれないか。その方が私も嬉しい」
背中に触れられる手からまるで一歩踏み出していいのだと教えられているよう。
両手を胸の前でぎゅっと握り、千冬は悩んでいることを言葉にした。
「こんな貧相な格好が恥ずかしくなってしまって……。わたし、新しい物を買うお金すら持っていないのです」
言葉にすると想像以上に悲しくなる。
着ているお下がりのお仕着せ服は貰った時点でかなり古かった。
頻繁に繋ぎ目が破れて自分で繕うことも多々あり、薄い生地と僅かな隙間から入る冷気で余計、精神的に追いつめる。
視界が涙で滲んだとき、握りしめていた手の上に灯璃が自らの手を重ねた。
「不安になることはない。新しい着物も他に必要な物も全てこちらで揃える」
「それは出来ません……!働き口を見つけたら、そのお給料で買いますから」
住む場所まで用意してくれたのに花嫁だからといってそこまでしてもらうわけにはいかない。
慌てて首を横に振ると灯璃が急に真剣な表情になる。
「駄目だ。千冬の願いでもそれは叶えられない」
「え……!どうしてですか?」
共に暮らすといいという提案に最大限、甘えたつもりだがなぜ町で働くことが駄目になるのか千冬には分からない。
「人間の中には花嫁を狙った誘拐事件などを企てる者もいる。そのため、あやかし達は花嫁を働きに出すこと、ましてや一人で外出させることさえ許さない」
「そんな……」
住む場所以外はせめて自立した生活を送ろうと思ったのだが、それも儚く消えてゆく。
肩を落とした千冬を見て灯璃は何か考えを巡らせた後、口を開いた。
「気に病む必要はない。千冬には頼みたいことがあるからな」
その言葉に千冬は俯かせていた顔を上げ、今日一番の笑顔を浮かべた。
「本当ですか……!わたし、何でもします」
嬉しそうにしている千冬に気づかれぬよう蓮司は灯璃にひっそりと耳打ちをする。
「灯璃さま、まさか本当に花嫁さまを働かせるおつもりですか?」
「そんなわけないだろう。私にも考えがある」
「は、はぁ……」
余裕のある表情と言葉に蓮司はそれ以上問いかける勇気は出なかった。
その考えとやらは教えてはくれなかったが、幼い頃から彼の傍にいて見ていればきっと大丈夫なのだろうと蓮司は思う。
灯璃はそっと千冬に視線を移す。
頼られることがよほど嬉しいのか目を細めて微笑む千冬を見て愛おしさが増していく。
そんなにも想われていることに灯璃と出逢って間もない千冬はまだ気づかない。
吹いた風が三人の間を通り抜けたとき、灯璃は細く小さな千冬の手をとった。
「そろそろ車へ戻って屋敷へ帰ろう」
「は、はい」
近くに止めてあった自動車まで行くと待機していた運転手がドアを開ける。
高価な自動車は多額の資産を所有している者しか買えない。
帝都で知らぬ人はいない有名な嶺木家にも当然あるが勿論、千冬は乗ったことがない。
全員が乗り込むのを確認すると「出せ」と灯璃が運転手に伝える。
自動車が走り出し橋を越えるとかくりよ國に入っていく。
(緊張してきたわ……)
千冬はそんな思いを隠すように窓から外を見る。
鬼城家はかくりよ國の一番奥にあるそうで自動車だと十分程度で到着するようだ。
遅い時間だからか、ほとんどの屋敷の明かりは点いていない。
しかし少ない明かりでもどの構えている屋敷も広大であることがわかる。
純和風の屋敷以外にも洋館のような建物もあって、そのモダンさは人間が住む帝都とさほど変わりはない。
改めてあやかし達の凄さをひしひしと感じていると辺り一帯の雰囲気が変わった。
白い外壁がどこまでも長く続き、その上から僅かに瓦屋根が見える。
「もしかしてここが……」
「ああ。鬼城家だ」
鬼帝の住まいはきっと、とてつもない広さなのだろうと思っていたがそんな想像をはるかに超えている。
門の前に自動車が着くと、内側からゆっくりと開けられ敷地内に進んでいくと玄関の近くに並んで立っている人の姿が見えた。
自動車が止まると先に降りた灯璃に手を差し伸べられる。
一切の無駄なく動く紳士な姿に胸が高鳴りながらそっとその手をとった。
千冬が降りると玄関の前に立っていた数名の中から一人の老女が前に出てくる。
「お帰りなさいませ、灯璃さま。そちらのご令嬢が花嫁さまでいらっしゃいますか?」
穏やかに微笑みながら視線を千冬に向ける。
「ああ。念話で伝えた通り今日からこの屋敷で暮らすことになった」
念話とは離れていても脳内から語りかけることで会話ができ、あやかしなら誰でも使える術。
どうやら鬼城家まで向かう道中で屋敷の使用人達に伝えていたようだ。
「初めまして、嶺木千冬と申します。よろしくお願いします」
千冬が丁寧に頭を下げると使用人達が慌てふためく。
「は、花嫁さま!どうかお顔をお上げくださいませ!この屋敷の女主人となる御方が我々などに頭など下げなくてよろしいのですよ……!」
「そんな女主人だなんて……。お世話になる身なのですから当然のことです」
それに頭を下げることが身体に染みついてしまって今すぐ変えるのは難しいだろう。
堂々としていることなど控えめな自分の性格からして出来ないと諦めている。
「奥ゆかしいところも千冬の魅力だ。無理して変える必要はない」
謙遜している千冬の背に灯璃の手が優しく触れる。
継母達から虐げられていても何も言い返すことが出来ず、ずっと黙っていた。
黙っていることでまた苛つかせるのも事実で「こんな自分なんて大嫌い」とも思った。
しかしあまり好きではなかったこの性格も灯璃は肯定してくれる。
それが何より嬉しくて初めて自分を好きになれたかもしれない。
「鬼城さま……。ありがとうございます」
礼を言うと灯璃は微笑みながら頷いてくれた。
二人のやり取りを見ていた使用人達も理解してくれたようで「今後、花嫁さまが我々に頭を下げられても動揺しないようにしよう」とその場で決めていた。
「この者は使用人頭の詩乃。千冬のお世話係も兼任することになった。何か困ったことがあれば詩乃に言ってくれ。勿論、他の使用人でも構わない」
「改めまして、詩乃と申します。千冬さま、よろしくお願い致します」
「よろしくお願いします……!」
まさか自分にお世話係がつくとは思ってもおらず驚き、申し訳なくなったがあまり自分の意見を言いすぎても良くないと思い、何も言わずにそのまま受け入れた。
「では詩乃を中心に使用人達は食事と風呂の準備、あと千冬の着物を仕立てたい。反物をいくつか用意してくれ」
「かしこまりました」
灯璃からの指示を受け使用人達は動き始める。
決してうろたえることはなく、素早く冷静な行動。
無駄のない動きに思わず圧倒されていると灯璃が口を開く。
「私達も中へ入ろう」
「は、はい」
今日からこの広大な屋敷で暮らすかと思うとかなり緊張してしまう。
ゆっくりと深呼吸をして気持ちを落ち着かせる。
庭にある草花のにおいも鼻に抜けて少しだけほぐれた。
千冬は灯璃に手を引かれながら鬼城家の屋敷の中へ足を踏み入れた。