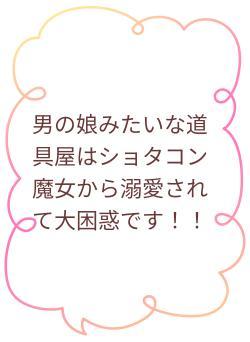過ぎ去る夏の日を惜しむような蝉しぐれを聞きながら、私はこの日記を書いていた。
これは二人だけの大切な思い出。
○△□○△□○△□
高校二年生の夏休みも残り数日というある日、私たちはK県の海岸にやって来た。
お盆が過ぎたこともあって、観光客もまばら。海にはサーフィンを楽しむ人達しかいない。
私と真緒は、砂浜の見渡せる防波堤に腰を下ろしていた。
お尻の下には小さなビニールシート。ふたり並んで海を眺める。
私は荷物の中からお弁当を取り出した。
「今日はね、真緒と一緒に食べたくてお弁当を作ってきたんだ」
大量の保冷剤に包まれた弁当箱は、大きく無骨なアルミ製だった。
男手一つで育ててくれた父と、スポーツ好きな弟達の中で育ったため、家には女性物の可愛らしい弁当箱などは無い。
私は顔を真っ赤にしながら、大きな体をこれでもかと縮めた。
「こんなお弁当箱しか無くて恥ずかしいけど……」
真緒は目を輝かせて弁当箱を覗き込んでいる。
「若葉のお手製ってだけで、ボクは死ぬほど嬉しいよ! 大きいお弁当箱だって、二人で食べれば丁度いい大きさだよ!」
屈託のない笑顔みせる真緒。
薄水色のワンピースに赤い麦わら帽子。
真緒は私よりも遥かに小柄。愛らしいロングヘアーが似合う少女だが、何事にも積極果敢で少し短気。まるで少年のような女の子だった。
真緒は待ちきれないとばかりに、弁当箱の蓋を開ける。
私たちの眼前に美しい花畑が広がった。
鈍色の器の中に、色とりどりのおかずたち。
お手製のBLTサンドに唐揚げと卵焼き。
色鮮やかなカットフルーツに、ポテトサラダとミニトマト。他にもたくさん詰まっている。
自分で言うのも恥ずかしいが、今回のお弁当は自信作だった。
高校で寮に入るまで、毎日家族の食事を作っていたから料理は得意だ。ただ、家族の好みから、どうしてもガッツリ系に寄ってしまうのはやや難ありだが……。
「真緒。手を拭いてから食べようね」
私は待ちきれない様子の真緒に、ウエットティッシュを差し出す。
真緒は慌ただしく手を拭くと「いただきます!」とお弁当に手を伸ばした。
美味しそうに頬張る真緒の姿が見られて私も嬉しくなった。
――思い切って二人で来て良かった。
真緒を見ながら、私は今回の小旅行が決まった時の事を思い出していた。
○△□○△□○△□
「ねぇ若葉、二人だけで何処か旅行に行かない?」
私は真緒の急な提案にドキリとした。
――えっ、行きたいけど。そんな急に言われても心の準備が出来ていないというか。
「夏と言えばやっぱり海かな! ボクねぇ、高校生になってから一度も行って無いんだよね!」
真緒はどんどん話を進めて行く。
私と真緒は普段は高校で寮生活をしているけど、夏休み期間中はお互いの実家に帰省していて、なかなか会えていなかった。
だから夏休みの宿題をやるという理由でも真緒と会えるのが楽しみだった。
私達の通う高校は中から大学まである百本桜学園。校内や寮は、夏休み中でも帰省しない生徒や、部活動に参加する生徒のために、常時開放されていた。
ここの図書館でも数人の生徒たちが勉強をしている。
「真緒。少し声を小さくして。図書委員に怒られちゃうよ……」
視線を向けると、貸し出しコーナーに座っている図書委員の女生徒と目があった。
彼女は一瞬だけこちらに視線を送ると、すぐに読みかけの書籍に目を落とした。
「あれ特進コースの三栗谷さんだよね。確かハーフの?」
真緒が耳元でささやく。
「ひゃっ!」
真緒の吐息が耳にかかり私は変な声を上げてしまった。
館内の生徒たちが一斉に私のことを見る。
私はうつむきながら、頬が焼けるように熱くなるのを感じ、あまりの恥ずかしさに薄っすらと目に涙が浮かんで来た。
生憎と大柄な私の体では、真緒の影に隠れることも出来ない。
私は机に突っ伏して出来るだけ目立たないようにした。
「ゴメン若葉。ビックリさせちゃった?」
「真緒ぉ、寿命が縮むから勘弁してぇ……」
私の心臓はまだ落ち着きを取り戻していない。
――いや、真緒とこうやって一緒に入られて嬉しいんだけどね。
「それで、海なんだけどね……」
真緒の顔がさらに寄ってくる。
あぁ、もう勘弁して!
○△□○△□○△□
打ち寄せる波が、砂浜に書いた二人の名前を消していく。
真緒が貝殻を拾って海に投げた。
海風に煽られて貝殻は波打ち際に落ちてしまった。
「あれー……、あんまり飛ばないなあ。若葉が投げたらどこまで飛ぶ?」
真緒に促されて私も同じぐらいの貝殻を投げた。桜色の貝殻はきれいな放物線を描いて波間に着水する。
「おぉ。さすが若葉だね! 若葉もスポーツやったら良いのに?」
真緒は麦わら帽子を持ち上げながら私の顔を見上げた。
――スポーツやれば?
生まれてから何度と無く聞かされた言葉だ。男ばかりのスポーツ一家に生まれ、体格にも恵まれた。
だが、如何せん性格が向いていなかった。他人と競い合うことが苦手で、スポーツには良い思い出が全く無かった……。
「ゴメン。この話題は苦手だったね」
少しうつむいていた私の心を察したのか、真緒が申し訳無さそうな顔をした。
「でも楽しかったね! 夜だったら花火をしたかったのになぁ!」
日が傾き始めた浜辺に二人の影が伸びる。
「大学行ったら一泊二日とかで旅行に行きたいね」
私はポロッと本音を漏らしてしまった。
真緒が振り返る。
夕日に照らされたその顔は満面の笑みで満ちていた。
「まだ一年以上あるよ。それでも良いの?」
私は静かにうなずく。
小さな真緒の手が、私の大きい手を握りしめた。
「約束だからね!」
私はもう一度うなずくと、真緒の手を優しく握り返した。
二人だけの大切な夏のお出かけ。
そんな思い出を私は日記にしたためた。
了
これは二人だけの大切な思い出。
○△□○△□○△□
高校二年生の夏休みも残り数日というある日、私たちはK県の海岸にやって来た。
お盆が過ぎたこともあって、観光客もまばら。海にはサーフィンを楽しむ人達しかいない。
私と真緒は、砂浜の見渡せる防波堤に腰を下ろしていた。
お尻の下には小さなビニールシート。ふたり並んで海を眺める。
私は荷物の中からお弁当を取り出した。
「今日はね、真緒と一緒に食べたくてお弁当を作ってきたんだ」
大量の保冷剤に包まれた弁当箱は、大きく無骨なアルミ製だった。
男手一つで育ててくれた父と、スポーツ好きな弟達の中で育ったため、家には女性物の可愛らしい弁当箱などは無い。
私は顔を真っ赤にしながら、大きな体をこれでもかと縮めた。
「こんなお弁当箱しか無くて恥ずかしいけど……」
真緒は目を輝かせて弁当箱を覗き込んでいる。
「若葉のお手製ってだけで、ボクは死ぬほど嬉しいよ! 大きいお弁当箱だって、二人で食べれば丁度いい大きさだよ!」
屈託のない笑顔みせる真緒。
薄水色のワンピースに赤い麦わら帽子。
真緒は私よりも遥かに小柄。愛らしいロングヘアーが似合う少女だが、何事にも積極果敢で少し短気。まるで少年のような女の子だった。
真緒は待ちきれないとばかりに、弁当箱の蓋を開ける。
私たちの眼前に美しい花畑が広がった。
鈍色の器の中に、色とりどりのおかずたち。
お手製のBLTサンドに唐揚げと卵焼き。
色鮮やかなカットフルーツに、ポテトサラダとミニトマト。他にもたくさん詰まっている。
自分で言うのも恥ずかしいが、今回のお弁当は自信作だった。
高校で寮に入るまで、毎日家族の食事を作っていたから料理は得意だ。ただ、家族の好みから、どうしてもガッツリ系に寄ってしまうのはやや難ありだが……。
「真緒。手を拭いてから食べようね」
私は待ちきれない様子の真緒に、ウエットティッシュを差し出す。
真緒は慌ただしく手を拭くと「いただきます!」とお弁当に手を伸ばした。
美味しそうに頬張る真緒の姿が見られて私も嬉しくなった。
――思い切って二人で来て良かった。
真緒を見ながら、私は今回の小旅行が決まった時の事を思い出していた。
○△□○△□○△□
「ねぇ若葉、二人だけで何処か旅行に行かない?」
私は真緒の急な提案にドキリとした。
――えっ、行きたいけど。そんな急に言われても心の準備が出来ていないというか。
「夏と言えばやっぱり海かな! ボクねぇ、高校生になってから一度も行って無いんだよね!」
真緒はどんどん話を進めて行く。
私と真緒は普段は高校で寮生活をしているけど、夏休み期間中はお互いの実家に帰省していて、なかなか会えていなかった。
だから夏休みの宿題をやるという理由でも真緒と会えるのが楽しみだった。
私達の通う高校は中から大学まである百本桜学園。校内や寮は、夏休み中でも帰省しない生徒や、部活動に参加する生徒のために、常時開放されていた。
ここの図書館でも数人の生徒たちが勉強をしている。
「真緒。少し声を小さくして。図書委員に怒られちゃうよ……」
視線を向けると、貸し出しコーナーに座っている図書委員の女生徒と目があった。
彼女は一瞬だけこちらに視線を送ると、すぐに読みかけの書籍に目を落とした。
「あれ特進コースの三栗谷さんだよね。確かハーフの?」
真緒が耳元でささやく。
「ひゃっ!」
真緒の吐息が耳にかかり私は変な声を上げてしまった。
館内の生徒たちが一斉に私のことを見る。
私はうつむきながら、頬が焼けるように熱くなるのを感じ、あまりの恥ずかしさに薄っすらと目に涙が浮かんで来た。
生憎と大柄な私の体では、真緒の影に隠れることも出来ない。
私は机に突っ伏して出来るだけ目立たないようにした。
「ゴメン若葉。ビックリさせちゃった?」
「真緒ぉ、寿命が縮むから勘弁してぇ……」
私の心臓はまだ落ち着きを取り戻していない。
――いや、真緒とこうやって一緒に入られて嬉しいんだけどね。
「それで、海なんだけどね……」
真緒の顔がさらに寄ってくる。
あぁ、もう勘弁して!
○△□○△□○△□
打ち寄せる波が、砂浜に書いた二人の名前を消していく。
真緒が貝殻を拾って海に投げた。
海風に煽られて貝殻は波打ち際に落ちてしまった。
「あれー……、あんまり飛ばないなあ。若葉が投げたらどこまで飛ぶ?」
真緒に促されて私も同じぐらいの貝殻を投げた。桜色の貝殻はきれいな放物線を描いて波間に着水する。
「おぉ。さすが若葉だね! 若葉もスポーツやったら良いのに?」
真緒は麦わら帽子を持ち上げながら私の顔を見上げた。
――スポーツやれば?
生まれてから何度と無く聞かされた言葉だ。男ばかりのスポーツ一家に生まれ、体格にも恵まれた。
だが、如何せん性格が向いていなかった。他人と競い合うことが苦手で、スポーツには良い思い出が全く無かった……。
「ゴメン。この話題は苦手だったね」
少しうつむいていた私の心を察したのか、真緒が申し訳無さそうな顔をした。
「でも楽しかったね! 夜だったら花火をしたかったのになぁ!」
日が傾き始めた浜辺に二人の影が伸びる。
「大学行ったら一泊二日とかで旅行に行きたいね」
私はポロッと本音を漏らしてしまった。
真緒が振り返る。
夕日に照らされたその顔は満面の笑みで満ちていた。
「まだ一年以上あるよ。それでも良いの?」
私は静かにうなずく。
小さな真緒の手が、私の大きい手を握りしめた。
「約束だからね!」
私はもう一度うなずくと、真緒の手を優しく握り返した。
二人だけの大切な夏のお出かけ。
そんな思い出を私は日記にしたためた。
了