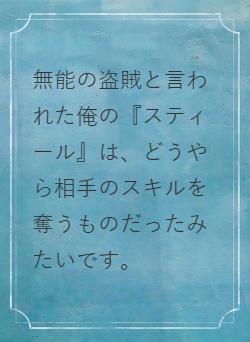本当は街に着いてからゆっくりと話をしたかった。しかし、これから帰路を二時間歩いて帰るというのに、未知の女の子としてずっと話すのはさすがに無理だった。
「とりあえず、リリの正体から聞いてもいいか?」
「私ですか? 私は助手ですよ、アイクさんの」
「えーと、もう少し詳しく知りたい。できれば、一から教えて欲しい」
俺と初めて会った時も、リリは自分のことを助手だと言っていた。
俺が助手を取った記憶がないことを告げると、俺が【ユニークスキル 助手】を使用したから、リリが現れたと言っていた。
そんな無から人間が生まれるようなことってあるのだろうか?
「そうですね……えっと、アイクさんってこの前まで『道化師見習い』だったじゃないですか」
「ああ、その認識だった」
「それで、アイクさんは条件を満たしたので、進化したんですよ。そして、『道化師』になったんです」
「条件?」
『道化師見習い』だった昨日から今日にかけて、何かの条件を達成したとでもいうのだろうか。
ギース達のパーティと一緒にクエストに行って、その後にパーティを追い出されただけ。クエスト中も特に変わることなく酷い言葉を浴びせられただけ。
何か条件となる物を達成したような気がしないのだが。
「アイクさんが独立したからですよ」
「独立? あっ……パーティを追放されたからか」
「そのとおりです。その結果、アイクさんは『道化師見習い』から『道化師』になったんです」
まさか、ギース達のパーティから抜けたことが進化の条件だったとは。見習いが力をつけてパーティから抜けると、見習いから独り立ちをした扱いになるのか。
そうなると、ますますギース達のパーティから抜けてよかったと思ってしまうな。
変に気を遣わないでいいし、無理にして下出に出る必要もなくなって、ジョブも進化をすることができて。
何というか、いいもの尽くしのような気がしてしまう。
「でも、なんで『道化師』のステータスがこんなに強いんだよ」
「なに言ってるんですか、『道化師』ですよ? 強くて当たり前じゃないですか」
「いや、『道化師』って大道芸とかやるんじゃないのか?」
実際に、俺のステータスも器用さというのが一番高い。というか、『道化師』が強いなんて誰も思いもしないだろう。
「人にバレないように問題を解決して悪を暴く。誰にもその裏側を見せずに人々を笑顔にする。そんな『道化師』が弱いはずがありません。剣だって魔法だってなんだって使えるに決まってます」
「いや、それって『道化師』とは別物のような気がするけど」
「そんなことはありません。現に、『道化師』を欠いて笑顔を失っている人たちだっていますよ」
「笑顔を失っている人?」
含みのある笑みを向けているリリの考えが読めず、俺は一人で首をかしげてしまっていた。
一体、何のことを言っているのかまるで分らない。
「まぁ、とりあえず、スキルをたくさん取得したことと、ステータスが強い理由は分かったよ。あとは、【ユニークスキル 助手】について教えて欲しい」
「そのままの意味ですよ。『道化師』には助手がいるものです。そして、それが私リリです」
リリは自慢げに胸を張ってそんなことを口にした。
見習いから独立した道化師には助手がいる。だから、俺の進化に伴って助手として生まれたということか?
生まれるって、そんなことありえるのか?
「えっと、助手をする前は何をしてたんだ? というか、どこにいたんだ?」
「ずっとアイクさんを見てました。どこにいたのかは……分かりませんけど」
「ずっと見てた? いや、分からないってどういうことだよ?」
俺はリリの言葉の意味が分からなかったので、オウム返しのような返答をしてしまった。しかし、リリはその説明をしようとしながらも、うまく言葉出てこないようだった。
「えっと、アイクさんが『道化師見習い』になってから、アイクさんのことを見てたんですよ。ただ、どこで見てたのかって言われると、どこなのか私にも分からなくて、アイクさんが私を【助手】として呼んでくれて、ようやくこうして隣に立てるようになったと言いますか」
「存在しなかったってことか? いや、存在はしてたけど実体はなかったって感じなのかな?」
「あ、多分、そんな感じです。まぁ『助手』が見習い時代のアイクさんを知らないなんてことはありえませんしね」
何かに納得するように頷いたリリの姿を見て、俺は少し頭を整理することにした。
リリは俺が『道化師見習い』のジョブを授かったときから、ずっと俺と一緒にいた。それは、将来的に助手として隣に立つためであり、俺が独り立ちするまでは姿を見せることもできなかった。
誰にも知られず、ただじっと俺に呼ばれることを待って。
そう考えると、リリが凄いけなげな女の子に見えてきた。微かな表情の動きや所作さえも、奇跡の上で成り立っているような気がして、他人のようには思えなくもなってきた。
「そっか、なんか凄い待たせちゃったんだな。ずっと一緒だったのか……なんか兄妹みたいだな」
「兄妹というよりも、父娘? いえ、それだとどちらも困りますね……うん、やっぱり私は助手です! だから、何も問題はありません!」
「問題?」
失言をしたとでも言いたげに頬を赤く染めたリリは、話を紛らわすように話題を無理やり変えてきた。
一体どうしたのだろうか?
俺はリリの頬の熱が下がるまで、ずっとそんな視線を向けていた。
「とりあえず、リリの正体から聞いてもいいか?」
「私ですか? 私は助手ですよ、アイクさんの」
「えーと、もう少し詳しく知りたい。できれば、一から教えて欲しい」
俺と初めて会った時も、リリは自分のことを助手だと言っていた。
俺が助手を取った記憶がないことを告げると、俺が【ユニークスキル 助手】を使用したから、リリが現れたと言っていた。
そんな無から人間が生まれるようなことってあるのだろうか?
「そうですね……えっと、アイクさんってこの前まで『道化師見習い』だったじゃないですか」
「ああ、その認識だった」
「それで、アイクさんは条件を満たしたので、進化したんですよ。そして、『道化師』になったんです」
「条件?」
『道化師見習い』だった昨日から今日にかけて、何かの条件を達成したとでもいうのだろうか。
ギース達のパーティと一緒にクエストに行って、その後にパーティを追い出されただけ。クエスト中も特に変わることなく酷い言葉を浴びせられただけ。
何か条件となる物を達成したような気がしないのだが。
「アイクさんが独立したからですよ」
「独立? あっ……パーティを追放されたからか」
「そのとおりです。その結果、アイクさんは『道化師見習い』から『道化師』になったんです」
まさか、ギース達のパーティから抜けたことが進化の条件だったとは。見習いが力をつけてパーティから抜けると、見習いから独り立ちをした扱いになるのか。
そうなると、ますますギース達のパーティから抜けてよかったと思ってしまうな。
変に気を遣わないでいいし、無理にして下出に出る必要もなくなって、ジョブも進化をすることができて。
何というか、いいもの尽くしのような気がしてしまう。
「でも、なんで『道化師』のステータスがこんなに強いんだよ」
「なに言ってるんですか、『道化師』ですよ? 強くて当たり前じゃないですか」
「いや、『道化師』って大道芸とかやるんじゃないのか?」
実際に、俺のステータスも器用さというのが一番高い。というか、『道化師』が強いなんて誰も思いもしないだろう。
「人にバレないように問題を解決して悪を暴く。誰にもその裏側を見せずに人々を笑顔にする。そんな『道化師』が弱いはずがありません。剣だって魔法だってなんだって使えるに決まってます」
「いや、それって『道化師』とは別物のような気がするけど」
「そんなことはありません。現に、『道化師』を欠いて笑顔を失っている人たちだっていますよ」
「笑顔を失っている人?」
含みのある笑みを向けているリリの考えが読めず、俺は一人で首をかしげてしまっていた。
一体、何のことを言っているのかまるで分らない。
「まぁ、とりあえず、スキルをたくさん取得したことと、ステータスが強い理由は分かったよ。あとは、【ユニークスキル 助手】について教えて欲しい」
「そのままの意味ですよ。『道化師』には助手がいるものです。そして、それが私リリです」
リリは自慢げに胸を張ってそんなことを口にした。
見習いから独立した道化師には助手がいる。だから、俺の進化に伴って助手として生まれたということか?
生まれるって、そんなことありえるのか?
「えっと、助手をする前は何をしてたんだ? というか、どこにいたんだ?」
「ずっとアイクさんを見てました。どこにいたのかは……分かりませんけど」
「ずっと見てた? いや、分からないってどういうことだよ?」
俺はリリの言葉の意味が分からなかったので、オウム返しのような返答をしてしまった。しかし、リリはその説明をしようとしながらも、うまく言葉出てこないようだった。
「えっと、アイクさんが『道化師見習い』になってから、アイクさんのことを見てたんですよ。ただ、どこで見てたのかって言われると、どこなのか私にも分からなくて、アイクさんが私を【助手】として呼んでくれて、ようやくこうして隣に立てるようになったと言いますか」
「存在しなかったってことか? いや、存在はしてたけど実体はなかったって感じなのかな?」
「あ、多分、そんな感じです。まぁ『助手』が見習い時代のアイクさんを知らないなんてことはありえませんしね」
何かに納得するように頷いたリリの姿を見て、俺は少し頭を整理することにした。
リリは俺が『道化師見習い』のジョブを授かったときから、ずっと俺と一緒にいた。それは、将来的に助手として隣に立つためであり、俺が独り立ちするまでは姿を見せることもできなかった。
誰にも知られず、ただじっと俺に呼ばれることを待って。
そう考えると、リリが凄いけなげな女の子に見えてきた。微かな表情の動きや所作さえも、奇跡の上で成り立っているような気がして、他人のようには思えなくもなってきた。
「そっか、なんか凄い待たせちゃったんだな。ずっと一緒だったのか……なんか兄妹みたいだな」
「兄妹というよりも、父娘? いえ、それだとどちらも困りますね……うん、やっぱり私は助手です! だから、何も問題はありません!」
「問題?」
失言をしたとでも言いたげに頬を赤く染めたリリは、話を紛らわすように話題を無理やり変えてきた。
一体どうしたのだろうか?
俺はリリの頬の熱が下がるまで、ずっとそんな視線を向けていた。