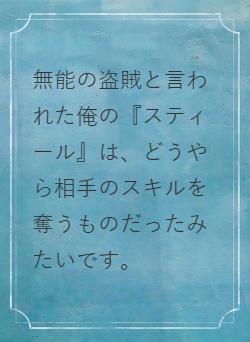「それで、お話というのはなんですか?」
「あるパーティに頼まれていたことがあったんですよ」
俺たちは用があるというミリアに連れられて、冒険者ギルドのカウンターに来ていた。あの後、クリスタルダイナソーの解体依頼もバングにお願いしてきたのだが、そこもがっつりミリアに見られてしまって、冒険者カードの更新もしていけと言われてしまった次第である。
「『白竜の髭』ってパーティが、盗賊団を捕まえたんですよ。その時に、『道化師の集い』に助けてもらったから、懸賞金は『道化師の集い』にって言ってこれを置いていきまして」
ミリアはそう言うと、小袋をカウンターの上に置いた。なんというか、その膨らみからして少ない量ではない気がする。
ガルドの鍛冶場に行くときに盗賊団を捕まえたことがあった。その後の処理はパーティのリーダーだったリードという剣士に任せたのだった。
まさか、あの盗賊団に懸賞金が掛けられていたとは。それに、全額置いていかなくても良かったのにな。
そんなことを思いながら、その小袋に手を伸ばそうとすると、ミリアはその袋の先を持ってひょいっと俺の手を交わした。
「えっと、ミリアさん?」
「盗賊団は懸賞金が掛けられるほどの指名手配集団。聞いた話では、C級パーティが怪我をして全滅しそうだった所に、颯爽と駆け付けて一瞬でやっつけてしまったとか」
ミリアのジトっとした目には何かを疑う色が混じっている気がした。
おかしい。確か、リードが上手いこと言っておくとか言ってた気がしたんだけどな。
……なんで全て筒抜けになっているんだろう。
「ははっ、話が盛られている気がするなー、なんて。一体、誰がそんなことを?」
「リーダーのリードさんが熱く語ってくれましたよ。中々口を割りませんでしたけど、『道化師の集い』を私が少し褒めたら、熱弁してくれましたよ。謙虚なパーティらしいですね、『道化師の集い』って。リードさん良い人なんですけど、まっすぐ過ぎるんですよ。人選を見誤りましたね」
この口ぶりからして、俺たちの名前を隠そうとしていたこともバレているようだ。これは、変に勘違いに乗っからない方が良かったかもしれないな。
勝手に俺たちが力を隠した実力者だと勘違いしていたので、その勘違いに適当に乗ってしまったのだが、それがこんな所でバレるとは。
俺がついっと視線をミリアから逸らしても、ミリアはそのまま言葉を続けた。
「『白竜の髭』のメンバーには、B級の冒険者もいました。それでも敵わなかったのに、D級パーティ『道化師の集い』が盗賊団を瞬殺したと。挙句の果てに、あんな身長の四倍以上あるクリスタルダイナソーを倒してましたね。……アイクさん、私に力隠してませんか?」
「いやいや、隠してなんてないですよ。隠せるものでもないですって。なぁ、リリ?」
「ふふんっ、アイクさんが強いのは当たり前のことです」
俺たちの潔白を晴らすためにリリに話を振ると、リリは俺の強さが伝わったことを誇るように胸を張っていた。
その表情を浮かべるのは絶対に今ではない気がするのだが、リリの得意げな笑みを見て、ミリアは少しだけ呆れたように口元を緩めた。
「とりあえず、またレベルが上がってる可能性があるので冒険者カードの更新をさせてください」
「わ、分かりました」
こんな頻度で冒険者カードの更新をしたことはないんだけどなと思いながら、俺たちはミリアに差し出された水晶に手のひらを置いた。
すると、水晶には次のようなステータスが表示されていた。
【名前 アイク】
【ジョブ 道化師】
【レベル 28】
【冒険者ランク D】
【ステータス 体力 10600 魔力 12240 攻撃力 10800 防御力 10400 素早さ 13100 器用さ 12300 魅力 12000】
【ユニークスキル:道化師 全属性魔法 助手】
【アルティメットスキル:アイテムボックス(無限・時間停止) 投てきS 近接格闘S 剣技S 気配感知S 生産S 鑑定S 錬金S】
【名前 リリ】
【ジョブ 助手】
【レベル 21】
【冒険者ランク D】
【ステータス 体力 7420 魔力 8570 攻撃力 7560 防御力 7280 素早さ 9170器用さ 8610 魅力 8700】
【ユニークスキル:助手】
【スキル:アイテムボックス 投てきB 近接格闘B 剣技B 気配感知B 鑑定B 錬金C】
「お、あれだけ魔物倒したからレベル結構上がったな。リリはどうだ?」
「はい、私も結構上がりましたよ!」
「どれ? お、凄いじゃないか、リリ」
「えへへっ、アイクさんには全然敵いませんけどね」
そんなふうに和気藹々としている俺たちと対照的に、ミリアは言葉を失って固まってしまっていた。
「……一週間前と全然違うじゃないですか」
ミリアはきゅっと目元を両手で隠して、誰に対してでもなく一人でそんなことを嘆いていた。
「あるパーティに頼まれていたことがあったんですよ」
俺たちは用があるというミリアに連れられて、冒険者ギルドのカウンターに来ていた。あの後、クリスタルダイナソーの解体依頼もバングにお願いしてきたのだが、そこもがっつりミリアに見られてしまって、冒険者カードの更新もしていけと言われてしまった次第である。
「『白竜の髭』ってパーティが、盗賊団を捕まえたんですよ。その時に、『道化師の集い』に助けてもらったから、懸賞金は『道化師の集い』にって言ってこれを置いていきまして」
ミリアはそう言うと、小袋をカウンターの上に置いた。なんというか、その膨らみからして少ない量ではない気がする。
ガルドの鍛冶場に行くときに盗賊団を捕まえたことがあった。その後の処理はパーティのリーダーだったリードという剣士に任せたのだった。
まさか、あの盗賊団に懸賞金が掛けられていたとは。それに、全額置いていかなくても良かったのにな。
そんなことを思いながら、その小袋に手を伸ばそうとすると、ミリアはその袋の先を持ってひょいっと俺の手を交わした。
「えっと、ミリアさん?」
「盗賊団は懸賞金が掛けられるほどの指名手配集団。聞いた話では、C級パーティが怪我をして全滅しそうだった所に、颯爽と駆け付けて一瞬でやっつけてしまったとか」
ミリアのジトっとした目には何かを疑う色が混じっている気がした。
おかしい。確か、リードが上手いこと言っておくとか言ってた気がしたんだけどな。
……なんで全て筒抜けになっているんだろう。
「ははっ、話が盛られている気がするなー、なんて。一体、誰がそんなことを?」
「リーダーのリードさんが熱く語ってくれましたよ。中々口を割りませんでしたけど、『道化師の集い』を私が少し褒めたら、熱弁してくれましたよ。謙虚なパーティらしいですね、『道化師の集い』って。リードさん良い人なんですけど、まっすぐ過ぎるんですよ。人選を見誤りましたね」
この口ぶりからして、俺たちの名前を隠そうとしていたこともバレているようだ。これは、変に勘違いに乗っからない方が良かったかもしれないな。
勝手に俺たちが力を隠した実力者だと勘違いしていたので、その勘違いに適当に乗ってしまったのだが、それがこんな所でバレるとは。
俺がついっと視線をミリアから逸らしても、ミリアはそのまま言葉を続けた。
「『白竜の髭』のメンバーには、B級の冒険者もいました。それでも敵わなかったのに、D級パーティ『道化師の集い』が盗賊団を瞬殺したと。挙句の果てに、あんな身長の四倍以上あるクリスタルダイナソーを倒してましたね。……アイクさん、私に力隠してませんか?」
「いやいや、隠してなんてないですよ。隠せるものでもないですって。なぁ、リリ?」
「ふふんっ、アイクさんが強いのは当たり前のことです」
俺たちの潔白を晴らすためにリリに話を振ると、リリは俺の強さが伝わったことを誇るように胸を張っていた。
その表情を浮かべるのは絶対に今ではない気がするのだが、リリの得意げな笑みを見て、ミリアは少しだけ呆れたように口元を緩めた。
「とりあえず、またレベルが上がってる可能性があるので冒険者カードの更新をさせてください」
「わ、分かりました」
こんな頻度で冒険者カードの更新をしたことはないんだけどなと思いながら、俺たちはミリアに差し出された水晶に手のひらを置いた。
すると、水晶には次のようなステータスが表示されていた。
【名前 アイク】
【ジョブ 道化師】
【レベル 28】
【冒険者ランク D】
【ステータス 体力 10600 魔力 12240 攻撃力 10800 防御力 10400 素早さ 13100 器用さ 12300 魅力 12000】
【ユニークスキル:道化師 全属性魔法 助手】
【アルティメットスキル:アイテムボックス(無限・時間停止) 投てきS 近接格闘S 剣技S 気配感知S 生産S 鑑定S 錬金S】
【名前 リリ】
【ジョブ 助手】
【レベル 21】
【冒険者ランク D】
【ステータス 体力 7420 魔力 8570 攻撃力 7560 防御力 7280 素早さ 9170器用さ 8610 魅力 8700】
【ユニークスキル:助手】
【スキル:アイテムボックス 投てきB 近接格闘B 剣技B 気配感知B 鑑定B 錬金C】
「お、あれだけ魔物倒したからレベル結構上がったな。リリはどうだ?」
「はい、私も結構上がりましたよ!」
「どれ? お、凄いじゃないか、リリ」
「えへへっ、アイクさんには全然敵いませんけどね」
そんなふうに和気藹々としている俺たちと対照的に、ミリアは言葉を失って固まってしまっていた。
「……一週間前と全然違うじゃないですか」
ミリアはきゅっと目元を両手で隠して、誰に対してでもなく一人でそんなことを嘆いていた。