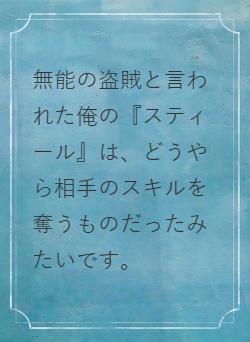「リリ。料理をしてもらううえで必要な物があると思うから、これから買いに行こう。何が必要だ?」
俺たちは武器屋を後にして、市場へと向かっていた。
これからしばらく街を離れることになるので、今のうちに必要な物を買っておこうと思って市場に来ていた。
これから一週間はリリに食事を作ってもらうことになる。そうなると、必要な物はそれえておく必要があるだろう。
「そうですね。……包丁とか鍋とか基本的な物はありますか?」
「そこらへんはあるよ。食器類もルードさんから貸してもらったセットに入ってるみたいだ」
話を聞いた限り、どこかに遠征に行くときに使用していたセットらしい。貸してもらったものを色々見てみたが、基本的に必要な物はそろっていた。
足りないのは食材と調味料くらい。
これならかなり出費を抑えることができるだろう。
「なるほど、そうなると調味料とかですかね。外で料理をするということなので、簡単な物だけでも揃えておきましょう」
「そうだな。外でそんなに手の込んだものはいらないかもな。うん、料理のことはよく分らないし、リリに任せるよ」
「任せてください! ふふっ、ようやく助手みたいになってきましたね。行きましょう、アイクさん」
リリは嬉しそうに頬を緩めると、俺の手を引いて歩き出した。
同じくらいの年齢の子に手を引かれて街を歩く、そんな状況がデートのように思えたりして、俺は微かに鼓動を大きくしてしまっていた。
そして、俺が分からないことを手伝ってくれるあたり、本当に助手なのだなと少し感心したりしたのだった。
「あっ……」
「……リリ?」
俺がそんなことを考えて口元を緩めていると、リリがピタリと足を止めてしまった。そして、こちらに向けられた瞳を微かに揺らしていた。
もしかして、俺が変なことを考えていたことに気づかれてしまっただろうか。
リリに正面から見つめられて、俺は微かに体温を上げてしまったような気がした。リリはその俺の反応を見て恥ずかしがるように頬の熱を上げると、静かに口を開いた。
「……お、お塩ってどこのお店に売ってるんですかね?」
「……こっちの店だな」
俺は平常運転になったリリを見て、少しだけ安心したように溜息を一つ吐いた。
確かに、市場を回るのは初めてだもんな。当然、そんな反応にもなるか。
俺はリリの手を引きながら、市場を見て料理に必要な食材やパン、水やポーションなどを買って着々と明日の準備を整えていった。
傍から見たらデートをしているように見えるかもしれない。
そう思うと胸の奥の方が熱くなっていく気がしたので、俺はそれ以上は考えないようにしながら買い物を進めていった。
「あっ、まだ宿代残ってるんだった」
宿に戻って店主のおばさんに挨拶をしたところで、俺はふとそんなことを思い出したのだった。
しばらくはここから動かないだろうと思って、リリの分含めて数日分の宿代を払ってしまっていた。
宿代を無駄にするのはもったいないが、今さら気づいたところで遅すぎたか。
「なんだい、どこかに行くのかい?」
「ええ、少しの間王都を離れることになりまして」
俺のお話を聞いて店主のおばさんは予約表のような物を確認して、数度頷いた後に言葉を続けた。
「確か二階の角部屋のところだったよね? 確かに数日残ってるみたいだね。明日の朝までいるなら朝ごはん食べた後にまた声かけておくれ。それ以降の料金は返金するよ」
「え、いいんですか? 結構急な気もしますけど、大丈夫ですか?」
「問題ないよ。なに、また王都に来るときがあったら寄ってくれればチャラだよ」
店主のおばさんはそんなことを言って笑っていた。
どうやら、この宿屋が長く続き理由はただ飯が旨いだけではないようだった。長く続く理由は店主の人柄もあるらしい。
これから魔物肉を使って商売をするかもしれない俺は、そんなおばさんの考えを少し見習わなければならないと思うのだった。
俺たちは武器屋を後にして、市場へと向かっていた。
これからしばらく街を離れることになるので、今のうちに必要な物を買っておこうと思って市場に来ていた。
これから一週間はリリに食事を作ってもらうことになる。そうなると、必要な物はそれえておく必要があるだろう。
「そうですね。……包丁とか鍋とか基本的な物はありますか?」
「そこらへんはあるよ。食器類もルードさんから貸してもらったセットに入ってるみたいだ」
話を聞いた限り、どこかに遠征に行くときに使用していたセットらしい。貸してもらったものを色々見てみたが、基本的に必要な物はそろっていた。
足りないのは食材と調味料くらい。
これならかなり出費を抑えることができるだろう。
「なるほど、そうなると調味料とかですかね。外で料理をするということなので、簡単な物だけでも揃えておきましょう」
「そうだな。外でそんなに手の込んだものはいらないかもな。うん、料理のことはよく分らないし、リリに任せるよ」
「任せてください! ふふっ、ようやく助手みたいになってきましたね。行きましょう、アイクさん」
リリは嬉しそうに頬を緩めると、俺の手を引いて歩き出した。
同じくらいの年齢の子に手を引かれて街を歩く、そんな状況がデートのように思えたりして、俺は微かに鼓動を大きくしてしまっていた。
そして、俺が分からないことを手伝ってくれるあたり、本当に助手なのだなと少し感心したりしたのだった。
「あっ……」
「……リリ?」
俺がそんなことを考えて口元を緩めていると、リリがピタリと足を止めてしまった。そして、こちらに向けられた瞳を微かに揺らしていた。
もしかして、俺が変なことを考えていたことに気づかれてしまっただろうか。
リリに正面から見つめられて、俺は微かに体温を上げてしまったような気がした。リリはその俺の反応を見て恥ずかしがるように頬の熱を上げると、静かに口を開いた。
「……お、お塩ってどこのお店に売ってるんですかね?」
「……こっちの店だな」
俺は平常運転になったリリを見て、少しだけ安心したように溜息を一つ吐いた。
確かに、市場を回るのは初めてだもんな。当然、そんな反応にもなるか。
俺はリリの手を引きながら、市場を見て料理に必要な食材やパン、水やポーションなどを買って着々と明日の準備を整えていった。
傍から見たらデートをしているように見えるかもしれない。
そう思うと胸の奥の方が熱くなっていく気がしたので、俺はそれ以上は考えないようにしながら買い物を進めていった。
「あっ、まだ宿代残ってるんだった」
宿に戻って店主のおばさんに挨拶をしたところで、俺はふとそんなことを思い出したのだった。
しばらくはここから動かないだろうと思って、リリの分含めて数日分の宿代を払ってしまっていた。
宿代を無駄にするのはもったいないが、今さら気づいたところで遅すぎたか。
「なんだい、どこかに行くのかい?」
「ええ、少しの間王都を離れることになりまして」
俺のお話を聞いて店主のおばさんは予約表のような物を確認して、数度頷いた後に言葉を続けた。
「確か二階の角部屋のところだったよね? 確かに数日残ってるみたいだね。明日の朝までいるなら朝ごはん食べた後にまた声かけておくれ。それ以降の料金は返金するよ」
「え、いいんですか? 結構急な気もしますけど、大丈夫ですか?」
「問題ないよ。なに、また王都に来るときがあったら寄ってくれればチャラだよ」
店主のおばさんはそんなことを言って笑っていた。
どうやら、この宿屋が長く続き理由はただ飯が旨いだけではないようだった。長く続く理由は店主の人柄もあるらしい。
これから魔物肉を使って商売をするかもしれない俺は、そんなおばさんの考えを少し見習わなければならないと思うのだった。