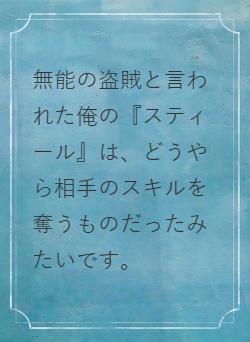「まさか、アイクがあんなブラフをするとは思わなかったな。中々やり手だな、アイク」
イーナがギルドの倉庫を後にすると、バングが笑いながらそんなことを言ってきた。俺の想像通り、バングは勘違いをしているらしかった。
「いや、本当にこれから王都離れるんですよ。どのくらい離れるか見当もついてないんですけど」
「え? ああ、あの話本当だったのか? なんだ、どこに行くんだよ?」
「さっきここに来る前に依頼を頼まれまして。あそこの武器屋の鍛冶師の人からお使いを頼まれて、鉱石集めに行くんです」
「ほぅ、あの武器屋に依頼されたのか。……随分と見る目がある奴がいたんだな」
バングは依頼のことを詳しく聞いたりするのではなく、俺に依頼をよこした依頼主の目を褒めるように短く息を吐いていた。
なんだろうか。なぜか同業者を見るような目をしている気がした。
「バングさん?」
「ん? いや、なんでもない。そっか、王都を離れるか」
「はい。まぁ、でも、リリの武器もまだ冒険者ギルドから借りてるままなので、またすぐに戻ってくるとは思いますけどね」
ギース達のパーティを出た頃はすぐにこの王都を離れようと思っていたが、色々と都合を考えるとここに残るのも便利な気がしてきた。
今後この王都を出るのかどうかはまた考えることにしよう。
「そっか、それなら問題ないか。こっちも色々準備しておくから、本格的にここを離れるようになったら教えてくれ。手紙はここの冒険者ギルド当てで構わないから」
「分かりました。そうなった時は連絡しますね」
「あっ、その連絡はリリがしてくれるんだったか?」
「そうです。そういうことは助手の私の仕事ですから」
リリはバングにからかうようにそんなことを言われて、少しムッとしながら胸を張ってそんな反応をしていた。
それから俺と目が合うと、少しだけ気まずそうに視線を逸らした後にイーナからもらった紙を折りたたんでしまった。
「……な、なんですか」
「いや、別に何も言ってないって」
なぜか助手であることを強調しているリリの様子が気になるが、変に突いて藪蛇になるのも面倒だしスルーすることにするか。
「そうだ。昨日狩った残りの魔物はどうするんだ? 今、アイクのアイテムボックスのなかにあるんだろ? あと、ここにあるブラックポークとか」
「あー、そうですね。……どうしましょうか」
念のために数体の魔物を解体せずに持っていたが、どうやら使うのは一体だけで済んだし、もう使うことはないだろう。
それなら、ここで解体してもらって金に換えた方がいいかもしれない。
「そうだ。ここで解体だけしてもらうことって出来ますか?」
「ん? できるけど、解体後の肉は持って帰るのか?」
「ええ、いつ帰ってくるか分からないんで、食材は手元にあった方がいいかなと」
「食材は手元にあった方がいいかなって、アイク料理なんかできるのか?」
そう言われて思い出してみたが、あまり料理をした記憶がない。というか、基本的に冒険者は自分で料理をしたりはしないのだ。するとしても、クエストで泊まりになったときに軽くするだけだ。
理由は簡単で、持ち家を持っていないからである。自分専用のキッチンがないという状況なので、料理をするという環境にいない。
それに、下手に食材を買って料理するよりも、安い所で外食した方が手間を考えると安かったりするのだ。
「えっと、火をつけて炙るくらいなら?」
「おまっ、こんな新鮮で良い肉をなんて食べ方で食べようとしてんだ。食材に失礼だろ」
「でも、料理できないんじゃしかたないーーん? どうしたリリ?」
俺とバングがそんなことを話していると、リリが嬉々とした表情で俺の服の裾をくいくいっと引っ張っていた。
そして、俺が話しを振ると、リリは待ってましたと言わんばかりに口を開いた。
「ふふっ、アイクさん。私がいることをお忘れですか?」
「え、リリって料理できるのか?」
俺が驚いた表情をしているのを見て、リリはどや顔でその言葉を肯定した。
「アイクさん。私、助手ですよ!」
リリは胸を張りながらそんなこと言うと、きらきらとした瞳をこちらに向けてきた。
……いや、料理に助手要素関係あるのか?
そんな俺の考えが伝わっていないのだろう。リリは羨望の眼差しでも受けているかのように誇らしげな笑みを浮かべていた。
イーナがギルドの倉庫を後にすると、バングが笑いながらそんなことを言ってきた。俺の想像通り、バングは勘違いをしているらしかった。
「いや、本当にこれから王都離れるんですよ。どのくらい離れるか見当もついてないんですけど」
「え? ああ、あの話本当だったのか? なんだ、どこに行くんだよ?」
「さっきここに来る前に依頼を頼まれまして。あそこの武器屋の鍛冶師の人からお使いを頼まれて、鉱石集めに行くんです」
「ほぅ、あの武器屋に依頼されたのか。……随分と見る目がある奴がいたんだな」
バングは依頼のことを詳しく聞いたりするのではなく、俺に依頼をよこした依頼主の目を褒めるように短く息を吐いていた。
なんだろうか。なぜか同業者を見るような目をしている気がした。
「バングさん?」
「ん? いや、なんでもない。そっか、王都を離れるか」
「はい。まぁ、でも、リリの武器もまだ冒険者ギルドから借りてるままなので、またすぐに戻ってくるとは思いますけどね」
ギース達のパーティを出た頃はすぐにこの王都を離れようと思っていたが、色々と都合を考えるとここに残るのも便利な気がしてきた。
今後この王都を出るのかどうかはまた考えることにしよう。
「そっか、それなら問題ないか。こっちも色々準備しておくから、本格的にここを離れるようになったら教えてくれ。手紙はここの冒険者ギルド当てで構わないから」
「分かりました。そうなった時は連絡しますね」
「あっ、その連絡はリリがしてくれるんだったか?」
「そうです。そういうことは助手の私の仕事ですから」
リリはバングにからかうようにそんなことを言われて、少しムッとしながら胸を張ってそんな反応をしていた。
それから俺と目が合うと、少しだけ気まずそうに視線を逸らした後にイーナからもらった紙を折りたたんでしまった。
「……な、なんですか」
「いや、別に何も言ってないって」
なぜか助手であることを強調しているリリの様子が気になるが、変に突いて藪蛇になるのも面倒だしスルーすることにするか。
「そうだ。昨日狩った残りの魔物はどうするんだ? 今、アイクのアイテムボックスのなかにあるんだろ? あと、ここにあるブラックポークとか」
「あー、そうですね。……どうしましょうか」
念のために数体の魔物を解体せずに持っていたが、どうやら使うのは一体だけで済んだし、もう使うことはないだろう。
それなら、ここで解体してもらって金に換えた方がいいかもしれない。
「そうだ。ここで解体だけしてもらうことって出来ますか?」
「ん? できるけど、解体後の肉は持って帰るのか?」
「ええ、いつ帰ってくるか分からないんで、食材は手元にあった方がいいかなと」
「食材は手元にあった方がいいかなって、アイク料理なんかできるのか?」
そう言われて思い出してみたが、あまり料理をした記憶がない。というか、基本的に冒険者は自分で料理をしたりはしないのだ。するとしても、クエストで泊まりになったときに軽くするだけだ。
理由は簡単で、持ち家を持っていないからである。自分専用のキッチンがないという状況なので、料理をするという環境にいない。
それに、下手に食材を買って料理するよりも、安い所で外食した方が手間を考えると安かったりするのだ。
「えっと、火をつけて炙るくらいなら?」
「おまっ、こんな新鮮で良い肉をなんて食べ方で食べようとしてんだ。食材に失礼だろ」
「でも、料理できないんじゃしかたないーーん? どうしたリリ?」
俺とバングがそんなことを話していると、リリが嬉々とした表情で俺の服の裾をくいくいっと引っ張っていた。
そして、俺が話しを振ると、リリは待ってましたと言わんばかりに口を開いた。
「ふふっ、アイクさん。私がいることをお忘れですか?」
「え、リリって料理できるのか?」
俺が驚いた表情をしているのを見て、リリはどや顔でその言葉を肯定した。
「アイクさん。私、助手ですよ!」
リリは胸を張りながらそんなこと言うと、きらきらとした瞳をこちらに向けてきた。
……いや、料理に助手要素関係あるのか?
そんな俺の考えが伝わっていないのだろう。リリは羨望の眼差しでも受けているかのように誇らしげな笑みを浮かべていた。