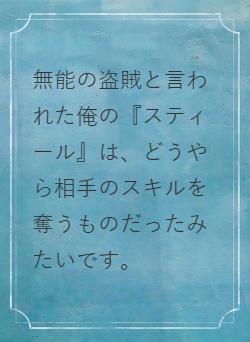「みなさん、聞いてください。この度、決戦のときに力を貸してもらえるようになった、ミノラルの冒険者たちです。彼らなら、あのギースにも引けを取らないでしょう」
モンドル王国の属国になったアンデル王国の端。今はそこに彼らのアジトがあるらしく、俺たちは挨拶をするため、その組織のアジトにお呼ばれされていた。
少し大きめの宿屋を貸切ったようなその場所で、俺たちはモルンの紹介によって、初めて会うメンバー達に温かく歓迎をされてーー
「……」
いるはずがなかった。
まぁ、それも当然だよな。
急に知らない冒険者がやってきましたと言われて、歓迎されるようなことはないだろう。
紹介の後、俺たちは大勢の人から、一気に不審な者を見るような視線を向けられていた。
それと、少しの威圧するような物も混ぜられていた。
どんなメンバーがいるのかと思ったが、どうも武闘派ばかりいるという訳ではなさそうだ。
性別問わず、線が細いようなメンバーもいるみたいだし、ただの近接格闘が取りえの奴らばかりではないらしい。
彼らがどんな戦闘スタイルなのか、それはまだ分からないが。
「モルンさん、一ついいですか?」
「なんですか?」
そんな事を考えて、周囲に目を向けていると、一人の男が挙手と共に席から立ち上がった。
体は全体的に俺の一回りくらい大きい、短髪の男。足元には体の半分くらいありそうな斧が立てかけられていた。
「主力になりそうな人材に声をかけてくると言って、連れてきたのがそいつらですか?」
「ええ、彼らは……いえ、彼は一人でワイバーンを倒すほどの腕が立つ冒険者です」
モルンが静かにそう答えると、周りがざわつきだしたのが分かった。
「ワイバーンを?!」「……S級か?」「いや、さすがに無理だろ」
驚きと少し困惑するような反応。どちらかというと、ワイバーンを倒したということを信じられないといった声の方が多いように感じた。
「モルンさん、俺たちは比喩的な強さを知りたいんじゃないんです」
「比喩じゃありません。私もノアンも、ワイバーンが倒されるところを目の前で見ました」
モルンの言葉を受けて、その男は肩をぴくんとさせて驚いていた。実際に見たという証言が影響したのか、先程まで疑っていたような目も和らいでいくのが分かった。
「この男が、ワイバーンをですか……」
「ドエルさん。先程から少し失礼ですよ」
「悪いとは思ってますよ。しかし……」
ドエルはちらりと横目で他のメンバーに目をやった。モルンの言葉を受けて、俺たちの力を信じている者たちが増えているのは確かだが、信じ切っていないものがいるのも事実。
ドエルと呼ばれているこの男も、そのメンバーの不安を取り除くために、こんなことを言っているのかもしれない。
確かに、少しの気持ちの乱れが作戦を失敗する可能性もある。
それなら、俺がここでしてやるべき行動は……。
「確かに、ドエルさんの言う通りだと思います」
「アイクさん?」
突然、俺がドエルの意見に頷いたことに驚いたのか、モルンは少し不安そうな声を漏らしていた。
「負ければ死罪って言う状況で、戦力も身元も分からない相手を仲間に入れろって言うのは、難しいですよ」
「い、いえ、そんなことはないです! アイクさんの力が必要なんですよ!」
俺の言葉を聞いて、何かを察したようなノアンが慌てたようにそんな言葉を口にしていた。
もしかしたら、俺が協力するのをやめると言い出すと勘違いしたのかもしれない。
当然、そんなことをしたりはない。
一度受けた依頼。そして、ミノラルが深く関わって言いるという状況で、引くわけにはいかない。
「なので、せめて力の強さだけでも証明しましょう」
力を信じてもらえないのなら、ここで証明するまでだ。
「えっと、この中で一番強い人と戦って、俺が勝てば力を認めてくれますよね?」
俺がそう呼びかけると、また周囲がざわざわとし始めた。
「一番っていうと、モルンさんか」「……まぁ、モルンさんだろうな」「大丈夫か、あの男死ぬんじゃないか?」
「え?」
すぐに上がった名前はモルンの名前。
予想もしなかったその名前に驚いて目を向けると、モルンは体をビクンとさせた後、こちらから視線を逸らしていた。
「い、いちおう、この中では私が一番強いと思いますけど、その、アイクさんとやるのは……」
……そんなに本気で嫌がることないだろうに。
どうやら、ワイバーンの二の舞になると思っているのか、モルンは血の気の引いた顔で、手をぶんぶんと横に振って拒絶していた。
「それなら、俺にやらせてくれ」
モルンが本気で嫌がっていると、ドエルは何やら自信ありげに手を上げてきた。
まぁ、言い出しっぺがやるのが妥当か。
こうして、俺は『モンドルの夜明け』のメンバーに、少しだけ力を見せることにしたのだった。
ドエルの胸を借りて、強さを証明しなければ。
そんなふうに考える俺は、少しだけ張り切ってしまっていた。
モンドル王国の属国になったアンデル王国の端。今はそこに彼らのアジトがあるらしく、俺たちは挨拶をするため、その組織のアジトにお呼ばれされていた。
少し大きめの宿屋を貸切ったようなその場所で、俺たちはモルンの紹介によって、初めて会うメンバー達に温かく歓迎をされてーー
「……」
いるはずがなかった。
まぁ、それも当然だよな。
急に知らない冒険者がやってきましたと言われて、歓迎されるようなことはないだろう。
紹介の後、俺たちは大勢の人から、一気に不審な者を見るような視線を向けられていた。
それと、少しの威圧するような物も混ぜられていた。
どんなメンバーがいるのかと思ったが、どうも武闘派ばかりいるという訳ではなさそうだ。
性別問わず、線が細いようなメンバーもいるみたいだし、ただの近接格闘が取りえの奴らばかりではないらしい。
彼らがどんな戦闘スタイルなのか、それはまだ分からないが。
「モルンさん、一ついいですか?」
「なんですか?」
そんな事を考えて、周囲に目を向けていると、一人の男が挙手と共に席から立ち上がった。
体は全体的に俺の一回りくらい大きい、短髪の男。足元には体の半分くらいありそうな斧が立てかけられていた。
「主力になりそうな人材に声をかけてくると言って、連れてきたのがそいつらですか?」
「ええ、彼らは……いえ、彼は一人でワイバーンを倒すほどの腕が立つ冒険者です」
モルンが静かにそう答えると、周りがざわつきだしたのが分かった。
「ワイバーンを?!」「……S級か?」「いや、さすがに無理だろ」
驚きと少し困惑するような反応。どちらかというと、ワイバーンを倒したということを信じられないといった声の方が多いように感じた。
「モルンさん、俺たちは比喩的な強さを知りたいんじゃないんです」
「比喩じゃありません。私もノアンも、ワイバーンが倒されるところを目の前で見ました」
モルンの言葉を受けて、その男は肩をぴくんとさせて驚いていた。実際に見たという証言が影響したのか、先程まで疑っていたような目も和らいでいくのが分かった。
「この男が、ワイバーンをですか……」
「ドエルさん。先程から少し失礼ですよ」
「悪いとは思ってますよ。しかし……」
ドエルはちらりと横目で他のメンバーに目をやった。モルンの言葉を受けて、俺たちの力を信じている者たちが増えているのは確かだが、信じ切っていないものがいるのも事実。
ドエルと呼ばれているこの男も、そのメンバーの不安を取り除くために、こんなことを言っているのかもしれない。
確かに、少しの気持ちの乱れが作戦を失敗する可能性もある。
それなら、俺がここでしてやるべき行動は……。
「確かに、ドエルさんの言う通りだと思います」
「アイクさん?」
突然、俺がドエルの意見に頷いたことに驚いたのか、モルンは少し不安そうな声を漏らしていた。
「負ければ死罪って言う状況で、戦力も身元も分からない相手を仲間に入れろって言うのは、難しいですよ」
「い、いえ、そんなことはないです! アイクさんの力が必要なんですよ!」
俺の言葉を聞いて、何かを察したようなノアンが慌てたようにそんな言葉を口にしていた。
もしかしたら、俺が協力するのをやめると言い出すと勘違いしたのかもしれない。
当然、そんなことをしたりはない。
一度受けた依頼。そして、ミノラルが深く関わって言いるという状況で、引くわけにはいかない。
「なので、せめて力の強さだけでも証明しましょう」
力を信じてもらえないのなら、ここで証明するまでだ。
「えっと、この中で一番強い人と戦って、俺が勝てば力を認めてくれますよね?」
俺がそう呼びかけると、また周囲がざわざわとし始めた。
「一番っていうと、モルンさんか」「……まぁ、モルンさんだろうな」「大丈夫か、あの男死ぬんじゃないか?」
「え?」
すぐに上がった名前はモルンの名前。
予想もしなかったその名前に驚いて目を向けると、モルンは体をビクンとさせた後、こちらから視線を逸らしていた。
「い、いちおう、この中では私が一番強いと思いますけど、その、アイクさんとやるのは……」
……そんなに本気で嫌がることないだろうに。
どうやら、ワイバーンの二の舞になると思っているのか、モルンは血の気の引いた顔で、手をぶんぶんと横に振って拒絶していた。
「それなら、俺にやらせてくれ」
モルンが本気で嫌がっていると、ドエルは何やら自信ありげに手を上げてきた。
まぁ、言い出しっぺがやるのが妥当か。
こうして、俺は『モンドルの夜明け』のメンバーに、少しだけ力を見せることにしたのだった。
ドエルの胸を借りて、強さを証明しなければ。
そんなふうに考える俺は、少しだけ張り切ってしまっていた。