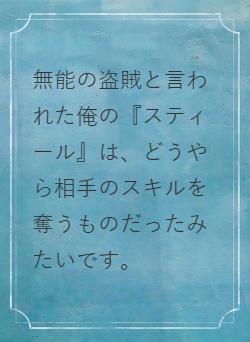「王女?」
手を貸してくれ。そう言われたモルンの言葉の中で、引っかかってしまった言葉が合った。
反射的に聞き返してしまった言葉を受けて、モルン小さく頷いた。
「はい。我が国では、最終的に王子などの王族に、最強のスキルや魔力を付加させることを目標にしています。その対象には、王女も含まれます」
「最強の力を王にってことか」
研究の最終段階、最強のスキルや魔力を付加させることができるようになったら、その力は誰が手にするのか。
そんなの考えるまでもない。当然、王やそれに近い血縁が手にするだろう。
「今は王子に付加させる前段階として、第三王女のサラ王女が実験の対象にされているんです。……今なら、まだサラ王女を救えるかもしれない」
モルンの言葉は、後半に行くにつれて言葉に感情が込められていた。まるで、そっちが本当の目的のように。
「最終段階まで言っているのに、まだ危険なんですか?」
一般的に研究が最終段階に向かっていると言われれば、それは安全性が保障されているように思う。
それなら、ただ王女が強い力を手に入れるだけのように思うが。
そんな事を考えて尋ねると、モルンはすぐに首を横に振った。
「第一後継者の王子にスキルを何個まで付加できるか。それを、血の近いサラ王女で試そうとしています。……おそらく、自意識がなくなる限界まで」
モルンは説明をしながら拳を強く握りしめていた。表情から隠してはいるが、どうやら感情は長切れなくなっているようだった。
「王女相手にそんな手荒なことしますか」
「そういう王なんです。この国の王は。ずっとサラ王女の御付きをしていましたから、そこら辺は分かるんです」
想像もしていなかった返答が返ってきたので、俺は少し目を見開いていた。
元御付きの人間が、反モンドル勢力に加わっているということか? そんなことってあり得るのだろうか?
御付きと言われて、思い出すのはハンスのことだった。
元御付きの人が反勢力として戦うことができるのかと思ったが、ハンスがモルンの立場だったらと思ったら、想像以上にしっくりきてしまった。
ずっと支えてきた人が壊れてしまう前に救いたい。そんな思いから、王城を抜けて反モンドル勢力に加わったということなのか。
そこまでの熱量を前に、俺は力を貸したくなっていた。しかし、ギリギリの所で俺は踏み留まっていた。
「助けたい気持ちはあります。ですが、他国の人間が関わるのは……」
正直、力を貸して欲しいという声に、この場で頷いてしまいたい気持ちが強い。でも、俺はあくまでミノラルの人間だ。
意味もなく他国でのテロ活動に関わるというのは、ミノラルにも迷惑をかけることになるかもしれない。
そう考えたとき、この場ですぐに頷くことは難しいと思った。
「今はまだ噂があるから平気ですけど、モンドル王国は近いうちにミノラルに戦争を仕掛けるかもしれませんよ」
「え? な、なんで?」
モルンの思いもよらなかった返答が返ってきて、俺はそんな言葉を返していた。
ふざけて言っている様子はなくて、モルンはどことなく真剣な表情をしていた。
「モンドル王国は、スキルとかを人工的に付与できる力が圧倒的に強いことを証明したい。その対象が強ければ強いほど、アピールになりますから」
確かに、その文言は納得いくものがあった。それでも、これだけ道化師の噂が歩いている国を襲撃するだろうか?
「でも、わざわざ悪魔がいるって国を襲うか?」
「襲いますね。長年の研究で得た戦力なら勝てると思ってるんですよ。むしろ、道化師の噂のせいで、焦っている節もあります」
普通は躊躇するところだが、長年の年月を積み重ねてできた自信は、突如生まれた噂には負けないということだろう。
そうなると、近くない未来に本当にミノラルが襲われる可能性がある。
本格的な戦争にでもなれば、きっとミノラルの住民にも被害が及ぶことになるだろう。
「ですので、戦争を未然に防ぐと思って頂ければと」
「……そう言われると、揺らぎますね」
まるで俺の考えを読むようなモルンの言葉に、俺は苦笑交じりにそんな言葉を漏らしていた。
未然に戦争を防ぐ。それが一番平和的な解決になるということを、この身は体を持って知っているのだろう。
気がつけば、俺はモルンの言葉を前のめりで聞いていた。
「でも、モンドル王国はミノラルを潰せるくらいの戦力があるってことですよね? それを倒すほどの戦力がいるとなると、『モンドルの夜明け』が勝利を収めるのは難しいのでは?」
「その点は大丈夫……とは言えませんね。ですが、勝算はあります」
モルンが含みのあるような笑みを浮かべると、その隣にいたノアンが待っていましたとばかりに、得意げな笑みを浮かべた。
「実験体として囚われている人たちを開放して、共に王城を襲いに行きます!」
「つまり、戦力は戦争中に増やしていくってことか」
「はい。実験体とされている人たちで、不満を持っていない人は限りなく少ないですから」
実験体として扱われているということは、何かしらスキルや魔力を人工的に付加されている可能性がある。
ということは、それって結構な戦力になるのではないだろうか。おそらく、そこまで見込んだうえでの計画なのだろう。
「少ないっていうことは、一定層望んでる人がいるんですか?」
「いますね。戦闘狂や国への忠誠心が強い人とかは望んでいます。彼らは精神力が強いせいか、過度の実験にも耐えていて、戦力的にも強いんですね」
「それは随分と厄介な」
強い力を望むというのは、冒険者をしていると分かる部分がある。
今まで戦ってきた盗賊団や、裏傭兵団のような連中も、人工的に強くなる方法があるのなら、その実験を望んで受けるのだろう。
「その中でも、一番の戦力がいます。アイクさんと同じミノラルの冒険者、ギース。彼が一番の障害かもしれません」
「……ぎ、ギース?」
一聞き流そうとして、急に食いついてきた俺の態度にモルンは少し驚きながら、言葉を続けた。
「は、はい。元S級冒険者で、ミノラルのある冒険者への恨み異常だと聞いたことがあります。ミノラルを滅ぼすためなら、なんでもすると言っていて、モンドル王国の一番過酷な実験の被検体にーーアイクさん?」
もしかしたら、人違いなのかもしれない。そんなふうに考えたが、経歴を聞くと完全に俺の知っているギースだった。
元S級パーティ『黒龍の牙』。俺が抜けてからボロボロになって、実質上解散まで追い込まれたパーティのリーダー。
そういえば、以前にエルドがギースの行方が分からなくなったと言っていたな。そして、俺に強い恨みを持っているということも。
「はぁーー……」
「えっと、アイクさん?」
思わず深いため息が出てしまった俺を心配するように、モルンが少し焦ったよう顔していた。
何か自分の言葉が気に障ったと思ったのだろう。
嫌な思い出を思い出しそうにもなったが、それ以上に他国にまで迷惑をかけている元パーティメンバーに、嫌気がさしただけだ。
これは、さすがに無視することはできないよな。
「……多分、その冒険者って俺だわ」
「「え?!」」
いつミノラルに仕掛けてくるのか分からない状況。そして、その主戦力としてミノラルの冒険者が絡んでいる。
それも、元パーティメンバーがだ。
そんな状況なら、俺がこの戦いに参戦しないわけにはいかないだろう。
「分かった。協力させてくれ、『モンドルの夜明け』の戦いに」
引き受けなければならない。最後に俺の背中を押したのは、ミノラルの一冒険者としての責任からだった。
後付けの理由としては、十分な理由だ。
こうして、俺たちは反モンドル勢力の『モンドルの夜明け』に、力を貸すことにしたのだった。
手を貸してくれ。そう言われたモルンの言葉の中で、引っかかってしまった言葉が合った。
反射的に聞き返してしまった言葉を受けて、モルン小さく頷いた。
「はい。我が国では、最終的に王子などの王族に、最強のスキルや魔力を付加させることを目標にしています。その対象には、王女も含まれます」
「最強の力を王にってことか」
研究の最終段階、最強のスキルや魔力を付加させることができるようになったら、その力は誰が手にするのか。
そんなの考えるまでもない。当然、王やそれに近い血縁が手にするだろう。
「今は王子に付加させる前段階として、第三王女のサラ王女が実験の対象にされているんです。……今なら、まだサラ王女を救えるかもしれない」
モルンの言葉は、後半に行くにつれて言葉に感情が込められていた。まるで、そっちが本当の目的のように。
「最終段階まで言っているのに、まだ危険なんですか?」
一般的に研究が最終段階に向かっていると言われれば、それは安全性が保障されているように思う。
それなら、ただ王女が強い力を手に入れるだけのように思うが。
そんな事を考えて尋ねると、モルンはすぐに首を横に振った。
「第一後継者の王子にスキルを何個まで付加できるか。それを、血の近いサラ王女で試そうとしています。……おそらく、自意識がなくなる限界まで」
モルンは説明をしながら拳を強く握りしめていた。表情から隠してはいるが、どうやら感情は長切れなくなっているようだった。
「王女相手にそんな手荒なことしますか」
「そういう王なんです。この国の王は。ずっとサラ王女の御付きをしていましたから、そこら辺は分かるんです」
想像もしていなかった返答が返ってきたので、俺は少し目を見開いていた。
元御付きの人間が、反モンドル勢力に加わっているということか? そんなことってあり得るのだろうか?
御付きと言われて、思い出すのはハンスのことだった。
元御付きの人が反勢力として戦うことができるのかと思ったが、ハンスがモルンの立場だったらと思ったら、想像以上にしっくりきてしまった。
ずっと支えてきた人が壊れてしまう前に救いたい。そんな思いから、王城を抜けて反モンドル勢力に加わったということなのか。
そこまでの熱量を前に、俺は力を貸したくなっていた。しかし、ギリギリの所で俺は踏み留まっていた。
「助けたい気持ちはあります。ですが、他国の人間が関わるのは……」
正直、力を貸して欲しいという声に、この場で頷いてしまいたい気持ちが強い。でも、俺はあくまでミノラルの人間だ。
意味もなく他国でのテロ活動に関わるというのは、ミノラルにも迷惑をかけることになるかもしれない。
そう考えたとき、この場ですぐに頷くことは難しいと思った。
「今はまだ噂があるから平気ですけど、モンドル王国は近いうちにミノラルに戦争を仕掛けるかもしれませんよ」
「え? な、なんで?」
モルンの思いもよらなかった返答が返ってきて、俺はそんな言葉を返していた。
ふざけて言っている様子はなくて、モルンはどことなく真剣な表情をしていた。
「モンドル王国は、スキルとかを人工的に付与できる力が圧倒的に強いことを証明したい。その対象が強ければ強いほど、アピールになりますから」
確かに、その文言は納得いくものがあった。それでも、これだけ道化師の噂が歩いている国を襲撃するだろうか?
「でも、わざわざ悪魔がいるって国を襲うか?」
「襲いますね。長年の研究で得た戦力なら勝てると思ってるんですよ。むしろ、道化師の噂のせいで、焦っている節もあります」
普通は躊躇するところだが、長年の年月を積み重ねてできた自信は、突如生まれた噂には負けないということだろう。
そうなると、近くない未来に本当にミノラルが襲われる可能性がある。
本格的な戦争にでもなれば、きっとミノラルの住民にも被害が及ぶことになるだろう。
「ですので、戦争を未然に防ぐと思って頂ければと」
「……そう言われると、揺らぎますね」
まるで俺の考えを読むようなモルンの言葉に、俺は苦笑交じりにそんな言葉を漏らしていた。
未然に戦争を防ぐ。それが一番平和的な解決になるということを、この身は体を持って知っているのだろう。
気がつけば、俺はモルンの言葉を前のめりで聞いていた。
「でも、モンドル王国はミノラルを潰せるくらいの戦力があるってことですよね? それを倒すほどの戦力がいるとなると、『モンドルの夜明け』が勝利を収めるのは難しいのでは?」
「その点は大丈夫……とは言えませんね。ですが、勝算はあります」
モルンが含みのあるような笑みを浮かべると、その隣にいたノアンが待っていましたとばかりに、得意げな笑みを浮かべた。
「実験体として囚われている人たちを開放して、共に王城を襲いに行きます!」
「つまり、戦力は戦争中に増やしていくってことか」
「はい。実験体とされている人たちで、不満を持っていない人は限りなく少ないですから」
実験体として扱われているということは、何かしらスキルや魔力を人工的に付加されている可能性がある。
ということは、それって結構な戦力になるのではないだろうか。おそらく、そこまで見込んだうえでの計画なのだろう。
「少ないっていうことは、一定層望んでる人がいるんですか?」
「いますね。戦闘狂や国への忠誠心が強い人とかは望んでいます。彼らは精神力が強いせいか、過度の実験にも耐えていて、戦力的にも強いんですね」
「それは随分と厄介な」
強い力を望むというのは、冒険者をしていると分かる部分がある。
今まで戦ってきた盗賊団や、裏傭兵団のような連中も、人工的に強くなる方法があるのなら、その実験を望んで受けるのだろう。
「その中でも、一番の戦力がいます。アイクさんと同じミノラルの冒険者、ギース。彼が一番の障害かもしれません」
「……ぎ、ギース?」
一聞き流そうとして、急に食いついてきた俺の態度にモルンは少し驚きながら、言葉を続けた。
「は、はい。元S級冒険者で、ミノラルのある冒険者への恨み異常だと聞いたことがあります。ミノラルを滅ぼすためなら、なんでもすると言っていて、モンドル王国の一番過酷な実験の被検体にーーアイクさん?」
もしかしたら、人違いなのかもしれない。そんなふうに考えたが、経歴を聞くと完全に俺の知っているギースだった。
元S級パーティ『黒龍の牙』。俺が抜けてからボロボロになって、実質上解散まで追い込まれたパーティのリーダー。
そういえば、以前にエルドがギースの行方が分からなくなったと言っていたな。そして、俺に強い恨みを持っているということも。
「はぁーー……」
「えっと、アイクさん?」
思わず深いため息が出てしまった俺を心配するように、モルンが少し焦ったよう顔していた。
何か自分の言葉が気に障ったと思ったのだろう。
嫌な思い出を思い出しそうにもなったが、それ以上に他国にまで迷惑をかけている元パーティメンバーに、嫌気がさしただけだ。
これは、さすがに無視することはできないよな。
「……多分、その冒険者って俺だわ」
「「え?!」」
いつミノラルに仕掛けてくるのか分からない状況。そして、その主戦力としてミノラルの冒険者が絡んでいる。
それも、元パーティメンバーがだ。
そんな状況なら、俺がこの戦いに参戦しないわけにはいかないだろう。
「分かった。協力させてくれ、『モンドルの夜明け』の戦いに」
引き受けなければならない。最後に俺の背中を押したのは、ミノラルの一冒険者としての責任からだった。
後付けの理由としては、十分な理由だ。
こうして、俺たちは反モンドル勢力の『モンドルの夜明け』に、力を貸すことにしたのだった。