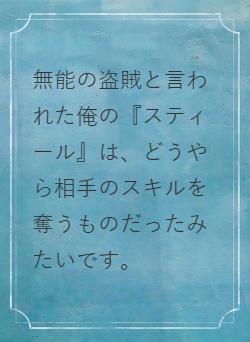「来ましたよ、ポチっ!」
「きゃんっ!」
俺たちが魔法で灯した光に向かって突っ込んできたのは、両手を広げたくらいの大きさのあるネズミのような魔物。
アングラマウスという種類で、ダンジョンに出てくる定番の魔物だった。
そして、そんなアングラマウス二体の突進に対して、ポチが小さい体のまま軽く吠えると、地面から現れた二つの氷柱が突進してくるアングラマウスを貫いた。
「「ぎゅぴぃっ!!」」
突き刺した場所が良かったのか、アングラマウスはそれっきり動かなくなり、氷柱が消えて地面に落ちてきたアングラマウスは、鈍い音を立てて地面に叩きつけられただけだった。
動かなくなった二体のアングラマウス。その姿を見たリリは、小さく首を傾げていた。
「さっきから、この魔物多くないですか?」
「まぁ、ダンジョンの定番ではあるからな。……いや、それにしても多いか」
先程から何度も魔物とは対峙していた。
まぁ、リリとポチが対応してくれたので、俺はただダンジョン内を歩いているだけだったけれども。
エルシルという街自体、魔物が多いとされている場所だし、そこのダンジョンなのだから魔物が多くいるのは不思議ではない。
問題があるとすれば、あまりにもその魔物に偏りがあることだ。
「アングラマウスは確かに繁殖力が強いから、比率的に多くなるのは分かる。ただ、ここまで偏りがあるものなのか?」
戦ってきた魔物の内、八割がアングラマウスというのは明らかにおかしい気がする。もっと強い魔物がダンジョンを住処にしていてもおかしくないはず。
いや、ダンジョンに生息する魔物ってこんなもんなのか?
ダンジョン経験が浅いがゆえに、この状況が異常なのかどうかの判断が難しい。
「昔行ったことのあるダンジョンは、こんなことなかったんだけどな」
数度行ったことのあるダンジョンの記憶を思い出しては見たが、ここまで生息する魔物に偏りがあったことはない。
そもそも、エルシルのダンジョンに入るのが初めてな時点で、いくら思い出しても仕方がないのかもしれないけれども。
それでも、何かおかしいよな。
「相手はアングラマウスだけど、いちおう気をつけて進んでーーん? なんか来るな」
雲息が怪しい気がしてきたので、【気配感知】のスキルを使って周辺を散策してみると、こちらに凄い勢いで走ってくる気配が二つあった。
この速度はアングラマウスの速さではない。
念のために、その気配の正体を探るために【鑑定】のスキルを使用して、その正体を探ったところで、俺は小さな声を漏らしていた。
「え? どういうことだ?」
「アイクさん?」
そんなはずはない。そう思いながら、こちらに向かってくる気配の方に視線を向けると、魔法で灯した灯りの方に突っ込んでくる影が二つあった。
「わんっ!」
匂いか何かですでに気づいていたのか、ポチはその影がこちらに近づくよりも早く吠えて、地面を強く叩いた。
それに合わせて地面から出てきた氷柱に、その二つの影は見事に突き刺さった。
「「ぎゅぴぃっ!!」」
聞き覚えのある鳴き声。というか、少し前に聞いたばかりの鳴き声だ。氷柱に突き刺さっている魔物に少し近づいてみると、その正体はすぐに分かった。
先程から何度も相手にしてきた魔物。氷柱に体を貫かれながら、こちらに体をググっと伸ばして、鋭い前歯をカチカチとさせている大きなネズミのような姿。
「……アングラマウス」
今日だけで何度も見た魔物。姿形は完全にアングラマウスのそれだった。
それだというのに、今まで見てきたアングラマウスとは確実に何かが違っていた。
今まで即死していたアングラマウスとは大きく違う、氷柱で貫かれても即死しない生命力。
それは、まだポチが急所を外したという理由をつけることができるが、それ以上に明らかにおかしい点があった。
「「ぎゅぴぃぃぃっ!! ぎぎぃっ!」」
体を貫かれて、痛みに苦しむのならまだ分かる。むしろ、生物としてそうあるべきだろう。
それだというのに、目の前のアングラマウスは痛みに苦しむ声を上げるのではなく、氷柱をぐっと前足で押しながら、頭をこちらに突っ込もうとしていた。
鋭い牙で噛みつくことしか頭にないのか、自身の体が貫かれていることに気づいていないのか。
やがて、ぶちぶちっという筋繊維が引きちぎられるような音がして、アングラマウスは自分の体に空いた穴を広げるだけ広げてから、動かなくなった。
その異常な光景に、俺たちはしばらく言葉を失っていた。
獰猛という言葉では片づけられないほど、異常な相手への執着心。
それは、先程まで相手をしてきたアングラマウスとは、別の魔物にしか見えなかった。
しかし、【鑑定】の解析結果には、何度見ても『アングラマウス』と表示されていた。
「……どうなってんだ」
心から漏れたようなその声は、静かなダンジョンの中でよく響いていた。
「きゃんっ!」
俺たちが魔法で灯した光に向かって突っ込んできたのは、両手を広げたくらいの大きさのあるネズミのような魔物。
アングラマウスという種類で、ダンジョンに出てくる定番の魔物だった。
そして、そんなアングラマウス二体の突進に対して、ポチが小さい体のまま軽く吠えると、地面から現れた二つの氷柱が突進してくるアングラマウスを貫いた。
「「ぎゅぴぃっ!!」」
突き刺した場所が良かったのか、アングラマウスはそれっきり動かなくなり、氷柱が消えて地面に落ちてきたアングラマウスは、鈍い音を立てて地面に叩きつけられただけだった。
動かなくなった二体のアングラマウス。その姿を見たリリは、小さく首を傾げていた。
「さっきから、この魔物多くないですか?」
「まぁ、ダンジョンの定番ではあるからな。……いや、それにしても多いか」
先程から何度も魔物とは対峙していた。
まぁ、リリとポチが対応してくれたので、俺はただダンジョン内を歩いているだけだったけれども。
エルシルという街自体、魔物が多いとされている場所だし、そこのダンジョンなのだから魔物が多くいるのは不思議ではない。
問題があるとすれば、あまりにもその魔物に偏りがあることだ。
「アングラマウスは確かに繁殖力が強いから、比率的に多くなるのは分かる。ただ、ここまで偏りがあるものなのか?」
戦ってきた魔物の内、八割がアングラマウスというのは明らかにおかしい気がする。もっと強い魔物がダンジョンを住処にしていてもおかしくないはず。
いや、ダンジョンに生息する魔物ってこんなもんなのか?
ダンジョン経験が浅いがゆえに、この状況が異常なのかどうかの判断が難しい。
「昔行ったことのあるダンジョンは、こんなことなかったんだけどな」
数度行ったことのあるダンジョンの記憶を思い出しては見たが、ここまで生息する魔物に偏りがあったことはない。
そもそも、エルシルのダンジョンに入るのが初めてな時点で、いくら思い出しても仕方がないのかもしれないけれども。
それでも、何かおかしいよな。
「相手はアングラマウスだけど、いちおう気をつけて進んでーーん? なんか来るな」
雲息が怪しい気がしてきたので、【気配感知】のスキルを使って周辺を散策してみると、こちらに凄い勢いで走ってくる気配が二つあった。
この速度はアングラマウスの速さではない。
念のために、その気配の正体を探るために【鑑定】のスキルを使用して、その正体を探ったところで、俺は小さな声を漏らしていた。
「え? どういうことだ?」
「アイクさん?」
そんなはずはない。そう思いながら、こちらに向かってくる気配の方に視線を向けると、魔法で灯した灯りの方に突っ込んでくる影が二つあった。
「わんっ!」
匂いか何かですでに気づいていたのか、ポチはその影がこちらに近づくよりも早く吠えて、地面を強く叩いた。
それに合わせて地面から出てきた氷柱に、その二つの影は見事に突き刺さった。
「「ぎゅぴぃっ!!」」
聞き覚えのある鳴き声。というか、少し前に聞いたばかりの鳴き声だ。氷柱に突き刺さっている魔物に少し近づいてみると、その正体はすぐに分かった。
先程から何度も相手にしてきた魔物。氷柱に体を貫かれながら、こちらに体をググっと伸ばして、鋭い前歯をカチカチとさせている大きなネズミのような姿。
「……アングラマウス」
今日だけで何度も見た魔物。姿形は完全にアングラマウスのそれだった。
それだというのに、今まで見てきたアングラマウスとは確実に何かが違っていた。
今まで即死していたアングラマウスとは大きく違う、氷柱で貫かれても即死しない生命力。
それは、まだポチが急所を外したという理由をつけることができるが、それ以上に明らかにおかしい点があった。
「「ぎゅぴぃぃぃっ!! ぎぎぃっ!」」
体を貫かれて、痛みに苦しむのならまだ分かる。むしろ、生物としてそうあるべきだろう。
それだというのに、目の前のアングラマウスは痛みに苦しむ声を上げるのではなく、氷柱をぐっと前足で押しながら、頭をこちらに突っ込もうとしていた。
鋭い牙で噛みつくことしか頭にないのか、自身の体が貫かれていることに気づいていないのか。
やがて、ぶちぶちっという筋繊維が引きちぎられるような音がして、アングラマウスは自分の体に空いた穴を広げるだけ広げてから、動かなくなった。
その異常な光景に、俺たちはしばらく言葉を失っていた。
獰猛という言葉では片づけられないほど、異常な相手への執着心。
それは、先程まで相手をしてきたアングラマウスとは、別の魔物にしか見えなかった。
しかし、【鑑定】の解析結果には、何度見ても『アングラマウス』と表示されていた。
「……どうなってんだ」
心から漏れたようなその声は、静かなダンジョンの中でよく響いていた。