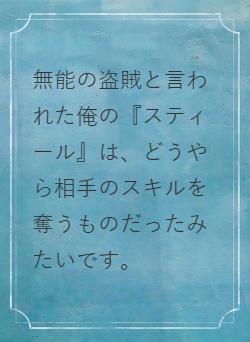「ギルド長のガリアさんから、アイクさんの予定を押さえてと言われて、理由聞いたら色々と聞かされたくない内容をしゃべられました!」
イリスの護衛の依頼が無事に終わって、少し経った頃。
ハンスから個人的なお礼として、高そうな酒が十数本送られてきた。
報奨金としてたんまりお金を貰うことになるのだから、別に気を遣わなくてもいいのだが、酒屋に台車を引かせて屋敷まで持ってこられてしまうと、それを断るのも失礼な気がして、そのお礼を受け取ることにした。
その酒をリリと二人だけで飲み干すことは出来ないと判断したので、夕方からいつもの面々を集めてお酒を飲みかわすことにしたのだった。
そして、リリの手料理がずらりと並ぶ中、度数の高いお酒を呷ったミリアは開口一番そんな言葉を口にしたのだった。
「ああ。やっぱり、巻き込まれたんですね」
「普通、一介のギルド職員に頼みませんよ。なんでそんな裏の政治事情聞かされなくちゃならないんですかっ」
どうやら、ミリアは意図しない形で俺の護衛の依頼について聞かされたらしい。おそらく、結構なプレッシャーだったとは思う。
裏で戦争が始まろうとしているなんて知らされたら、誰にも言えないしプレッシャーも感じるよな、普通は。
まぁ、依頼の中身を知らされたところで逃げたりはしなかったと思うが、それでもプレッシャーには感じるだろう。
愚痴を言い出すような口調で話し始めたのだが、ミリアはハンスが持ってきてくれたお酒が美味しかったのか、すぐに不満げな表情を和らげていた。
……いや、そこまでプレッシャーでもなかったのかな?
「ていうか、それって言っちゃっていいんですか?」
ワルド王国と戦争になろうとしていたことは、表向きにはまだ公表していないんじゃないか?
そう思ってバングとイーナにちらりと視線を向けたが、二人は特に驚くような顔もせずにリリの作った料理に舌鼓を打っていた。
「あれ? 二人とも知ってたんですか?」
二人の反応があまりにも薄かったので小首を傾げながら聞いてみると、口の中いっぱいに食べ物を入れてしまったイーナの代わりに、バングが口を開いた。
「もう知らない奴なんていないだろ。今やミノラルはその噂で持ち切りだぞ」
「あー、やっぱり、そうですよね」
「『恐怖の道化師』。ミノラルに手を出そうとしたワルド王国の騎士たちは、道化師の姿をした悪魔によって、精神と肉体をズタボロにされて、地獄に引きずり込まれたのだった、って話だったか?」
「……はい?」
バングは噂話を思い出すような口調で、そんな言葉を真剣な顔で口にしていた。
当然、地獄に引きずり込んだ覚えはないし、それだとその道化師は地獄に棲んでいることにならないか?
俺が知らない内容の噂に対して、思わず固まってしまっていると、口に入れていた食べ物を呑み込んだイーナが小首を傾げてから口を開いた。
「あら? 私は可愛らしい少女が誘拐犯の精神を壊したあと、ワルド王国の騎士たちの神経を生きたまま引き抜いて、毒ガスを巻いて去ったって聞いたけど。だから、ワルド王国は戦力を失ったって」
「え、待ってくれ。怖すぎないか、その話」
イーナの方の話に至っては半分以上作り話になっている。尾びれ背びれどころの騒ぎではない気がするんだが。
しかし、俺の最もな指摘に対して二人は真顔で言葉を続けた。
「「だって、『恐怖の道化師』だし」」
「いや……さすがに恐怖が過ぎるでしょ」
二人で声を揃えてそんなことを言われてしまい、俺は少しだけ肩を落としてしまった。
まぁ、これでミノラルが安全になるならいいのかもしれないけど、話がただのホラーではなくて、スプラッター的な要素が入っていて怖い。
さすがに根も葉もない噂……でもないのが質が悪いな。
でも、精神は壊れていないと思うぞ。ワルド王国の王から手紙が来たらしいし。
「それで、その、『恐怖の道化師』の正体って、アイクなのか?」
「た、多分?」
一瞬、誤魔化そうとしたが、おそらく流れ的に誤魔化すのは不可能だろう。
それなら認めてしまった方がいいかと思ってそう言ったのだが、その瞬間、俺とリリとポチ以外の全員の肩がビクンと跳ねた。
あれ? 何か空気が変わった気がする。
そう思っていると、イーナが生唾を呑み込んで意を決するような表情で言葉を口にした。
「まさかアイク君がそこまでやるとはね……。でも、ちゃんと何か理由があったのよね?」
「ああ。バケモノ染みた強さだとは思っていたが、まさか、そこまでとは。だが、アイクは多くの被害を出さないために、ワルド王国の騎士たちを殲滅させたんだよな? 大丈夫だ、俺たちは分かっているからな」
「もちろんですよ、私も信じます。アイクさんはミノラルのギルドの大事な冒険者です。……で、ですから、この話は聞かなかったことにして、別の話をしましょうよ」
……ん?
なぜか俺を慰めるような、気を遣っているような雰囲気が漂っている気がして、俺は少しだけ会話を振り返って考えてみることにした。
しかし、その際中も何か優しい視線を向けられている。なんというか、無条件に優しいような視線だった。
そこで、俺は大きな誤解を招いていることに気がついた。
「いやっ、違いますから! そんな噂みたいな惨いことはしてないですから!」
向けられていた視線は、俺が仕方なくワルドの騎士たちを殺戮したことを慰めてくれているものだった。
俺が苦しみながらも、止むを得ず噂通りの行動をしたかのような反応。
気を遣うような優しい態度を前に、俺は必死にその噂の真相について弁解したのだった。
どうやら、俺の知らない所で、噂は想像よりも大きな尾びれと背びれを手に入れていたようだった。
イリスの護衛の依頼が無事に終わって、少し経った頃。
ハンスから個人的なお礼として、高そうな酒が十数本送られてきた。
報奨金としてたんまりお金を貰うことになるのだから、別に気を遣わなくてもいいのだが、酒屋に台車を引かせて屋敷まで持ってこられてしまうと、それを断るのも失礼な気がして、そのお礼を受け取ることにした。
その酒をリリと二人だけで飲み干すことは出来ないと判断したので、夕方からいつもの面々を集めてお酒を飲みかわすことにしたのだった。
そして、リリの手料理がずらりと並ぶ中、度数の高いお酒を呷ったミリアは開口一番そんな言葉を口にしたのだった。
「ああ。やっぱり、巻き込まれたんですね」
「普通、一介のギルド職員に頼みませんよ。なんでそんな裏の政治事情聞かされなくちゃならないんですかっ」
どうやら、ミリアは意図しない形で俺の護衛の依頼について聞かされたらしい。おそらく、結構なプレッシャーだったとは思う。
裏で戦争が始まろうとしているなんて知らされたら、誰にも言えないしプレッシャーも感じるよな、普通は。
まぁ、依頼の中身を知らされたところで逃げたりはしなかったと思うが、それでもプレッシャーには感じるだろう。
愚痴を言い出すような口調で話し始めたのだが、ミリアはハンスが持ってきてくれたお酒が美味しかったのか、すぐに不満げな表情を和らげていた。
……いや、そこまでプレッシャーでもなかったのかな?
「ていうか、それって言っちゃっていいんですか?」
ワルド王国と戦争になろうとしていたことは、表向きにはまだ公表していないんじゃないか?
そう思ってバングとイーナにちらりと視線を向けたが、二人は特に驚くような顔もせずにリリの作った料理に舌鼓を打っていた。
「あれ? 二人とも知ってたんですか?」
二人の反応があまりにも薄かったので小首を傾げながら聞いてみると、口の中いっぱいに食べ物を入れてしまったイーナの代わりに、バングが口を開いた。
「もう知らない奴なんていないだろ。今やミノラルはその噂で持ち切りだぞ」
「あー、やっぱり、そうですよね」
「『恐怖の道化師』。ミノラルに手を出そうとしたワルド王国の騎士たちは、道化師の姿をした悪魔によって、精神と肉体をズタボロにされて、地獄に引きずり込まれたのだった、って話だったか?」
「……はい?」
バングは噂話を思い出すような口調で、そんな言葉を真剣な顔で口にしていた。
当然、地獄に引きずり込んだ覚えはないし、それだとその道化師は地獄に棲んでいることにならないか?
俺が知らない内容の噂に対して、思わず固まってしまっていると、口に入れていた食べ物を呑み込んだイーナが小首を傾げてから口を開いた。
「あら? 私は可愛らしい少女が誘拐犯の精神を壊したあと、ワルド王国の騎士たちの神経を生きたまま引き抜いて、毒ガスを巻いて去ったって聞いたけど。だから、ワルド王国は戦力を失ったって」
「え、待ってくれ。怖すぎないか、その話」
イーナの方の話に至っては半分以上作り話になっている。尾びれ背びれどころの騒ぎではない気がするんだが。
しかし、俺の最もな指摘に対して二人は真顔で言葉を続けた。
「「だって、『恐怖の道化師』だし」」
「いや……さすがに恐怖が過ぎるでしょ」
二人で声を揃えてそんなことを言われてしまい、俺は少しだけ肩を落としてしまった。
まぁ、これでミノラルが安全になるならいいのかもしれないけど、話がただのホラーではなくて、スプラッター的な要素が入っていて怖い。
さすがに根も葉もない噂……でもないのが質が悪いな。
でも、精神は壊れていないと思うぞ。ワルド王国の王から手紙が来たらしいし。
「それで、その、『恐怖の道化師』の正体って、アイクなのか?」
「た、多分?」
一瞬、誤魔化そうとしたが、おそらく流れ的に誤魔化すのは不可能だろう。
それなら認めてしまった方がいいかと思ってそう言ったのだが、その瞬間、俺とリリとポチ以外の全員の肩がビクンと跳ねた。
あれ? 何か空気が変わった気がする。
そう思っていると、イーナが生唾を呑み込んで意を決するような表情で言葉を口にした。
「まさかアイク君がそこまでやるとはね……。でも、ちゃんと何か理由があったのよね?」
「ああ。バケモノ染みた強さだとは思っていたが、まさか、そこまでとは。だが、アイクは多くの被害を出さないために、ワルド王国の騎士たちを殲滅させたんだよな? 大丈夫だ、俺たちは分かっているからな」
「もちろんですよ、私も信じます。アイクさんはミノラルのギルドの大事な冒険者です。……で、ですから、この話は聞かなかったことにして、別の話をしましょうよ」
……ん?
なぜか俺を慰めるような、気を遣っているような雰囲気が漂っている気がして、俺は少しだけ会話を振り返って考えてみることにした。
しかし、その際中も何か優しい視線を向けられている。なんというか、無条件に優しいような視線だった。
そこで、俺は大きな誤解を招いていることに気がついた。
「いやっ、違いますから! そんな噂みたいな惨いことはしてないですから!」
向けられていた視線は、俺が仕方なくワルドの騎士たちを殺戮したことを慰めてくれているものだった。
俺が苦しみながらも、止むを得ず噂通りの行動をしたかのような反応。
気を遣うような優しい態度を前に、俺は必死にその噂の真相について弁解したのだった。
どうやら、俺の知らない所で、噂は想像よりも大きな尾びれと背びれを手に入れていたようだった。