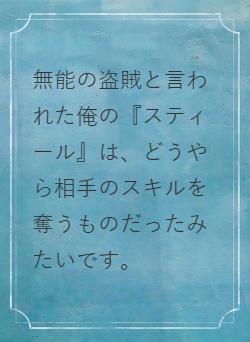「おい、どこだここは」
盾を構えているタルネスは不安の色を押し殺しながら、俺たちにそんな言葉を投げかけてきた。
当然、俺たちがその疑問に対する答えを持っている訳がなく、誰もそれに対する返答をしようとしなかった。
その後ろではただ不安を煽るような音楽だけが流れて、心臓を嫌な速度にさせてくる。
その状況に耐えられなくなったのか、タルネスは質問に対する答えを求めて視線を舞台上へと向けた。
そこには、先程通りこちらに会釈をしているあいつの姿がーーなかった。
「……何してんだ、あいつは」
先程までいたステージ上にあいつの姿はなかった。今は舞台の上空。端と端を繋ぐように張られたロープの上にあいつはいた。
そして、その下には、剣山のように切っ先を上に向いた状態で固定されている無数の短剣があった。
長い棒を持ちながらフラフラとその綱を渡っていく様子は、サーカスそのものなのに、あいつの足取りはぎこちなかった。
不慣れな足取りで無数の短剣の上まで綱を渡ってくると、そこで丁度バランスを崩したように、あいつは足を滑らせた。
そして、そのままそいつは落下して、無数の短剣に体を串刺しにされた。
「うわっ」
予期しないタイミングで見せつけられたグロイ映像を前に、誰かがそんな言葉を漏らした。
声に出さないまでも、俺だって驚きを隠せなかった。
「……何がしたいんだよ」
盗賊職のレルドがため息まじりにそんな言葉を漏らして、舞台の方に向かって行った。それに倣う形で俺たちも舞台上へと集まっていくと、そこにあったのはあいつの死体だった。
ピクリとも動かないそれは、体にいくつもの短剣が突き刺さって即死の状態だった。
全力を出させると意気込んでいたというのに、思いもしない幕引きだ。
後味の悪さと、奇妙に鳴り続けるオルゴールを前に、俺は何とも言い難い感情から顔を歪ませられていた。
「あれ? ……こいつ、ボアロじゃないか?」
「ボアロ? 何言ってんだ、どこをどう見たらこいつがボアロにーー」
倒れているあいつを見ていると、急にレルドとタルネスが訳の分からないことを言い始めた。
何か恐怖に歪んだような口調で話す二人の会話に小首を傾げながら、俺はじっとそのそいつの死体を見ていた。
どこからどう見ても、ボアロには見えない。そもそも服装も違うし、顔だって違う。
……顔?
確か、あいつは仮面をつけていたはずだから、顔が見えるなんてことはおかしい。いや、そもそもあいつはこんな顔をしていたか? こんな服装をしていたか?
これじゃあ、まるでーー
「ボアロだ」
そこに倒れていたのは、疑う余地もないボアロの姿だった。
「ボアロ? は? なんでボアロが死んでんだ?」
レルドは目の前の事態を呑み込めず、ただその声を震わせていた。そんな反応になるのも当然だ。
ここにいる誰もが、目の前の事態についていけなくなっているのだから。
いや、それだとさっきまですぐ近くにいたボアロは誰なんだ?
そこまで考えたところで、俺はハッと顔を上げていた。
その正体に気づいて、俺は急いでレルドの後ろにいたあいつに視線を向けた。しかし、俺がそれに気づいて動き出すよりも早く、あいつは動き出していた。
「避けろ! レルド!!」
「え、避けるって何をーー」
そして、レルドが言葉を言いきるよりも早く、あいつは姿見鏡のような物でレルドの後頭部を思いっきりぶん殴った。
「は?」
しかし、その姿見鏡は割れることはなかった。
その代わり、レルドの姿が消えた。
手品のように急に目の前から人が消えた。タネも仕掛けも臭わせない華麗な手さばきでレルドの姿を消したあいつは、その抱えていた姿見鏡をこちらに見せびらかすように見せてきた。
そこには消えたと思っていたレルドの姿があった。
「か、鏡の中に? 嘘だろ?」
タルネスはすぐ隣にいたレルドが鏡に閉じ込められている様を見て、言葉を震わせていた。
出してくれと必死に訴えかけるように鏡を叩いているレルド姿が映し出されており、その様子を見てご満悦な様子のあいつが鏡を片手に立っていた。
手品なんて可愛らしい物ではない。鏡に捕らわれている気が狂いだしそうなレルドの姿を見て、それを確信した。
「くそがっ! 何をしやがった!」
「やめなさい! タルネス!!」
冷静さを欠いたタルネスを止めようとオードが声を出したが、タルネスはそのまま隣にいるあいつに掴みかかろうとしてしまった。
それを見たそいつは、姿見鏡を反対向きにして、それでタルネスをぶん殴った。そして、その衝撃を受けた姿見鏡は大きな音を立てて粉々に割れてしまった。
「……っ」
頭を殴られた衝撃はただ頭から血を流すだけだったが、それよりも目の前の景色を前にタルネスは言葉を失っていた。
レルドが捕らえられていた鏡が粉々に砕けた。その意味が分からないはずがなかった。
「れ、レルド? 俺が殺したのか? レルドを俺が……」
タルネスが力なくあいつに視線を向けると、あいつは手のひらを口元に持っていき、大袈裟に驚く素振りを見せた。
その反応を見て、何かが確信に変わってうな垂れるタルネスの姿を見て、そいつはケタケタと笑い声をあげていた。
やがて、タルネスが力なく顔を上げると、そいつは右手の人差し指を立てて左右に振った後、ラルドを指さした。
突然指を指されたラルドは苛立ちを露にして、肩にかけていた大剣を片手で持ち上げて上段に構えた。
そのままあいつの頭をかち割るように大剣を振り下ろそうとしたところで、不意にその手を止めた。
「うおぉえっ!!」
そして、そのままステージ上で吐しゃ物を吐き出した。
突然吐き出したラルドの様子に驚き、その場にいたあいつ以外が舞台上に漂う酸っぱい匂いに顔を歪めていた。
当然、俺もそこに含まれるわけで、俺はその吐しゃ物からすぐに目を背けた。
「……レルドだ」
「は? お、おい、タルネス。おまえ、何言ってんだ?」
目が座ってしまった状態のタルネスが何を見たのか、俺の位置からは見えなかった。しかし、それを吐き出したラルドまでもが顔を真っ青にさせていた。
人間から人間が吐き出されることなんてあるはずがない。だから、そこにはさっきまでいたレルドの姿があるなんてことはあり得ないのだ。
それは分かっている。分かっているのだが、なぜこんなに血の気が引いてしまっているのか。
それは分かってはならないはずだった。
「タルネス! ラルド! しっかりしなさい! 気をしっかり持たないと、すぐにあなた達もーー」
オードが二人にそう呼び掛けた瞬間、あいつが急に手拍子を始めた。
音楽に合わせて、何かの登場を促すようなリズミカルな手拍子。その音を前に俺たちは何が起こるのか、何をされるのか恐怖で心を震わせていた。
そして、照明がぱっと俺たちの後方を照らしたのを見て、俺たちの視線はそこに集められた。
しかし、何もない観客席に向けられたライトは、ただ宙を舞う埃を照らすだけだった。
いつの間にかその手拍子も鳴りやんでいて、何も起こらなかったことにどこ安心していた。
「驚かせやがって……」
胸を撫で下ろして振り返ってみると、そこにはタルネスとラルドの姿がなくなっていた。
代わりに、その二人を包み込むほど大きな影からできたような両手が、二人のいた場所に現れていた。
強く両手を握りつぶすようにぐりぐりっと何かを押し潰すと、その何かを持った状態でその影はステージの裏側へとはけていった。
「くっ!」
それを見たオードは、勢いに任せるように矢を数発あいつに打ち込んだ。着弾するなりその矢は爆発を引き起こして、それをもろに食らったあいつは、そのまま力なく前のめりに倒れた。
「ラルド! 気をしっかり持たないと、あなたもやられますよ!!」
声を震わせながらそんな言葉を口にしたオードは、そいつが倒れているというのに、何度も矢を放っていた。
気が狂ったように、何度も何度も何度も何度も何度も。
肩で息をしながら何度も矢を放ち、ステージ上には爆炎が上がっていた。爆発によって焼かれた体と服は黒く焦げて、その顔にあった眼鏡のフレームまでもが溶けてーー。
眼鏡?
「……くそっ、悪い夢でも見てるみたいだな」
振り向いた先にいたのは、先程まで隣にいたオードではなく、目元から赤いインクを垂らしている仮面をつけたあいつの姿だった。
俺の顔を見てケタケタと笑うあいつに切っ先を向けてみても、あいつは特に動こうとはしなかった。
まるで、これから何をされても、この先の決着が変わることはないことを確信しているようだった。
「……最後は、剣士らしく死ぬか」
俺は誰に聞かせるわけでもなくそう呟くと、あいつに向けた切っ先を一度引っ込めて、刀を構え直した。
刀の震えを押さえ込むように深呼吸を深くして、ただ一振りすることに集中して、俺は人生最後の一振りをしたのだった。
「……っくそ」
再び目を覚ますと、俺たちは屋敷の前に転がっていた。
重い瞼を無理やり開いて、俺はそこに広がる景色を見た。
俺が見たのは倒れる俺たちと、仮面をつけているあいつの姿だけだった。
先程までいたサーカスの円形劇場のような場所はどこにもなくて、ただ悲しく聞こえるようなオルゴールの音を聞いて、空を見上げている奇妙な仮面をつけたあいつの姿があるだけだった。
せっかく悪夢のような時間が去ったというのに、俺は再び瞼を閉じようとしていた。今度目を閉じたら、おそらく目覚めることはないのだろう。
そこまで分かっていながら、重くなっていく瞼に耐えられず、俺は静かにそのまま瞼を閉じてしまった。
あいつに全力を出させることができた。叩き潰すことはできなかったが、今は少しだけ清々しい気持ちがあった。
あれが本当に夢だったのか、現実だったのか。それは最後の最後まで分からなかった。
俺たちは、俺はあいつに負けたのだな。
そんなふうに敗北を受け入れながら、俺はそっと深い眠りについたのだった。
盾を構えているタルネスは不安の色を押し殺しながら、俺たちにそんな言葉を投げかけてきた。
当然、俺たちがその疑問に対する答えを持っている訳がなく、誰もそれに対する返答をしようとしなかった。
その後ろではただ不安を煽るような音楽だけが流れて、心臓を嫌な速度にさせてくる。
その状況に耐えられなくなったのか、タルネスは質問に対する答えを求めて視線を舞台上へと向けた。
そこには、先程通りこちらに会釈をしているあいつの姿がーーなかった。
「……何してんだ、あいつは」
先程までいたステージ上にあいつの姿はなかった。今は舞台の上空。端と端を繋ぐように張られたロープの上にあいつはいた。
そして、その下には、剣山のように切っ先を上に向いた状態で固定されている無数の短剣があった。
長い棒を持ちながらフラフラとその綱を渡っていく様子は、サーカスそのものなのに、あいつの足取りはぎこちなかった。
不慣れな足取りで無数の短剣の上まで綱を渡ってくると、そこで丁度バランスを崩したように、あいつは足を滑らせた。
そして、そのままそいつは落下して、無数の短剣に体を串刺しにされた。
「うわっ」
予期しないタイミングで見せつけられたグロイ映像を前に、誰かがそんな言葉を漏らした。
声に出さないまでも、俺だって驚きを隠せなかった。
「……何がしたいんだよ」
盗賊職のレルドがため息まじりにそんな言葉を漏らして、舞台の方に向かって行った。それに倣う形で俺たちも舞台上へと集まっていくと、そこにあったのはあいつの死体だった。
ピクリとも動かないそれは、体にいくつもの短剣が突き刺さって即死の状態だった。
全力を出させると意気込んでいたというのに、思いもしない幕引きだ。
後味の悪さと、奇妙に鳴り続けるオルゴールを前に、俺は何とも言い難い感情から顔を歪ませられていた。
「あれ? ……こいつ、ボアロじゃないか?」
「ボアロ? 何言ってんだ、どこをどう見たらこいつがボアロにーー」
倒れているあいつを見ていると、急にレルドとタルネスが訳の分からないことを言い始めた。
何か恐怖に歪んだような口調で話す二人の会話に小首を傾げながら、俺はじっとそのそいつの死体を見ていた。
どこからどう見ても、ボアロには見えない。そもそも服装も違うし、顔だって違う。
……顔?
確か、あいつは仮面をつけていたはずだから、顔が見えるなんてことはおかしい。いや、そもそもあいつはこんな顔をしていたか? こんな服装をしていたか?
これじゃあ、まるでーー
「ボアロだ」
そこに倒れていたのは、疑う余地もないボアロの姿だった。
「ボアロ? は? なんでボアロが死んでんだ?」
レルドは目の前の事態を呑み込めず、ただその声を震わせていた。そんな反応になるのも当然だ。
ここにいる誰もが、目の前の事態についていけなくなっているのだから。
いや、それだとさっきまですぐ近くにいたボアロは誰なんだ?
そこまで考えたところで、俺はハッと顔を上げていた。
その正体に気づいて、俺は急いでレルドの後ろにいたあいつに視線を向けた。しかし、俺がそれに気づいて動き出すよりも早く、あいつは動き出していた。
「避けろ! レルド!!」
「え、避けるって何をーー」
そして、レルドが言葉を言いきるよりも早く、あいつは姿見鏡のような物でレルドの後頭部を思いっきりぶん殴った。
「は?」
しかし、その姿見鏡は割れることはなかった。
その代わり、レルドの姿が消えた。
手品のように急に目の前から人が消えた。タネも仕掛けも臭わせない華麗な手さばきでレルドの姿を消したあいつは、その抱えていた姿見鏡をこちらに見せびらかすように見せてきた。
そこには消えたと思っていたレルドの姿があった。
「か、鏡の中に? 嘘だろ?」
タルネスはすぐ隣にいたレルドが鏡に閉じ込められている様を見て、言葉を震わせていた。
出してくれと必死に訴えかけるように鏡を叩いているレルド姿が映し出されており、その様子を見てご満悦な様子のあいつが鏡を片手に立っていた。
手品なんて可愛らしい物ではない。鏡に捕らわれている気が狂いだしそうなレルドの姿を見て、それを確信した。
「くそがっ! 何をしやがった!」
「やめなさい! タルネス!!」
冷静さを欠いたタルネスを止めようとオードが声を出したが、タルネスはそのまま隣にいるあいつに掴みかかろうとしてしまった。
それを見たそいつは、姿見鏡を反対向きにして、それでタルネスをぶん殴った。そして、その衝撃を受けた姿見鏡は大きな音を立てて粉々に割れてしまった。
「……っ」
頭を殴られた衝撃はただ頭から血を流すだけだったが、それよりも目の前の景色を前にタルネスは言葉を失っていた。
レルドが捕らえられていた鏡が粉々に砕けた。その意味が分からないはずがなかった。
「れ、レルド? 俺が殺したのか? レルドを俺が……」
タルネスが力なくあいつに視線を向けると、あいつは手のひらを口元に持っていき、大袈裟に驚く素振りを見せた。
その反応を見て、何かが確信に変わってうな垂れるタルネスの姿を見て、そいつはケタケタと笑い声をあげていた。
やがて、タルネスが力なく顔を上げると、そいつは右手の人差し指を立てて左右に振った後、ラルドを指さした。
突然指を指されたラルドは苛立ちを露にして、肩にかけていた大剣を片手で持ち上げて上段に構えた。
そのままあいつの頭をかち割るように大剣を振り下ろそうとしたところで、不意にその手を止めた。
「うおぉえっ!!」
そして、そのままステージ上で吐しゃ物を吐き出した。
突然吐き出したラルドの様子に驚き、その場にいたあいつ以外が舞台上に漂う酸っぱい匂いに顔を歪めていた。
当然、俺もそこに含まれるわけで、俺はその吐しゃ物からすぐに目を背けた。
「……レルドだ」
「は? お、おい、タルネス。おまえ、何言ってんだ?」
目が座ってしまった状態のタルネスが何を見たのか、俺の位置からは見えなかった。しかし、それを吐き出したラルドまでもが顔を真っ青にさせていた。
人間から人間が吐き出されることなんてあるはずがない。だから、そこにはさっきまでいたレルドの姿があるなんてことはあり得ないのだ。
それは分かっている。分かっているのだが、なぜこんなに血の気が引いてしまっているのか。
それは分かってはならないはずだった。
「タルネス! ラルド! しっかりしなさい! 気をしっかり持たないと、すぐにあなた達もーー」
オードが二人にそう呼び掛けた瞬間、あいつが急に手拍子を始めた。
音楽に合わせて、何かの登場を促すようなリズミカルな手拍子。その音を前に俺たちは何が起こるのか、何をされるのか恐怖で心を震わせていた。
そして、照明がぱっと俺たちの後方を照らしたのを見て、俺たちの視線はそこに集められた。
しかし、何もない観客席に向けられたライトは、ただ宙を舞う埃を照らすだけだった。
いつの間にかその手拍子も鳴りやんでいて、何も起こらなかったことにどこ安心していた。
「驚かせやがって……」
胸を撫で下ろして振り返ってみると、そこにはタルネスとラルドの姿がなくなっていた。
代わりに、その二人を包み込むほど大きな影からできたような両手が、二人のいた場所に現れていた。
強く両手を握りつぶすようにぐりぐりっと何かを押し潰すと、その何かを持った状態でその影はステージの裏側へとはけていった。
「くっ!」
それを見たオードは、勢いに任せるように矢を数発あいつに打ち込んだ。着弾するなりその矢は爆発を引き起こして、それをもろに食らったあいつは、そのまま力なく前のめりに倒れた。
「ラルド! 気をしっかり持たないと、あなたもやられますよ!!」
声を震わせながらそんな言葉を口にしたオードは、そいつが倒れているというのに、何度も矢を放っていた。
気が狂ったように、何度も何度も何度も何度も何度も。
肩で息をしながら何度も矢を放ち、ステージ上には爆炎が上がっていた。爆発によって焼かれた体と服は黒く焦げて、その顔にあった眼鏡のフレームまでもが溶けてーー。
眼鏡?
「……くそっ、悪い夢でも見てるみたいだな」
振り向いた先にいたのは、先程まで隣にいたオードではなく、目元から赤いインクを垂らしている仮面をつけたあいつの姿だった。
俺の顔を見てケタケタと笑うあいつに切っ先を向けてみても、あいつは特に動こうとはしなかった。
まるで、これから何をされても、この先の決着が変わることはないことを確信しているようだった。
「……最後は、剣士らしく死ぬか」
俺は誰に聞かせるわけでもなくそう呟くと、あいつに向けた切っ先を一度引っ込めて、刀を構え直した。
刀の震えを押さえ込むように深呼吸を深くして、ただ一振りすることに集中して、俺は人生最後の一振りをしたのだった。
「……っくそ」
再び目を覚ますと、俺たちは屋敷の前に転がっていた。
重い瞼を無理やり開いて、俺はそこに広がる景色を見た。
俺が見たのは倒れる俺たちと、仮面をつけているあいつの姿だけだった。
先程までいたサーカスの円形劇場のような場所はどこにもなくて、ただ悲しく聞こえるようなオルゴールの音を聞いて、空を見上げている奇妙な仮面をつけたあいつの姿があるだけだった。
せっかく悪夢のような時間が去ったというのに、俺は再び瞼を閉じようとしていた。今度目を閉じたら、おそらく目覚めることはないのだろう。
そこまで分かっていながら、重くなっていく瞼に耐えられず、俺は静かにそのまま瞼を閉じてしまった。
あいつに全力を出させることができた。叩き潰すことはできなかったが、今は少しだけ清々しい気持ちがあった。
あれが本当に夢だったのか、現実だったのか。それは最後の最後まで分からなかった。
俺たちは、俺はあいつに負けたのだな。
そんなふうに敗北を受け入れながら、俺はそっと深い眠りについたのだった。