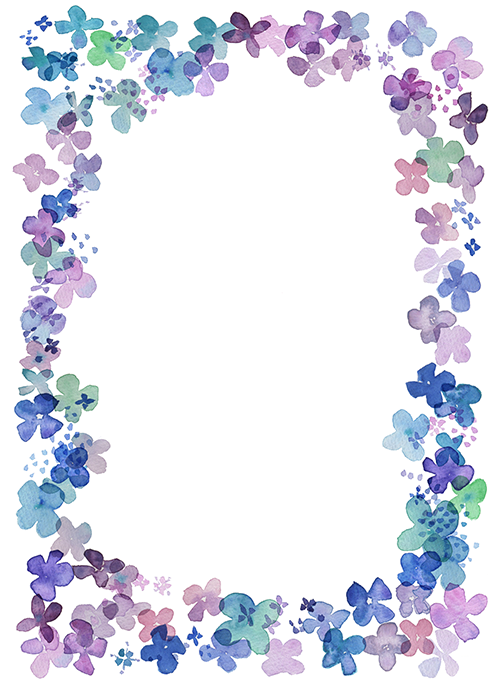「ぴーくにーっく!!!ゆお、たのしみすぎてふるえてる」
そう言って膝をガクガクさせながら飛び込んできた結織を抱きとめる。最近、話せる言葉がどんどん増えてきて日々感情豊かになる結織を微笑ましく思いながら俺は頷いた。
「そうだな。楽しみだな」
「ぱるくんは何がすきー?」
「何って?」
「お弁当のなかみ!」
結織がいる生活にも段々と馴染んできた。結織がいるからこそ、俺は今まっとうに生きれているのかもしれない。あの日、むすびのいた部屋に引っ越してきた結織を見捨てずに向き合えてよかった。心からそう思う。
君がいないのは少し、心が痛むけれど。
「俺は無難におにぎりが好きだ。鮭がいい」
「えぇー?!ゆお、しゃけさん苦手ー。ゆおはね、あまいたまごまきまきが好きだよ!」
「あぁ、卵焼き。ワカに頼めば作ってくれるんじゃないか?」
「そんじゃ、今すぐワカにぃのとこ行こ!」
俺の腕で暴れていた小さな体はするりとすり抜けて、小さな掌でスーツの裾を引っ張る。
そうだな、ワカのところに行ってお弁当をこしらえてもらおう。
それと甘い卵焼きの作り方も教わろう。知っておけば、また結織に作ってあげられるし。
そんな考えが自然と湧きだしたことに気づいた俺は、胸があたたかくなった。
なんだ、俺。線引きする必要なんてなかったんだ。負い目を感じることも、人から一歩後ろを歩む必要もなかったんだ。
誰かのためにしてあげたいって思える心、ちゃんとあったんだ。
それを気づかせてくれたのは、君の代わりに現れた嵐のような少女だった。
「さぁ、いこ!ぱるくん!」
『さぁ行こう、こんぱる!』
俺を引く手の大きさは違うけれど、俺を前へと進める力は同じくらい強かった。
きっと俺はこれからもふとしたことでまた愛しい人を思い出すのだろう。そんな時にどうか君に誇れる自分でありたいと願う。一歩でも十歩でも百歩でも俺の足で、俺だけの道のりで、前へと進んでいたい。
そしてまたいつか会う時にはちゃんと隣で歩めるように。もう、手は引いてもらわなくても大丈夫だよと肩を並べながら繋がり合う手のぬくもりを感じて一緒に生きたい。
だからそれまでは、
「結織、走るか」
大人ぶって、この小さな手が迷わないように引いてあげるんだ。
明るい方へ、煌めく方へ、回り道も時々しよう。俺の方が迷って立ち止まってしまうかもしれない。
それでも最後は笑えるように、小さな手が華奢な大人の手になるまで、俺はこの手を離さないだろう。
「その前に結織」
「んー?」
「これから先、大変なこともあるかもしれない。俺がうざくなってこんな奴と一緒にいたくないって思ったり、俺が口出しして喧嘩もするかもしれない。
それでも絶対に幸せにしてみせる。ずっとは笑えなくても、きっとお前が大人になったとき昔のことを思い出すと笑顔だった思い出しかないって言わせてみせる。
だから。……だから、お前が成長するまで、俺がそれを見届けていいか?」
なんて幼い結織に言っても最初の一文すら理解できないか。
困惑した顔の少女と必死な俺の間にひゅうっと風が通り過ぎていく。
「やっぱり忘れてくれ」、そう言おうとしたとき、うーんと唸っていた少女がとことこと近づいてきて、唐突にぎゅっと俺の足に腕を回した。
「ゆお、むずかしいことばわかんない。けど……ぱるくんとずっと一緒がいいよ」
本当か
嬉しかった。拙い言葉で、自分が知っている精一杯の言葉で、想いを伝えてくれたことが何物にも代えがたい幸福だった。
声が震える。しっかりしなくちゃいけないのに、俺は今からこの子の親なのに。
「ぱるくん、泣いてるの?」
「……泣いてない。でもごめん、しばらく立てないかも」
脚に力が入らない。体の末端から染み渡る幸せで心も体もいっぱいいっぱいだった。そんな状況が滑稽なのか、結織は腹を抱えて笑う。俺も釣られて口角が緩んだ。
ピクニックはもうすぐだ。準備をしなくちゃ。
それだというのに今は幸せを嚙みしめるのに必死で、二人が笑い合う声は暫く絶えなかった。
そう言って膝をガクガクさせながら飛び込んできた結織を抱きとめる。最近、話せる言葉がどんどん増えてきて日々感情豊かになる結織を微笑ましく思いながら俺は頷いた。
「そうだな。楽しみだな」
「ぱるくんは何がすきー?」
「何って?」
「お弁当のなかみ!」
結織がいる生活にも段々と馴染んできた。結織がいるからこそ、俺は今まっとうに生きれているのかもしれない。あの日、むすびのいた部屋に引っ越してきた結織を見捨てずに向き合えてよかった。心からそう思う。
君がいないのは少し、心が痛むけれど。
「俺は無難におにぎりが好きだ。鮭がいい」
「えぇー?!ゆお、しゃけさん苦手ー。ゆおはね、あまいたまごまきまきが好きだよ!」
「あぁ、卵焼き。ワカに頼めば作ってくれるんじゃないか?」
「そんじゃ、今すぐワカにぃのとこ行こ!」
俺の腕で暴れていた小さな体はするりとすり抜けて、小さな掌でスーツの裾を引っ張る。
そうだな、ワカのところに行ってお弁当をこしらえてもらおう。
それと甘い卵焼きの作り方も教わろう。知っておけば、また結織に作ってあげられるし。
そんな考えが自然と湧きだしたことに気づいた俺は、胸があたたかくなった。
なんだ、俺。線引きする必要なんてなかったんだ。負い目を感じることも、人から一歩後ろを歩む必要もなかったんだ。
誰かのためにしてあげたいって思える心、ちゃんとあったんだ。
それを気づかせてくれたのは、君の代わりに現れた嵐のような少女だった。
「さぁ、いこ!ぱるくん!」
『さぁ行こう、こんぱる!』
俺を引く手の大きさは違うけれど、俺を前へと進める力は同じくらい強かった。
きっと俺はこれからもふとしたことでまた愛しい人を思い出すのだろう。そんな時にどうか君に誇れる自分でありたいと願う。一歩でも十歩でも百歩でも俺の足で、俺だけの道のりで、前へと進んでいたい。
そしてまたいつか会う時にはちゃんと隣で歩めるように。もう、手は引いてもらわなくても大丈夫だよと肩を並べながら繋がり合う手のぬくもりを感じて一緒に生きたい。
だからそれまでは、
「結織、走るか」
大人ぶって、この小さな手が迷わないように引いてあげるんだ。
明るい方へ、煌めく方へ、回り道も時々しよう。俺の方が迷って立ち止まってしまうかもしれない。
それでも最後は笑えるように、小さな手が華奢な大人の手になるまで、俺はこの手を離さないだろう。
「その前に結織」
「んー?」
「これから先、大変なこともあるかもしれない。俺がうざくなってこんな奴と一緒にいたくないって思ったり、俺が口出しして喧嘩もするかもしれない。
それでも絶対に幸せにしてみせる。ずっとは笑えなくても、きっとお前が大人になったとき昔のことを思い出すと笑顔だった思い出しかないって言わせてみせる。
だから。……だから、お前が成長するまで、俺がそれを見届けていいか?」
なんて幼い結織に言っても最初の一文すら理解できないか。
困惑した顔の少女と必死な俺の間にひゅうっと風が通り過ぎていく。
「やっぱり忘れてくれ」、そう言おうとしたとき、うーんと唸っていた少女がとことこと近づいてきて、唐突にぎゅっと俺の足に腕を回した。
「ゆお、むずかしいことばわかんない。けど……ぱるくんとずっと一緒がいいよ」
本当か
嬉しかった。拙い言葉で、自分が知っている精一杯の言葉で、想いを伝えてくれたことが何物にも代えがたい幸福だった。
声が震える。しっかりしなくちゃいけないのに、俺は今からこの子の親なのに。
「ぱるくん、泣いてるの?」
「……泣いてない。でもごめん、しばらく立てないかも」
脚に力が入らない。体の末端から染み渡る幸せで心も体もいっぱいいっぱいだった。そんな状況が滑稽なのか、結織は腹を抱えて笑う。俺も釣られて口角が緩んだ。
ピクニックはもうすぐだ。準備をしなくちゃ。
それだというのに今は幸せを嚙みしめるのに必死で、二人が笑い合う声は暫く絶えなかった。