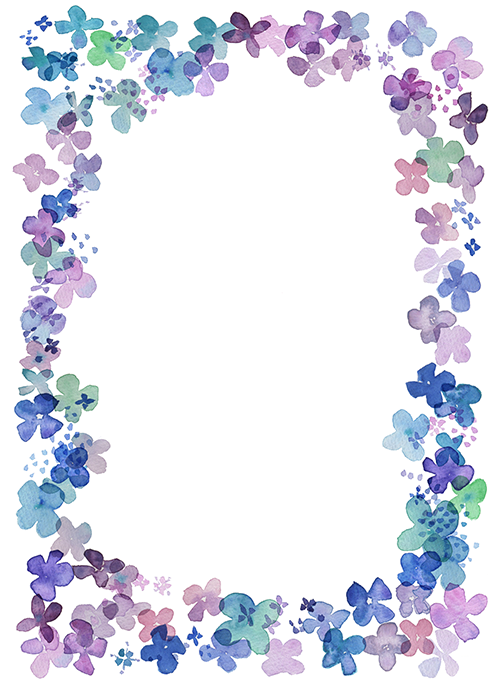誰だって失うことは怖いだろう。
けれど忘れてしまうことはもっと怖い。だって失うことは前提だからだ。物はいつかは無くなり、目の前にいた人もいつかは灰となる。分かっていることだから、怖いけれど受け止める他ない。
けれど忘却というのは、どれだけ忘れたくないと思っていても、大切にしていても、いつかは訪れる。
そこに前提などない。
忘れたくなくて、忘れてしまう未来を想像するのが怖くて、それでもいつかは認めなくてはならない。
俺は最近むすびのことを忘れてしまいそうだった。
「……ごめんな」
こういう日は決まって墓参りに行くと決めていた。むくりとベンチから立ち上がると、花屋で模造紙に花を包んでもらう。足取りはおぼつかない。こうやって会いに行くのも贖罪みたいで嫌だった。純粋な気持ちで、会いたいという衝動で、君の石に手を合わせに行っていた頃が懐かしい。胸にわだかまる黒い感情が肺を圧迫させ、息を浅くする。なんだかいつもより足取りが重い、そう感じた時だった。
「あれ、こんぱるくんだ」
聞きなれたアルトの声が後ろから聞こえる。振り返ると予想通り、色素の薄い髪をなびかせた少年が首を傾げながらそこに立っていた。
陽翔、俺は正直彼のことが苦手だった。決して嫌いではないのだ。けれど時々彼を纏う重い空気に、どう接していいのか分からなくなるときがある。きっと彼は嘘を吐くのが上手だ、背負うものの重さを誰にも気づかれないように気丈に振る舞っている。けれど、その裏で苦しんでいるのが俺にはなんとなく分かった。
「……陽翔」
「もしかして、今からむすびちゃんのとこ?」
戸惑いながら頷く俺に、彼はあたたかい瞳を細める。あぁ、だから苦手なんだ。人一倍苦しんでいるはずなのに、どうしてこんなにも優しさを持ち合わせているんだろう。あまりの眩しさに俺は目を逸らした。それから少し話した後、「僕もついて行っていい?」と聞かれたので少し迷った挙句頷くと、彼は嬉しそうに「ありがとう」と笑った。
整地されていない森を潜り抜けると、数個の墓石が並ぶ墓地にたどり着いた。定期的に掃除しているからか、どの墓石も新品のように艶を持っている。その中でもひと際綺麗な青みがかった石の前に立つと、墓石に埋め込まれているタンザナイトをそっと撫でた。
久しぶり、むすび。遅くなってごめん。
心の中で呼びかける。返事はない。
花束を添えると、今日は陽翔もいることを伝えた。陽翔はいつものように懐っこい笑みを浮かべるとひらひらと手を振る。
二人でしゃがんで手を合わせると、ゆっくり瞼を伏せる。
なぁ、最近忘れてしまいそうなんだ。
忘れたくないのに、誰よりも何よりも大切なむすびのことが時々思い出せないときがある。
君はどんな風に笑っていたっけ?どんな風に怒っていたっけ?
体というのは不思議なことに「声」から忘れていくらしい。
残念ながら俺も例外なく、今では君の鈴を鳴らしたような綺麗な声を、頭の中で再生できないんだ。
君はたくさんの言葉を俺にくれたのに、忘れないって約束したのに、最低だよな。
自虐的な笑みが零れた。約束したのに、俺。何一つ守れてない。
そんな俺に君の隣に立つ資格なんてあるんだろうか。愛してるって言う資格あるんだろうか。
無いに決まってる。だって俺は
『こんぱる……!』
突然、爪先からつむじまで全身に響いたのは俺の胸をいっぱいにさせた君の声だった。
なんで、どうして、なんて言葉より先に目尻に涙が滲む。呼吸をするので精一杯にさせた君の声は、あまりにも懐かしくて、あまりにもいとおしくて。
ふと君がいなくなった日のことを思い出す。
「俺はこれから更に苦しいことが待っているだろうな。むすびを救おうと必死になってた時より大変だと思う時期がくるかもしれない」
そんな時
もし、もう一度俺の前に現れてくれたら。
「……どうか、笑って俺の名前を呼んでくれ」
君は
君は俺との約束を覚えていたのか……?
あの時のぐちゃぐちゃだった俺の言葉をちゃんと今でも、いなくなっても、会えなくても、ちゃんと覚えていてくれたのか
「あぁくそ……本当に情けないなぁ」
誰にも聞こえないようにそっと呟く。
君には何年たったとしても敵いやしない。
うだうだ戯言を連ねていたけれど、本当に伝えたかったのは『会いたい』の四文字だけだったということにやっと気づけた。
会いたいよ、むすび。
毎朝君の姿が見えないかななんて期待してしまう。くりーむぱんを見ると美味しそうに頬張る姿を探してしまう。誰かに名前を呼ばれる度、振り返ったら君がいないかななんて浅はかな妄想をしてしまう。
本当に俺の中はどれだけ経っても君ばかりなんだ。
忘れてしまうことも時にはあるけれど、それ以上に俺に染みついた君との思い出は年月を重ねるたび色濃く残り続ける。
これはきっととんでもなく厄介な呪いだ。
いつまでもいつまでも残り続ける俺たちの幸せの呪いだ。
ようやく瞼を持ち上げる。滲んだ涙を誤魔化すように瞬きをした。
後ろで手を合わせている彼も俺と同じように悩む日がいつかは来るだろう。そのときに、今度は俺が背負うものを軽くしてやりたい。
君が俺の希望だったように、今度は俺が誰かの希望になりたい。
願いは穏やかな風に運ばれて夕焼けの空に吸い込まれていった。
けれど忘れてしまうことはもっと怖い。だって失うことは前提だからだ。物はいつかは無くなり、目の前にいた人もいつかは灰となる。分かっていることだから、怖いけれど受け止める他ない。
けれど忘却というのは、どれだけ忘れたくないと思っていても、大切にしていても、いつかは訪れる。
そこに前提などない。
忘れたくなくて、忘れてしまう未来を想像するのが怖くて、それでもいつかは認めなくてはならない。
俺は最近むすびのことを忘れてしまいそうだった。
「……ごめんな」
こういう日は決まって墓参りに行くと決めていた。むくりとベンチから立ち上がると、花屋で模造紙に花を包んでもらう。足取りはおぼつかない。こうやって会いに行くのも贖罪みたいで嫌だった。純粋な気持ちで、会いたいという衝動で、君の石に手を合わせに行っていた頃が懐かしい。胸にわだかまる黒い感情が肺を圧迫させ、息を浅くする。なんだかいつもより足取りが重い、そう感じた時だった。
「あれ、こんぱるくんだ」
聞きなれたアルトの声が後ろから聞こえる。振り返ると予想通り、色素の薄い髪をなびかせた少年が首を傾げながらそこに立っていた。
陽翔、俺は正直彼のことが苦手だった。決して嫌いではないのだ。けれど時々彼を纏う重い空気に、どう接していいのか分からなくなるときがある。きっと彼は嘘を吐くのが上手だ、背負うものの重さを誰にも気づかれないように気丈に振る舞っている。けれど、その裏で苦しんでいるのが俺にはなんとなく分かった。
「……陽翔」
「もしかして、今からむすびちゃんのとこ?」
戸惑いながら頷く俺に、彼はあたたかい瞳を細める。あぁ、だから苦手なんだ。人一倍苦しんでいるはずなのに、どうしてこんなにも優しさを持ち合わせているんだろう。あまりの眩しさに俺は目を逸らした。それから少し話した後、「僕もついて行っていい?」と聞かれたので少し迷った挙句頷くと、彼は嬉しそうに「ありがとう」と笑った。
整地されていない森を潜り抜けると、数個の墓石が並ぶ墓地にたどり着いた。定期的に掃除しているからか、どの墓石も新品のように艶を持っている。その中でもひと際綺麗な青みがかった石の前に立つと、墓石に埋め込まれているタンザナイトをそっと撫でた。
久しぶり、むすび。遅くなってごめん。
心の中で呼びかける。返事はない。
花束を添えると、今日は陽翔もいることを伝えた。陽翔はいつものように懐っこい笑みを浮かべるとひらひらと手を振る。
二人でしゃがんで手を合わせると、ゆっくり瞼を伏せる。
なぁ、最近忘れてしまいそうなんだ。
忘れたくないのに、誰よりも何よりも大切なむすびのことが時々思い出せないときがある。
君はどんな風に笑っていたっけ?どんな風に怒っていたっけ?
体というのは不思議なことに「声」から忘れていくらしい。
残念ながら俺も例外なく、今では君の鈴を鳴らしたような綺麗な声を、頭の中で再生できないんだ。
君はたくさんの言葉を俺にくれたのに、忘れないって約束したのに、最低だよな。
自虐的な笑みが零れた。約束したのに、俺。何一つ守れてない。
そんな俺に君の隣に立つ資格なんてあるんだろうか。愛してるって言う資格あるんだろうか。
無いに決まってる。だって俺は
『こんぱる……!』
突然、爪先からつむじまで全身に響いたのは俺の胸をいっぱいにさせた君の声だった。
なんで、どうして、なんて言葉より先に目尻に涙が滲む。呼吸をするので精一杯にさせた君の声は、あまりにも懐かしくて、あまりにもいとおしくて。
ふと君がいなくなった日のことを思い出す。
「俺はこれから更に苦しいことが待っているだろうな。むすびを救おうと必死になってた時より大変だと思う時期がくるかもしれない」
そんな時
もし、もう一度俺の前に現れてくれたら。
「……どうか、笑って俺の名前を呼んでくれ」
君は
君は俺との約束を覚えていたのか……?
あの時のぐちゃぐちゃだった俺の言葉をちゃんと今でも、いなくなっても、会えなくても、ちゃんと覚えていてくれたのか
「あぁくそ……本当に情けないなぁ」
誰にも聞こえないようにそっと呟く。
君には何年たったとしても敵いやしない。
うだうだ戯言を連ねていたけれど、本当に伝えたかったのは『会いたい』の四文字だけだったということにやっと気づけた。
会いたいよ、むすび。
毎朝君の姿が見えないかななんて期待してしまう。くりーむぱんを見ると美味しそうに頬張る姿を探してしまう。誰かに名前を呼ばれる度、振り返ったら君がいないかななんて浅はかな妄想をしてしまう。
本当に俺の中はどれだけ経っても君ばかりなんだ。
忘れてしまうことも時にはあるけれど、それ以上に俺に染みついた君との思い出は年月を重ねるたび色濃く残り続ける。
これはきっととんでもなく厄介な呪いだ。
いつまでもいつまでも残り続ける俺たちの幸せの呪いだ。
ようやく瞼を持ち上げる。滲んだ涙を誤魔化すように瞬きをした。
後ろで手を合わせている彼も俺と同じように悩む日がいつかは来るだろう。そのときに、今度は俺が背負うものを軽くしてやりたい。
君が俺の希望だったように、今度は俺が誰かの希望になりたい。
願いは穏やかな風に運ばれて夕焼けの空に吸い込まれていった。