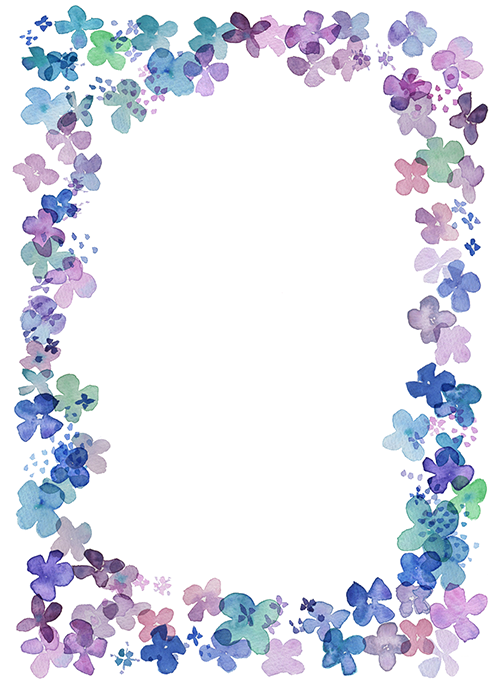激しい頭痛で目が覚めた。二重にぶれて霞む視界。起こした体は熱を持っていて、すぐに前後不覚に陥った。
「今日はどこにも行けないや」
布団から窓の外を見た。外の世界も分厚い雲が覆う曇り空で、窓には夜に降った小雨が数滴、跡を残す。何も頑張っていないのに、何もまだ出来ていないのに、すぐこうなってしまう体が嫌いだ。せっかく自由になったはずの体が鈍りのように動かない。そういえば昨日図書室で少し読んだ本の中にこんなメモが挟まれていたような気がする。
「軽い怪我はあっと言う間に治るが、体内の不調は薬を使わなければ治らないことが多い。これは人間に似た私たちの運命である……だったっけ」
耳鳴りが思考をかき乱し、また意識を朦朧とさせる。薬なんてないから今日は駄目かもしれない、もう一度寝よう。体を横たわらせると、いつの間にかまた微睡んだ。
2回目は物音で目が覚めた。ガチャと何かを閉じる音に、んん……?と薄目を開けて部屋の様子を見ると誰かがドアを引いていく影がフローリングに映る。何か盗まれたり傷つけられたりしたのかと思い辺りを見回すと、お盆が置いてありそこからいい香りが漂ってきた。自分では置いた記憶のないものだ。
「陽翔……?」
掠れた声が静かに部屋に響いた。その瞬間、ドアにいた影は驚いたように肩を揺らして後ずさりする。今にも逃げ出しそうな体制の人影。逃げられてたまるのもかと、私も出来る限り声を張り上げた。
「た、助けてくれてありがとう」
人影は踵を返すことなく立ち去る。けれど一瞬、たった一瞬だが立ち止まってこちらを振り向いたような気がした。逆光でよく見えない。目を細めると、そこには何を考えているのか分からない、どこか冷淡な印象も与える無表情な顔で立ち尽くす少女がいた。
ということは、これを運んできてくれたのは陽翔じゃない……?
視線は自然とローテーブルの上に置かれたお盆へと移動する。漆塗りのお盆の上にはおにぎりと、お茶。
「それとこれは……?」
隣には何か白いものが添えてある。ベットから手を伸ばしてそれを手に取ると、薄い和紙が折りたたまれていた。中を広げると端正な文字でシンプルにこう綴られていた。
「梅は疲労回復に効果あり。体を壊したら何も出来ません、しっかり休んでください、か……優しい人だなぁ」
凛とした文字とは反対に、内容はとても心温まるものだった。おにぎりを手に取り、一口齧る。一口目は塩の塩味と米の甘みの素朴な味。二口目には、それに加えて鼻を抜ける爽やかな酸味が口に広がった。塩辛くない、病人の胃を刺激しない酸っぱさは蜂蜜につけてあるのだろうか。
「梅干し……ふふ、本当に不器用だなぁ。直接伝えてくれればいいのに」
おにぎり一つでこんなにも幸せな気持ちになってしまう。自然と顔に微笑が浮かんだところで、忙しないノックの音が玄関から聞こえた。
「むすびちゃん、大丈夫かーい」
「陽翔!」
ゆったりと私の隣に座ったのは、黄色い髪の少年だった。少年は私の顔を除くと昨日の穏やかな表情とは少し違う心配の色を見せる。私、そんなにやつれた顔をしてるのかな。無理やり笑顔を張り付けると、彼は困ったように笑う。
「熱出たの?大変だったねぇ。調子はどう?」
「ええと、今はもう平気です!たくさん寝たら元気いっぱいに戻りました!」
「そう。それはよかったぁ」
「あんまり無理しちゃ駄目だよ。ここの住人さんは皆優しいからねぇ」
「え、」
「そう、本当に優しすぎるくらいにね。困っている声が聞こえたり、熱でうなされた声が聞こえたら放っておけない人ばかり。今日だって小梅ちゃんが教えてくれた」
小梅……。聞きなれない単語に首を傾げると陽翔は「ああ、もしかしてまだ話してないの?」と尋ねてくる。こくりと頷くと、彼は苦笑いをした。
「小梅ちゃんはね、喋るのが少し苦手なんだ。僕も数回話したことがあるだけかなぁ。でもね、とっても優しいし可愛い女の子なんだよ。今日だってむすびちゃんが体調悪いことに一番に気づいて教えてくれた」
あの少女は、小梅だったんだ。
逆光の中に一つ浮かび上がる着物を着た影が鮮明に蘇った。自分が助けたことも言わずに去っていくなんて……ずるいよ。あまりにもかっこよすぎるだろう。
陽翔がしみじみと「久しぶりに焦っているような顔、見たなぁ」と呟く。それだけ沢山尽くしてもらったんだ、迷惑も沢山かけてしまったかもしれない。彼女のことを知る度に、見ず知らずの人の為にこんなにも行動できる少女への尊敬が溢れる。
「私、いつかまた小梅に会って、この間はありがとうって言いに行きます!」
「ん、いーこいーこ。じゃあしっかり体調整えてねぇ」
陽翔は微笑みを浮かべたまま、部屋の戸を静かに閉めた。手元に残ったおにぎりの乗っていた皿と、湯呑を洗いに洗面所へ向かう。私の部屋にはキッチンが付いていない。私は料理ができないから場所をとるキッチンが設置されていないことはとてもありがたいが、何かを洗うためにはやっぱり必要なのかなぁと考えさせられる。
「あ」
ふと顔をあげると、鏡に映る自分が目に飛び込んできた。
頬の結晶が少し大きくなっていた。
「今日はどこにも行けないや」
布団から窓の外を見た。外の世界も分厚い雲が覆う曇り空で、窓には夜に降った小雨が数滴、跡を残す。何も頑張っていないのに、何もまだ出来ていないのに、すぐこうなってしまう体が嫌いだ。せっかく自由になったはずの体が鈍りのように動かない。そういえば昨日図書室で少し読んだ本の中にこんなメモが挟まれていたような気がする。
「軽い怪我はあっと言う間に治るが、体内の不調は薬を使わなければ治らないことが多い。これは人間に似た私たちの運命である……だったっけ」
耳鳴りが思考をかき乱し、また意識を朦朧とさせる。薬なんてないから今日は駄目かもしれない、もう一度寝よう。体を横たわらせると、いつの間にかまた微睡んだ。
2回目は物音で目が覚めた。ガチャと何かを閉じる音に、んん……?と薄目を開けて部屋の様子を見ると誰かがドアを引いていく影がフローリングに映る。何か盗まれたり傷つけられたりしたのかと思い辺りを見回すと、お盆が置いてありそこからいい香りが漂ってきた。自分では置いた記憶のないものだ。
「陽翔……?」
掠れた声が静かに部屋に響いた。その瞬間、ドアにいた影は驚いたように肩を揺らして後ずさりする。今にも逃げ出しそうな体制の人影。逃げられてたまるのもかと、私も出来る限り声を張り上げた。
「た、助けてくれてありがとう」
人影は踵を返すことなく立ち去る。けれど一瞬、たった一瞬だが立ち止まってこちらを振り向いたような気がした。逆光でよく見えない。目を細めると、そこには何を考えているのか分からない、どこか冷淡な印象も与える無表情な顔で立ち尽くす少女がいた。
ということは、これを運んできてくれたのは陽翔じゃない……?
視線は自然とローテーブルの上に置かれたお盆へと移動する。漆塗りのお盆の上にはおにぎりと、お茶。
「それとこれは……?」
隣には何か白いものが添えてある。ベットから手を伸ばしてそれを手に取ると、薄い和紙が折りたたまれていた。中を広げると端正な文字でシンプルにこう綴られていた。
「梅は疲労回復に効果あり。体を壊したら何も出来ません、しっかり休んでください、か……優しい人だなぁ」
凛とした文字とは反対に、内容はとても心温まるものだった。おにぎりを手に取り、一口齧る。一口目は塩の塩味と米の甘みの素朴な味。二口目には、それに加えて鼻を抜ける爽やかな酸味が口に広がった。塩辛くない、病人の胃を刺激しない酸っぱさは蜂蜜につけてあるのだろうか。
「梅干し……ふふ、本当に不器用だなぁ。直接伝えてくれればいいのに」
おにぎり一つでこんなにも幸せな気持ちになってしまう。自然と顔に微笑が浮かんだところで、忙しないノックの音が玄関から聞こえた。
「むすびちゃん、大丈夫かーい」
「陽翔!」
ゆったりと私の隣に座ったのは、黄色い髪の少年だった。少年は私の顔を除くと昨日の穏やかな表情とは少し違う心配の色を見せる。私、そんなにやつれた顔をしてるのかな。無理やり笑顔を張り付けると、彼は困ったように笑う。
「熱出たの?大変だったねぇ。調子はどう?」
「ええと、今はもう平気です!たくさん寝たら元気いっぱいに戻りました!」
「そう。それはよかったぁ」
「あんまり無理しちゃ駄目だよ。ここの住人さんは皆優しいからねぇ」
「え、」
「そう、本当に優しすぎるくらいにね。困っている声が聞こえたり、熱でうなされた声が聞こえたら放っておけない人ばかり。今日だって小梅ちゃんが教えてくれた」
小梅……。聞きなれない単語に首を傾げると陽翔は「ああ、もしかしてまだ話してないの?」と尋ねてくる。こくりと頷くと、彼は苦笑いをした。
「小梅ちゃんはね、喋るのが少し苦手なんだ。僕も数回話したことがあるだけかなぁ。でもね、とっても優しいし可愛い女の子なんだよ。今日だってむすびちゃんが体調悪いことに一番に気づいて教えてくれた」
あの少女は、小梅だったんだ。
逆光の中に一つ浮かび上がる着物を着た影が鮮明に蘇った。自分が助けたことも言わずに去っていくなんて……ずるいよ。あまりにもかっこよすぎるだろう。
陽翔がしみじみと「久しぶりに焦っているような顔、見たなぁ」と呟く。それだけ沢山尽くしてもらったんだ、迷惑も沢山かけてしまったかもしれない。彼女のことを知る度に、見ず知らずの人の為にこんなにも行動できる少女への尊敬が溢れる。
「私、いつかまた小梅に会って、この間はありがとうって言いに行きます!」
「ん、いーこいーこ。じゃあしっかり体調整えてねぇ」
陽翔は微笑みを浮かべたまま、部屋の戸を静かに閉めた。手元に残ったおにぎりの乗っていた皿と、湯呑を洗いに洗面所へ向かう。私の部屋にはキッチンが付いていない。私は料理ができないから場所をとるキッチンが設置されていないことはとてもありがたいが、何かを洗うためにはやっぱり必要なのかなぁと考えさせられる。
「あ」
ふと顔をあげると、鏡に映る自分が目に飛び込んできた。
頬の結晶が少し大きくなっていた。