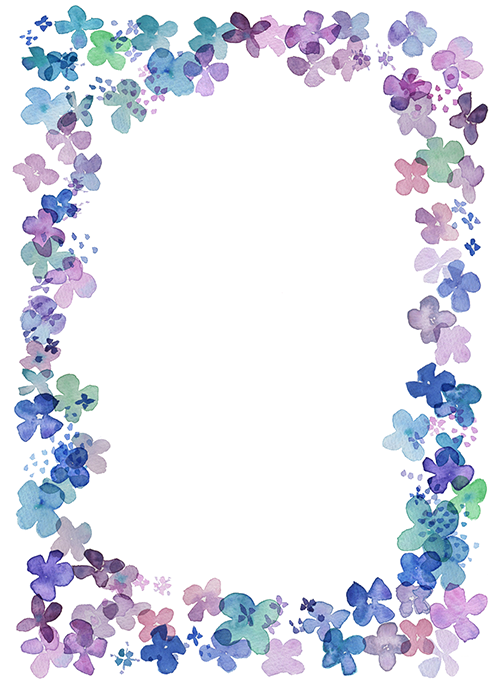今日の目覚めは悪い。というか最近はずっと寝起きの調子が悪かった。頭の中がぼうっとして、自分が誰でここがどこか分からなくなってしまう。
「変だなぁ」
いよいよかと思った。覚悟を決めなければならない、そんな気がする。上体を起こして、朝食の準備をしようとしたところで私の目は大きく見開かれた。枕シーツに落ちる無数の欠片。薄い青のそれは私の頬についていた鉱石だった。二つ、私の肌と一体化していたそれは割れてしまって、ガラスのようにベット一面に散乱している。
「あ……え……?」
ここに来てからずっと肥大していた頬の鉱石。割れるとは思っていなかった。驚きつつも、キッチンから新聞を取ってきて欠片を落とさないように丁寧に拾う。紙を丸めてから放心状態に陥り、フローリングに脱力した。なんで……まだやらなきゃいけないこと沢山あるのに。
滲んだ涙を拭って立ち上がる。いけない、泣いても意味ない。誰か慰めてくれるわけじゃないし慰めたい訳でもない。時間が限られているんだったら、その中でできることを精いっぱいすればいい。そうだろう?
「……よおし、今日はとびっきりの朝食を作っちゃおう!」
気持ちを切り替えればもうそこにいるのはいつもの私だ。
明るくて、人懐っこくて、真っすぐな、
いつもの私だ。
朝食の「むすび特製!スーパーハイパーマジカルプレート」を完食した私は、上がらない気分をどうにか上げるために散歩にでることにした。もう何日ぶりかのスニーカーの紐を結んで、鍵を閉め外に出る。「ショウテンガイ」に行く途中で、はちみつ色の髪の毛の少年の姿を見かけた。
「あ、陽翔」
私の声に立ち止まった人影はゆったりと振り返る。声を掛けたのが私だと知ると彼は驚いたように目を見開いたあと、優しくその瞳を細めた。
「あれぇ、むーちゃん久しぶりだねぇ……おはよぉ」
「おはっ、おはよ……」
「きょーはどうしたの?最近全然見なかったけど……部屋に籠もりっきりでみんな心配してたんだよぉ」
「あ、えっと……じ、実は料理にハマっちゃって!!!でも私すぐ焦がしちゃうからアハハ……」
咄嗟に嘘を吐く。料理にはまってたわけじゃない。体がだるくて動けなかっただけだ。体全体が石になってしまったかのように重たく四肢すら動かせない日が続き、ここ数日は部屋から一歩も出れなかった。
えへへと誤魔化すように笑うと、陽翔は相も変わらず穏やかな表情で私を見つめる。しかし、その奥にはさっきまでは見つけることのできなかった鋭さがあった。
「……むーちゃん、隠してることなーい?僕、相談に乗るよ?」
「でも……えと……は、はると、」
「僕は誰にも秘密を言ったりしないよぉ。僕は皆のリーダーだから、皆が悩んだ時には一緒に解決して、幸せに過ごしてほしいだけなんだぁ。ゆっくりでいいし大丈夫だから、ねっ」
陽翔の微笑みは優しいながら、どこか有無を言わせない圧があるような気がする。それは彼自身が持つものではなく、彼の背負うものがあまりにも重すぎて彼自身でも時々制御できていない節があるからだ。私の為にも、彼の為にもここは本当のことを打ち明けた方がいいような。
私は喉までせり上がった言葉を空気に含ませようとした。
「これ以上むすびに関わらないほうがいい」
突然、低い声が私を遮る。後ろからの気配にビクッと体を震わせながら振り返ると、すぐそこに先ほどまでいなかったはずのスーツの少年の姿があった。「わっ」と小さく声をあげると、綺麗に整った顔が不機嫌そうな顔で私を見下ろすものだから、私は委縮して思わず体をちぢこめる。
「何してるんだ」
「……こんぱるくん、こんにちは。僕ねぇ、今むすびちゃんと話してるから、」
「むすびを、困らせんな」
突如こんぱるからから発せられた何の脈絡もない言葉に、私と陽翔は唖然とした。
「ちょ、こんぱる!陽翔にそんな態度無いでしょ?!」
「お前も無理するな、とっとと部屋に戻れよ」
「え……」
「呼吸の乱れ、唇の色、自分では気づいてないかもしれないが顔真っ青だぞ。早く休めよ、医者呼んでやるから」
私よりも疲れたような瞳には、隠しきることの出来なかった心配の色が僅かに滲んでいる。彼の細い手が私の頭を撫でた時、彼を纏う香りもいつもと少し違うことに気づいた。爽やかなシトラスが、今日は何故か甘ったるい。これは……バニラ?だが、この香水は元の香りを覆い隠すような使い方をしている。嗅覚を集中させると濃厚な香りの奥に、酒と煙草の匂いが隠れていた。
普段、こんぱるはよくBarいることは聞いているがここまで酷く匂いが染み付いたことはないだろう。二日……いや三日は確実にそこにいなければこんな有様にはならないはず。
なんで……?
「早く、帰れよ」
「わ、わかった」
半ば強制的に退場させられた私はその場を離れてから自分の体の異常に気付いた。確かに呼吸が苦しい。咄嗟におでこに手を当てるとやかんのように熱かった。
「うわっ!やばいやばい!!早く体あっためて寝なきゃ……」
これ以上悪化しないことを祈りながら私は家に戻った。
同時刻
にっこりと笑みを浮かべた少年がこんぱるの袖に鼻を近づける。すんすんと匂いを嗅いだ後、彼は困ったように言った。
「君も随分無茶してるようだねぇ。隠しきれてないよ、煙草」
「Barでどうすればむすびを救えるのか模索してただけだ」
淡々と喋るこんぱるに陽翔は更に困惑した。最近の彼らは無茶のし過ぎだ。どう頑張ったって運命に抗えないことは、時にはある。諦めた方が早いのに、こんなことしたって意味ないって分かってるのに、ボロボロになってまで抗ってしまうのはここの子どもたちの性なのだろうか。
陽翔はそんな姿が哀れでもあり愛おしいと感じた。
「ねぇ、この間の続きを教えてくれないかい?むすびちゃんがあと二カ月弱で死んじゃうっていうあの、」
「これ以上は言えない。むすびが寿命を背負うように、俺には俺の枷がある。むすびの寿命についての情報を開示する度に俺にも被害がでるんだ。前回、リーダーにむすびの情報を伝えた時には一週間意識を失ったよ。けれど、それは嫌なんだろ?だってリーダーさんは誰も傷つけたくないもんな」
「なんでそれを」
「むすびの秘密を知ったと同時に俺の体に革命がおこった。むすびのことと、むすびが話していたことは覚えてられるようになったんだよ」
陽翔は目を見張る。だとしてもどうして。陽翔は自分の本心はなるべく見せないように取り繕っていた。それが、普段のほほんとした少女にまで気づかれてしまう程バレバレだったのか。彼の背中に冷たいものが走った瞬間、こんぱるが初めて優しい表情を浮かべた。見上げた陽翔に向けて静かに首を振る。
その仕草は大丈夫と言っているようだった。
「むすびは案外周りが見えてるよ。楽天家に見えてリーダーが持つ皆への愛情くらいは気づいている」
「……そっか、そうなんだね」
君はこんな表情ができたんだね。こんぱるの緩やかながら確実な成長に陽翔は安堵した。ここに来たばかりの頃、何も信じられないと無表情で他人を避けて過ごしていたあの少年とは違う。
きっと出会ったからだ、彼女に。どのような経緯かは知らない。けれど彼女は無邪気な笑顔で、真っすぐな言葉で彼を救ったのだろう。
だからこんなにも必死になれるんだ。感情の無かった少年は、心に光を灯したむすびを助けたいと思えるようになったんだ。
気づいてしまった陽翔をどうしようもない感情が襲う。
「むすびちゃんを救う方法はないの……?」
問いかけた言葉に返ってきた言葉は想像よりずっと淡白だった。
「無い、寿命だからな。無理をさせないようにじっくり、じっくり、ここで生きることの出来る日数を伸ばすしかないんだ」
「番えば少しは」
「あいつは……皆が好きだから。きっと誰か一人のことを愛しぬくことはできないよ。ここにいる人たち皆のことが大切で、大好きで。きっとここにいる誰が番おうって誘ったって『私は私だから!』って一人を貫くんだ」
それは陽翔にも想像ができた。だからこそ胸が苦しくなった。こんぱるはそれでも言葉を続けた。初めて零した本音は、とどまることを知らず溢れる。
「俺はむすびのそういうところが好きなんだ。だから……汚したくない」
「そっか……」
沈黙があった。辺りを静寂が包み込む。やがて陽翔から出てきた言葉は「彼女は苦しまずに逝けるのか……?」だった。もっと他に掛ける言葉があっただろうと気づいたのは発してから暫く経ってのことでもう取り返しはつかない。ふと隣のこんぱるを伺うと意外にも考えの分からない不思議な顔だった。彼は空を見上げると一言、寂しそうに呟く。
「さぁ、そんなの……俺も知りたいよ」
時間の流れが遅かった。こんぱるが過ぎないでと願った一分一秒が、今は早く過ぎてほしいと思う。耐えられなかった。
むすびが弱っていくのを見るのが、むすびの死について誰かと語らうのが。
そんなこんぱるの心情を察して、陽翔は提案をする。今日は彼を一人にしてはいけない、直感でそう感じたのだ。
「ねぇ、行きつけのBarに行こうよ。こんぱるくんオススメのカクテル知りたいなぁ」
「はは、いいなそれ。ノンアルでもいいなら是非」
むすびの診療はよもぎ先生に任せ、少年二人は商店街への道を歩き出す。そうだ、リーダーにはダイキリを紹介しよう。ダイキリはこんぱるが好んで飲むカクテルだ。未成年なのでホワイトラムのアルコールを飛ばしてもらっているのだが、ライムが合わさり爽やかな口当たりで気持ちを切り替えたいときにぴったりだと思った。
ふと、頭の中に浮かんだ言葉をこんぱるは呟く。
「リーダーはさ、大切な人がいなくなったらどう思う?それ以前にそういう経験あったりする?」
「……んふふ、君には関係ないことだよぉ。ただ一つ言えるのは……僕にも消えてほしくない人はいる、かなぁ」
「……もしその人が消える運命だとしたら?」
「えー。どんな住人であっても、ここの子たちを守りきれなかったら僕はリーダー失格だよぉ」
「のらりくらりしすぎなんだよ、アンタ。掴みどころ無くて俺ばかりボロが出て腹が立つ」
「そのくらい余裕がなくっちゃ、この仕事は務まらないってことだよぉ」
「……リーダーの消えてほしくない人って番?」
「さぁ」
その横顔は頬骨が少し赤い。上ずる声が全てを物語っていた。こんぱるは小さく笑うと、また前を向いた。
「アンタって時々嘘が下手になることあるよな」
「……君もねぇ」
まだ日は高い。夜になるまでの道のりは長い。だから語らい合おう。お互いが酔いつぶれるまで。
全てを忘れ、またいつも通りに戻れるまで。
「変だなぁ」
いよいよかと思った。覚悟を決めなければならない、そんな気がする。上体を起こして、朝食の準備をしようとしたところで私の目は大きく見開かれた。枕シーツに落ちる無数の欠片。薄い青のそれは私の頬についていた鉱石だった。二つ、私の肌と一体化していたそれは割れてしまって、ガラスのようにベット一面に散乱している。
「あ……え……?」
ここに来てからずっと肥大していた頬の鉱石。割れるとは思っていなかった。驚きつつも、キッチンから新聞を取ってきて欠片を落とさないように丁寧に拾う。紙を丸めてから放心状態に陥り、フローリングに脱力した。なんで……まだやらなきゃいけないこと沢山あるのに。
滲んだ涙を拭って立ち上がる。いけない、泣いても意味ない。誰か慰めてくれるわけじゃないし慰めたい訳でもない。時間が限られているんだったら、その中でできることを精いっぱいすればいい。そうだろう?
「……よおし、今日はとびっきりの朝食を作っちゃおう!」
気持ちを切り替えればもうそこにいるのはいつもの私だ。
明るくて、人懐っこくて、真っすぐな、
いつもの私だ。
朝食の「むすび特製!スーパーハイパーマジカルプレート」を完食した私は、上がらない気分をどうにか上げるために散歩にでることにした。もう何日ぶりかのスニーカーの紐を結んで、鍵を閉め外に出る。「ショウテンガイ」に行く途中で、はちみつ色の髪の毛の少年の姿を見かけた。
「あ、陽翔」
私の声に立ち止まった人影はゆったりと振り返る。声を掛けたのが私だと知ると彼は驚いたように目を見開いたあと、優しくその瞳を細めた。
「あれぇ、むーちゃん久しぶりだねぇ……おはよぉ」
「おはっ、おはよ……」
「きょーはどうしたの?最近全然見なかったけど……部屋に籠もりっきりでみんな心配してたんだよぉ」
「あ、えっと……じ、実は料理にハマっちゃって!!!でも私すぐ焦がしちゃうからアハハ……」
咄嗟に嘘を吐く。料理にはまってたわけじゃない。体がだるくて動けなかっただけだ。体全体が石になってしまったかのように重たく四肢すら動かせない日が続き、ここ数日は部屋から一歩も出れなかった。
えへへと誤魔化すように笑うと、陽翔は相も変わらず穏やかな表情で私を見つめる。しかし、その奥にはさっきまでは見つけることのできなかった鋭さがあった。
「……むーちゃん、隠してることなーい?僕、相談に乗るよ?」
「でも……えと……は、はると、」
「僕は誰にも秘密を言ったりしないよぉ。僕は皆のリーダーだから、皆が悩んだ時には一緒に解決して、幸せに過ごしてほしいだけなんだぁ。ゆっくりでいいし大丈夫だから、ねっ」
陽翔の微笑みは優しいながら、どこか有無を言わせない圧があるような気がする。それは彼自身が持つものではなく、彼の背負うものがあまりにも重すぎて彼自身でも時々制御できていない節があるからだ。私の為にも、彼の為にもここは本当のことを打ち明けた方がいいような。
私は喉までせり上がった言葉を空気に含ませようとした。
「これ以上むすびに関わらないほうがいい」
突然、低い声が私を遮る。後ろからの気配にビクッと体を震わせながら振り返ると、すぐそこに先ほどまでいなかったはずのスーツの少年の姿があった。「わっ」と小さく声をあげると、綺麗に整った顔が不機嫌そうな顔で私を見下ろすものだから、私は委縮して思わず体をちぢこめる。
「何してるんだ」
「……こんぱるくん、こんにちは。僕ねぇ、今むすびちゃんと話してるから、」
「むすびを、困らせんな」
突如こんぱるからから発せられた何の脈絡もない言葉に、私と陽翔は唖然とした。
「ちょ、こんぱる!陽翔にそんな態度無いでしょ?!」
「お前も無理するな、とっとと部屋に戻れよ」
「え……」
「呼吸の乱れ、唇の色、自分では気づいてないかもしれないが顔真っ青だぞ。早く休めよ、医者呼んでやるから」
私よりも疲れたような瞳には、隠しきることの出来なかった心配の色が僅かに滲んでいる。彼の細い手が私の頭を撫でた時、彼を纏う香りもいつもと少し違うことに気づいた。爽やかなシトラスが、今日は何故か甘ったるい。これは……バニラ?だが、この香水は元の香りを覆い隠すような使い方をしている。嗅覚を集中させると濃厚な香りの奥に、酒と煙草の匂いが隠れていた。
普段、こんぱるはよくBarいることは聞いているがここまで酷く匂いが染み付いたことはないだろう。二日……いや三日は確実にそこにいなければこんな有様にはならないはず。
なんで……?
「早く、帰れよ」
「わ、わかった」
半ば強制的に退場させられた私はその場を離れてから自分の体の異常に気付いた。確かに呼吸が苦しい。咄嗟におでこに手を当てるとやかんのように熱かった。
「うわっ!やばいやばい!!早く体あっためて寝なきゃ……」
これ以上悪化しないことを祈りながら私は家に戻った。
同時刻
にっこりと笑みを浮かべた少年がこんぱるの袖に鼻を近づける。すんすんと匂いを嗅いだ後、彼は困ったように言った。
「君も随分無茶してるようだねぇ。隠しきれてないよ、煙草」
「Barでどうすればむすびを救えるのか模索してただけだ」
淡々と喋るこんぱるに陽翔は更に困惑した。最近の彼らは無茶のし過ぎだ。どう頑張ったって運命に抗えないことは、時にはある。諦めた方が早いのに、こんなことしたって意味ないって分かってるのに、ボロボロになってまで抗ってしまうのはここの子どもたちの性なのだろうか。
陽翔はそんな姿が哀れでもあり愛おしいと感じた。
「ねぇ、この間の続きを教えてくれないかい?むすびちゃんがあと二カ月弱で死んじゃうっていうあの、」
「これ以上は言えない。むすびが寿命を背負うように、俺には俺の枷がある。むすびの寿命についての情報を開示する度に俺にも被害がでるんだ。前回、リーダーにむすびの情報を伝えた時には一週間意識を失ったよ。けれど、それは嫌なんだろ?だってリーダーさんは誰も傷つけたくないもんな」
「なんでそれを」
「むすびの秘密を知ったと同時に俺の体に革命がおこった。むすびのことと、むすびが話していたことは覚えてられるようになったんだよ」
陽翔は目を見張る。だとしてもどうして。陽翔は自分の本心はなるべく見せないように取り繕っていた。それが、普段のほほんとした少女にまで気づかれてしまう程バレバレだったのか。彼の背中に冷たいものが走った瞬間、こんぱるが初めて優しい表情を浮かべた。見上げた陽翔に向けて静かに首を振る。
その仕草は大丈夫と言っているようだった。
「むすびは案外周りが見えてるよ。楽天家に見えてリーダーが持つ皆への愛情くらいは気づいている」
「……そっか、そうなんだね」
君はこんな表情ができたんだね。こんぱるの緩やかながら確実な成長に陽翔は安堵した。ここに来たばかりの頃、何も信じられないと無表情で他人を避けて過ごしていたあの少年とは違う。
きっと出会ったからだ、彼女に。どのような経緯かは知らない。けれど彼女は無邪気な笑顔で、真っすぐな言葉で彼を救ったのだろう。
だからこんなにも必死になれるんだ。感情の無かった少年は、心に光を灯したむすびを助けたいと思えるようになったんだ。
気づいてしまった陽翔をどうしようもない感情が襲う。
「むすびちゃんを救う方法はないの……?」
問いかけた言葉に返ってきた言葉は想像よりずっと淡白だった。
「無い、寿命だからな。無理をさせないようにじっくり、じっくり、ここで生きることの出来る日数を伸ばすしかないんだ」
「番えば少しは」
「あいつは……皆が好きだから。きっと誰か一人のことを愛しぬくことはできないよ。ここにいる人たち皆のことが大切で、大好きで。きっとここにいる誰が番おうって誘ったって『私は私だから!』って一人を貫くんだ」
それは陽翔にも想像ができた。だからこそ胸が苦しくなった。こんぱるはそれでも言葉を続けた。初めて零した本音は、とどまることを知らず溢れる。
「俺はむすびのそういうところが好きなんだ。だから……汚したくない」
「そっか……」
沈黙があった。辺りを静寂が包み込む。やがて陽翔から出てきた言葉は「彼女は苦しまずに逝けるのか……?」だった。もっと他に掛ける言葉があっただろうと気づいたのは発してから暫く経ってのことでもう取り返しはつかない。ふと隣のこんぱるを伺うと意外にも考えの分からない不思議な顔だった。彼は空を見上げると一言、寂しそうに呟く。
「さぁ、そんなの……俺も知りたいよ」
時間の流れが遅かった。こんぱるが過ぎないでと願った一分一秒が、今は早く過ぎてほしいと思う。耐えられなかった。
むすびが弱っていくのを見るのが、むすびの死について誰かと語らうのが。
そんなこんぱるの心情を察して、陽翔は提案をする。今日は彼を一人にしてはいけない、直感でそう感じたのだ。
「ねぇ、行きつけのBarに行こうよ。こんぱるくんオススメのカクテル知りたいなぁ」
「はは、いいなそれ。ノンアルでもいいなら是非」
むすびの診療はよもぎ先生に任せ、少年二人は商店街への道を歩き出す。そうだ、リーダーにはダイキリを紹介しよう。ダイキリはこんぱるが好んで飲むカクテルだ。未成年なのでホワイトラムのアルコールを飛ばしてもらっているのだが、ライムが合わさり爽やかな口当たりで気持ちを切り替えたいときにぴったりだと思った。
ふと、頭の中に浮かんだ言葉をこんぱるは呟く。
「リーダーはさ、大切な人がいなくなったらどう思う?それ以前にそういう経験あったりする?」
「……んふふ、君には関係ないことだよぉ。ただ一つ言えるのは……僕にも消えてほしくない人はいる、かなぁ」
「……もしその人が消える運命だとしたら?」
「えー。どんな住人であっても、ここの子たちを守りきれなかったら僕はリーダー失格だよぉ」
「のらりくらりしすぎなんだよ、アンタ。掴みどころ無くて俺ばかりボロが出て腹が立つ」
「そのくらい余裕がなくっちゃ、この仕事は務まらないってことだよぉ」
「……リーダーの消えてほしくない人って番?」
「さぁ」
その横顔は頬骨が少し赤い。上ずる声が全てを物語っていた。こんぱるは小さく笑うと、また前を向いた。
「アンタって時々嘘が下手になることあるよな」
「……君もねぇ」
まだ日は高い。夜になるまでの道のりは長い。だから語らい合おう。お互いが酔いつぶれるまで。
全てを忘れ、またいつも通りに戻れるまで。