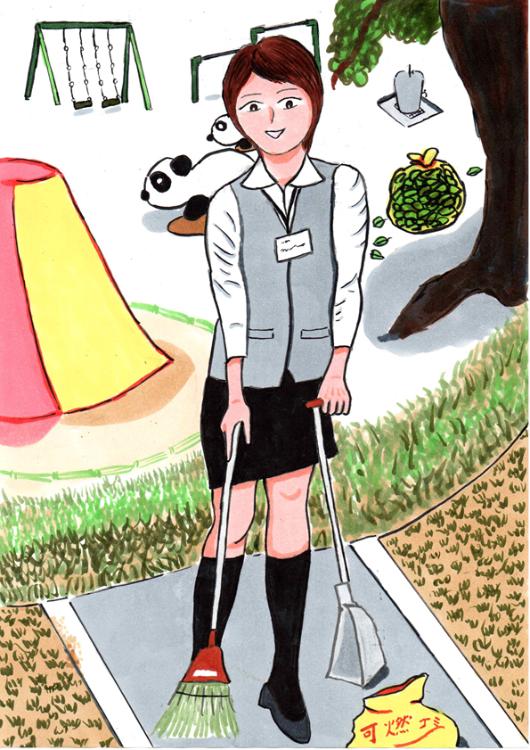翌朝。チャイムが鳴って遠野さんが待っていた。
いつものキリっとした顏。歩きだしてから重々しく口を開く。
「君のこと、まだ信用できない。友だちに見られたらなんて説明するの? 『母親』だって逃げるんじゃない。わたし、大声で『フィアンセ』と言い返すからね」
「僕ってそんなこと言いませんってば」
「婚姻届は銀行の貸金庫だから。わたしの留守に家に忍び込んだってなにもありませんからね」
「だからそんなこと、ぜったいしませんってば」
ホワイトデー。あれだけ勇気見せたつもりなんだけど、まだ信じてくれないのかなあ?
僕は深呼吸して、もっともっと大きな勇気を見せた。遠野さんに、そっと手を差し出した。
遠野さんの顏に満面の笑みが浮かんだ。たぶん、この笑顔。何年経っても、何十年経っても、僕は忘れないと思う。
遠野さんったら僕の手を強く引っ張って歩き出した。
信号交差点もそのまま直進。
「わたしね。今日から遠回りする。 いいよね」
それからかすかな声が僕の耳元で聞こえた。
「わたしだって、ひとりぼっちはイヤだから」
遠野さんの声が震えている。僕は心配して次の言葉を待った。
「主任になったよ」
遠野さんったら緊張した表情で、笑顔ひとつ見せてくれない。
「君がいるから頑張れた。次は統括主任をめざす。ねっ、わたし、嘘なんか言ってなかったよ。君だって大きな夢があったでしょう」
「はいっ、僕も彼氏として東洋教育大学推薦をめざします」
僕が遠野さんをまっすぐ見つめる。ふたりの目と目がしっかり合った。
「だからね。帰ったらキスしようよ」
「は、はいっ」
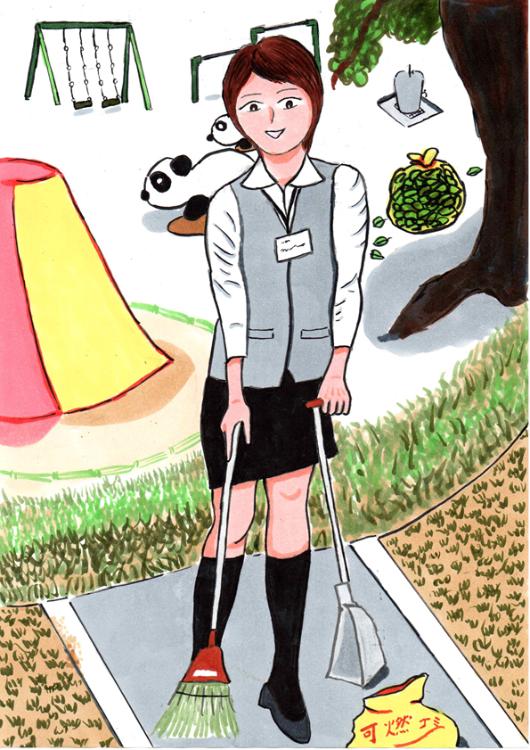
いつものキリっとした顏。歩きだしてから重々しく口を開く。
「君のこと、まだ信用できない。友だちに見られたらなんて説明するの? 『母親』だって逃げるんじゃない。わたし、大声で『フィアンセ』と言い返すからね」
「僕ってそんなこと言いませんってば」
「婚姻届は銀行の貸金庫だから。わたしの留守に家に忍び込んだってなにもありませんからね」
「だからそんなこと、ぜったいしませんってば」
ホワイトデー。あれだけ勇気見せたつもりなんだけど、まだ信じてくれないのかなあ?
僕は深呼吸して、もっともっと大きな勇気を見せた。遠野さんに、そっと手を差し出した。
遠野さんの顏に満面の笑みが浮かんだ。たぶん、この笑顔。何年経っても、何十年経っても、僕は忘れないと思う。
遠野さんったら僕の手を強く引っ張って歩き出した。
信号交差点もそのまま直進。
「わたしね。今日から遠回りする。 いいよね」
それからかすかな声が僕の耳元で聞こえた。
「わたしだって、ひとりぼっちはイヤだから」
遠野さんの声が震えている。僕は心配して次の言葉を待った。
「主任になったよ」
遠野さんったら緊張した表情で、笑顔ひとつ見せてくれない。
「君がいるから頑張れた。次は統括主任をめざす。ねっ、わたし、嘘なんか言ってなかったよ。君だって大きな夢があったでしょう」
「はいっ、僕も彼氏として東洋教育大学推薦をめざします」
僕が遠野さんをまっすぐ見つめる。ふたりの目と目がしっかり合った。
「だからね。帰ったらキスしようよ」
「は、はいっ」