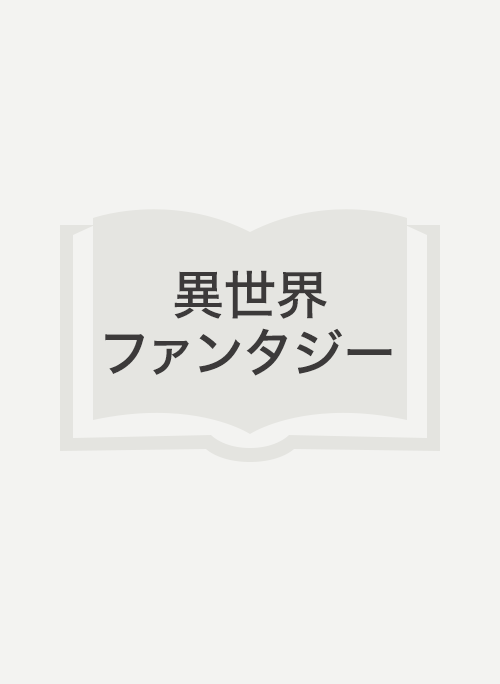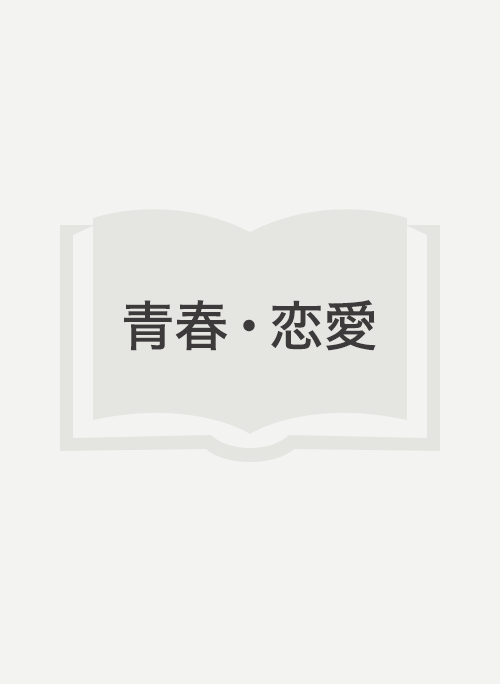さかのぼること遙かなる御世に、黄河のほとりに広がる都の大路を一人の青年が歩いていた。
名は玄龍。
涼やかな目に鼻筋の通った二十歳ほどの男だが、背が高い割に線が細く、腰には佩刀ではなく木刀を差している。
よく晴れた昼下がりの大路を行き交う人波をかわしながら歩いていると、路地から子供たちが駆け出してきた。
「やーい、ここまでおいで!」
追いかけてくる連中に向かって小馬鹿にしながら振り返った少年が玄龍に気づかずぶつかってきた。
「おっと、危ないぞ」
転ばないように受け止めてやったにもかかわらず、仲間に追いつかれたのが不満なのか、小僧が口をとがらせる。
「おじさん、邪魔だよ」
「おじさんはないだろ」
今度は玄龍が不満を述べたが、子供たちはそんな抗議など無視して駆けていってしまう。
――賑やかでいいものだ。
街は活気に満ちて、子供たちの笑顔にあふれている。
と、大路から寺院の門前町へ入ったところで、玄龍は騒動に遭遇した。
饅頭屋台の前で、武人三人を相手に若者が啖呵を切っている。
「どういうことだい? 金を払えねえだと?」
さらしを巻いた胸をはだけた若者はまだ十代半ばくらいか、ふかしたての饅頭のようにつるりとした頬が赤く染まっている。
武人たちは屋台に蹴りを入れながら野次馬に向かって食いかけの饅頭を投げつけた。
「おう。こんなまずい物にお代を取るのかよ」
「言ってくれるね。おいらの饅頭は門前一の名物って評判だぞ」
「だからこうして食いに来てみたら、まずいことまずいこと」
様子を見ていた玄龍が間に割って入った。
「せこい旦那方だね。饅頭代ぐらいおとなしく払ってやりなよ」
「なんだと、この野郎」
あっという間に荒くれどもに三方を囲まれて、毛むくじゃらの腕が伸びてきた。
「おい、兄さん。余計な口出しはしないでくれ」
後ろからも肩をつかまれ振り向くと、饅頭屋の若者が迷惑そうな目で見ている。
助けてやろうとしたつもりが前後から挟まれてしまった。
「だとよ」と、胸ぐらをつかんでいた武人が玄龍を脇に投げ飛ばす。「優男はすっこんでな」
よろよろと尻餅をつきそうになるのを、野次馬たちに助けられて玄龍はなんとか踏みとどまった。
卑怯にも荒くれどもが三人揃って饅頭屋に襲いかかる。
しかし、次の瞬間、信じられないことが起きた。
若者が千手観音も驚くほどの早業で相手の顔面や腹に次々と拳を突き出したかと思うと、韋駄天のごとく背後に回り、股間に狙いをすまして脚を振り上げ、あっという間に三人まとめて倒してしまったのだ。
あまりにも見事な立ち回りに拍手や歓声が沸き起こる。
――ほう、おもしろいものだな。
玄龍は腰から木刀を引き抜き、道に落ちていた財布を引っかけて取り上げた。
「ほら、これで足りるか?」
適当に小銭をつかんで差し出すと、若者は笑みを浮かべて受け取った。
「なんだ、あんたまだいたのかい? ありがとよ」
股間を押さえて後ずさる荒くれどもに財布を放ってやると、お決まりの捨て台詞が返ってくる。
「ち、ちくしょう。覚えてやがれよ」
「二度とこんな真似はするなよ」
鼻で笑いながら、倒れていた縁台を起こして玄龍は腰掛けた。
「せっかくだから俺も饅頭をもらおうか」
「あんた何もしてないのに偉そうだね。ちゃんとお代は払ってくれよ」
「あのような馬鹿者どもと一緒にされてはかなわぬな」
ひょいと差し出された皿を受け取って玄龍は小ぶりな饅頭を頬張った。
綿のようにふっくらと蒸し上がった皮の中にごまの風味の効いた餡が詰まっている。
「ほう、なるほど、これは美味だな」
「美味って、気取った言い方するもんだね」と、若者が笑う。「格好は地味だけど、あんた役人かい?」
「まあ、そんなところだ」
若者の表情が曇る。
「食ったら、とっとと行ってくれ」
「なんだ、冷たいな」
「役人は嫌いだ」
「なにゆえだ。恨みでもあるのか?」
「あんたみたいな下っ端に文句言っても始まらないさ」
まともな刀も持たない玄龍の姿を眺め回しながら若者がため息をついた。
「最近、御上が代替わりしたって騒いでただろ」
大帝国を統べる皇帝が崩御し、新帝が即位したのは半年ほど前だった。
即位後に大行列を引き連れて視察がおこなわれたときには、浮浪者は警護の武人たちに追い払われ、商売は役人たちの命令で中止させられた。
そのくせ日銭を稼がなければ死活問題の一般庶民は都の大路に狩り出され、平伏して祝賀の意を表すことを強要されたのである。
良い印象などあるわけがなかった。
「まだ若いんだかなんだか知らないけど、新しい皇帝ってやつが後宮で甘やかされてきた坊ちゃんだから、古株の役人どものやりたい放題でまともな政治がおこなわれていないってみんな困ってるよ」
「そうなのか?」と、玄龍は二つめの饅頭を頬張った。「街は賑やかなようだが」
「さっきみたいなくだらない騒動のせいだろ。風紀が乱れて、正直者が馬鹿を見るだけさ」
「そなたのような……か」
「褒めたっておいらの役人嫌いは変わらねえよ」
「そなたほどの腕なら宮廷の衛士になれるだろうに。給料も良いぞ」
腕組みをした饅頭屋が玄龍の前に立ちはだかる。
「よしてくれよ。頼まれたってごめんだね」
「そなたの腕を世のために役立たせてみてはどうだ?」
「俺一人の腕じゃ、何も変わらないさ」
饅頭屋の顔を見上げて玄龍はふっと笑みを浮かべた。
「なんだよ」と、若者は顔を背けた。「その笑い方、気に入らねえな」
「そなたも逃げておるではないか」
「なんだと」と、今度は間合いを詰めてにらむ。「どういうことだ?」
「世の中に変わってほしいなら、自分から動かねば何も変わるまい」
「俺は饅頭屋だ。俺の饅頭をみんな喜んで食ってくれる。それの何が悪い」
「いや、すまん」と、玄龍は頭を下げた。「たしかにうまかった」
若者は玄龍の態度に勢いをそがれて肩をすくめると、さっさと皿を片付けた。
「ん……、お?」
立ち上がって懐を探っていた玄龍が首をかしげる。
「おかしいな。財布がないぞ」
「おいおい、まさかあんたまで食い逃げしようってんじゃねえだろうな」
呆れた顔で詰め寄る若者に玄龍は両手を突き出して、ちぎれるほどに振った。
「いや、ちょっと待ってくれ」
――あのときか。
路地から駆け出してきた子供たちの姿は思い浮かぶが、顔までは覚えていなかった。
なるほど、世の賑わいもかりそめか。
子供の心まですさんでおるようだな。
「すまん」と、玄龍は若者に頭を下げた。「財布を忘れてきたようだ」
「まったくなんて世の中だよ」と、若者が天を仰ぐ。「役人がこれじゃあ、この先も期待できそうにないな」
「食い逃げをするつもりはない」と、玄龍は手から指輪を抜き取って差し出した。「これを質に置いていく」
金地の指輪には碧玉がならんで象嵌されている。
「よしてくれよ。こんな物もらってもおいらには意味がないぜ」
「必ず後で使いの者をよこす」と、玄龍は若者の手を取って指輪を握らせた。
荒くれどもを倒したとは思えないような柔らかい手と細い指だった。
「困るんだよ」と、若者が肩を落とす。「これじゃあ妹の薬が買えねえんだ」
「妹がおるのか?」
「病気で寝てるんだ。だから薬代を稼がなくちゃならないし、この町を離れるわけにはいかないんだ」
「なるほど、そういうことか」と、玄龍は腕組みをしながらうなずいた。「ならば急がなければならぬな」
そして、笑みを浮かべてたずねた。
「そなた、名は?」
「蘭……」と、言いかけて咳払いをする。「嵐雲」
「いい名前だ。覚えておく」
玄龍は背を向けると、右手を挙げて去っていった。
「おい、あんたは……」
名前を聞きそびれた饅頭屋の若者は左手の中指に指輪をはめながらため息をつくのだった。
名は玄龍。
涼やかな目に鼻筋の通った二十歳ほどの男だが、背が高い割に線が細く、腰には佩刀ではなく木刀を差している。
よく晴れた昼下がりの大路を行き交う人波をかわしながら歩いていると、路地から子供たちが駆け出してきた。
「やーい、ここまでおいで!」
追いかけてくる連中に向かって小馬鹿にしながら振り返った少年が玄龍に気づかずぶつかってきた。
「おっと、危ないぞ」
転ばないように受け止めてやったにもかかわらず、仲間に追いつかれたのが不満なのか、小僧が口をとがらせる。
「おじさん、邪魔だよ」
「おじさんはないだろ」
今度は玄龍が不満を述べたが、子供たちはそんな抗議など無視して駆けていってしまう。
――賑やかでいいものだ。
街は活気に満ちて、子供たちの笑顔にあふれている。
と、大路から寺院の門前町へ入ったところで、玄龍は騒動に遭遇した。
饅頭屋台の前で、武人三人を相手に若者が啖呵を切っている。
「どういうことだい? 金を払えねえだと?」
さらしを巻いた胸をはだけた若者はまだ十代半ばくらいか、ふかしたての饅頭のようにつるりとした頬が赤く染まっている。
武人たちは屋台に蹴りを入れながら野次馬に向かって食いかけの饅頭を投げつけた。
「おう。こんなまずい物にお代を取るのかよ」
「言ってくれるね。おいらの饅頭は門前一の名物って評判だぞ」
「だからこうして食いに来てみたら、まずいことまずいこと」
様子を見ていた玄龍が間に割って入った。
「せこい旦那方だね。饅頭代ぐらいおとなしく払ってやりなよ」
「なんだと、この野郎」
あっという間に荒くれどもに三方を囲まれて、毛むくじゃらの腕が伸びてきた。
「おい、兄さん。余計な口出しはしないでくれ」
後ろからも肩をつかまれ振り向くと、饅頭屋の若者が迷惑そうな目で見ている。
助けてやろうとしたつもりが前後から挟まれてしまった。
「だとよ」と、胸ぐらをつかんでいた武人が玄龍を脇に投げ飛ばす。「優男はすっこんでな」
よろよろと尻餅をつきそうになるのを、野次馬たちに助けられて玄龍はなんとか踏みとどまった。
卑怯にも荒くれどもが三人揃って饅頭屋に襲いかかる。
しかし、次の瞬間、信じられないことが起きた。
若者が千手観音も驚くほどの早業で相手の顔面や腹に次々と拳を突き出したかと思うと、韋駄天のごとく背後に回り、股間に狙いをすまして脚を振り上げ、あっという間に三人まとめて倒してしまったのだ。
あまりにも見事な立ち回りに拍手や歓声が沸き起こる。
――ほう、おもしろいものだな。
玄龍は腰から木刀を引き抜き、道に落ちていた財布を引っかけて取り上げた。
「ほら、これで足りるか?」
適当に小銭をつかんで差し出すと、若者は笑みを浮かべて受け取った。
「なんだ、あんたまだいたのかい? ありがとよ」
股間を押さえて後ずさる荒くれどもに財布を放ってやると、お決まりの捨て台詞が返ってくる。
「ち、ちくしょう。覚えてやがれよ」
「二度とこんな真似はするなよ」
鼻で笑いながら、倒れていた縁台を起こして玄龍は腰掛けた。
「せっかくだから俺も饅頭をもらおうか」
「あんた何もしてないのに偉そうだね。ちゃんとお代は払ってくれよ」
「あのような馬鹿者どもと一緒にされてはかなわぬな」
ひょいと差し出された皿を受け取って玄龍は小ぶりな饅頭を頬張った。
綿のようにふっくらと蒸し上がった皮の中にごまの風味の効いた餡が詰まっている。
「ほう、なるほど、これは美味だな」
「美味って、気取った言い方するもんだね」と、若者が笑う。「格好は地味だけど、あんた役人かい?」
「まあ、そんなところだ」
若者の表情が曇る。
「食ったら、とっとと行ってくれ」
「なんだ、冷たいな」
「役人は嫌いだ」
「なにゆえだ。恨みでもあるのか?」
「あんたみたいな下っ端に文句言っても始まらないさ」
まともな刀も持たない玄龍の姿を眺め回しながら若者がため息をついた。
「最近、御上が代替わりしたって騒いでただろ」
大帝国を統べる皇帝が崩御し、新帝が即位したのは半年ほど前だった。
即位後に大行列を引き連れて視察がおこなわれたときには、浮浪者は警護の武人たちに追い払われ、商売は役人たちの命令で中止させられた。
そのくせ日銭を稼がなければ死活問題の一般庶民は都の大路に狩り出され、平伏して祝賀の意を表すことを強要されたのである。
良い印象などあるわけがなかった。
「まだ若いんだかなんだか知らないけど、新しい皇帝ってやつが後宮で甘やかされてきた坊ちゃんだから、古株の役人どものやりたい放題でまともな政治がおこなわれていないってみんな困ってるよ」
「そうなのか?」と、玄龍は二つめの饅頭を頬張った。「街は賑やかなようだが」
「さっきみたいなくだらない騒動のせいだろ。風紀が乱れて、正直者が馬鹿を見るだけさ」
「そなたのような……か」
「褒めたっておいらの役人嫌いは変わらねえよ」
「そなたほどの腕なら宮廷の衛士になれるだろうに。給料も良いぞ」
腕組みをした饅頭屋が玄龍の前に立ちはだかる。
「よしてくれよ。頼まれたってごめんだね」
「そなたの腕を世のために役立たせてみてはどうだ?」
「俺一人の腕じゃ、何も変わらないさ」
饅頭屋の顔を見上げて玄龍はふっと笑みを浮かべた。
「なんだよ」と、若者は顔を背けた。「その笑い方、気に入らねえな」
「そなたも逃げておるではないか」
「なんだと」と、今度は間合いを詰めてにらむ。「どういうことだ?」
「世の中に変わってほしいなら、自分から動かねば何も変わるまい」
「俺は饅頭屋だ。俺の饅頭をみんな喜んで食ってくれる。それの何が悪い」
「いや、すまん」と、玄龍は頭を下げた。「たしかにうまかった」
若者は玄龍の態度に勢いをそがれて肩をすくめると、さっさと皿を片付けた。
「ん……、お?」
立ち上がって懐を探っていた玄龍が首をかしげる。
「おかしいな。財布がないぞ」
「おいおい、まさかあんたまで食い逃げしようってんじゃねえだろうな」
呆れた顔で詰め寄る若者に玄龍は両手を突き出して、ちぎれるほどに振った。
「いや、ちょっと待ってくれ」
――あのときか。
路地から駆け出してきた子供たちの姿は思い浮かぶが、顔までは覚えていなかった。
なるほど、世の賑わいもかりそめか。
子供の心まですさんでおるようだな。
「すまん」と、玄龍は若者に頭を下げた。「財布を忘れてきたようだ」
「まったくなんて世の中だよ」と、若者が天を仰ぐ。「役人がこれじゃあ、この先も期待できそうにないな」
「食い逃げをするつもりはない」と、玄龍は手から指輪を抜き取って差し出した。「これを質に置いていく」
金地の指輪には碧玉がならんで象嵌されている。
「よしてくれよ。こんな物もらってもおいらには意味がないぜ」
「必ず後で使いの者をよこす」と、玄龍は若者の手を取って指輪を握らせた。
荒くれどもを倒したとは思えないような柔らかい手と細い指だった。
「困るんだよ」と、若者が肩を落とす。「これじゃあ妹の薬が買えねえんだ」
「妹がおるのか?」
「病気で寝てるんだ。だから薬代を稼がなくちゃならないし、この町を離れるわけにはいかないんだ」
「なるほど、そういうことか」と、玄龍は腕組みをしながらうなずいた。「ならば急がなければならぬな」
そして、笑みを浮かべてたずねた。
「そなた、名は?」
「蘭……」と、言いかけて咳払いをする。「嵐雲」
「いい名前だ。覚えておく」
玄龍は背を向けると、右手を挙げて去っていった。
「おい、あんたは……」
名前を聞きそびれた饅頭屋の若者は左手の中指に指輪をはめながらため息をつくのだった。