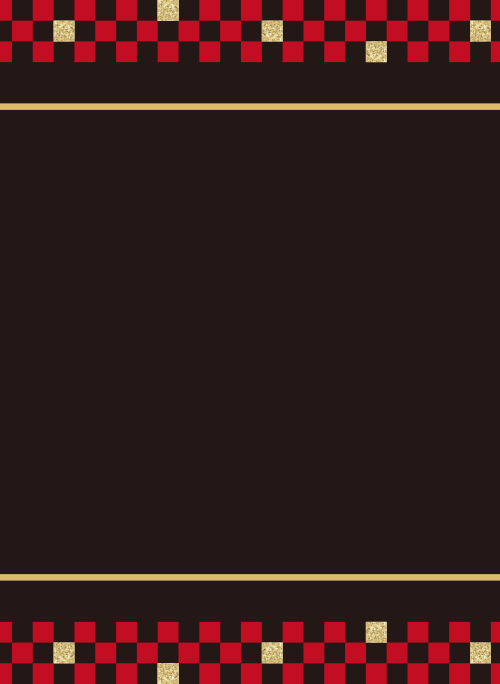庄屋の屋敷。村の女達によって強引に風呂に入れられた雪は、身ぎれいになったものの、病が悪化していた。
一方、真っ白な死装束を着せられた雪の変貌を見た村の男達はどよめいた。
雪は幽霊のような美しい娘だった。
櫛を入れた長い黒髪は絹のようにしっとりと光沢がある。細い首筋やちらりと覗く足首からは、得も言われぬ色香が漂う。
濡れた漆黒の瞳を伏せ、雪は苦しそうに胸を抑えた。
その仕草でさえ、品が良く、見るものの心を奪う。
「さあさ! どきな野次馬どもっ。お前たち、雪を隣の部屋へ運ぶんだよっ!」
庄屋の妻は男どもを蹴散らし、雪を夫の葬式を行う座敷へ連れて行く。
襖で隔てた隣の部屋では、葬式の準備の真っ最中だ。雪は死んだ庄屋の身代わりとして、生贄らしく白い布団が用意された。
枕元には、燭台が一つ置かれた。
この蝋燭の火は、決して絶やしてはならない。火が消えた瞬間、屍食鬼が死体をさらってしまうと伝承されている。
布団に横たえられた雪は、浅い呼吸を繰り返した。
艶やかな黒髪はさらりと揺れ、透けるほど白い肌を彩る。
「それだけの美貌があると知ってたら、あたしの旦那は手ぇ出してただろうね」
女は皮肉げに舌打ちする。
「まあいい。・・・この器量なら、鬼はうちの旦那よりお前を選ぶだろ。――雪。お疲れだったね。もう死んでもいいよ」
女は言い捨て、さっさと隣の部屋へ向かう。野次馬たちはすごすごと退散し、雪はたったひとりぽつんと広い部屋に残された。