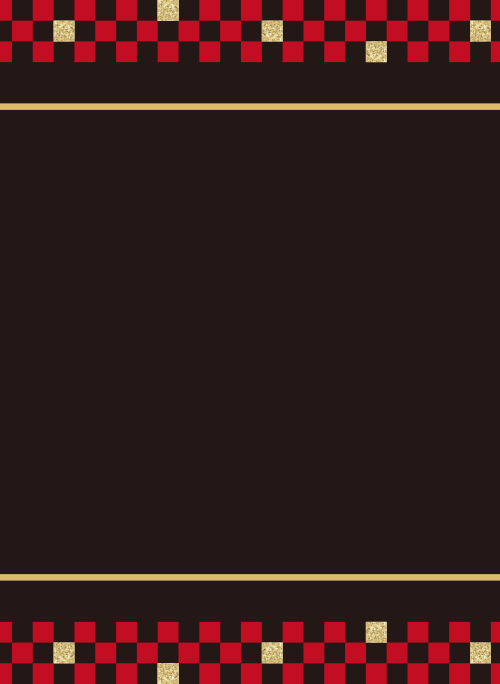僕だけを見てくれるひとはいなかった。
母親からの愛情は薄かった。
心にぽっかりと穴が空いたまま、時はすぎる。
そんなとき、好きな人ができた。黒猫を飼っていた村娘だ。
でも、彼女は僕を好きになってはくれなかった。
君がほしい。
君の目にうつるのは、僕だけでいい。
気がつけば君は、僕の腕の中で冷たくなっていた。
――死んだ君の瞳にうつる僕。やっと、僕を見てくれたね。
でもなぜか、君は人形のような顔をしていた。
まだたりない。
君の存在を知っているのは、僕だけでいい。
だから家族を殺してみたけれど。やっぱり気が晴れない。
――生きている君に、僕を見てほしかったのか・・・?
餓鬼は――俗名あやめは、首をひねる。
遠くで菫を抱く雪を見つめた。
『あなた、あやめっていうの?』
僕をはっきりと見て、こちらへ歩み寄ってきてくれた素敵な女の子は、君だけだった。
「ゆき・・・」
最期に、僕を見てくれないか?
「それはできない相談だ」
どんっ、と脳に衝撃が走る。
龍胆が、その眼球ごと突き刺し、とどめを刺したのだ。
「雪の目にうつるのは、俺だけで充分だ」
俺もお前と変わらないのかもしれない。
雪を愛したこと。
愛し方が違っただけ。
「――だが俺は、雪を悲しませない」
それだけが、違うところだと。
いつか、君に胸を張って言える日が来ることを願う。
人殺しの俺。
罪を償う事もできず、鬼になってしまった俺。
雪を幸せにできないのに、側にとどめおく、勝手な俺。
「龍胆さまぁっ!!」
雪が飛び込むように抱きついてくる。
よろけ、それを受け止めきれずに、尻餅をついた。
青い夜の闇を、雪、龍胆、菫の三人は歩く。
たどたどしい歩みだ。深手を負った二人を雪ひとりで連れ帰ることは難しい。雪は龍胆を肩で支え、片手で菫と手を繋いでいた。
夜空の月は雲が隠してしまっている。月明かりもない夜道はどこまでも続いているようで、雪は肩に回された龍胆の腕をぎゅっと握る。
「・・・ゆき?」
龍胆は怪訝な顔をした。荒い呼吸が入り混じった声だ。
「・・・なんでも、ありません」
雪ははにかんだ。
「――・・・」
龍胆は静かに目を見開く。
不意に、龍胆は立ち止まった。
「龍胆さま・・・?」
「――すまない。着物、せっかく純白で綺麗だったのに。・・・俺が用意したのに、俺が汚してしまった」
雪は最初、なんのことか分からなかったが、はっとして自分の体を見下ろす。
彼の言う通り、純白の振り袖は赤黒い血がべったりと付着していた。
龍胆は絞り出すように言う。
「俺の行く先々、血がつきまとう」
空からはふわり、白いわた雪が舞いはじめた。
凍える心にふたをするように。ふわりふわりと、踊りながら。
雪は首を振った。
「そんなことは、――・・・あっ」
龍胆は雪の手から、眠りこけた菫を抱き上げた。――まるで引きはがすようだ。
「俺たちは、ここで別れる。――鬼は鬼らしく、闇を選ぶよ」
そう言って、龍胆は微笑む。それは、雪を村人に預けたあの日と重なった。
龍胆さま、と名を呼ぶ雪を遮って、彼は続ける。
「俺と出会いさえしなければ、君はあんな恐ろしい目に合わずにすんだ。
・・・でもまだ、間に合う。太陽にはひなたが、鬼には夜が。あるべき場所へ帰ろう」
雪は肺の奥から凍っていくような、嫌な感覚に襲われた。
いま、ここで彼を引き止めなければ。
ここでちゃんと伝えなければ。
本当にもう、二度と逢えない気がした。そしてそれは、当たっている。
龍胆の白い髪は輪をかけて白い。向こう側が透けて見えるようにさえ思えた。
鬼は幽霊のように消えることはない。だが――・・・・・・。
心が、死にかけている。
雪はぎゅっと、拳を握った。
「――――・・・・・・龍胆さまは、太陽にはなれなくても、あたたかい人だと、わたしは思います」
一緒にいると、心がぽかぽかして、まるでひだまりの中にいるみたいで。
龍胆ははっと思い出した。
『龍胆さまは、あたたかいです』
耳をほんのり甘く染めて言った彼女の声が、今頃になって脳裏に響く。
雪はふわりと、はにかんだ。
「あなたに逢うまでは、いつ死んでもいいとさえ思っていましたが。――あなたに出逢ってからは、もっと、生きてみたいと思うようになりました」
「・・・・・・っ」
龍胆は片手で口を抑えた。そうでもしなければ、込み上げてくるこのみっともない感情を、隠しきれなかった。
「このお着物だって、汚れたなんて思いません。・・・思うわけ、ないじゃないですか。あなたの、血なのに」
雪は、龍胆の手をとる。額に、すがるように押し当てた。
「もう、いなくならないで」
龍胆は無言で掻き抱く。
ぎゅっと、自分の一部にするように。
――必要とされている。必要と、してくれている。
この世界が全員、俺を断罪しても。雪は。
俺を許してくれる。
ここが、俺の居場所だ。
そう、思っていいんだろう?
訪ね返す勇気はなかったが、きっと、彼女はうなずいてくれる気がして。
「わかった。・・・もう、いなくならないから」
鬼は再び、帰路についた。
闇ではない。彼女と過ごす、我が家へ。
続く。
母親からの愛情は薄かった。
心にぽっかりと穴が空いたまま、時はすぎる。
そんなとき、好きな人ができた。黒猫を飼っていた村娘だ。
でも、彼女は僕を好きになってはくれなかった。
君がほしい。
君の目にうつるのは、僕だけでいい。
気がつけば君は、僕の腕の中で冷たくなっていた。
――死んだ君の瞳にうつる僕。やっと、僕を見てくれたね。
でもなぜか、君は人形のような顔をしていた。
まだたりない。
君の存在を知っているのは、僕だけでいい。
だから家族を殺してみたけれど。やっぱり気が晴れない。
――生きている君に、僕を見てほしかったのか・・・?
餓鬼は――俗名あやめは、首をひねる。
遠くで菫を抱く雪を見つめた。
『あなた、あやめっていうの?』
僕をはっきりと見て、こちらへ歩み寄ってきてくれた素敵な女の子は、君だけだった。
「ゆき・・・」
最期に、僕を見てくれないか?
「それはできない相談だ」
どんっ、と脳に衝撃が走る。
龍胆が、その眼球ごと突き刺し、とどめを刺したのだ。
「雪の目にうつるのは、俺だけで充分だ」
俺もお前と変わらないのかもしれない。
雪を愛したこと。
愛し方が違っただけ。
「――だが俺は、雪を悲しませない」
それだけが、違うところだと。
いつか、君に胸を張って言える日が来ることを願う。
人殺しの俺。
罪を償う事もできず、鬼になってしまった俺。
雪を幸せにできないのに、側にとどめおく、勝手な俺。
「龍胆さまぁっ!!」
雪が飛び込むように抱きついてくる。
よろけ、それを受け止めきれずに、尻餅をついた。
青い夜の闇を、雪、龍胆、菫の三人は歩く。
たどたどしい歩みだ。深手を負った二人を雪ひとりで連れ帰ることは難しい。雪は龍胆を肩で支え、片手で菫と手を繋いでいた。
夜空の月は雲が隠してしまっている。月明かりもない夜道はどこまでも続いているようで、雪は肩に回された龍胆の腕をぎゅっと握る。
「・・・ゆき?」
龍胆は怪訝な顔をした。荒い呼吸が入り混じった声だ。
「・・・なんでも、ありません」
雪ははにかんだ。
「――・・・」
龍胆は静かに目を見開く。
不意に、龍胆は立ち止まった。
「龍胆さま・・・?」
「――すまない。着物、せっかく純白で綺麗だったのに。・・・俺が用意したのに、俺が汚してしまった」
雪は最初、なんのことか分からなかったが、はっとして自分の体を見下ろす。
彼の言う通り、純白の振り袖は赤黒い血がべったりと付着していた。
龍胆は絞り出すように言う。
「俺の行く先々、血がつきまとう」
空からはふわり、白いわた雪が舞いはじめた。
凍える心にふたをするように。ふわりふわりと、踊りながら。
雪は首を振った。
「そんなことは、――・・・あっ」
龍胆は雪の手から、眠りこけた菫を抱き上げた。――まるで引きはがすようだ。
「俺たちは、ここで別れる。――鬼は鬼らしく、闇を選ぶよ」
そう言って、龍胆は微笑む。それは、雪を村人に預けたあの日と重なった。
龍胆さま、と名を呼ぶ雪を遮って、彼は続ける。
「俺と出会いさえしなければ、君はあんな恐ろしい目に合わずにすんだ。
・・・でもまだ、間に合う。太陽にはひなたが、鬼には夜が。あるべき場所へ帰ろう」
雪は肺の奥から凍っていくような、嫌な感覚に襲われた。
いま、ここで彼を引き止めなければ。
ここでちゃんと伝えなければ。
本当にもう、二度と逢えない気がした。そしてそれは、当たっている。
龍胆の白い髪は輪をかけて白い。向こう側が透けて見えるようにさえ思えた。
鬼は幽霊のように消えることはない。だが――・・・・・・。
心が、死にかけている。
雪はぎゅっと、拳を握った。
「――――・・・・・・龍胆さまは、太陽にはなれなくても、あたたかい人だと、わたしは思います」
一緒にいると、心がぽかぽかして、まるでひだまりの中にいるみたいで。
龍胆ははっと思い出した。
『龍胆さまは、あたたかいです』
耳をほんのり甘く染めて言った彼女の声が、今頃になって脳裏に響く。
雪はふわりと、はにかんだ。
「あなたに逢うまでは、いつ死んでもいいとさえ思っていましたが。――あなたに出逢ってからは、もっと、生きてみたいと思うようになりました」
「・・・・・・っ」
龍胆は片手で口を抑えた。そうでもしなければ、込み上げてくるこのみっともない感情を、隠しきれなかった。
「このお着物だって、汚れたなんて思いません。・・・思うわけ、ないじゃないですか。あなたの、血なのに」
雪は、龍胆の手をとる。額に、すがるように押し当てた。
「もう、いなくならないで」
龍胆は無言で掻き抱く。
ぎゅっと、自分の一部にするように。
――必要とされている。必要と、してくれている。
この世界が全員、俺を断罪しても。雪は。
俺を許してくれる。
ここが、俺の居場所だ。
そう、思っていいんだろう?
訪ね返す勇気はなかったが、きっと、彼女はうなずいてくれる気がして。
「わかった。・・・もう、いなくならないから」
鬼は再び、帰路についた。
闇ではない。彼女と過ごす、我が家へ。
続く。