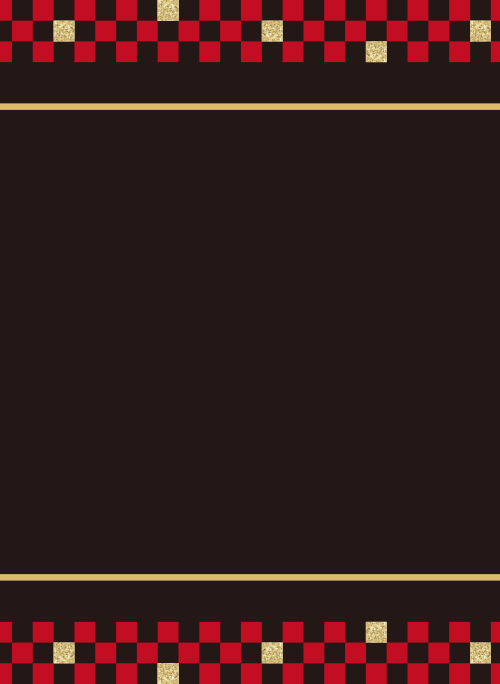龍胆が向かったのは、椿の咲き乱れる庭園だった。
真っ赤な花びらは女の唇のように赤い。
「いい香り・・・」
雪は龍胆の腕から降りると、深く息を吸い込んだ。地面にはふかふかの雪が積もっている。
「所有者の金持ちが、庶民向けに開放しているんだ。・・・雪に椿は映えるね」
うまいことを言う。龍胆は得意げに胸を反らす。昼どきだからか人は少なく、貸し切り状態だ。
雪は目を輝かせ、椿を見て回る。白い振り袖を翻す姿は微笑ましい。
「あら?」
そんな中、雪はめずらしい一輪を見つけた。
(青い椿・・・?)
世にも珍しい。青い椿が一輪だけ咲いている。
思わず、雪は走り出した。
「まて、雪。はぐれるぞ・・・!」
龍胆は手を伸ばす。
その時だった。
背後に殺気を感じた。
「人斬りともあろうものが、僕ごときに後ろを取られるとは。ずいぶんと腑抜けになったものだ」
ドンッ!!
「――ぐ、あ・・・っ!?」
龍胆はごぼっと口から血を吐いた。
餓鬼が、片手で鋭く龍胆の胸を刺し貫いていた。
「さっきの花は・・・?」
雪は辺りをきょろきょろ見渡した。花が逃げるはずないのに、どこへ消えたのか。
「きれいだろう。僕のとっておきの花だ」
不意に、男の美声が響いた。
帽子(ハット)をかぶった美男。着流しをさらりと着ている。
青い瞳はギラリと光った。
餓鬼だ。
垣根からあらわれると、瞬間、雪を抱きよせた。
――!?
雪はいきなりのことについていけない。男は構わず、濡れた瞳でゆっくりと問うた。
「まずは君を消毒しなければ。あの男に何をされた? 一週間もいっしょにいたんだ。接吻だけではないはずだよ?」
――さあ、教えて?
その眼はぎらぎらと獰猛な獣のようだった。血で汚れた右手が目に入る。
「その手は・・・!」
雪は叫ぶ。嫌な予感が汗となって滑り落ちる。
餓鬼は笑う。
ふと。――茂みが音を立てた。
巨大な黒い影が餓鬼目掛け飛びかかってきた。
大きな黒猫だ。
男の手にがぶりと噛みつくと、右手を引きちぎった。
「おっと!」
男はさして痛がる様子もない。雪は猫にくわえられ、間合いから外れた場所へ降ろされた。
「くろちゃん? どうしてここに・・・?」
大きな猫又は、雪の友達だった。
真冬でも凍死せずに澄んだのは、この猫が温めてくれたからである。
「・・・ふん。死んだ飼い主の敵討ちか?」
男は噛みちぎられた腕を気に留める様子もなく言った。
「飼い主の血をすすって百年もの間、僕を殺すために生き延びたとは。・・・だが時とは残酷なものだな。今では死体を喰う火車にまで成り下がっている」
男はニヤリと笑う。
「その猫もあの男も。――雪。君の周りは揃いも揃って人殺しばかりだ」
刹那、男は間合いを詰めた。
猫は素早く反応する。男の首を噛みちぎろうと口を開けたが、男の動きの方が速かった。
剛腕で腹をえぐるように強烈な突きを放つ。
哀れ、猫は勢いもそのままにふっとばされた。
変怪が溶け、もとの普通の猫へと戻る。
「ああっ!!」
駆け寄ろうとした雪の肩を男はつかみ、引き寄せる。
「まだ僕の質問に答えていないよ、ゆき」
震える雪の頬に手を添え、ぐいっと顔を近づける。
「さあ、言え。どこまであの男に許したっ!?」
雪は涙に濡れる顔で首を振る。今どう答えても、男の逆鱗に触れるだろう。
男は舌打ちすると、めきめきと牙を生やした。
「や、やめて・・・っ!」
構わず、雪の襟をくつろげ、首筋をあらわにする。噛みつくつもりなのだ。
(たすけて・・・!!)
もともと病弱な体。朦朧とする意識の中、雪は雪の舞う灰色の空を見上げる。
涙が頬を伝う。次に来るであろう激痛へ体が身構える。
真っ赤な花びらは女の唇のように赤い。
「いい香り・・・」
雪は龍胆の腕から降りると、深く息を吸い込んだ。地面にはふかふかの雪が積もっている。
「所有者の金持ちが、庶民向けに開放しているんだ。・・・雪に椿は映えるね」
うまいことを言う。龍胆は得意げに胸を反らす。昼どきだからか人は少なく、貸し切り状態だ。
雪は目を輝かせ、椿を見て回る。白い振り袖を翻す姿は微笑ましい。
「あら?」
そんな中、雪はめずらしい一輪を見つけた。
(青い椿・・・?)
世にも珍しい。青い椿が一輪だけ咲いている。
思わず、雪は走り出した。
「まて、雪。はぐれるぞ・・・!」
龍胆は手を伸ばす。
その時だった。
背後に殺気を感じた。
「人斬りともあろうものが、僕ごときに後ろを取られるとは。ずいぶんと腑抜けになったものだ」
ドンッ!!
「――ぐ、あ・・・っ!?」
龍胆はごぼっと口から血を吐いた。
餓鬼が、片手で鋭く龍胆の胸を刺し貫いていた。
「さっきの花は・・・?」
雪は辺りをきょろきょろ見渡した。花が逃げるはずないのに、どこへ消えたのか。
「きれいだろう。僕のとっておきの花だ」
不意に、男の美声が響いた。
帽子(ハット)をかぶった美男。着流しをさらりと着ている。
青い瞳はギラリと光った。
餓鬼だ。
垣根からあらわれると、瞬間、雪を抱きよせた。
――!?
雪はいきなりのことについていけない。男は構わず、濡れた瞳でゆっくりと問うた。
「まずは君を消毒しなければ。あの男に何をされた? 一週間もいっしょにいたんだ。接吻だけではないはずだよ?」
――さあ、教えて?
その眼はぎらぎらと獰猛な獣のようだった。血で汚れた右手が目に入る。
「その手は・・・!」
雪は叫ぶ。嫌な予感が汗となって滑り落ちる。
餓鬼は笑う。
ふと。――茂みが音を立てた。
巨大な黒い影が餓鬼目掛け飛びかかってきた。
大きな黒猫だ。
男の手にがぶりと噛みつくと、右手を引きちぎった。
「おっと!」
男はさして痛がる様子もない。雪は猫にくわえられ、間合いから外れた場所へ降ろされた。
「くろちゃん? どうしてここに・・・?」
大きな猫又は、雪の友達だった。
真冬でも凍死せずに澄んだのは、この猫が温めてくれたからである。
「・・・ふん。死んだ飼い主の敵討ちか?」
男は噛みちぎられた腕を気に留める様子もなく言った。
「飼い主の血をすすって百年もの間、僕を殺すために生き延びたとは。・・・だが時とは残酷なものだな。今では死体を喰う火車にまで成り下がっている」
男はニヤリと笑う。
「その猫もあの男も。――雪。君の周りは揃いも揃って人殺しばかりだ」
刹那、男は間合いを詰めた。
猫は素早く反応する。男の首を噛みちぎろうと口を開けたが、男の動きの方が速かった。
剛腕で腹をえぐるように強烈な突きを放つ。
哀れ、猫は勢いもそのままにふっとばされた。
変怪が溶け、もとの普通の猫へと戻る。
「ああっ!!」
駆け寄ろうとした雪の肩を男はつかみ、引き寄せる。
「まだ僕の質問に答えていないよ、ゆき」
震える雪の頬に手を添え、ぐいっと顔を近づける。
「さあ、言え。どこまであの男に許したっ!?」
雪は涙に濡れる顔で首を振る。今どう答えても、男の逆鱗に触れるだろう。
男は舌打ちすると、めきめきと牙を生やした。
「や、やめて・・・っ!」
構わず、雪の襟をくつろげ、首筋をあらわにする。噛みつくつもりなのだ。
(たすけて・・・!!)
もともと病弱な体。朦朧とする意識の中、雪は雪の舞う灰色の空を見上げる。
涙が頬を伝う。次に来るであろう激痛へ体が身構える。