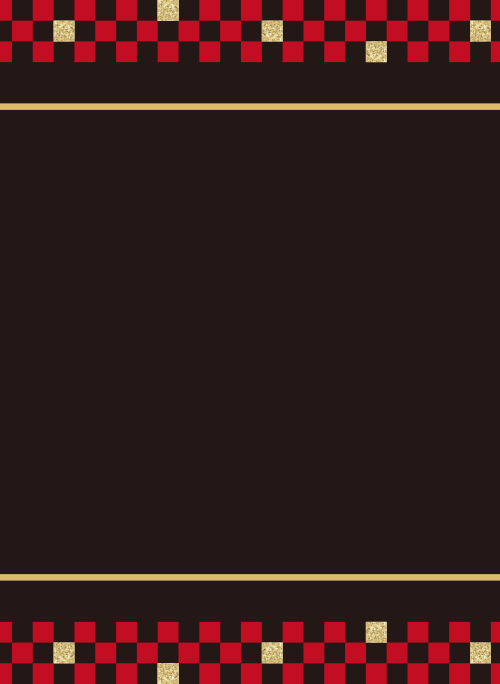・・・・・・・・・やがて、噛みつき妖怪(菫)は力尽きて寝た。
寒空の下、雪を探して疲れたのだろう。龍胆はやむなく、押し入れをこじ開け、布団を引っ張り出して隙間を作ると、菫を寝かせ、ピシャリと閉めた。
「なにゆえ押入れに・・・?」
「子供部屋だ。こうでもしなければ、君と二人きりになれない」
龍胆は腰に手を当て、「ようやく開放された!」と伸びをした。そして次に顔を上げたときには、余裕を取り戻していた。
「さて。邪魔者はいなくなった。俺の愛情たっぷりの粥を食べてくれ」
「おかゆを食べるだけなのに、菫ちゃんは邪魔なの?」
雪は警戒し、ちょっと体を丸める。思うように動けないのがなんとも腹立たしい。
「深い意味はない。・・・十年ぶりの再会なんだ。独り占めしたいのは当たり前だろ?」
「わたしは、あなたとお会いしたことはありません」
雪はピシャリと言った。
よくよく考えれば、彼は出会ったときから『雪』と呼んでいた。名前を知っていたのだ。
(他にも、妙に私のことに詳しいわ・・・)
ここに連れてこられたとき。彼は甲斐甲斐しく世話を焼いてくれた。
『枕はそばがらが好きだったね』
そう言いながら布団を敷いたのだ。
そんな私生活の、家族しか知らないようなことまで、彼は熟知している。
・・・若干、不気味に思えてくる。
でもこちらを見下ろす青い瞳は美しく、まっすぐだ。
はっきりと敵意をぶつけるのはためらわれた。
龍胆は、ぽつりと言う。
「憶(おぼ)えていないだけさ」
――・・・もっとも、俺にとって、人生最大の幸福な時間であり、『生(せい)』を失った出逢いでもあるが。
そっと唇を噛み、龍胆は言葉を飲み込む。
思い出したところで誰も幸せにならない記憶に、価値はない。
(だが、思いのほか寂しいな・・・)
――俺だけが憶えている時間。
龍胆は、はにかんだ。
雪は目を見開く。
(どうして・・・?)
無垢な笑顔。
鬼にはとても似つかわしくない、思いやりのにじむ瞳。
龍胆はさっさと切り替え、雪に食べさせる準備を始めたが、雪は熱に浮かされたように、ぼうっと鬼の横顔を眺めた。
――さっきの笑顔の理由が、わからなかった。
体を起こされ、膝に抱き上げられても、雪は抵抗しなかった。
笑顔の理由(わけ)ばかり考える。
粥をレンゲですくい、口元に持っていく。雪はなんの疑いもなくそれを食べた。
ひとくち。
ふたくち・・・。
「――」
「どうしたのだね?」
龍胆は慌てた。
雪は、涙を流していた。ぽろぽろと。大粒の涙は次から次にあふれてとまらない。
「・・・・・・あたたかい」
龍胆はギクッと体を強張らせた。
やがて、それが粥のことを指していると気づくと、ほっと力を抜く。