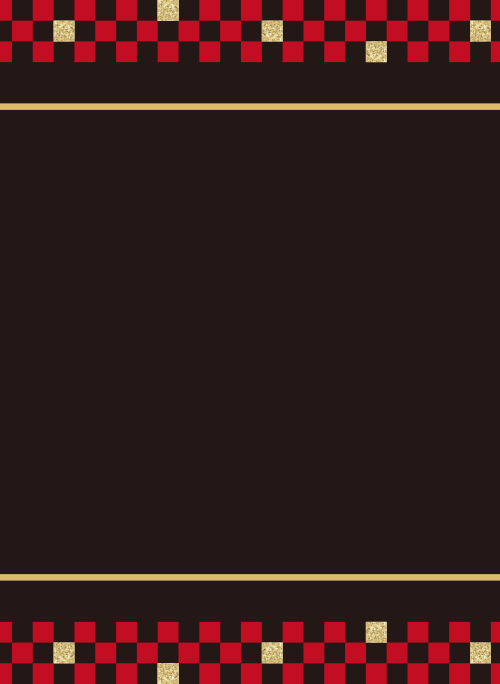花散里の山奥に踏み入る男の影。
着流し姿に異国の帽子(ハット)をかぶり、寒そうに襟巻きを巻いている。
――餓鬼は、たっぷりと微笑した。舌なめずりする唇はふっくらとし、遊女のように赤々としている。
「屍食鬼め。うまくやったものだ。・・・この僕に居場所を気取らせないとは」
帽子の隙間から覗く瞳は、苛立ちにゆれている。村中しらみつぶしに探し回ったが、雪の髪の毛一筋すら見つけられなかった。
――・・・はやく雪を取り戻さねば。
「彼女は幼い頃から大切に保管してきた一級品。・・・処女雪を汚された気分だね」
餓鬼の足元では、ネズミほども小さい影がぞわぞわとうごめいた。
暗闇でよく見えない。しかし月の光に照らし出されたそれらは、髪の毛、五本の指、四肢がそれぞれ生えており、まるで人間が縮んだような生き物の集団のようだ。
一匹一匹のまなこは青く輝き、生者の肉を欲している。きぃ、きぃ・・・と鳴きながら、歯をカタカタと鳴らす。
男は、そのうちの一匹を手にすくい取る。あやすように指先で小さな頭をなでた。
「・・・雪には十年前『飴玉』を食べさせた」
――時期に動き出すだろう。