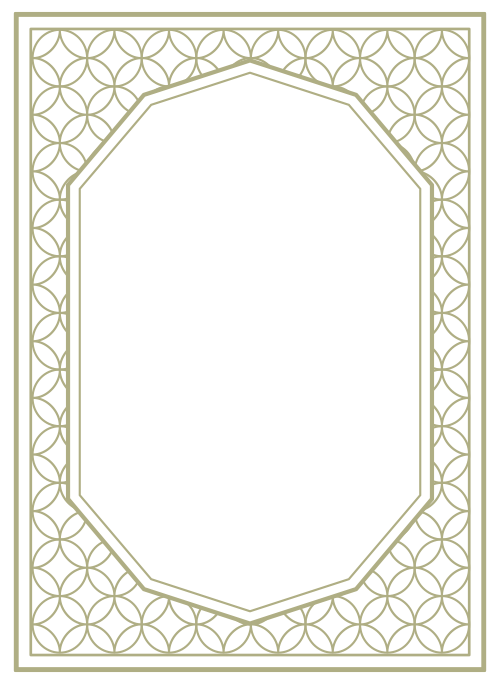「うん?」
「いつもと違いすぎます。――出生のこと、咲桜に話す気はなかったんじゃないんですか?」
「……君の瞳は随分鍛えられたねえ」
「お蔭さまです。咲桜の父君ということで、俺も心配する権利はあると思いますが」
「………」
在義さんは観念したように口元を歪めた。
「……流夜くんは、天龍の千歳の家を憶えているかい?」
「千歳? ……随分奥まったところにある家ですよね? でも、あそこは治外法権だとかじいさんに言われて近づいたことはありませんでしたが……」
うん、と在義さんは肯いた。
「それでいいんだよ。天龍の郷自体、はぐれ者たちが集まって作った集落だからね。同じ系統同士が同じ谷に住んでいる。君や――龍生の家や春芽の家は比較的新しく入った普通の人たちが作った集落だからね。知らなくていいんだ」
そうだったのか。確かに天龍では山間ごとにまとまった感じのある郷だった。
山をまるごと天龍と呼んでいたし、地名でもあったけれど。
集落はたくさんあって、あまり相互付き合いはなかったと記憶している。
「華取の家は――拝み屋というのは、違うんですか?」
「ああ。華取は影小路(かげのこうじ)っていう、天龍の大元締めの一つに繋がる家柄でね。……そこから面倒を頼まれたんだ」
「面倒……?」
「千歳は、いわゆる没落貴族だ。けれど今もそれなりの格式と権力がある。そこで動きがありそうだから対応しろ、とね」
「在義さんに命令したんですかっ? 命知らずな……」
「命令出来る立場にあるんだよ。まあ――元々、私は本家に籍は戻していないから華取の名をもってどうこうするわけじゃない。華取の家はあの火事で絶えている。それでいいんだ。けれどここが分家で、私が唯一の直系である以上、ある程度はしないといけないことがある」
と、苦笑したあとに額に組んだ手を当てて長くため息をついた。
「ほんとーにあの小路(こうじ)と千歳は厄介ごとばかり起こしやがって……まったく忌々しい……」