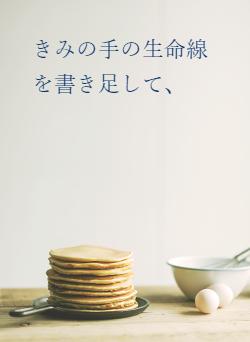二十六歳、春。六年付き合い結婚間近だった婚約者に振られ、仕事を辞め、母の実家がある京都へやって来た。
母の実家は江戸時代からあるという立派な門構えの大きな旧家で、使っていない部屋が多数ある。婚約破棄を聞き心を痛めた祖父母と伯父夫妻が、気分転換にと誘ってくれたのだ。柔和な雰囲気の祖父母と伯父夫妻は温かく迎え入れてくれて、ささくれていたわたしの心をたいそう癒した。
結婚が無くなったのも、仕事を辞めたのも、まあ良い。いくらでもやり直せる。でもどうして急に、京都に来る気になったのか。それだけが不思議でならない。
誘われたからとはいえ、そこまで思い入れがあるわけではない。母の実家のため数年に一度は遊びに来ていたけれど、それは子どもの頃の話だ。大きくなるにつれ部活や勉強やアルバイトで忙しくなったため、遠く離れた京都へはなかなか足が向かなかった。特に成人してからの六年は、一度も来ていない。高校の修学旅行は沖縄だったし、大学の卒業旅行は北海道へ行った。
それなのに祖父母からの連絡をもらったとき、行かなければと思ったのだ。むしろ、今行かなければならない気がした。
とにもかくにも久しぶりの京都だ。お寺巡りでもして、しばらくゆっくりして、心を静めて。それからまた職探しをすればいい。新しい恋だっていつか見つかるはずだ。
祖父母宅に到着して数日は、のんびり過ごした。祖父母とおしゃべりをしたり、伯母と一緒に家事をしたり買い物に出かけたり。
そして週末。伯父が朝から蔵の掃除をしていたから、手伝うことにした。どうやらあまりの古道具の多さに横着して、ここ数十年、一度も掃除をしていなかったらしい。
足を踏み入れた蔵は、なるほど確かに埃にまみれ、見るからに古そうな道具でいっぱいだった。
この多くはもう売ってしまうか捨ててしまうか、歴史的な価値があるものなら施設や団体へ寄付するか。そうでもしないとせっかくの大きな蔵なのに新しいものが入れられないし、どこに何があるのかすらも分からない。だから気に入るものがあったら持って行ってもいいよ、と。伯父は蔵の惨状に苦笑いしつつ言った。
しかし気になるものと言っても。これだけ古く、乱雑に置かれた道具の中から「これぞ」というものを見つけるのは難しい。わたしも苦笑いしつつ「そうします」と返しておいた。