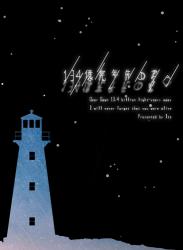歩き出した私の横を、ポケットに手を突っ込んだ瀬川が並ぶ。
ぺしゃんこに潰れた瀬川のスクバは、私の空っぽのリュックの隣で揺れていた。それだけでどこか安心した気分になるのは、これが初めてではない。
私だけ苦しいレースを早上がりしてしまったこと。
どんな応援も傷付けそうで、友達と上手く話せないこと。
なんの目標もないまま、子供と大人の境目に取り残されてしまったこと。
瀬川と暇潰しをする間は、全部考えずに済んだ。
逃げているのだと糾弾されてもいい。
ただ瀬川だけは、何も言わず私の背中に立ってくれるのだろうと確信めいた自信と信頼があった。
同じ想いを共有しているだけ。
踏み込むことはしない。
ただ、この不思議な関係がもうすぐ終わりを迎えることは、私を少しだけ感傷的な気持ちにさせた。
ぺしゃんこに潰れた瀬川のスクバは、私の空っぽのリュックの隣で揺れていた。それだけでどこか安心した気分になるのは、これが初めてではない。
私だけ苦しいレースを早上がりしてしまったこと。
どんな応援も傷付けそうで、友達と上手く話せないこと。
なんの目標もないまま、子供と大人の境目に取り残されてしまったこと。
瀬川と暇潰しをする間は、全部考えずに済んだ。
逃げているのだと糾弾されてもいい。
ただ瀬川だけは、何も言わず私の背中に立ってくれるのだろうと確信めいた自信と信頼があった。
同じ想いを共有しているだけ。
踏み込むことはしない。
ただ、この不思議な関係がもうすぐ終わりを迎えることは、私を少しだけ感傷的な気持ちにさせた。