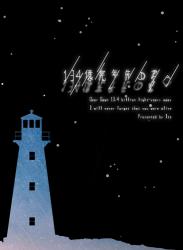微睡みに誘われそうな午後の陽射しの波は、ちらちらと私の手の甲を撫でていた。
もうすぐやってくる季節の兆しが、指先を覆うようにして伸ばしたセーターの隙間から忍び込む。手指が冷たいから、まだ冬の残り香の方が優勢だ。
窓の外を眺めたかったけど、そうすると瀬川の姿が視界に入るから向かない。
これは意地を張っているわけじゃなくて、本当に癪なのだということを、私は一体誰に釈明しようとしているんだろうか。
そんなことを考えながら人差し指の腹で消しカスを集め、くるくると丸めていると、瀬川が私の方へ自分のノートを差し出した。
「何?」
尋ねると、瀬川は何も言わずにシャーペンの頭でノートの上の一点を指す。
私は瀬川の細長い指、綺麗に揃えられた爪、剥げたシャーペンのキャップの先を辿った。
そのタイミングを計って、瀬川がぽつりと漏らす。
もうすぐやってくる季節の兆しが、指先を覆うようにして伸ばしたセーターの隙間から忍び込む。手指が冷たいから、まだ冬の残り香の方が優勢だ。
窓の外を眺めたかったけど、そうすると瀬川の姿が視界に入るから向かない。
これは意地を張っているわけじゃなくて、本当に癪なのだということを、私は一体誰に釈明しようとしているんだろうか。
そんなことを考えながら人差し指の腹で消しカスを集め、くるくると丸めていると、瀬川が私の方へ自分のノートを差し出した。
「何?」
尋ねると、瀬川は何も言わずにシャーペンの頭でノートの上の一点を指す。
私は瀬川の細長い指、綺麗に揃えられた爪、剥げたシャーペンのキャップの先を辿った。
そのタイミングを計って、瀬川がぽつりと漏らす。