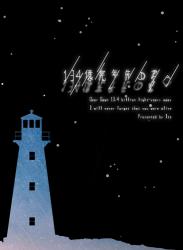「三波。お前のことが好きじゃなくても、俺はきっとお前と暇潰ししてた」
「え……」
瀬川は「すみません。ペン貸して貰えますか」と、乗務員からペンを借り受けると、私の前に立つ。
「手、出せ」
恐る恐る差し出した左手が、瀬川の左手の熱に触れる。
瀬川は右手に持ったペンで、私の手の甲に十一桁の数字を書き連ねた。
「暇潰し、呼べよ。同志なんだから」
そう言って瀬川が残したのは、瀬川の携帯番号だった。
その瞬間、ぶわりと視界が滲んで、橙の光が網膜に広がった。
ぽろぽろと零れる涙は、頬を伝い、顎先滑り、私と瀬川の間に落ちる。
違わなかった。
瀬川はずっと瀬川のままだった。
ずっと、隣に並んでいてくれたのだ。
私を好きだと言った時も、私が瀬川を拒絶した時も。
出会った頃から変わらずに。
「……ふ、ミミズが這った字」
泣いているのか笑っているのか分からない、不格好な顔で呟くと、瀬川は私を軽く小突いた。
私は左手を右手で包み、胸の前で力いっぱい抱きしめる。
消えないように。忘れないように。
どんな想いも、全部私の中の傷になればいい。
瀬川はそう願う私の隣で、ただやって来る季節を待つように、マフラーに顔を埋めていた。
「え……」
瀬川は「すみません。ペン貸して貰えますか」と、乗務員からペンを借り受けると、私の前に立つ。
「手、出せ」
恐る恐る差し出した左手が、瀬川の左手の熱に触れる。
瀬川は右手に持ったペンで、私の手の甲に十一桁の数字を書き連ねた。
「暇潰し、呼べよ。同志なんだから」
そう言って瀬川が残したのは、瀬川の携帯番号だった。
その瞬間、ぶわりと視界が滲んで、橙の光が網膜に広がった。
ぽろぽろと零れる涙は、頬を伝い、顎先滑り、私と瀬川の間に落ちる。
違わなかった。
瀬川はずっと瀬川のままだった。
ずっと、隣に並んでいてくれたのだ。
私を好きだと言った時も、私が瀬川を拒絶した時も。
出会った頃から変わらずに。
「……ふ、ミミズが這った字」
泣いているのか笑っているのか分からない、不格好な顔で呟くと、瀬川は私を軽く小突いた。
私は左手を右手で包み、胸の前で力いっぱい抱きしめる。
消えないように。忘れないように。
どんな想いも、全部私の中の傷になればいい。
瀬川はそう願う私の隣で、ただやって来る季節を待つように、マフラーに顔を埋めていた。