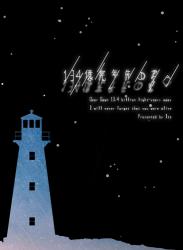聞き間違いかもしれない。
幻想だったのかもしれない。
それでも私は、瀬川にあんな言葉を吐かせてしまったのだ。
一番言いたくなかったであろうことを、言わせてしまった。
謝らなければ。そう思うのに、足はその場に縫い付けられたように動かない。
心が錆び付いたようにざらついて、指の先が冷えていた。
それが後悔というのだと気がついた時、私は溢れ出す感情を抑えることが出来なかった。
手の甲に透明な雫が落ちて、セーターが濃灰に滲む。
私は俯いて、右手を額に押し当てた。
瀬川も、瀬川と過ごした一ヶ月も、どちらもかけがえのないものだった。
どちらも大切で、手放し難くて、だからこそ選べなかった。
そう素直に伝えていたら、今と違う未来が隣にあったのかもしれない。
瀬川はまた、笑ってくれたかもしれない。
明日、小さくて短い青春が終わりを告げる時、もしも、まだ未来に触れることができたなら。
「ごめん、瀬川……」
呟いた名前は、零れ落ちた一粒の涙と共に、机の上で弾けて消える。
窓の外では、枝の先に新しい命が芽吹いていた。
幻想だったのかもしれない。
それでも私は、瀬川にあんな言葉を吐かせてしまったのだ。
一番言いたくなかったであろうことを、言わせてしまった。
謝らなければ。そう思うのに、足はその場に縫い付けられたように動かない。
心が錆び付いたようにざらついて、指の先が冷えていた。
それが後悔というのだと気がついた時、私は溢れ出す感情を抑えることが出来なかった。
手の甲に透明な雫が落ちて、セーターが濃灰に滲む。
私は俯いて、右手を額に押し当てた。
瀬川も、瀬川と過ごした一ヶ月も、どちらもかけがえのないものだった。
どちらも大切で、手放し難くて、だからこそ選べなかった。
そう素直に伝えていたら、今と違う未来が隣にあったのかもしれない。
瀬川はまた、笑ってくれたかもしれない。
明日、小さくて短い青春が終わりを告げる時、もしも、まだ未来に触れることができたなら。
「ごめん、瀬川……」
呟いた名前は、零れ落ちた一粒の涙と共に、机の上で弾けて消える。
窓の外では、枝の先に新しい命が芽吹いていた。