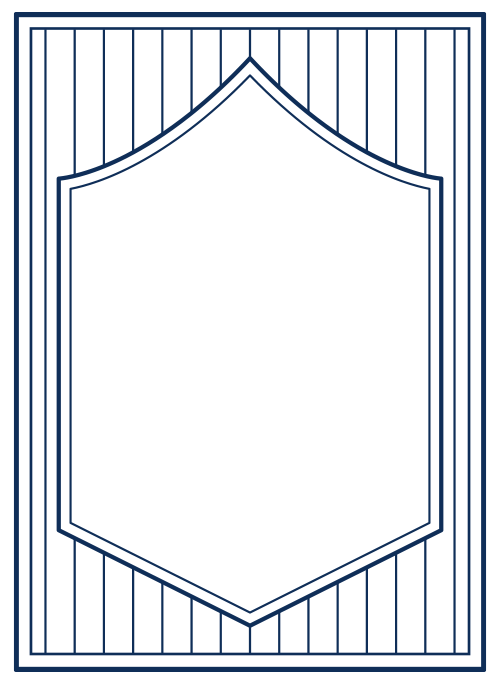「本家に呼び出したと思ったら、またその話か。パーティーと言い見合いと言い、いい加減にしてくれ!父さん。母さん」
タイを緩めながら、心底うんざりした顔で畳に座する一人息子を、刀隠家現当主にして境御前たる夜斗と、夜斗の妻たる紗由香は「そう言わないで」と宥めた。
「これでも『鞘』が見付かれば…って、思っているんだよ。僕も紗由香も」
「霊術士の女の子達が全員違ったから、今度は違うタイプの子にしたのだけれど。とりあえず、写真だけでも見てみなさいな。『鞘』は見ればわかるんでしょう?」
母の視線につられて見た先には、山と積まれた釣書。げんなりと美斗は首を横に振った。
そんな息子の様子に、紗由香は困ったように眉を下げる。
「本来だったら、分家から一番霊力が高い子を許婚として小さい内から相手に決めるものだけれど、美斗が嫌だって言うから」
「美斗はこれでロマンチストだからねえ」
「似合わなくて悪かったな。父さん」
夜斗は笑い、同時に遠くを見るような顔になった。
「代々の境御前にとって、『鞘』は絶対的な存在。僕達刀隠の一族が守る弥籟刀の力を引き出すだけじゃない。ただひたすら愛しく思えて、一途な愛を生涯捧げ続ける事ができる、唯一無二の伴侶。うん。憧れるのはわかるよ」
「ちょっと。貴方」
軽く咎め立てするような声で呼びかける紗由香の肩を、夜斗は優しく引き寄せる。慈しむような眼差しを妻に向けた。
「確かに、当代の境御前である僕に『鞘』は見付からなかった。でもね。家同士が決めた許婚。政略結婚でこそあるけれど。僕にとって、君と過ごしてきた時間こそが最も大切なものなんだよ。紗由香。それだけ多くの時間の中で、君と想いを育んできた事に他ならないんだから」
「貴方…」
「紗由香」
「貴方」
「紗由香」
「この万年新婚夫婦は…」
語尾にハートマークでも付きそうな口調で互いを呼び合う両親の姿に、頭痛を堪える顔で美斗は呻いた。息子としては、夫婦仲が良い事は決して悪い事ではない。だがこのようにカップルめいた姿を見せ付けられると、呆れるものがある。
息子とは対照的に、父は笑顔で息子に視線を戻した。
「だから僕達としてはね。美斗。君も結婚適齢期になる事だし、『鞘』を見付ける力になりたいんだよ」
「俺は大学を卒業すらしていないんだ…。早すぎるだろう」
「高校の時もそう言っていたわね。で、よくパーティーから桃李君と一緒に逃げ出して、弓弦さん達が大騒ぎしていたわ」
紗由香の言葉に登場した『桃李君』と『弓弦さん』とは、刀隠の分家にあたる各務家の親子である。父子揃って刀隠に仕えているのだが、美斗にとって幼馴染でもある桃李は、どちらかと言うと同い年の友人と言える気安い間柄だった。なので、高校時代から突出した美貌の美斗が令嬢達に囲まれ辟易としている場合、令嬢達をうまくかわし、あわよくば揃って会場から脱走する手配もしていたのである。お付きの者達が手を焼いていたのは言うまでもない。そして後で2人は大目玉を食らっていた訳だが。
「今度こそはと思って行って、毎回がっかりする俺の身にもなってくれ…」
最初は刀隠の分家の少女達だった。次は日本中の霊術士の一族の中でも、名だたる家の娘達だった。それでも見付からなかったので、一般人の中でも有力な家の令嬢達を集めた。しかし「この人だ」と思える女性は、誰一人として見付からなかったのである。『霊術士の美しき次期筆頭の花嫁探し』という事で、どの女性達も華やいだ雰囲気を纏っていたが、対して美斗は温度の無い目で集う女性達を見ていたものだった。
夜斗は「うーん」と真剣な顔になる。
「どういう理屈になっているのか、刀隠の家が始まって以来、ずっとわからないままだけれど、『鞘』を特定する術は無いんだよね。まず血筋じゃない。家柄でもない。代々『鞘』として見出された――とは言っても、数はとても少ないけれど――女性達は、霊術士や一般人を問わない場合もあった。極端な話、日本中の女性という女性を集めてみないと、『鞘』を見付ける事は難しいだろうね」
眩暈を起こしたような息子に、紗由香は気遣わしげな眼差しを向ける。
「美斗。貴方の気持ちは汲みたいけれど、ここはやっぱり、分家から婚約者を決めた方がいいんじゃないのかしら」
「そうそう。政略結婚とは言っても、後から幾らでもラブラブになる事はできるよ。僕と紗由香みたいに」
「貴方ったら」
「本当だろう?」
「とにかく」
再び2人だけの世界を展開しそうな両親に、美斗は割って入った。
「俺は妥協して婚約者を決めるつもりは無い。俺が花嫁にするのは、『鞘』だけだ」
「ならまずは写真だけでも見なさいな。釣書まで読みなさいとは言わないから」
美斗の眼前に、どんと釣書の山が置かれた。
タイを緩めながら、心底うんざりした顔で畳に座する一人息子を、刀隠家現当主にして境御前たる夜斗と、夜斗の妻たる紗由香は「そう言わないで」と宥めた。
「これでも『鞘』が見付かれば…って、思っているんだよ。僕も紗由香も」
「霊術士の女の子達が全員違ったから、今度は違うタイプの子にしたのだけれど。とりあえず、写真だけでも見てみなさいな。『鞘』は見ればわかるんでしょう?」
母の視線につられて見た先には、山と積まれた釣書。げんなりと美斗は首を横に振った。
そんな息子の様子に、紗由香は困ったように眉を下げる。
「本来だったら、分家から一番霊力が高い子を許婚として小さい内から相手に決めるものだけれど、美斗が嫌だって言うから」
「美斗はこれでロマンチストだからねえ」
「似合わなくて悪かったな。父さん」
夜斗は笑い、同時に遠くを見るような顔になった。
「代々の境御前にとって、『鞘』は絶対的な存在。僕達刀隠の一族が守る弥籟刀の力を引き出すだけじゃない。ただひたすら愛しく思えて、一途な愛を生涯捧げ続ける事ができる、唯一無二の伴侶。うん。憧れるのはわかるよ」
「ちょっと。貴方」
軽く咎め立てするような声で呼びかける紗由香の肩を、夜斗は優しく引き寄せる。慈しむような眼差しを妻に向けた。
「確かに、当代の境御前である僕に『鞘』は見付からなかった。でもね。家同士が決めた許婚。政略結婚でこそあるけれど。僕にとって、君と過ごしてきた時間こそが最も大切なものなんだよ。紗由香。それだけ多くの時間の中で、君と想いを育んできた事に他ならないんだから」
「貴方…」
「紗由香」
「貴方」
「紗由香」
「この万年新婚夫婦は…」
語尾にハートマークでも付きそうな口調で互いを呼び合う両親の姿に、頭痛を堪える顔で美斗は呻いた。息子としては、夫婦仲が良い事は決して悪い事ではない。だがこのようにカップルめいた姿を見せ付けられると、呆れるものがある。
息子とは対照的に、父は笑顔で息子に視線を戻した。
「だから僕達としてはね。美斗。君も結婚適齢期になる事だし、『鞘』を見付ける力になりたいんだよ」
「俺は大学を卒業すらしていないんだ…。早すぎるだろう」
「高校の時もそう言っていたわね。で、よくパーティーから桃李君と一緒に逃げ出して、弓弦さん達が大騒ぎしていたわ」
紗由香の言葉に登場した『桃李君』と『弓弦さん』とは、刀隠の分家にあたる各務家の親子である。父子揃って刀隠に仕えているのだが、美斗にとって幼馴染でもある桃李は、どちらかと言うと同い年の友人と言える気安い間柄だった。なので、高校時代から突出した美貌の美斗が令嬢達に囲まれ辟易としている場合、令嬢達をうまくかわし、あわよくば揃って会場から脱走する手配もしていたのである。お付きの者達が手を焼いていたのは言うまでもない。そして後で2人は大目玉を食らっていた訳だが。
「今度こそはと思って行って、毎回がっかりする俺の身にもなってくれ…」
最初は刀隠の分家の少女達だった。次は日本中の霊術士の一族の中でも、名だたる家の娘達だった。それでも見付からなかったので、一般人の中でも有力な家の令嬢達を集めた。しかし「この人だ」と思える女性は、誰一人として見付からなかったのである。『霊術士の美しき次期筆頭の花嫁探し』という事で、どの女性達も華やいだ雰囲気を纏っていたが、対して美斗は温度の無い目で集う女性達を見ていたものだった。
夜斗は「うーん」と真剣な顔になる。
「どういう理屈になっているのか、刀隠の家が始まって以来、ずっとわからないままだけれど、『鞘』を特定する術は無いんだよね。まず血筋じゃない。家柄でもない。代々『鞘』として見出された――とは言っても、数はとても少ないけれど――女性達は、霊術士や一般人を問わない場合もあった。極端な話、日本中の女性という女性を集めてみないと、『鞘』を見付ける事は難しいだろうね」
眩暈を起こしたような息子に、紗由香は気遣わしげな眼差しを向ける。
「美斗。貴方の気持ちは汲みたいけれど、ここはやっぱり、分家から婚約者を決めた方がいいんじゃないのかしら」
「そうそう。政略結婚とは言っても、後から幾らでもラブラブになる事はできるよ。僕と紗由香みたいに」
「貴方ったら」
「本当だろう?」
「とにかく」
再び2人だけの世界を展開しそうな両親に、美斗は割って入った。
「俺は妥協して婚約者を決めるつもりは無い。俺が花嫁にするのは、『鞘』だけだ」
「ならまずは写真だけでも見なさいな。釣書まで読みなさいとは言わないから」
美斗の眼前に、どんと釣書の山が置かれた。