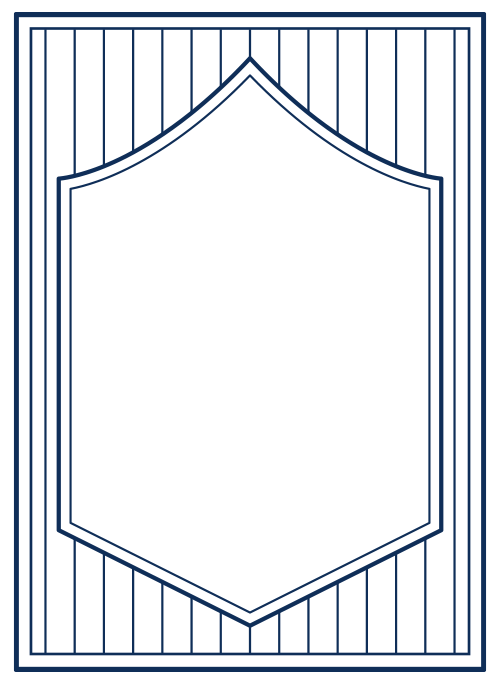「さて、皆さんにお配りした『アイギス・シリーズ』と名付けたその品ですが、名前の通りです。貴方を守ります」
気を取り直したように彼女は口を開いた。
「端的に言いますと、害意を持って近付いた者がいた場合、危害を加えるに使おうとした体の部位を壊死させます」
………………………。
先程とはうって変わって、講堂は静まり返った。強烈な言葉に、「壊死…?」と女子生徒達がうすら寒そうにストラップを見つめる。弟に「お姉ちゃん。お姉ちゃん。端的すぎ。もうちょい詳しく」と耳打ちされ、彼女は「わかっている」の意味を込めて頷いた。
「ここから先は具体的な話も入りますので、気分が悪くなった方はすぐに仰って下さい」
彼女は慎重な口調で前置きした。
「例えば、通学にあたって電車等の公共交通機関をご利用の方が大半と思われます。そこでもし害意を持って皆さんに近付く者がいた場合、『アイギス・シリーズ』が害意を感知し、加害者にまず警告発作を起こします」
ゼミ生達も女子生徒達も「警告発作?」と首を傾げた。その疑問符を想定していたように、彼女は続ける。
「『警告発作』とは、『アイギス・シリーズ』に込めた霊術で加害者の心臓や肺を締め上げる事により、頭痛や息苦しさ、胸の痛みを与える事です。ここで加害をやめれば最悪でも『車内に急病人のお客様が』で済みます」
「えーとつまり、もし皆さんの周りでそういう症状が出る奴がいたら、そいつは加害者予備軍だって事です。助けなくていいですし、そもそも助ける価値無いですし、なんだったら駅員とか呼べばいいだけです」
彼女の説明に、瑤太が合いの手を入れた。
「与える苦痛を具体的に言いますと、嘔吐感を覚えるレベルの苦痛です。普通でしたらそこで加害をやめる、と言いたい所ですが、その手の不審者に『普通』は通用しません。もし苦痛を覚えても加害行為を継続しようとした場合は、加害に至る前に、例えば手を使った加害でしたら、その手が壊死します」
「いや…何もそこまでする事ないんじゃないですか…?」
ゼミ生のスペースに座る男子生徒が遠慮がちに訊いた。気分を害した様子も無く、彼女は返す。
「この手の犯罪は現代の日本では裁かれにくく、また裁かれたとしても再犯率が非常に高いです。法的に裁く事も再犯を止める事もできない以上、単純かつ決定的な手段として、身体を使い物にならなくする事が一番です」
「そもそも、いきなり身体を腐らせたりしないで『警告発作』っていう猶予を与えているだけ、姉は優しくなった方です…。…昔は問答無用で腐らせていたんで」
「昔は!?」
瑤太の補足に、社長以外の全員から声が上がった。彼女は何の事も無さそうに「はい」と首肯する。社長は社長で「あーそんな事もあったね」と遠い目になっていた。
気を取り直したように彼女は口を開いた。
「端的に言いますと、害意を持って近付いた者がいた場合、危害を加えるに使おうとした体の部位を壊死させます」
………………………。
先程とはうって変わって、講堂は静まり返った。強烈な言葉に、「壊死…?」と女子生徒達がうすら寒そうにストラップを見つめる。弟に「お姉ちゃん。お姉ちゃん。端的すぎ。もうちょい詳しく」と耳打ちされ、彼女は「わかっている」の意味を込めて頷いた。
「ここから先は具体的な話も入りますので、気分が悪くなった方はすぐに仰って下さい」
彼女は慎重な口調で前置きした。
「例えば、通学にあたって電車等の公共交通機関をご利用の方が大半と思われます。そこでもし害意を持って皆さんに近付く者がいた場合、『アイギス・シリーズ』が害意を感知し、加害者にまず警告発作を起こします」
ゼミ生達も女子生徒達も「警告発作?」と首を傾げた。その疑問符を想定していたように、彼女は続ける。
「『警告発作』とは、『アイギス・シリーズ』に込めた霊術で加害者の心臓や肺を締め上げる事により、頭痛や息苦しさ、胸の痛みを与える事です。ここで加害をやめれば最悪でも『車内に急病人のお客様が』で済みます」
「えーとつまり、もし皆さんの周りでそういう症状が出る奴がいたら、そいつは加害者予備軍だって事です。助けなくていいですし、そもそも助ける価値無いですし、なんだったら駅員とか呼べばいいだけです」
彼女の説明に、瑤太が合いの手を入れた。
「与える苦痛を具体的に言いますと、嘔吐感を覚えるレベルの苦痛です。普通でしたらそこで加害をやめる、と言いたい所ですが、その手の不審者に『普通』は通用しません。もし苦痛を覚えても加害行為を継続しようとした場合は、加害に至る前に、例えば手を使った加害でしたら、その手が壊死します」
「いや…何もそこまでする事ないんじゃないですか…?」
ゼミ生のスペースに座る男子生徒が遠慮がちに訊いた。気分を害した様子も無く、彼女は返す。
「この手の犯罪は現代の日本では裁かれにくく、また裁かれたとしても再犯率が非常に高いです。法的に裁く事も再犯を止める事もできない以上、単純かつ決定的な手段として、身体を使い物にならなくする事が一番です」
「そもそも、いきなり身体を腐らせたりしないで『警告発作』っていう猶予を与えているだけ、姉は優しくなった方です…。…昔は問答無用で腐らせていたんで」
「昔は!?」
瑤太の補足に、社長以外の全員から声が上がった。彼女は何の事も無さそうに「はい」と首肯する。社長は社長で「あーそんな事もあったね」と遠い目になっていた。