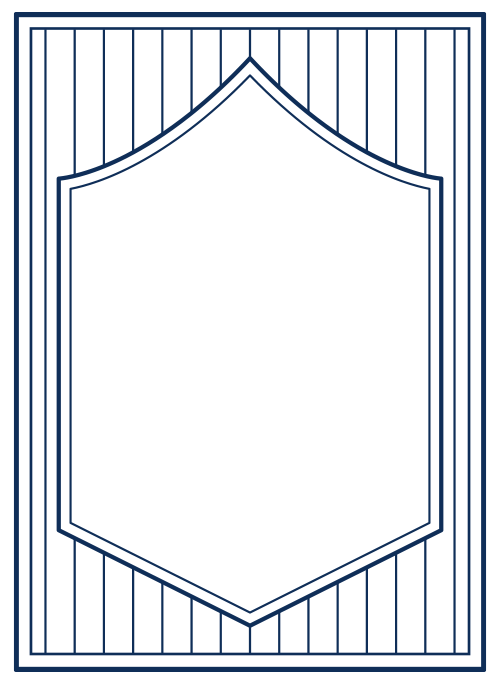時間を現在に戻す。
瑤太は理解した。あの女子生徒こそが、あの日姉が助けた人物なのだと。名前以前に同じ大学に通っている事、しかも同じ1年生である事すらも姉が話さなかったのは、ひとえに女子生徒の精神面を慮っての事だとも推測できる。姉の言葉を借りるなら『センシティブな案件』。取り扱い注意な事柄だから。
「件の女子生徒に持たせた『アイギス・シリーズ』が霊術を仕込んだ物だって、菅凪先生やゼミのメンバーもわかったらしい。流石だね。で、その制作者である私と直に顔合わせをしたいのと、どんなロジックで術を仕込んでいるのかを知りたいんだと」
「そんな事になってたんだな」
生憎と、そのタイミングで瑤太はゼミを抜ける為に何かと忙しかったので、話を知る余地が無かったのである。彼女は「んで」と続ける。
「うちの社長も出てきてこんにちはする」
「社長が!?」
「あの社長が?」
驚く母と弟に彼女は「うん」と首肯した。
「社長含むうちのメンバー全員に『アイギス・シリーズ』を持たせてるって事もあるけど。そもそも『アイギス・シリーズ』を広めるGOサインを出してくれたのは、社長だからね」
瑤太は理解した。あの女子生徒こそが、あの日姉が助けた人物なのだと。名前以前に同じ大学に通っている事、しかも同じ1年生である事すらも姉が話さなかったのは、ひとえに女子生徒の精神面を慮っての事だとも推測できる。姉の言葉を借りるなら『センシティブな案件』。取り扱い注意な事柄だから。
「件の女子生徒に持たせた『アイギス・シリーズ』が霊術を仕込んだ物だって、菅凪先生やゼミのメンバーもわかったらしい。流石だね。で、その制作者である私と直に顔合わせをしたいのと、どんなロジックで術を仕込んでいるのかを知りたいんだと」
「そんな事になってたんだな」
生憎と、そのタイミングで瑤太はゼミを抜ける為に何かと忙しかったので、話を知る余地が無かったのである。彼女は「んで」と続ける。
「うちの社長も出てきてこんにちはする」
「社長が!?」
「あの社長が?」
驚く母と弟に彼女は「うん」と首肯した。
「社長含むうちのメンバー全員に『アイギス・シリーズ』を持たせてるって事もあるけど。そもそも『アイギス・シリーズ』を広めるGOサインを出してくれたのは、社長だからね」