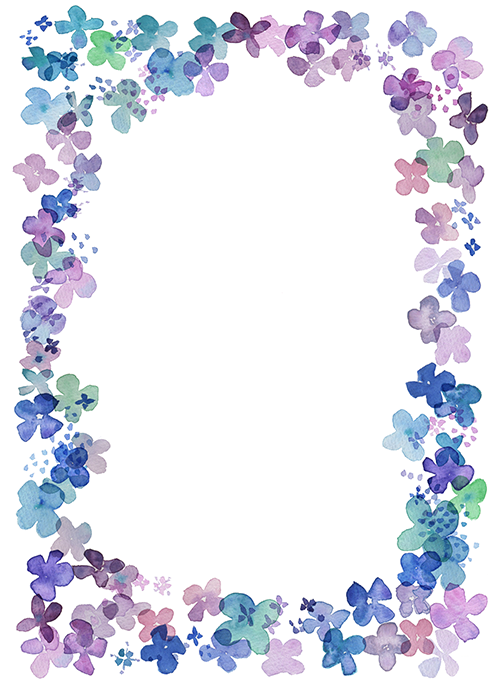気づけば、白いベットに横たわっていた。
これが棺のなかであればよかったのに、ただの保健室のベットだった。
「起きた?よかった」
顔を綻ばせたのは、私がりおくんだと勘違いしていた男の子だった。
「君、叫んでそのまま気絶したんだよ。調子は?」
悪いに決まっている。
私は静かに首を振る。彼はそうか、と頷いて少しだけパイプ椅子を私に近づけた位置に座った。
「僕は凛音の兄だ」
「りおくんのお兄さん?」
「そう。君にも何度か会ってるはずなんだけどな」
「小さい頃なのでよく覚えていません」
普通に会話できていることが、堪らなく滑稽に思えた。さっきまでの気持ちは何処へいったのか、怒りも憎しみもなかった。
代わりに何も感じなくなっていた。
心にぽっかり穴があいたようだ……というありきたりな表現そのもので、本当に何の感情もない。
「凛音は一週間前に死んだ。これは分かる?」
「思い出しました」
「……理由は?」
「思い出しました」
「そう」
彼はそれ以上何も言及してこなかった。責めも怒りもしない。
代わりに不思議なほど、穏やかな表情をしていた。
「今日、僕は学校にあった凛音の荷物を取りに来るついでに、一日凛音の席に座っていた。もちろん上からの許可は取っているよ」
「なんで……なんでそんなことをしたんですか?」
お兄さんは一呼吸置くと、私の目をじっと見つめてきた。
「凛音がとても楽しそうに君の話をしていたからだよ」
「……え」
思考が停止する。まさか、私の話をしていたとは思ってもみなかった。お兄さんは思い出したように次々とりおくんのことを語る。
「小学生の時からそうだった。家に帰ってくるなり君の話ばかり。中学生にもなると流石に回数は減ったが、話してくるときのあの表情は本当に幸せそうだったな。それで久しぶりに会ってみたいと思ったんだよ」
「そう、だったんですか」
知らなかった。幼馴染とはいえ、親や兄弟と私のことについて話しているなんて一度も聞いたことがなかった。
「予想通りだった。凛音が言っていた通りの女の子だった」
「……幻滅しないんですか?」
「しないよ」
当然と言うように彼は力強く頷く。
その仕草が少しだけりおくんに似ているなぁと思った。自分に対しての質問の返事は曖昧なことしか言わないくせに、他人のことについて話すときは酷く真剣に考えたり答えたりしていたっけ。
私がぼうっと思い出に浸っていると、彼は一度だけ深呼吸をした。
「ねぇ」
りおくんより少しだけ高い声が私を呼びかける。
「君は君を置いて逝った凛音のことが憎いと思うかい?それとも、凛音を身代わりにしてしまった自分を憎いと思うかい?」
そう問われると、もう何も感じないと思っていた心に不思議と憎悪の気持ちが湧いてきた。
「両方です。前者も後者も憎くて苦しいです」
彼はどうしてかホッとしたような顔をして椅子から立ち上がると、カーテンをめくって出て行ってしまう。
「凛音がどう思って逝ったのか、ちゃんと確認しなよ」
どういう意味だろう。
一人取り残された空間では、先ほどの言葉が脳内で渦巻いて耐えられなかった。
布団を畳むと、ゆっくりと足を地面につける。
「歩ける。大丈夫」
自分に言い聞かせて、今にも震えてガクンとなってしまいそうな膝を必死に動かした。暫く歩いていると、夕陽が差し、茜色に染まった教室が見えた。私はそこに引き込まれるように立ち入る。
「りお、くん」
ゆっくり、ゆっくり、君の席に近づく。
椅子を引いて、座った。
そのまま机に突っ伏した。
あたたかかった。
日差しがちょうど当たって心地よかった。
自然に涙が出た。
「りおくん」
ねぇ、返事して。
「……りおくん」
さっさと起きてよ馬鹿。私、起こしてるよ。早くしないと先生に怒られちゃうよ。
「ねぇ、好きだよ」
ずっと言えなかった気持ちを、言葉にした。
ずっと言いたかった言葉は、君にはもう届かなかった。
「りおくん、だいすき」
いないと分かっている。
いくら「りおくん」と呼んでも君は蘇らないと分かっている。
けれど君に気づいて欲しかった。私はここで息をしているよと、君のことを想っていると知って欲しかった。
ふと、机の隅にシャープペンシルで書かれた細かな文字を見つける。脱力していた体を無理矢理起こして、それを読んだ。
こんなこといつ書いたんだろう。
何度も書き直したように黒い跡が残る机で、ただ一文はっきりと読み取れたことがあった。
あいつの声が好きだ
しょうがないなって起こしてくれる時のその気だるげなところが好きだ
呆れたようにこっちをみる瞳が好きだ
それなのに、優しく笑っている口元が好きだ
いつも変わらずりおくんって呼んでくれるところが好きだ
ありきたりかもだけど、ありふれた言葉かもだけど
ぜんぶぜんぶ、好きだ
「っ……う、あ」
嗚咽が止まらなかった。
お兄さんが言っていたのはこのことなのか。
「りおくん、りおくん」
もう会えないの?あいたいよ。今すぐ会いたい。
何度でも起こすから。何回居眠りしたって私がりおくんを起こしてあげる。
だから、いなくならないでよ。
君が死んだら私が居眠りしたときどうするの?誰も起こしてくれないよ。
「ほんとに馬鹿だ。私も、りおくんも」
私はもう一度机に頬を寄せた瞼を閉じると、彼の笑顔を思い浮かべる。
暫く眠れていなかったから、目を閉じるとすっと意識を手放せた。
「全部好きだったら、起こしに来て。私はもう大丈夫だって背中を押しに来て」
眠る直前、ふわりと唇に何かのぬくもりが触れた。それはたった一瞬の出来事で、神経を研ぎ澄ましていないと気づかないレベルの感触。けれど私にはりおくんからの気持ちがしっかりと伝わった。
ふわりと太陽のあたたかい匂いが鼻孔をくすぐる。りおくんの優しさ全部をぎゅっと閉じ込めたようなその香りは、柔らかな昼の日差しを受けながら寝ていた君の香り。
嗚呼、やっぱり私は君のことが大好きだ。
君がいなくなったって変わらず、頭の中は大好きの気持ちでいっぱいなのだ。
約束を守って私にもう一度前を向かせてくれたりおくんに恥じないように精いっぱい明日からも生きよう。君が好きだって言ってくれた笑顔も声も絶やさずに命を全うしよう。
でも、今日は。
「今日だけはどうか、君へのこの感情を抱いて泣いてもいいかな」
溢れる涙を咎めるものは何もなかった。
嗚咽混じりで、呼吸は荒くて、溢れる感情は止まらない。
今まで逃げていた現実は辛く苦しいことばかりだったけれど、それでも君がボロボロだった私の心を救ってくれたから、君が許してくれたから、私は今ここで生きていてこうやって君のために泣ける。
ちゃんと向き合えてよかった。
肺をいっぱいにしていた二酸化炭素と共に苦しみを少しずつ吐き出すと、少しだけ息がしやすくなった気がした。
これが棺のなかであればよかったのに、ただの保健室のベットだった。
「起きた?よかった」
顔を綻ばせたのは、私がりおくんだと勘違いしていた男の子だった。
「君、叫んでそのまま気絶したんだよ。調子は?」
悪いに決まっている。
私は静かに首を振る。彼はそうか、と頷いて少しだけパイプ椅子を私に近づけた位置に座った。
「僕は凛音の兄だ」
「りおくんのお兄さん?」
「そう。君にも何度か会ってるはずなんだけどな」
「小さい頃なのでよく覚えていません」
普通に会話できていることが、堪らなく滑稽に思えた。さっきまでの気持ちは何処へいったのか、怒りも憎しみもなかった。
代わりに何も感じなくなっていた。
心にぽっかり穴があいたようだ……というありきたりな表現そのもので、本当に何の感情もない。
「凛音は一週間前に死んだ。これは分かる?」
「思い出しました」
「……理由は?」
「思い出しました」
「そう」
彼はそれ以上何も言及してこなかった。責めも怒りもしない。
代わりに不思議なほど、穏やかな表情をしていた。
「今日、僕は学校にあった凛音の荷物を取りに来るついでに、一日凛音の席に座っていた。もちろん上からの許可は取っているよ」
「なんで……なんでそんなことをしたんですか?」
お兄さんは一呼吸置くと、私の目をじっと見つめてきた。
「凛音がとても楽しそうに君の話をしていたからだよ」
「……え」
思考が停止する。まさか、私の話をしていたとは思ってもみなかった。お兄さんは思い出したように次々とりおくんのことを語る。
「小学生の時からそうだった。家に帰ってくるなり君の話ばかり。中学生にもなると流石に回数は減ったが、話してくるときのあの表情は本当に幸せそうだったな。それで久しぶりに会ってみたいと思ったんだよ」
「そう、だったんですか」
知らなかった。幼馴染とはいえ、親や兄弟と私のことについて話しているなんて一度も聞いたことがなかった。
「予想通りだった。凛音が言っていた通りの女の子だった」
「……幻滅しないんですか?」
「しないよ」
当然と言うように彼は力強く頷く。
その仕草が少しだけりおくんに似ているなぁと思った。自分に対しての質問の返事は曖昧なことしか言わないくせに、他人のことについて話すときは酷く真剣に考えたり答えたりしていたっけ。
私がぼうっと思い出に浸っていると、彼は一度だけ深呼吸をした。
「ねぇ」
りおくんより少しだけ高い声が私を呼びかける。
「君は君を置いて逝った凛音のことが憎いと思うかい?それとも、凛音を身代わりにしてしまった自分を憎いと思うかい?」
そう問われると、もう何も感じないと思っていた心に不思議と憎悪の気持ちが湧いてきた。
「両方です。前者も後者も憎くて苦しいです」
彼はどうしてかホッとしたような顔をして椅子から立ち上がると、カーテンをめくって出て行ってしまう。
「凛音がどう思って逝ったのか、ちゃんと確認しなよ」
どういう意味だろう。
一人取り残された空間では、先ほどの言葉が脳内で渦巻いて耐えられなかった。
布団を畳むと、ゆっくりと足を地面につける。
「歩ける。大丈夫」
自分に言い聞かせて、今にも震えてガクンとなってしまいそうな膝を必死に動かした。暫く歩いていると、夕陽が差し、茜色に染まった教室が見えた。私はそこに引き込まれるように立ち入る。
「りお、くん」
ゆっくり、ゆっくり、君の席に近づく。
椅子を引いて、座った。
そのまま机に突っ伏した。
あたたかかった。
日差しがちょうど当たって心地よかった。
自然に涙が出た。
「りおくん」
ねぇ、返事して。
「……りおくん」
さっさと起きてよ馬鹿。私、起こしてるよ。早くしないと先生に怒られちゃうよ。
「ねぇ、好きだよ」
ずっと言えなかった気持ちを、言葉にした。
ずっと言いたかった言葉は、君にはもう届かなかった。
「りおくん、だいすき」
いないと分かっている。
いくら「りおくん」と呼んでも君は蘇らないと分かっている。
けれど君に気づいて欲しかった。私はここで息をしているよと、君のことを想っていると知って欲しかった。
ふと、机の隅にシャープペンシルで書かれた細かな文字を見つける。脱力していた体を無理矢理起こして、それを読んだ。
こんなこといつ書いたんだろう。
何度も書き直したように黒い跡が残る机で、ただ一文はっきりと読み取れたことがあった。
あいつの声が好きだ
しょうがないなって起こしてくれる時のその気だるげなところが好きだ
呆れたようにこっちをみる瞳が好きだ
それなのに、優しく笑っている口元が好きだ
いつも変わらずりおくんって呼んでくれるところが好きだ
ありきたりかもだけど、ありふれた言葉かもだけど
ぜんぶぜんぶ、好きだ
「っ……う、あ」
嗚咽が止まらなかった。
お兄さんが言っていたのはこのことなのか。
「りおくん、りおくん」
もう会えないの?あいたいよ。今すぐ会いたい。
何度でも起こすから。何回居眠りしたって私がりおくんを起こしてあげる。
だから、いなくならないでよ。
君が死んだら私が居眠りしたときどうするの?誰も起こしてくれないよ。
「ほんとに馬鹿だ。私も、りおくんも」
私はもう一度机に頬を寄せた瞼を閉じると、彼の笑顔を思い浮かべる。
暫く眠れていなかったから、目を閉じるとすっと意識を手放せた。
「全部好きだったら、起こしに来て。私はもう大丈夫だって背中を押しに来て」
眠る直前、ふわりと唇に何かのぬくもりが触れた。それはたった一瞬の出来事で、神経を研ぎ澄ましていないと気づかないレベルの感触。けれど私にはりおくんからの気持ちがしっかりと伝わった。
ふわりと太陽のあたたかい匂いが鼻孔をくすぐる。りおくんの優しさ全部をぎゅっと閉じ込めたようなその香りは、柔らかな昼の日差しを受けながら寝ていた君の香り。
嗚呼、やっぱり私は君のことが大好きだ。
君がいなくなったって変わらず、頭の中は大好きの気持ちでいっぱいなのだ。
約束を守って私にもう一度前を向かせてくれたりおくんに恥じないように精いっぱい明日からも生きよう。君が好きだって言ってくれた笑顔も声も絶やさずに命を全うしよう。
でも、今日は。
「今日だけはどうか、君へのこの感情を抱いて泣いてもいいかな」
溢れる涙を咎めるものは何もなかった。
嗚咽混じりで、呼吸は荒くて、溢れる感情は止まらない。
今まで逃げていた現実は辛く苦しいことばかりだったけれど、それでも君がボロボロだった私の心を救ってくれたから、君が許してくれたから、私は今ここで生きていてこうやって君のために泣ける。
ちゃんと向き合えてよかった。
肺をいっぱいにしていた二酸化炭素と共に苦しみを少しずつ吐き出すと、少しだけ息がしやすくなった気がした。