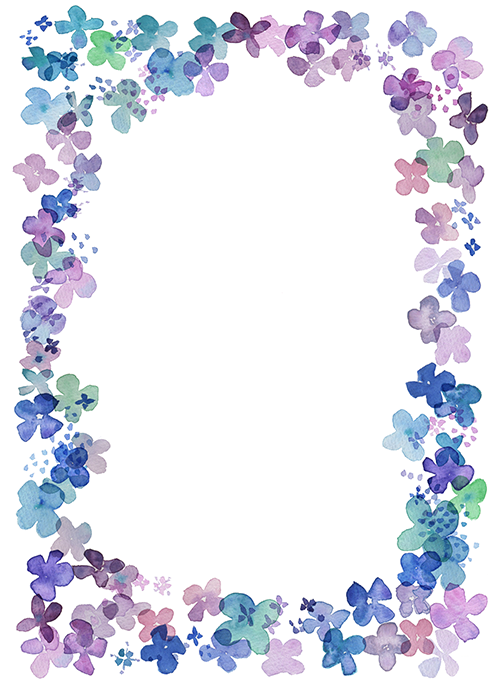どこにいても、何をしていても、いつもどこか息苦しい――こんな自分のことが大嫌いだ。
理由は何故だか忘れてしまった。こんな感情を持ったのはつい先日のことのようにも思えるし、ずっと前からのことにも思える。けれど、そのフレーズだけが頭の奥からこびりついて離れなかった。
授業中は自己嫌悪に陥って、シャーペンをくるくると回す。
早く授業終わらないかな。
願ったところで時間は早まるわけないけれど、それでも尚先生の話など頭に入ってこなかった。
家に帰ったら「ただいま」と一人で呟いて、塾から出された宿題をこなして、それでも時間が余るから予習をして。
気づけば机に張り付いてばかりいた。誰とも会話せずに一日が過ぎる。そして朝がやってくる。
ぼんやりした頭が突然覚醒して、私はがばっと上体を起こした。また朝だ。
嫌な夢をみたような気がする。誰かが事故に遭うような。
「朝から最悪な夢見ちゃったよ……。誰が事故られたのかわかんないけどさぁ」
記憶が曖昧にせよ、人が轢かれた夢を見ることはあまり良い気分ではない。
時計にちらりと目をやると、まだ六時半だった。全然二度寝できる時間だけど私はシーツを畳むことにした。
「おはよう、りおくん」
そこにはいない「りおくん」の名前を呼ぶと、さっきまでの胸のざわざわが凪いでいった。
りおくんは私の幼馴染だ。幼稚園の年少さんから一緒の腐れ縁。
女の子みたいなふわふわとした栗色の髪と、どこかハーフを漂わせるくりんとした色素の薄い瞳の男の子。一見か弱そうに見せて、意外と力強いし何より過保護。
毎朝私の姿を見るなり、「宿題はちゃんとやってきた?」「しっかり寝てる?」「寝ぼけ眼どうにかしろよ」のどれかがランダムで繰り出される。私はそれに毎回目を泳がせてげんこつを食らうのが日課。
幼馴染と言うよりお母さんと言った方がしっくりくるような気がする。
けれど、彼も行動全てがしっかりしているわけではなくて、授業中はだいたい居眠りをしているのだ。
そんなギャップも可愛くて、完璧すぎないところがりおくんらしくていいなと思っている。
「りおくん、今日は部活で朝早いって言ってたっけ?それじゃあ学校一緒に行けないな」
今朝は珍しくいい目覚めだった。加えて宿題も前日に全て終えるという、私にとってかつてない偉業を成し遂げている。偉すぎるのであさイチでりおくんに褒めてもらいたい!と考えていたが、今日は難しいようだ。
シーツを畳み終わった私は洗面所に移動すると冷水を顔にぶっかけた。
「……目が腫れてる」
気づきたくもない現実に悲しくなった。
それから今日は張り切ってお弁当まで作ってしまった。両親は共働きの為、いつも料理上手のりおくんが前日に作り置きしてくれているのだが昨日はどうしたのか来てくれなかった。忙しかったのかな?それでも、正午のことを考えるときゅぅとお腹が鳴って気づけばキッチンに立っていた。
「腹が減っては戦はできんよね」
料理はあまり上手ではないので、電子レンジで温めた冷凍ご飯と梅干をぎゅうぎゅうに詰めて家を出る。
教室に入ったら真っ先に栗色の髪の毛を見つけた。
「りおくん」
私が声を掛けても彼は振り向いてくれない。何か怒らせてしまったのかも……。拗ねた時のりおくんは放っておくのが一番なので、私は肩を落としつつ席についた。
しばらくしてチャイムが鳴り、担任が教室へと入ってくる。今日の予定なんかを報告している間、ふと窓側に目をやるとやはり君は机に突っ伏していた。
ホームルームの時間が始まったというのに、いつものようにあたたかな光を受けながら規則正しく上下する体が可愛らしい。
その姿を見てふと思い出す。一年前、まだ私たちが高校に入学したての頃。
授業中に先生からの鋭い視線を感じ、ふと顔をあげる。やばい居眠りしかけてたのバレたかもという私の不安に対し、彼は瞬きもせずじっとこちらに顔を向けていた。
「うげっ。なんかめっちゃ怖い顔で睨んでくるんですけど……」
ついそんなことを呟いてしまうくらいに、物理教師はお怒りだった。
けれど幸い、視線は私にではなく隣の彼に一点集中している。いや、油断はできない。あの先生、怒ると永遠に機嫌直らないんだよなぁ。隣の席の私も連帯責任にされては困るので、隣ですやすやと気持ちよさそうに寝ているりおくんを起こすことにした。
「りおくん」
小さく肩を揺さぶると、茶色の頭がびくっと飛び上がった。
「ん……」
緩慢な動きで起き上がったりおくんを私は慌てて制す。
「先生、睨んでるから……!はやくシャキッとして!」
寝ぼけ眼の彼はまだ状況を理解できていないようで、ゆったり目を擦った。最早諦めた私は黒板に意識を戻そうとしたのだが、何故かできない。
りおくんから目が、体が、逸らせないのだ。いや、きっと私は逸らせたくないのだ。
彼の焦げ茶の睫毛が雫を含んで揺れているのが言葉に表せない位に綺麗だった。
「……んう」
ふぁっとあくびをした彼とぱちりと目が合ってしまった。
慌てて顔を背けようとすると、君がにこりと笑ったのだ。春のお昼寝の時のような、柔らかくあたたかなそんな感じで。
「おはよ」
「おっ……おはよう?」
「どしたの?そんなに焦って」
「いやだから先生が……」
「かわい」
「へっ?」
「今日も可愛いなぁって思って」
困惑する私の手を自分の方に引き寄せたりおくんは、手首から指先の隅々の感覚を確かめるように優しく撫でた。私はまるで沸騰したように掌と、顔の中心が熱くなる。
やがて満足したのか肌のぬくもりが離れていった。ようやく彼の手から解放されたと思いきや、無理やり細い指が絡んでぎゅっと力を込められた。
「俺、明日も明後日も昼寝するから」
「……馬鹿なの?話の流れ分かった上でそれ言う?」
「こわーい。辛辣―。もっと乙女に優しくしてー」
「ほら黙って授業聞こうよ、乙女(自称)」
私が冷たくあしらうと、ぐいっと繋がれた手があっちに引き寄せられて必然的に至近距離で目があってしまう。
先生は呆れて授業を再開したようだけど、もはや他人の視線など気にする余裕なんてなく、視線は逸らせずに君の瞳を見つめる。
彼は私を確かめるように覗き込むと、もう一度笑った。
「この先高校で、下手したら大学でも寝るからさ。その度にお前が起こしてよ」
「一緒のクラスになること前提なんだね」
「そんなのどうだっていいんだよ。起きた時にお前がいると胸がぽかぽかする」
「幼稚園児みたいな表現の仕方―。本当にぽかぽかしてる?今」
「どっちかっていうとドキドキしてる。だってぷろぽーずしてんだもん」
「そんな軽いプロポーズある?」
「約束してくれる?これからずっと」
その言葉と、その瞳と、その色気づいた微笑みに堪えられない。
逃げ場がなくなった私は返事をする代わりに、繋がれた右手に力を入れた。りおくんはわかってくれるかな。言葉では冷静を装っていたけれど、私も内心ドキドキしてるんだよ。脈が速くて、胸が痛くて、繋がれた手から鼓動が伝わらないか不安に襲われてるってことわかる?
反応を伺う為に今度は私が彼を確かめるように覗き込むと、端正な顔は驚きの感情で満ちていた。
「これはおーけーってこと?」
「……どうせ私が嫌だって言っても、逃げたとしても、りおくんは寝るでしょ」
「……やった!」
君は本当に嬉しそうに笑っていた。きゅっと目を細めて、でも瞳はしっかり私を捉えていて。
歯をむき出しにして笑ったりおくんは、いつの間にか接近していた先生にゲンコツを入れられてクラス中に笑いが起こった。
私は笑えなかった。
何故だかわからない。つい五分前まで幼馴染のはずだったのに。あれが本気のプロポーズなのかもわからないのに。
五分前より確実にりおくんに惹かれている。
まるでずっとずっと秘めていた想いが、溢れて零れたように全身を駆け巡り心臓の動きを速める。
何度も何度もあの一瞬が頭の中でぐるぐる駆け巡って。
りおくんの笑い方が、私だけのものになることをただひたすら願った。
理由は何故だか忘れてしまった。こんな感情を持ったのはつい先日のことのようにも思えるし、ずっと前からのことにも思える。けれど、そのフレーズだけが頭の奥からこびりついて離れなかった。
授業中は自己嫌悪に陥って、シャーペンをくるくると回す。
早く授業終わらないかな。
願ったところで時間は早まるわけないけれど、それでも尚先生の話など頭に入ってこなかった。
家に帰ったら「ただいま」と一人で呟いて、塾から出された宿題をこなして、それでも時間が余るから予習をして。
気づけば机に張り付いてばかりいた。誰とも会話せずに一日が過ぎる。そして朝がやってくる。
ぼんやりした頭が突然覚醒して、私はがばっと上体を起こした。また朝だ。
嫌な夢をみたような気がする。誰かが事故に遭うような。
「朝から最悪な夢見ちゃったよ……。誰が事故られたのかわかんないけどさぁ」
記憶が曖昧にせよ、人が轢かれた夢を見ることはあまり良い気分ではない。
時計にちらりと目をやると、まだ六時半だった。全然二度寝できる時間だけど私はシーツを畳むことにした。
「おはよう、りおくん」
そこにはいない「りおくん」の名前を呼ぶと、さっきまでの胸のざわざわが凪いでいった。
りおくんは私の幼馴染だ。幼稚園の年少さんから一緒の腐れ縁。
女の子みたいなふわふわとした栗色の髪と、どこかハーフを漂わせるくりんとした色素の薄い瞳の男の子。一見か弱そうに見せて、意外と力強いし何より過保護。
毎朝私の姿を見るなり、「宿題はちゃんとやってきた?」「しっかり寝てる?」「寝ぼけ眼どうにかしろよ」のどれかがランダムで繰り出される。私はそれに毎回目を泳がせてげんこつを食らうのが日課。
幼馴染と言うよりお母さんと言った方がしっくりくるような気がする。
けれど、彼も行動全てがしっかりしているわけではなくて、授業中はだいたい居眠りをしているのだ。
そんなギャップも可愛くて、完璧すぎないところがりおくんらしくていいなと思っている。
「りおくん、今日は部活で朝早いって言ってたっけ?それじゃあ学校一緒に行けないな」
今朝は珍しくいい目覚めだった。加えて宿題も前日に全て終えるという、私にとってかつてない偉業を成し遂げている。偉すぎるのであさイチでりおくんに褒めてもらいたい!と考えていたが、今日は難しいようだ。
シーツを畳み終わった私は洗面所に移動すると冷水を顔にぶっかけた。
「……目が腫れてる」
気づきたくもない現実に悲しくなった。
それから今日は張り切ってお弁当まで作ってしまった。両親は共働きの為、いつも料理上手のりおくんが前日に作り置きしてくれているのだが昨日はどうしたのか来てくれなかった。忙しかったのかな?それでも、正午のことを考えるときゅぅとお腹が鳴って気づけばキッチンに立っていた。
「腹が減っては戦はできんよね」
料理はあまり上手ではないので、電子レンジで温めた冷凍ご飯と梅干をぎゅうぎゅうに詰めて家を出る。
教室に入ったら真っ先に栗色の髪の毛を見つけた。
「りおくん」
私が声を掛けても彼は振り向いてくれない。何か怒らせてしまったのかも……。拗ねた時のりおくんは放っておくのが一番なので、私は肩を落としつつ席についた。
しばらくしてチャイムが鳴り、担任が教室へと入ってくる。今日の予定なんかを報告している間、ふと窓側に目をやるとやはり君は机に突っ伏していた。
ホームルームの時間が始まったというのに、いつものようにあたたかな光を受けながら規則正しく上下する体が可愛らしい。
その姿を見てふと思い出す。一年前、まだ私たちが高校に入学したての頃。
授業中に先生からの鋭い視線を感じ、ふと顔をあげる。やばい居眠りしかけてたのバレたかもという私の不安に対し、彼は瞬きもせずじっとこちらに顔を向けていた。
「うげっ。なんかめっちゃ怖い顔で睨んでくるんですけど……」
ついそんなことを呟いてしまうくらいに、物理教師はお怒りだった。
けれど幸い、視線は私にではなく隣の彼に一点集中している。いや、油断はできない。あの先生、怒ると永遠に機嫌直らないんだよなぁ。隣の席の私も連帯責任にされては困るので、隣ですやすやと気持ちよさそうに寝ているりおくんを起こすことにした。
「りおくん」
小さく肩を揺さぶると、茶色の頭がびくっと飛び上がった。
「ん……」
緩慢な動きで起き上がったりおくんを私は慌てて制す。
「先生、睨んでるから……!はやくシャキッとして!」
寝ぼけ眼の彼はまだ状況を理解できていないようで、ゆったり目を擦った。最早諦めた私は黒板に意識を戻そうとしたのだが、何故かできない。
りおくんから目が、体が、逸らせないのだ。いや、きっと私は逸らせたくないのだ。
彼の焦げ茶の睫毛が雫を含んで揺れているのが言葉に表せない位に綺麗だった。
「……んう」
ふぁっとあくびをした彼とぱちりと目が合ってしまった。
慌てて顔を背けようとすると、君がにこりと笑ったのだ。春のお昼寝の時のような、柔らかくあたたかなそんな感じで。
「おはよ」
「おっ……おはよう?」
「どしたの?そんなに焦って」
「いやだから先生が……」
「かわい」
「へっ?」
「今日も可愛いなぁって思って」
困惑する私の手を自分の方に引き寄せたりおくんは、手首から指先の隅々の感覚を確かめるように優しく撫でた。私はまるで沸騰したように掌と、顔の中心が熱くなる。
やがて満足したのか肌のぬくもりが離れていった。ようやく彼の手から解放されたと思いきや、無理やり細い指が絡んでぎゅっと力を込められた。
「俺、明日も明後日も昼寝するから」
「……馬鹿なの?話の流れ分かった上でそれ言う?」
「こわーい。辛辣―。もっと乙女に優しくしてー」
「ほら黙って授業聞こうよ、乙女(自称)」
私が冷たくあしらうと、ぐいっと繋がれた手があっちに引き寄せられて必然的に至近距離で目があってしまう。
先生は呆れて授業を再開したようだけど、もはや他人の視線など気にする余裕なんてなく、視線は逸らせずに君の瞳を見つめる。
彼は私を確かめるように覗き込むと、もう一度笑った。
「この先高校で、下手したら大学でも寝るからさ。その度にお前が起こしてよ」
「一緒のクラスになること前提なんだね」
「そんなのどうだっていいんだよ。起きた時にお前がいると胸がぽかぽかする」
「幼稚園児みたいな表現の仕方―。本当にぽかぽかしてる?今」
「どっちかっていうとドキドキしてる。だってぷろぽーずしてんだもん」
「そんな軽いプロポーズある?」
「約束してくれる?これからずっと」
その言葉と、その瞳と、その色気づいた微笑みに堪えられない。
逃げ場がなくなった私は返事をする代わりに、繋がれた右手に力を入れた。りおくんはわかってくれるかな。言葉では冷静を装っていたけれど、私も内心ドキドキしてるんだよ。脈が速くて、胸が痛くて、繋がれた手から鼓動が伝わらないか不安に襲われてるってことわかる?
反応を伺う為に今度は私が彼を確かめるように覗き込むと、端正な顔は驚きの感情で満ちていた。
「これはおーけーってこと?」
「……どうせ私が嫌だって言っても、逃げたとしても、りおくんは寝るでしょ」
「……やった!」
君は本当に嬉しそうに笑っていた。きゅっと目を細めて、でも瞳はしっかり私を捉えていて。
歯をむき出しにして笑ったりおくんは、いつの間にか接近していた先生にゲンコツを入れられてクラス中に笑いが起こった。
私は笑えなかった。
何故だかわからない。つい五分前まで幼馴染のはずだったのに。あれが本気のプロポーズなのかもわからないのに。
五分前より確実にりおくんに惹かれている。
まるでずっとずっと秘めていた想いが、溢れて零れたように全身を駆け巡り心臓の動きを速める。
何度も何度もあの一瞬が頭の中でぐるぐる駆け巡って。
りおくんの笑い方が、私だけのものになることをただひたすら願った。