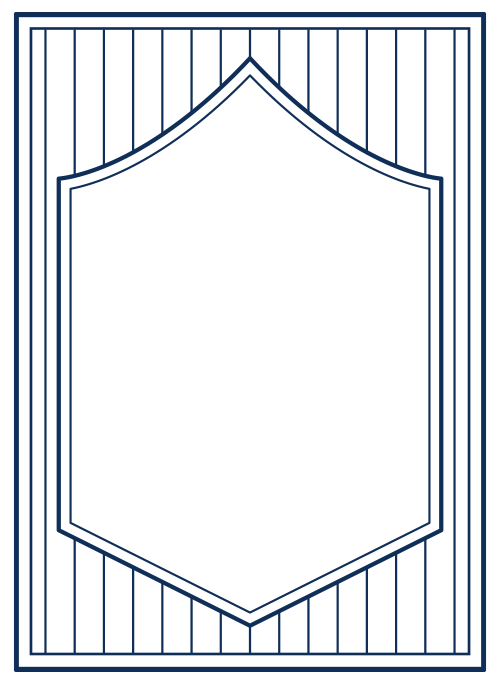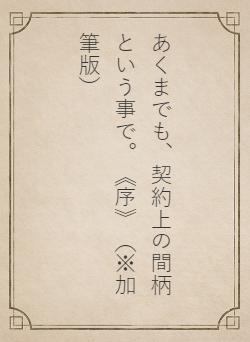「書類の上での手続きはしてしまいましたけど、本当に良かったんですか?」
新居へ向かうリムジンの中、彼女は美斗に問いかけた。屋敷の前に停まっていたリムジンには美斗と彼女が、自家用車には瑠子と瑤太がそれぞれ乗り込んだのである。
「先程の行為は見ましたでしょ。私は怖い所がある女ですよ」
「全ては御母堂を想いやった事だろう?」
「そりゃあ」
彼女は、自分が傷を負わされた事については、今や何も思ってはいない。伯母の「自分は子供も霊術も夫も失ったのに、何故妹には子供がいて、その一人は霊術も持っているのだろう」という理不尽な思いから来る八つ当たりと、それが曾祖母の死の原因となった事と、一連に対する祖母の態度に怒っていただけだ。傷を負わされて以来、ずっと。
「『焼骨牡丹』は伯母専用に組んだ仕掛けでしてね。母と弟を連れて家を出る時、絶対に発動させてやろうと思っていたんです。まあ使うのは私が思うより早かったですけど。若君様が連れ出してくれたお陰で」
美斗は悲しげな顔になった。
「その『若君様』と呼ぶのはやめてくれ。君は俺の従者でも何でもない。伴侶なのだから。俺の事は、美斗でいい」
「若君様が若君様だから若君様と呼んでいるだけであって、別に他意はありませんよ。いかん。『若君様』でゲシュタルト崩壊しそうになってきたな。名前呼びは、慣れたらまあおいおいという事で」
「そうか…」
美斗は肩を落とした。
「しかし、伯母君の仕打ちや君の傷の事までは知らなかったとはいえ、君が手を汚さずとも良かったのに」
「生まれながらの人類として、端くれとはいえ霊術を扱える者として、何より一連を把握していた者として。私の全ての誇りをもってして、個人的な復讐を果たしただけですよ。なので若君様が手を汚す事も下す事もありません」
彼女は「何より」と付け加えた。
「うちの祖母は悪口が大好きでしてね。若君様が何かしようものなら、刀隠の悪口をそこかしこで吹聴するでしょうよ。ある事一割、無い事九割くらいの割り合いで。あ。うちの祖母、極度の虚言癖持ちでもあるので」
「そうだったのか。…つまり君は、刀隠の事も考えて自分で復讐を?」
「今や落ち目を通り越して死にかけの死に体と言えど、司家も霊術士の一族の一つですからね。まあ刀隠からすれば吹けば飛ぶような一族でしょうけど、悪い噂は無い方がいいですから」
「…君は今までずっと、そうやって御母堂と義弟を守ってきたんだな…」
美斗は神妙な口調で呟き、静かに首を横に振る。
「いや全く、君は『鞘』である為に生まれてきたような人だ。霊術士達の筆頭として、俺の横に並ぶに相応しい」
「あくまでも、契約上の間柄ですけどね」
「…それなんだが、幾つか頼みがある」
「はい」
改まった様子で彼女に膝を向ける隣の美斗に、彼女も居住まいを正して膝を向けた。
「契約上の間柄と君は言うが、俺達は夫婦だ。御母堂と義弟を守る為に、君一人が矢面に立つ必要は、もう無い。これからはどうか、何事も俺に相談して、俺を頼って欲しい。頼っていいんだ。君の力になりたい」
「…はい。そうですね。自分で抱え込まないようにしようと思います」
真摯な口調に彼女は律儀かつ慎重に返す。
続いて美斗は「それと」と頭痛を堪えるような顔になった。
「…君の父親の一件は、察するに余りある。男性不信は決して拭い切れないかもしれないし、現実の男に失望しているからこそ、物語の中の男を愛するようになったのだとも思う」
「そうですね」
美斗の言う事は的を得ていたので、彼女は首肯した。
美斗は深刻さに満ちた、同時に鬼気迫ると言っていいような表情で、彼女を真っ直ぐに見据えた。
「だが頼む!君の不信感が晴れるように精一杯努力するから、物語の中の男に対するように、俺に恋をしてくれ!」
「つまりオタクとして愛する者…キャラクターはいてもいいから、三次元即ち若君様を好きになって欲しいと」
「そうだ」
ぽく、ぽく、ぽく、と音がしそうな間の中、彼女は考えた。
「オタクを理解できなくても許容をしてもらえるなら、それに越した事はありません。何せ辛い時苦しい時に心の支えになってくれたコンテンツを親だと思いついていくのが、オタクの習性の一つですので」
「一つなのか」
「オタクの生態は色々ありますよ」
彼女はこれでも大真面目に話している。
「刀隠の一族の本性が付喪神、つまり…あー。馬鹿にしている訳でも差別している訳でもなく。本性が人間ではない以上、人間の男性に当てはまらない所も多いと思います。心変わりをしないとか。その点を理解していけば、少なくとも付喪神の男性に対する不信感は無くなると思います。まずは相互理解からですね」
「あ、ああ!ゆっくりでいいから、俺を好きになってくれればいい!」
感極まって思わず彼女の手を取った美斗だが、その瞬間に彼女に変化が起きた。彼女は「キャッ恥ずかしい!」と叫び、座ったままだというのに思い切り跳び上がって距離を取ったのである。一転して真顔になり「すみません。慣れていないもので」と謝ったが。
ぽかんとした美斗は、同時に彼女の意外な一面に気が付いた。
この花嫁、相当に奥手であるらしい。
新居へ向かうリムジンの中、彼女は美斗に問いかけた。屋敷の前に停まっていたリムジンには美斗と彼女が、自家用車には瑠子と瑤太がそれぞれ乗り込んだのである。
「先程の行為は見ましたでしょ。私は怖い所がある女ですよ」
「全ては御母堂を想いやった事だろう?」
「そりゃあ」
彼女は、自分が傷を負わされた事については、今や何も思ってはいない。伯母の「自分は子供も霊術も夫も失ったのに、何故妹には子供がいて、その一人は霊術も持っているのだろう」という理不尽な思いから来る八つ当たりと、それが曾祖母の死の原因となった事と、一連に対する祖母の態度に怒っていただけだ。傷を負わされて以来、ずっと。
「『焼骨牡丹』は伯母専用に組んだ仕掛けでしてね。母と弟を連れて家を出る時、絶対に発動させてやろうと思っていたんです。まあ使うのは私が思うより早かったですけど。若君様が連れ出してくれたお陰で」
美斗は悲しげな顔になった。
「その『若君様』と呼ぶのはやめてくれ。君は俺の従者でも何でもない。伴侶なのだから。俺の事は、美斗でいい」
「若君様が若君様だから若君様と呼んでいるだけであって、別に他意はありませんよ。いかん。『若君様』でゲシュタルト崩壊しそうになってきたな。名前呼びは、慣れたらまあおいおいという事で」
「そうか…」
美斗は肩を落とした。
「しかし、伯母君の仕打ちや君の傷の事までは知らなかったとはいえ、君が手を汚さずとも良かったのに」
「生まれながらの人類として、端くれとはいえ霊術を扱える者として、何より一連を把握していた者として。私の全ての誇りをもってして、個人的な復讐を果たしただけですよ。なので若君様が手を汚す事も下す事もありません」
彼女は「何より」と付け加えた。
「うちの祖母は悪口が大好きでしてね。若君様が何かしようものなら、刀隠の悪口をそこかしこで吹聴するでしょうよ。ある事一割、無い事九割くらいの割り合いで。あ。うちの祖母、極度の虚言癖持ちでもあるので」
「そうだったのか。…つまり君は、刀隠の事も考えて自分で復讐を?」
「今や落ち目を通り越して死にかけの死に体と言えど、司家も霊術士の一族の一つですからね。まあ刀隠からすれば吹けば飛ぶような一族でしょうけど、悪い噂は無い方がいいですから」
「…君は今までずっと、そうやって御母堂と義弟を守ってきたんだな…」
美斗は神妙な口調で呟き、静かに首を横に振る。
「いや全く、君は『鞘』である為に生まれてきたような人だ。霊術士達の筆頭として、俺の横に並ぶに相応しい」
「あくまでも、契約上の間柄ですけどね」
「…それなんだが、幾つか頼みがある」
「はい」
改まった様子で彼女に膝を向ける隣の美斗に、彼女も居住まいを正して膝を向けた。
「契約上の間柄と君は言うが、俺達は夫婦だ。御母堂と義弟を守る為に、君一人が矢面に立つ必要は、もう無い。これからはどうか、何事も俺に相談して、俺を頼って欲しい。頼っていいんだ。君の力になりたい」
「…はい。そうですね。自分で抱え込まないようにしようと思います」
真摯な口調に彼女は律儀かつ慎重に返す。
続いて美斗は「それと」と頭痛を堪えるような顔になった。
「…君の父親の一件は、察するに余りある。男性不信は決して拭い切れないかもしれないし、現実の男に失望しているからこそ、物語の中の男を愛するようになったのだとも思う」
「そうですね」
美斗の言う事は的を得ていたので、彼女は首肯した。
美斗は深刻さに満ちた、同時に鬼気迫ると言っていいような表情で、彼女を真っ直ぐに見据えた。
「だが頼む!君の不信感が晴れるように精一杯努力するから、物語の中の男に対するように、俺に恋をしてくれ!」
「つまりオタクとして愛する者…キャラクターはいてもいいから、三次元即ち若君様を好きになって欲しいと」
「そうだ」
ぽく、ぽく、ぽく、と音がしそうな間の中、彼女は考えた。
「オタクを理解できなくても許容をしてもらえるなら、それに越した事はありません。何せ辛い時苦しい時に心の支えになってくれたコンテンツを親だと思いついていくのが、オタクの習性の一つですので」
「一つなのか」
「オタクの生態は色々ありますよ」
彼女はこれでも大真面目に話している。
「刀隠の一族の本性が付喪神、つまり…あー。馬鹿にしている訳でも差別している訳でもなく。本性が人間ではない以上、人間の男性に当てはまらない所も多いと思います。心変わりをしないとか。その点を理解していけば、少なくとも付喪神の男性に対する不信感は無くなると思います。まずは相互理解からですね」
「あ、ああ!ゆっくりでいいから、俺を好きになってくれればいい!」
感極まって思わず彼女の手を取った美斗だが、その瞬間に彼女に変化が起きた。彼女は「キャッ恥ずかしい!」と叫び、座ったままだというのに思い切り跳び上がって距離を取ったのである。一転して真顔になり「すみません。慣れていないもので」と謝ったが。
ぽかんとした美斗は、同時に彼女の意外な一面に気が付いた。
この花嫁、相当に奥手であるらしい。