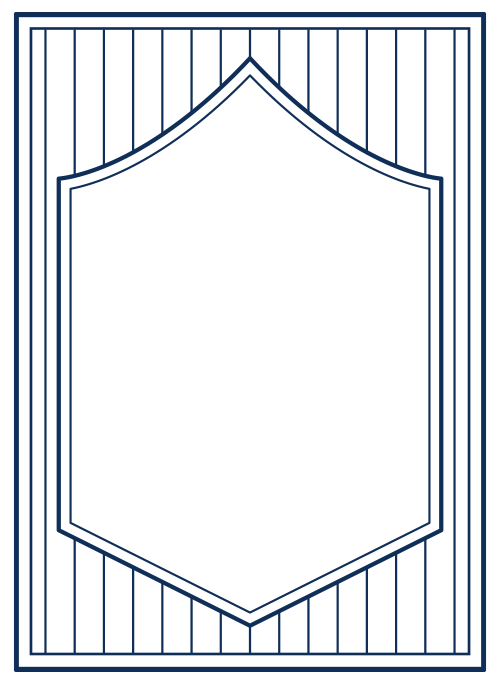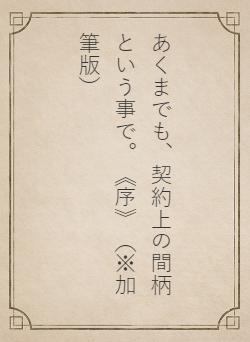職場にも予め事情は話していたので、彼女はそのまま職場に向かう事にした。なお社長の計らいで遅刻扱いにはならず、何より当の社長を始め他の社員達には「よくやった」と英雄扱いすらされた。
そして終業時刻を迎えての帰宅時、自宅の最寄り駅に着いた時だ。ポンポン、と軽いクラクションの音に振り返ると、車の中で瑠子と瑤太が手を振っていた。
「お母さん。瑤太。迎えに来てくれたの?」
「そりゃ、あんな事があった後じゃね」
後部座席に乗り込みドアを閉める彼女に、車を発進させながら瑠子は苦笑した。助手席から瑤太が彼女を振り返り、やや叱り付けるような口調で言う。
「お姉ちゃん。あんまり無茶な事すんなよ」
「んな事言われても」
運転席の瑠子は、顔は前に向けたまま「あのね」と諭す口調で彼女に語りかける。
「貴方が正義感が強い子で、霊術もあるからこその責任感…こういうのも、『高貴なる義務』に入るのかな?も強い子なのは知ってる。決して、目の前で困ってる人を見ない振りをしろって言っている訳じゃないよ?だけど、逆恨みとか…やっぱり心配だから、危ない事はしないで?」
「そういう問題じゃないってのはわかってるけど。少なくとも、逆恨みについては心配ないようにしているよ。件のお嬢さんには、『アイギス・シリーズ』を渡しておいたからね」
「あのえげつない奴か」
瑤太がバックミラー越しに苦笑した。彼女は「何言ってんのさ」と肩を竦めてみせる。
「一生もののトラウマやら後遺症やら障害やらを背負わされるレベルの行為に比べたら、可愛くて優しい対応にしか過ぎないよ」
「お姉ちゃんの『可愛い』とか『優しい』とかの基準がわからねえ」
いわゆる『引き笑い』で瑤太は身震いした。
しかし対照的に真顔の瑠子は、「うーん」と声を上げる。
「若い頃は毎日痴漢に遭っていた身としては、妥当だと私は思うけど?」
「は!?母ちゃんも!?」
瑤太が素っ頓狂な声を上げた。彼女は無言で、瑠子に視線だけを向ける。瑠子は「そうだよ」と首肯した。
「乗る時間や車両を変えてもついてきたんだから」
「何それ怖すぎるんですけど」
「思い出させてごめんね。お母さん。詳しく話さなくていいよ」
瑤太は顔を引きつらせた。彼女は静かに母を遮る。平坦な中に気遣わし気な色が混ざる娘の声に、瑠子は「気にしなくていいよ」と首を横に振った。
彼女は思い出したように「瑤太」と呼びかける。
「もしかしたらだけど。しばらくしたら、菅凪先生?だっけ?かナギゼミを通して、瑤太を探しに来る生徒がいるかもしれない。その時は私に連絡して」
「俺?どういう事?」
彼女はバックミラー越しに、弟と目を合わせる。
「今は何言っているかわからないだろうし、詳細はあえて話さないけど。多分忘れた頃にわかると思うよ」
「う、うん」
姉がこのような物言いをする時は本当に『そう』なので、瑤太は鏡の向こうの姉に向かって頷いた。
それからしばらくして、本当に姉が言った通り、一人の女子生徒が瑤太を探して、ナギゼミを訪れたのである。
そして終業時刻を迎えての帰宅時、自宅の最寄り駅に着いた時だ。ポンポン、と軽いクラクションの音に振り返ると、車の中で瑠子と瑤太が手を振っていた。
「お母さん。瑤太。迎えに来てくれたの?」
「そりゃ、あんな事があった後じゃね」
後部座席に乗り込みドアを閉める彼女に、車を発進させながら瑠子は苦笑した。助手席から瑤太が彼女を振り返り、やや叱り付けるような口調で言う。
「お姉ちゃん。あんまり無茶な事すんなよ」
「んな事言われても」
運転席の瑠子は、顔は前に向けたまま「あのね」と諭す口調で彼女に語りかける。
「貴方が正義感が強い子で、霊術もあるからこその責任感…こういうのも、『高貴なる義務』に入るのかな?も強い子なのは知ってる。決して、目の前で困ってる人を見ない振りをしろって言っている訳じゃないよ?だけど、逆恨みとか…やっぱり心配だから、危ない事はしないで?」
「そういう問題じゃないってのはわかってるけど。少なくとも、逆恨みについては心配ないようにしているよ。件のお嬢さんには、『アイギス・シリーズ』を渡しておいたからね」
「あのえげつない奴か」
瑤太がバックミラー越しに苦笑した。彼女は「何言ってんのさ」と肩を竦めてみせる。
「一生もののトラウマやら後遺症やら障害やらを背負わされるレベルの行為に比べたら、可愛くて優しい対応にしか過ぎないよ」
「お姉ちゃんの『可愛い』とか『優しい』とかの基準がわからねえ」
いわゆる『引き笑い』で瑤太は身震いした。
しかし対照的に真顔の瑠子は、「うーん」と声を上げる。
「若い頃は毎日痴漢に遭っていた身としては、妥当だと私は思うけど?」
「は!?母ちゃんも!?」
瑤太が素っ頓狂な声を上げた。彼女は無言で、瑠子に視線だけを向ける。瑠子は「そうだよ」と首肯した。
「乗る時間や車両を変えてもついてきたんだから」
「何それ怖すぎるんですけど」
「思い出させてごめんね。お母さん。詳しく話さなくていいよ」
瑤太は顔を引きつらせた。彼女は静かに母を遮る。平坦な中に気遣わし気な色が混ざる娘の声に、瑠子は「気にしなくていいよ」と首を横に振った。
彼女は思い出したように「瑤太」と呼びかける。
「もしかしたらだけど。しばらくしたら、菅凪先生?だっけ?かナギゼミを通して、瑤太を探しに来る生徒がいるかもしれない。その時は私に連絡して」
「俺?どういう事?」
彼女はバックミラー越しに、弟と目を合わせる。
「今は何言っているかわからないだろうし、詳細はあえて話さないけど。多分忘れた頃にわかると思うよ」
「う、うん」
姉がこのような物言いをする時は本当に『そう』なので、瑤太は鏡の向こうの姉に向かって頷いた。
それからしばらくして、本当に姉が言った通り、一人の女子生徒が瑤太を探して、ナギゼミを訪れたのである。