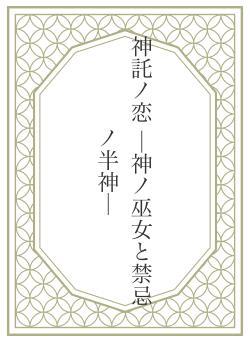朦朧とするような意識の中、肉体の奥で血潮がうねりを上げているのをちーちゃんは感じとった。流れ続ける血を見ながら『あの男と女の血なんや』と、現実と精神の狭間で思ったんよ。浴室に入り込む隙間風は秋とは思えないほど冷たい、というよりも沁みるように痛かった。風ひとつで泣けるくらいには、感受性が壊れていた。
右手の剃刀が浴槽の縁を滑り落ちて、カシャンと割れるような音が浴室に響いた。血に塗れた左腕は、これっぽっちも痛くなかった。心の方がずっと、ずっと痛かったんやもん。
血が止まらんかった。流れて、流れて、流れ続ける。もうこれで、ちーちゃんで、止まってほしいんよ。もう誰も、悲しませたくないけん。そう願いながら、ちーちゃんは咽び泣いた。狂うように、泣いた。泣いたから、狂った。
命が、血が、受け継がれてしまうこと。ちーちゃんにはそれが許せんかったんよ。
左手はもう取り返しがつかんくらい、傷だらけで、浴槽の湯が薔薇色に濁り始めとった気がする。最後の最期に、百万本の薔薇に囲まれて眠る、おとぎ話のお姫様になった気分やった。
気がするっていうのは、次に意識がはっきりした時には、ちーちゃんは病院のベッドに繋がれとったからなんよ。
目が覚めた時、文字通り、ちーちゃんはベッドに繋がれとった。身体拘束、というやつらしい。ちーちゃんは、隣の家で飼われとる犬のスペスになった気分やった。ちーちゃんは、人間やのに。
どうやら、ちーちゃんは、自殺の危険ありと判断されてしまったようやった。そりゃそうだ。血塗れの浴槽で意識を失った女が救急搬送されてきたんやから。
意識が戻って、最初に医者に聞かれたのは名前と年齢と住所やった。
「中原千夏(ちか)。18歳。鳥取県倉吉市葵町584。」
そう答えたちーちゃんの乾いた声は、とても久しぶりに聞いた気がした。自分でも、誰の声か分からんかった。
何を考えることもなく、ただぼうっと天井を眺めながらしばらくの日々をすごしとった。何も楽しくない、何もない。ただ時間だけが流れていた。
もう涙は流しすぎて、枯れきっとった。だから、苦しいのに、真夜中にうう、と小さく呻くことしかできんかったんよ。
それから少しして、ちーちゃんは「開放病棟」というところに移された。今までおったのは、「閉鎖病棟」というところらしい。そう教えてくれたのは、優しそうな瞳の看護師さんだった。閉鎖病棟にいる間、その看護師さんはずっと「絶対、大丈夫だから。だから、生きようね」とちーちゃんに声をかけ続けてくれたんよ。最初は何が大丈夫なんか分からんかった。だけどちーちゃんが暗示にかかるくらい、繰り返してくれたからいつしかその言葉を信じられるようになっとった。魔法の呪文みたいやと思った。
閉鎖病棟を出る時、その看護師さんはどうしてこんな地の底みたいな世界で働くことを、選んだんだろう。少しだけ、そう疑問に思った。どれだけの数の心が壊れてしまった人に、声をかけ続けてきたんかな。
右手の剃刀が浴槽の縁を滑り落ちて、カシャンと割れるような音が浴室に響いた。血に塗れた左腕は、これっぽっちも痛くなかった。心の方がずっと、ずっと痛かったんやもん。
血が止まらんかった。流れて、流れて、流れ続ける。もうこれで、ちーちゃんで、止まってほしいんよ。もう誰も、悲しませたくないけん。そう願いながら、ちーちゃんは咽び泣いた。狂うように、泣いた。泣いたから、狂った。
命が、血が、受け継がれてしまうこと。ちーちゃんにはそれが許せんかったんよ。
左手はもう取り返しがつかんくらい、傷だらけで、浴槽の湯が薔薇色に濁り始めとった気がする。最後の最期に、百万本の薔薇に囲まれて眠る、おとぎ話のお姫様になった気分やった。
気がするっていうのは、次に意識がはっきりした時には、ちーちゃんは病院のベッドに繋がれとったからなんよ。
目が覚めた時、文字通り、ちーちゃんはベッドに繋がれとった。身体拘束、というやつらしい。ちーちゃんは、隣の家で飼われとる犬のスペスになった気分やった。ちーちゃんは、人間やのに。
どうやら、ちーちゃんは、自殺の危険ありと判断されてしまったようやった。そりゃそうだ。血塗れの浴槽で意識を失った女が救急搬送されてきたんやから。
意識が戻って、最初に医者に聞かれたのは名前と年齢と住所やった。
「中原千夏(ちか)。18歳。鳥取県倉吉市葵町584。」
そう答えたちーちゃんの乾いた声は、とても久しぶりに聞いた気がした。自分でも、誰の声か分からんかった。
何を考えることもなく、ただぼうっと天井を眺めながらしばらくの日々をすごしとった。何も楽しくない、何もない。ただ時間だけが流れていた。
もう涙は流しすぎて、枯れきっとった。だから、苦しいのに、真夜中にうう、と小さく呻くことしかできんかったんよ。
それから少しして、ちーちゃんは「開放病棟」というところに移された。今までおったのは、「閉鎖病棟」というところらしい。そう教えてくれたのは、優しそうな瞳の看護師さんだった。閉鎖病棟にいる間、その看護師さんはずっと「絶対、大丈夫だから。だから、生きようね」とちーちゃんに声をかけ続けてくれたんよ。最初は何が大丈夫なんか分からんかった。だけどちーちゃんが暗示にかかるくらい、繰り返してくれたからいつしかその言葉を信じられるようになっとった。魔法の呪文みたいやと思った。
閉鎖病棟を出る時、その看護師さんはどうしてこんな地の底みたいな世界で働くことを、選んだんだろう。少しだけ、そう疑問に思った。どれだけの数の心が壊れてしまった人に、声をかけ続けてきたんかな。