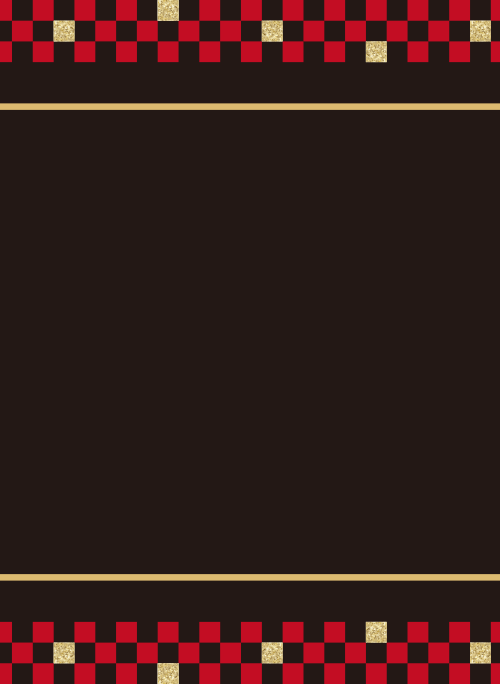背中の裂けた皮膚からは、じんじんとした痛みとともに、心にまで、絶対服従を烙印(らくいん)で押されたような気持ちがした。
「咲紀さま。ご恩情(おんじょう)を賜(たまわ)り、感謝します」
額を砂にこすりつける。そのさまを、咲紀は優雅に見下ろした。
「いいのよ。体を大切にね」
彼女は、あたかも人格者であるが如く振る舞う。奴婢を助けた咲紀を、宴の参加者や村人たち皆が称賛した。
「――」
傷を負わされた奴婢だけが、場違いに無表情だった。
奴婢の娘は、よろよろとぎこちない歩みで我が家へ向かう。
この村では、身分が最下位のものは、家を持つことを許されていない。
しかしいつでも命令を聞けるよう、待機せねばならないため、集落のそばから離れるわけにもいかず、目障りにならないよう、木陰に隠れるように身を寄せ合って暮らしていた。
「お母さん、帰ったよ。・・・具合はどう?」
背中の傷をかばい、娘ははにかむ。
顔はなぐられたせいで腫れ上がっている。背にはおびただしい数のあざと笞のあとが赤黒く皮膚を染めていた。
(お母さんに見せたら、きっと心配して、病が悪化してしまうわ・・・)
薬も医師もない今、それは避けるべきことだ。
幸い、今は夜。見えやしないだろう。
地面に気持ちばかりのわらを敷き、その上に横たわる母は、うつろな瞳を娘に向けた。
「あなたこそ、無事? ・・・あのお嬢様に、いじめられなかった?」
無事なわけがない。
しかし、痩せ細り、土(つち)気色(けいろ)のからからに乾燥した唇で娘を案じる母に、泣き言を漏らせるような神経を娘は持っていなかった。母も同じく、名を許されていない身分だ。もう、ずいぶん体調不良が続いている。起き上がるのもやっとなのだ。
娘は精一杯の笑顔をつくり、血のにじむ唇で言葉を紡ぐ。
「おかあさんったら。私の心配より、自分の心配をしてよ。――ごめん。今日の食事は手に入らなかったの」
普段は、村人の情けにすがって食料を得ている。
それも、食べ残しだ。
でも、宴で失態を犯した今日は、期待できないだろう。
「でもね、親切な人から変わった食べ物をもらったわ」
娘は獏という男がくれた饅頭(まんとう)を思い出した。さきほど乱暴を受けたせいで多少形はひしゃげているが、味は変わらないはずだ。
「あなた、どこでこれを・・・?」
「咲紀さま。ご恩情(おんじょう)を賜(たまわ)り、感謝します」
額を砂にこすりつける。そのさまを、咲紀は優雅に見下ろした。
「いいのよ。体を大切にね」
彼女は、あたかも人格者であるが如く振る舞う。奴婢を助けた咲紀を、宴の参加者や村人たち皆が称賛した。
「――」
傷を負わされた奴婢だけが、場違いに無表情だった。
奴婢の娘は、よろよろとぎこちない歩みで我が家へ向かう。
この村では、身分が最下位のものは、家を持つことを許されていない。
しかしいつでも命令を聞けるよう、待機せねばならないため、集落のそばから離れるわけにもいかず、目障りにならないよう、木陰に隠れるように身を寄せ合って暮らしていた。
「お母さん、帰ったよ。・・・具合はどう?」
背中の傷をかばい、娘ははにかむ。
顔はなぐられたせいで腫れ上がっている。背にはおびただしい数のあざと笞のあとが赤黒く皮膚を染めていた。
(お母さんに見せたら、きっと心配して、病が悪化してしまうわ・・・)
薬も医師もない今、それは避けるべきことだ。
幸い、今は夜。見えやしないだろう。
地面に気持ちばかりのわらを敷き、その上に横たわる母は、うつろな瞳を娘に向けた。
「あなたこそ、無事? ・・・あのお嬢様に、いじめられなかった?」
無事なわけがない。
しかし、痩せ細り、土(つち)気色(けいろ)のからからに乾燥した唇で娘を案じる母に、泣き言を漏らせるような神経を娘は持っていなかった。母も同じく、名を許されていない身分だ。もう、ずいぶん体調不良が続いている。起き上がるのもやっとなのだ。
娘は精一杯の笑顔をつくり、血のにじむ唇で言葉を紡ぐ。
「おかあさんったら。私の心配より、自分の心配をしてよ。――ごめん。今日の食事は手に入らなかったの」
普段は、村人の情けにすがって食料を得ている。
それも、食べ残しだ。
でも、宴で失態を犯した今日は、期待できないだろう。
「でもね、親切な人から変わった食べ物をもらったわ」
娘は獏という男がくれた饅頭(まんとう)を思い出した。さきほど乱暴を受けたせいで多少形はひしゃげているが、味は変わらないはずだ。
「あなた、どこでこれを・・・?」