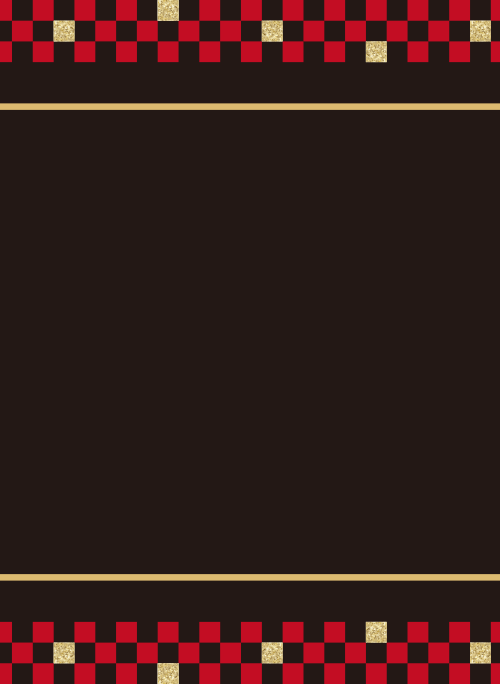(そりゃあ、別人でしょうね。裾を踏みまくって歩くことすらままならない天女なんて)
前例なきことだろう。
夢夜は悟りを開いたような顔をしていた。目に光がない。
獏は苦笑し、その頭をぽんぽんと撫でる。
「自信を持て。お前には天女の血がちゃんと流れている」
そうだろうか。服もまともに着られないのに。
祖母に似ていることは、本来であれば嬉しいことのはずなのに、こうも不安にさせられた。
会場には続々と来賓が訪れていた。
ここは高天原と桃源郷の境目。
天界の神仙たちはもちろんのこと、倭国の八百万の神々も招かれている。
一方、会場で待ち構える暇人たちがいた。
「譲葉さまのお孫さまがおられるとはまことか? それも婚約者として同棲しておられるそうではないか」
「人間の血が濃いのでしょう? どんな子か見たいわ」
「もしかして、あの馬車ではないか?」
鶴の一声で、群衆の目は一箇所に釘付けになる。
先に馬車から降りてきたのは獏。
その光景に、女性陣は息を呑んだ。
「獏様が・・・あんなにおだやかなお顔をするなんて」
彼は姫君を、いや、それ以上に大切な存在だと体現するように、中の女性に手を差し出す。
おずおずと、顔を出した娘は、人間の匂いが濃かった。
黒髪で、瞳のみ天女の血筋を感じさせるおもざし。
娘の方も、獏の手を取り、微笑んでいる。
とても、とても幸せそうな二人だった。
女性陣は絶望的な顔をしていた。
獏は影の薄さが魅力。そこからときおり垣間見える笑顔は、特別な人にしかみせない。
ゆえに天女たちは、挨拶程度の微笑みで、うかれていた。獏の特別な人はきっと自分だと、自慢しあって。
だが、夢夜へ向けられる笑顔は、そのいずれとも比較にすらならなかった。
裳の裾を踏んで転びそうになった夢夜を、馬車の下から獏が受け止める。そっと抱き上げ、地面に下ろす姿は、まさに相思相愛、しあわせな夫婦そのものだ。
天女たちはもうなにも言えなくなった。すごすごと、肩を落として会場へ向かう。なかには鼻をすするものもいた。
「獏さま、わたし、こわいです」
夢夜は、真面目に弱音を吐いた。
譲葉は見事な銀髪だった。顔かたち、身のこなし全てが劣る・・・気がする。
「天上界の作法も、狐牡丹さんにご指導いただきましたが、すべてはわかりません。・・・獏様に恥をかかせるのでは」
「そなたを護るのは、私の幸福だ」
前例なきことだろう。
夢夜は悟りを開いたような顔をしていた。目に光がない。
獏は苦笑し、その頭をぽんぽんと撫でる。
「自信を持て。お前には天女の血がちゃんと流れている」
そうだろうか。服もまともに着られないのに。
祖母に似ていることは、本来であれば嬉しいことのはずなのに、こうも不安にさせられた。
会場には続々と来賓が訪れていた。
ここは高天原と桃源郷の境目。
天界の神仙たちはもちろんのこと、倭国の八百万の神々も招かれている。
一方、会場で待ち構える暇人たちがいた。
「譲葉さまのお孫さまがおられるとはまことか? それも婚約者として同棲しておられるそうではないか」
「人間の血が濃いのでしょう? どんな子か見たいわ」
「もしかして、あの馬車ではないか?」
鶴の一声で、群衆の目は一箇所に釘付けになる。
先に馬車から降りてきたのは獏。
その光景に、女性陣は息を呑んだ。
「獏様が・・・あんなにおだやかなお顔をするなんて」
彼は姫君を、いや、それ以上に大切な存在だと体現するように、中の女性に手を差し出す。
おずおずと、顔を出した娘は、人間の匂いが濃かった。
黒髪で、瞳のみ天女の血筋を感じさせるおもざし。
娘の方も、獏の手を取り、微笑んでいる。
とても、とても幸せそうな二人だった。
女性陣は絶望的な顔をしていた。
獏は影の薄さが魅力。そこからときおり垣間見える笑顔は、特別な人にしかみせない。
ゆえに天女たちは、挨拶程度の微笑みで、うかれていた。獏の特別な人はきっと自分だと、自慢しあって。
だが、夢夜へ向けられる笑顔は、そのいずれとも比較にすらならなかった。
裳の裾を踏んで転びそうになった夢夜を、馬車の下から獏が受け止める。そっと抱き上げ、地面に下ろす姿は、まさに相思相愛、しあわせな夫婦そのものだ。
天女たちはもうなにも言えなくなった。すごすごと、肩を落として会場へ向かう。なかには鼻をすするものもいた。
「獏さま、わたし、こわいです」
夢夜は、真面目に弱音を吐いた。
譲葉は見事な銀髪だった。顔かたち、身のこなし全てが劣る・・・気がする。
「天上界の作法も、狐牡丹さんにご指導いただきましたが、すべてはわかりません。・・・獏様に恥をかかせるのでは」
「そなたを護るのは、私の幸福だ」