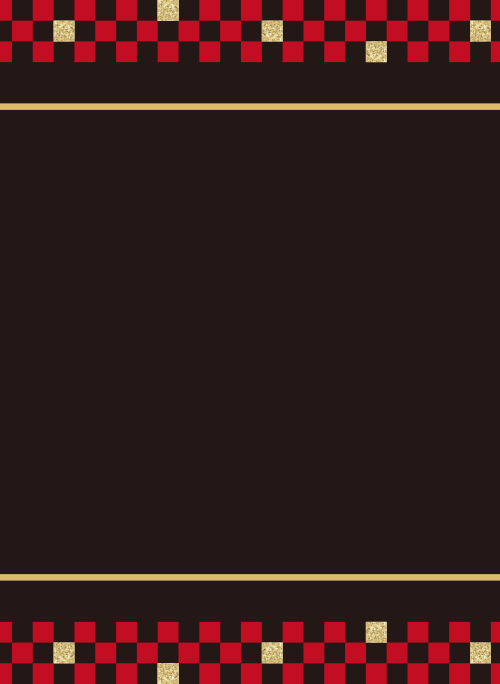「わしの情けで病の母親を追い出さずにやっているというのに。親子ともども使えぬ穀(ごく)潰(つぶ)しめ!」
「ガッ・・・!」
むち打たれている娘は、小さくうめき声を上げる。背を襲う痛みを、それでも歯を食いしばって耐えた。悲鳴を上げれば、余計に悪化するだけだと知っている。
若い娘が暴力をふるわれているというのに、村人は一様に目をそらして関わり合おうとしなかった。村長のすることだから。誰も咎(とが)めるものはいない。
それを階段の上から楽しそうに見下ろすのは、歳のそう変わらない咲紀だ。優雅に肩にかけた桜色の羽衣を引き寄せながら言う。
「お父さま。私の裾(すそ)を汚したぐらいで、そう怒らないであげてくださいな」
意地の悪い笑みだ。奴婢は唇を噛む。
(わたしは転ばされたのに・・・!!)
喉まで飛び出しかけたが、飲み込む。口答えは許されない。
反論も、弁解も、この身分は許されていない。下手をすれば、首が飛ぶのだ。
奴婢は痛みに耐え、砂利を引っ掻く。爪の間には砂が入り、背中に血が滲(にじ)んだとき、ようやくむち打つ手が止まった。
「咲紀・・・。なんて優しい子だ。このうすぎたない奴婢を許すのか?」
「お父さま。善行はまわりまわって己の身を助けるものですわ」
咲紀はゆっくりと階段を降りながら、善人を装った笑顔の仮面をはりつけた。首からさげた翡翠(ひすい)の勾玉(まがたま)は歩むたびに軽やかに音を立てる。
「この奴婢をお許しになれば、わたくしだけでなく、お父さまも皆から人望を集められるでしょう。許してあげても損はないわ」
(――よく言う)
奴婢の娘は、皮肉げに心のなかで毒づき、しかし顔では無表情を装った。
今顔に出せば、間違いなく斬首(ざんしゅ)だ。
咲紀は、わかって言っている。塵のようにかるい奴婢の命を、鬱憤晴(うっぷんば)らしのおもちゃにしてもてあそぶために。
まぬけな父親は、娘のうすぎたない裏の顔になど、まったく気づかない。
「咲紀よ。なんと懐(ふところ)が深くて思慮深い! 父のことまで考えてくれているのか」
村長は娘を誇らしげに抱き寄せると、笞を手に持ったまま、するどい視線を奴婢へ投げた。
「咲紀に感謝せよ。貴様の命の恩人だぞ」
「・・・はい」
奴婢は頷き、地面に這(は)いつくばるように、深く低頭した。
「ガッ・・・!」
むち打たれている娘は、小さくうめき声を上げる。背を襲う痛みを、それでも歯を食いしばって耐えた。悲鳴を上げれば、余計に悪化するだけだと知っている。
若い娘が暴力をふるわれているというのに、村人は一様に目をそらして関わり合おうとしなかった。村長のすることだから。誰も咎(とが)めるものはいない。
それを階段の上から楽しそうに見下ろすのは、歳のそう変わらない咲紀だ。優雅に肩にかけた桜色の羽衣を引き寄せながら言う。
「お父さま。私の裾(すそ)を汚したぐらいで、そう怒らないであげてくださいな」
意地の悪い笑みだ。奴婢は唇を噛む。
(わたしは転ばされたのに・・・!!)
喉まで飛び出しかけたが、飲み込む。口答えは許されない。
反論も、弁解も、この身分は許されていない。下手をすれば、首が飛ぶのだ。
奴婢は痛みに耐え、砂利を引っ掻く。爪の間には砂が入り、背中に血が滲(にじ)んだとき、ようやくむち打つ手が止まった。
「咲紀・・・。なんて優しい子だ。このうすぎたない奴婢を許すのか?」
「お父さま。善行はまわりまわって己の身を助けるものですわ」
咲紀はゆっくりと階段を降りながら、善人を装った笑顔の仮面をはりつけた。首からさげた翡翠(ひすい)の勾玉(まがたま)は歩むたびに軽やかに音を立てる。
「この奴婢をお許しになれば、わたくしだけでなく、お父さまも皆から人望を集められるでしょう。許してあげても損はないわ」
(――よく言う)
奴婢の娘は、皮肉げに心のなかで毒づき、しかし顔では無表情を装った。
今顔に出せば、間違いなく斬首(ざんしゅ)だ。
咲紀は、わかって言っている。塵のようにかるい奴婢の命を、鬱憤晴(うっぷんば)らしのおもちゃにしてもてあそぶために。
まぬけな父親は、娘のうすぎたない裏の顔になど、まったく気づかない。
「咲紀よ。なんと懐(ふところ)が深くて思慮深い! 父のことまで考えてくれているのか」
村長は娘を誇らしげに抱き寄せると、笞を手に持ったまま、するどい視線を奴婢へ投げた。
「咲紀に感謝せよ。貴様の命の恩人だぞ」
「・・・はい」
奴婢は頷き、地面に這(は)いつくばるように、深く低頭した。