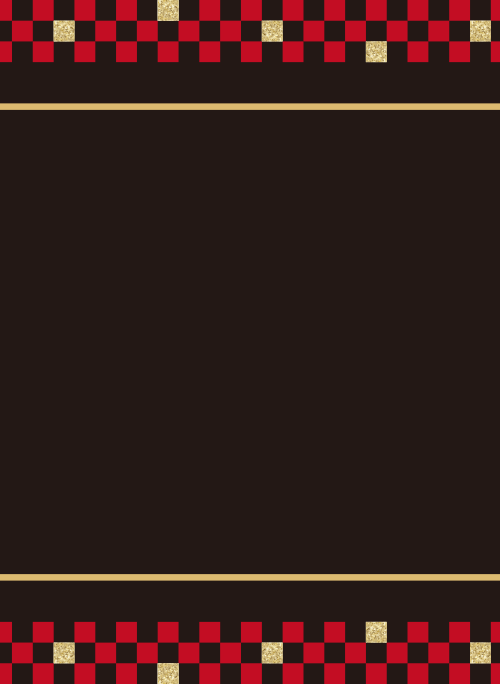獏は思う。
おかえりと言ってくれる人が欲しかった。
夢夜は思う。
ただいまと言える場所が欲しかった。
境遇は違っても、たがいに孤独だったふたりは、当然のように惹かれ合う。
そして恋が色づいた時、乙女は美しくなるのだ。
夢夜と名付けされ、数日たち、娘は私室ですやすやと眠る。熟睡したことすらなければ、明日我が身を襲うであろう痛みに怯え、震えて泣いていた。いまはなにも、怖くない。
村長に繋がれた首輪は獏の手によって引きちぎられ、自由の身となった。
もう、明日に怯えることもない。
夢夜は今、とても幸せな夢を見ている。
愛する人の前で蝶のように舞う夢だ。彼は琴をあやつり、その独特の音色に合わせて夢夜は踊る。
かろやかな脚。細い腰をいかして柳のように揺れ動く。陽気に、ときに妖艶に。
ふと。
寝台に散った髪が、ざわざわと波打った。長い黒髪は、頭皮から毛先へじわりと色を変えてゆく。
漆黒の髪は、月光のような銀の髪へ。
――・・・ふっと、また黒髪へ戻った。
それを知るものは、だれもいない。
翌朝。
「きゃああっ!?」
夢夜の叫び声で、屋敷のものは全員叩き起こされた。
「どうした! 夢夜っ」
獏は戸を蹴破る勢いで開ける。夢夜は、鏡台の椅子に掛け、顔を抑えてうずくまるように震えていた。
「目が・・・、わたしの目が・・・!」
「目が、どうかしたのか?」
獏はおそるおそる近づく。寝起きの無防備な体に自身の上着をかけつつ、膝をついて顔をうかがう。
夢夜は顔ではなく目を抑えているようだった。