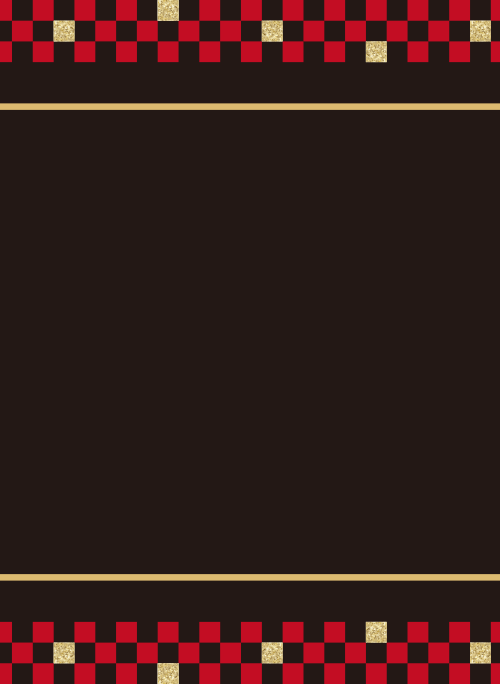(笑顔を見せるのは自分だけにしてほしい、・・・だなんて)
夢夜は自分にあきれた。いつからこんなに狭量になったのだろう?
――この特別な笑顔は、わたしだけの、もの。
素敵、すぎて。
きれい、すぎて。
だれにも、みせたくない。
夢夜の隠れた独占欲の葛藤に獏は気づかない。
一歩前へ出て、白々とした大きな両袖をふわりと広げた。
「わっ!?」
夢夜は思わずあとずさった。
みるみる景色は緑の生い茂る草原も、木々も、ゆらりかき消えていった。代わりに、湧き水が吹き出すように芳しいヤマユリの花畑がふわり、一面に咲きほこった。緑一色だった地面は、純白の花びらが彩る麗しい世界へ変貌する。
夢夜は足を踏み出した。
息を呑む。
それほど、眼前の光景は美しかった。
花びらにも、青葉にも朝露がたっぷりとたくわえられ、雫のひとつひとつが鏡のように、空の青を映す。朝日にきらきらと反射する花々はまぶしいほどだ。
「夢夜」
ふいに、獏はこちらを向いた。
いつも冷たい色をたたえた白銀の瞳は、いま、とろけるようにあまく濡れている。視線が合えば、しっとり絡みついて、はなれない。
ゆっくりと、彼は手を伸ばし、夢夜の腰を引き寄せた。
「っ!」
なぜだかわからないが、こわくなった。夢夜はぎゅっと目をつぶった。
骨ばった大きな手は、男性らしくたくましい。それは髪をすき、耳朶を撫で、頬を滑る。
「っ」
そのたびに、びくりと肩が震えた。
獏は終始、無言だった。夢夜の予想に反して、手は後頭部へ添えられることなく、額の傷を撫でていた。それは、大蛇の住む岩場で神輿から落ちた際、強打した場所だ。
「あ・・・っ」
不意に傷口に指が触れ、痛みに思わず声を上げた。針で縫ってもらっても、敏感な場所だ。
おそるおそる、目を開けると、彼はせつなげな顔をしていた。
なんども。なんども彼の手は傷跡を行き来する。
「・・・のこってしまったな」
獏はぽつりという。夢夜はチクッと胸が痛んだ。
何と言おう。いや、言葉にしたくない。それは夢夜がもっとも気にしていることだったから。
額に残った醜い傷跡は、名前をもらっても消えない。消えてくれない。
焼印のごとく、鏡で見るたび気を重くさせる。
・・・と。
獏は身をかがめ、ふわり、唇を傷に寄せた。
「ひっ」
夢夜は、痛くもないのに声が漏れた。口づけられたあとは、じんじんとあまくうずく。
夢夜は自分にあきれた。いつからこんなに狭量になったのだろう?
――この特別な笑顔は、わたしだけの、もの。
素敵、すぎて。
きれい、すぎて。
だれにも、みせたくない。
夢夜の隠れた独占欲の葛藤に獏は気づかない。
一歩前へ出て、白々とした大きな両袖をふわりと広げた。
「わっ!?」
夢夜は思わずあとずさった。
みるみる景色は緑の生い茂る草原も、木々も、ゆらりかき消えていった。代わりに、湧き水が吹き出すように芳しいヤマユリの花畑がふわり、一面に咲きほこった。緑一色だった地面は、純白の花びらが彩る麗しい世界へ変貌する。
夢夜は足を踏み出した。
息を呑む。
それほど、眼前の光景は美しかった。
花びらにも、青葉にも朝露がたっぷりとたくわえられ、雫のひとつひとつが鏡のように、空の青を映す。朝日にきらきらと反射する花々はまぶしいほどだ。
「夢夜」
ふいに、獏はこちらを向いた。
いつも冷たい色をたたえた白銀の瞳は、いま、とろけるようにあまく濡れている。視線が合えば、しっとり絡みついて、はなれない。
ゆっくりと、彼は手を伸ばし、夢夜の腰を引き寄せた。
「っ!」
なぜだかわからないが、こわくなった。夢夜はぎゅっと目をつぶった。
骨ばった大きな手は、男性らしくたくましい。それは髪をすき、耳朶を撫で、頬を滑る。
「っ」
そのたびに、びくりと肩が震えた。
獏は終始、無言だった。夢夜の予想に反して、手は後頭部へ添えられることなく、額の傷を撫でていた。それは、大蛇の住む岩場で神輿から落ちた際、強打した場所だ。
「あ・・・っ」
不意に傷口に指が触れ、痛みに思わず声を上げた。針で縫ってもらっても、敏感な場所だ。
おそるおそる、目を開けると、彼はせつなげな顔をしていた。
なんども。なんども彼の手は傷跡を行き来する。
「・・・のこってしまったな」
獏はぽつりという。夢夜はチクッと胸が痛んだ。
何と言おう。いや、言葉にしたくない。それは夢夜がもっとも気にしていることだったから。
額に残った醜い傷跡は、名前をもらっても消えない。消えてくれない。
焼印のごとく、鏡で見るたび気を重くさせる。
・・・と。
獏は身をかがめ、ふわり、唇を傷に寄せた。
「ひっ」
夢夜は、痛くもないのに声が漏れた。口づけられたあとは、じんじんとあまくうずく。