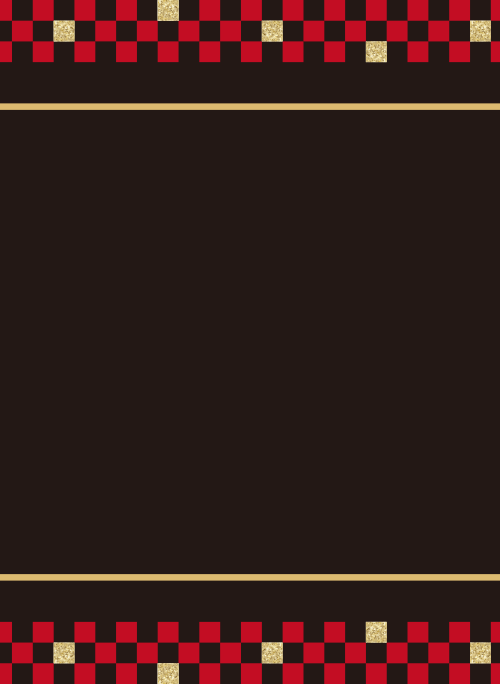獏は夢夜をまぶしそうな、とろけるような瞳で見つめた。彼女は、譲葉とも、ほかの誰とも違う。
心の鍵をこじ開け、光の道へ手を取り、導く月のような存在。
――そなたを・・・そなたのことを・・・私は・・・、
「私は・・・」
私はふたたび、恋をしてもいいのだろうか?
その問は、秋のそよ風に吹かれて、かき消えた。
紅(くれない)の紅葉(こうよう)は、燃える恋のように。
かつての想い人の孫と、恋に傷心した幻獣。
氷上を歩くように慎重に進まねば、簡単に壊れてしまう、もろい関係。
あせることはない。一歩一歩、紅(くれない)の絨毯(じゅうたん)を踏みしめてゆこう。
獏はそっと、その手に自分のそれを重ねる。それはまるで楓の葉が重なり合うように。
「名などなくとも、尊い人だった。そなたは」
「・・・・・・獏さま」
どの宝石にもまさる宝物だと、夢夜は紙をだきしめた。
〈夢糸の庭園〉では。
二本の夢の糸は月光のように輝いていた。
うすみどりの夢夜の糸と、獏の白糸だ。
しゅる・・・と二本の糸は絡み合う。よりあい、双糸となりつつあった。
獏はまだ知らない。
これはまだ、幸福のはじまりに過ぎないことを。
心の鍵をこじ開け、光の道へ手を取り、導く月のような存在。
――そなたを・・・そなたのことを・・・私は・・・、
「私は・・・」
私はふたたび、恋をしてもいいのだろうか?
その問は、秋のそよ風に吹かれて、かき消えた。
紅(くれない)の紅葉(こうよう)は、燃える恋のように。
かつての想い人の孫と、恋に傷心した幻獣。
氷上を歩くように慎重に進まねば、簡単に壊れてしまう、もろい関係。
あせることはない。一歩一歩、紅(くれない)の絨毯(じゅうたん)を踏みしめてゆこう。
獏はそっと、その手に自分のそれを重ねる。それはまるで楓の葉が重なり合うように。
「名などなくとも、尊い人だった。そなたは」
「・・・・・・獏さま」
どの宝石にもまさる宝物だと、夢夜は紙をだきしめた。
〈夢糸の庭園〉では。
二本の夢の糸は月光のように輝いていた。
うすみどりの夢夜の糸と、獏の白糸だ。
しゅる・・・と二本の糸は絡み合う。よりあい、双糸となりつつあった。
獏はまだ知らない。
これはまだ、幸福のはじまりに過ぎないことを。