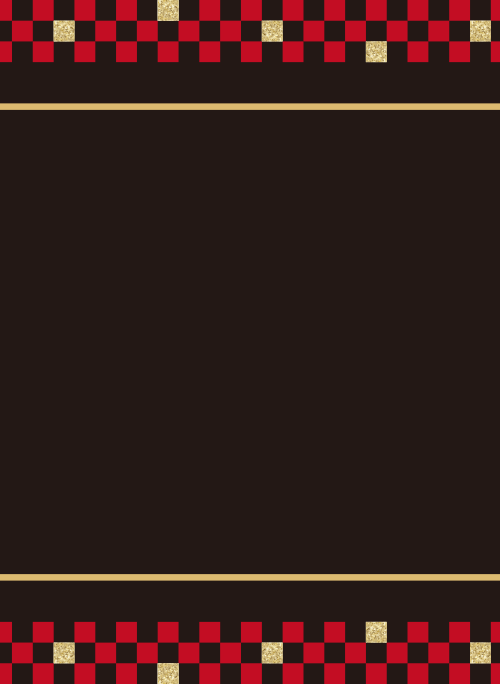ひとの顔色ばかりうかがってきた人生だ。相手がなにを考えているかくらい、すぐにわかる。
譲葉の話を聞いたあと、廊下ですれ違った彼の顔は、まさに恋に傷心した男の顔だった。
(おばあさまは、どんな人だったのかしら)
美人だったとは、聞いているけれど。
――あの人にあんな顔をさせられるくらい、魅力的な人だったの?
娘はちくりと胸が痛んだ。
(おばあさまのことなんて、考えたくもないっ!)
娘はどんっ、と花瓶を置いた。
祖母は生まれたときにはすでにいなかったし、母が奴婢の身分まで落とされたのは彼女のせいだ。まったく恨んでいないと言えば、嘘になる。
彼をここまで悩ませる祖母が、とてつもなく羨ましい。
(わたしは美人じゃない。ひとを魅了する華もない。・・・おばあさまのようには、なれない)
こうして、獏がいないときにせっせと部屋を掃除して。でも自分がやりましたと告げる気はない。親切の押し売りのような気がするから。
『裏返せば・・・自信がないだけではないのか?』
急に第三者から問われたような気がした。
娘は「ふう」と深く息を吐いた。まぶたを伏せる。
(これは世間一般の、単純な嫉妬とはわけが違うの)
彼女は母を生んでくれたひと。
自分がこの世に生まれる基礎となったひと。
正直、五十年前などと大昔の話をされても、よくわからないし、結局、血の繋がりはおそろしい。
嫉妬心を肉親にぶつけるのは、なんだか違う気もする。
・・・・・・・・・フクザツだ。
(おばあさまに嫉妬する女も、めずらしいものよね)
余裕めいた言葉を吐く。余裕なフリをしているだけ。・・・きっと流星になった祖母は笑っているはずだ。
話しかけられもせず、顔すら見られず、希望も皆無なこの状況で、よくも前向きに掃除などしていられるものだと。
(勝手に笑っているといいわ)
娘はふんっと息巻く。
獏はもともと、高嶺の花なのだ。こうして、同じ屋敷に住まわせてもらっていること自体、奇跡。
奴婢だった時間は、娘の幸せの器をとても小さくさせていた。
どんなことでも新鮮に感じるこころ。欲張らないこころ。無欲さを、とことん育ませた。
だいじょうぶ。足ることを知れば、不足はない。
だいじょうぶ。いつかきっと、わたしのことを、見てくれる日が来る。
だいじょうぶ。さみしいのは、我慢できる。
譲葉の話を聞いたあと、廊下ですれ違った彼の顔は、まさに恋に傷心した男の顔だった。
(おばあさまは、どんな人だったのかしら)
美人だったとは、聞いているけれど。
――あの人にあんな顔をさせられるくらい、魅力的な人だったの?
娘はちくりと胸が痛んだ。
(おばあさまのことなんて、考えたくもないっ!)
娘はどんっ、と花瓶を置いた。
祖母は生まれたときにはすでにいなかったし、母が奴婢の身分まで落とされたのは彼女のせいだ。まったく恨んでいないと言えば、嘘になる。
彼をここまで悩ませる祖母が、とてつもなく羨ましい。
(わたしは美人じゃない。ひとを魅了する華もない。・・・おばあさまのようには、なれない)
こうして、獏がいないときにせっせと部屋を掃除して。でも自分がやりましたと告げる気はない。親切の押し売りのような気がするから。
『裏返せば・・・自信がないだけではないのか?』
急に第三者から問われたような気がした。
娘は「ふう」と深く息を吐いた。まぶたを伏せる。
(これは世間一般の、単純な嫉妬とはわけが違うの)
彼女は母を生んでくれたひと。
自分がこの世に生まれる基礎となったひと。
正直、五十年前などと大昔の話をされても、よくわからないし、結局、血の繋がりはおそろしい。
嫉妬心を肉親にぶつけるのは、なんだか違う気もする。
・・・・・・・・・フクザツだ。
(おばあさまに嫉妬する女も、めずらしいものよね)
余裕めいた言葉を吐く。余裕なフリをしているだけ。・・・きっと流星になった祖母は笑っているはずだ。
話しかけられもせず、顔すら見られず、希望も皆無なこの状況で、よくも前向きに掃除などしていられるものだと。
(勝手に笑っているといいわ)
娘はふんっと息巻く。
獏はもともと、高嶺の花なのだ。こうして、同じ屋敷に住まわせてもらっていること自体、奇跡。
奴婢だった時間は、娘の幸せの器をとても小さくさせていた。
どんなことでも新鮮に感じるこころ。欲張らないこころ。無欲さを、とことん育ませた。
だいじょうぶ。足ることを知れば、不足はない。
だいじょうぶ。いつかきっと、わたしのことを、見てくれる日が来る。
だいじょうぶ。さみしいのは、我慢できる。