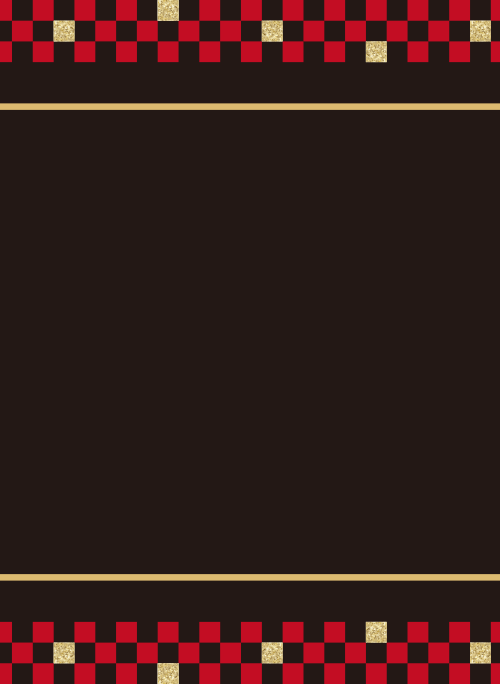「いやあ、いい新人見つけてきたねぇ。眠りにまで気を回してくれるなんてさ。おまえに気があるんじゃねーの?」
「・・・おい」
獏は目を平べったくすると、手の骨を順に鳴らしていった。もう新人への怒りはない。むしろ、せっかく掃除してくれたのに、果汁でベタベタになってしまったではないか。
仙人は危機を察知した。懐に詰め込めるだけ桃を詰め込むと、獏の手をかいくぐり、サササッと窓へ飛び移る。獏はすかさずあとを追った。
「待てっ! 桃をかえせ!」
「やなこった。おまえにゃもったいねーもんっ!」
言うが早いか、仙人はバッと窓から飛び降りた。
「貴様っ! いたずらだけして逃げる気かっ!」
獏は窓から顔を出し、桃泥棒へ怒声をあびせる。おかげで今夜の寝床が台無しだ。
いっぽう、仙人は桃をかじりながら、夜空の月を見上げる。
「女の好意を無にするなんざ、いいご身分だってことだよ。バカヤローめ」
ぺっ! と庭へ桃の種を吐き捨てた。
(そろそろ気づかないかなぁ)
娘は獏の部屋の中を掃除しながら、ほー・・・とため息をついた。
ここは彼のにおいがいっぱいで、落ち着く。
仙人に入れ知恵してもらった安眠のための桃は、結局撤去されてしまった。
彼はここ数日、日中は外出して帰ってこない。
(わたしたち親子と、顔を合わせたくないのだわ)
廊下ですれ違っても彼は挨拶こそしてくれるものの、かたくなに娘の顔を見ようとしなかった。
・・・かまわない。無理強いはするまい。
(掃除を拒絶されたわけではないから、まだわたしの仕業とはバレていない・・・と思うし)
母は快復した。仙人とおやつの桃を食べるほどだ。
幸せそうな母の、おだやかな顔を、はじめて見た気がする。
(獏さまと出逢ってから、〈はじめて〉がいっぱい増えた・・・)
それも、幸福な〈はじめて〉ばかり。
心安らぐ時間など、生涯無縁だと思っていたのに。獏には一生感謝してもたりないくらい。
――でも。
娘には気になっていることがあった。
自分の心だ。
(これは、ほんとうに〈感謝〉だけ?)
落ち込んでいる獏の顔を見れば見るほど、謎の熱情にかられる。
彼が孤独であるほど、そばにいたいと思う。
落ち込めば落ち込むほど、なにかしてやりたいと思う。
これはほんとうに、〈感謝〉なのか。
祖母と恋仲だったことは、侍女たちから聞いた。娘はうすうす感づいていた。
「・・・おい」
獏は目を平べったくすると、手の骨を順に鳴らしていった。もう新人への怒りはない。むしろ、せっかく掃除してくれたのに、果汁でベタベタになってしまったではないか。
仙人は危機を察知した。懐に詰め込めるだけ桃を詰め込むと、獏の手をかいくぐり、サササッと窓へ飛び移る。獏はすかさずあとを追った。
「待てっ! 桃をかえせ!」
「やなこった。おまえにゃもったいねーもんっ!」
言うが早いか、仙人はバッと窓から飛び降りた。
「貴様っ! いたずらだけして逃げる気かっ!」
獏は窓から顔を出し、桃泥棒へ怒声をあびせる。おかげで今夜の寝床が台無しだ。
いっぽう、仙人は桃をかじりながら、夜空の月を見上げる。
「女の好意を無にするなんざ、いいご身分だってことだよ。バカヤローめ」
ぺっ! と庭へ桃の種を吐き捨てた。
(そろそろ気づかないかなぁ)
娘は獏の部屋の中を掃除しながら、ほー・・・とため息をついた。
ここは彼のにおいがいっぱいで、落ち着く。
仙人に入れ知恵してもらった安眠のための桃は、結局撤去されてしまった。
彼はここ数日、日中は外出して帰ってこない。
(わたしたち親子と、顔を合わせたくないのだわ)
廊下ですれ違っても彼は挨拶こそしてくれるものの、かたくなに娘の顔を見ようとしなかった。
・・・かまわない。無理強いはするまい。
(掃除を拒絶されたわけではないから、まだわたしの仕業とはバレていない・・・と思うし)
母は快復した。仙人とおやつの桃を食べるほどだ。
幸せそうな母の、おだやかな顔を、はじめて見た気がする。
(獏さまと出逢ってから、〈はじめて〉がいっぱい増えた・・・)
それも、幸福な〈はじめて〉ばかり。
心安らぐ時間など、生涯無縁だと思っていたのに。獏には一生感謝してもたりないくらい。
――でも。
娘には気になっていることがあった。
自分の心だ。
(これは、ほんとうに〈感謝〉だけ?)
落ち込んでいる獏の顔を見れば見るほど、謎の熱情にかられる。
彼が孤独であるほど、そばにいたいと思う。
落ち込めば落ち込むほど、なにかしてやりたいと思う。
これはほんとうに、〈感謝〉なのか。
祖母と恋仲だったことは、侍女たちから聞いた。娘はうすうす感づいていた。