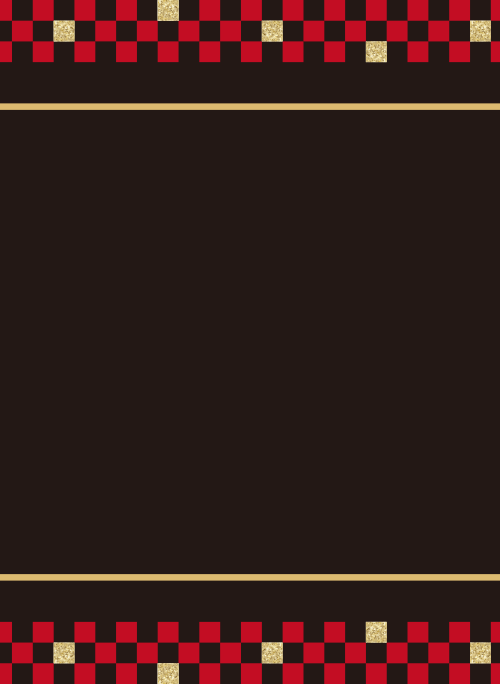季節は秋になろうとしていた。
今日も、獏はぼうっと窓から空を見上げていた。
同じ職人が作った料理が、変わらず運ばれてくる。
「いらないといったはずだが」
「生きる基本だと言ったはずですよ。いい歳して周りを心配させないでくださいな」
問答無用で箸を握らされる。
その日は饅頭だった。しかし、具材は大きく切りすぎていて、味付けもちぐはぐだ。
「・・・そのあたらしい新人とやらは、料理をしたことがないのか? 食材を見る目は確かなようだが」
獏は耐えかねて、侍女頭をにらむ。
「さあ? 苦労して育った娘ですので、いい食事がどんな味なのかご存知ないのでは?」
狐牡丹はさらりと言った。
今日も、獏は不思議と平らげることができた。
引きこもり、朦朧としていても、入浴は習慣化していた。
夜。風呂からあがり、部屋へもどると、獏は部屋に違和感を覚えた。
道具の配置が変わっている。それだけではなく、机の上、壁の装飾のくぼみにいたるまでホコリがきれいに拭き取られていた。
使用済みの燭(しょく)は撤去され、新品と交換されている。いつもより部屋が明るい気がしたのは、気のせいではなかったようだ。
「・・・誰だ。許可なく私の部屋へ入ったのは」
獏はむすっと唇を引き結ぶと、侍女たちをにらんだ。基本、他人に私物を触られるのは好きではない。
「私達じゃありませんよ。新人です」
侍女たちは妙な含み笑いをすると、すたこらと逃げていった。
謎の新人は、妙に気が利く狐のようだった。
でも、気づかいは過ぎればおせっかいである。
明日呼び出して叱っておこう。そう決めた時、甘い香りがふわりと鼻をくすぐった。
(――桃・・・?)
寝台の横に、桃がこれでもかと積み上げられていた。桃源郷では、桃は年中手に入る。
しかし、なんの意図があって桃を・・・?
獏は首を傾げた。ほんとうに奇妙な新人の狐だ。主人の寝所に果物など置いて、何がしたいのか。
そのとき、お子様の声がした。
「果物の香りは、安眠効果があるんだよ」
仙人が、こつこつと杖を突きながら部屋に押し入ってきた。
「おまえ、まだいたのか」
「いるよ。俺の他にも。・・・いろいろ忘れ過ぎだよ、おまえ」
ちいさな友人は、ぴょんと寝台へ飛び乗ると、桃を手に取り、しゃくしゃくとかじりつく。たっぷりの果汁が口から滴り落ち、敷布を汚していく。
今日も、獏はぼうっと窓から空を見上げていた。
同じ職人が作った料理が、変わらず運ばれてくる。
「いらないといったはずだが」
「生きる基本だと言ったはずですよ。いい歳して周りを心配させないでくださいな」
問答無用で箸を握らされる。
その日は饅頭だった。しかし、具材は大きく切りすぎていて、味付けもちぐはぐだ。
「・・・そのあたらしい新人とやらは、料理をしたことがないのか? 食材を見る目は確かなようだが」
獏は耐えかねて、侍女頭をにらむ。
「さあ? 苦労して育った娘ですので、いい食事がどんな味なのかご存知ないのでは?」
狐牡丹はさらりと言った。
今日も、獏は不思議と平らげることができた。
引きこもり、朦朧としていても、入浴は習慣化していた。
夜。風呂からあがり、部屋へもどると、獏は部屋に違和感を覚えた。
道具の配置が変わっている。それだけではなく、机の上、壁の装飾のくぼみにいたるまでホコリがきれいに拭き取られていた。
使用済みの燭(しょく)は撤去され、新品と交換されている。いつもより部屋が明るい気がしたのは、気のせいではなかったようだ。
「・・・誰だ。許可なく私の部屋へ入ったのは」
獏はむすっと唇を引き結ぶと、侍女たちをにらんだ。基本、他人に私物を触られるのは好きではない。
「私達じゃありませんよ。新人です」
侍女たちは妙な含み笑いをすると、すたこらと逃げていった。
謎の新人は、妙に気が利く狐のようだった。
でも、気づかいは過ぎればおせっかいである。
明日呼び出して叱っておこう。そう決めた時、甘い香りがふわりと鼻をくすぐった。
(――桃・・・?)
寝台の横に、桃がこれでもかと積み上げられていた。桃源郷では、桃は年中手に入る。
しかし、なんの意図があって桃を・・・?
獏は首を傾げた。ほんとうに奇妙な新人の狐だ。主人の寝所に果物など置いて、何がしたいのか。
そのとき、お子様の声がした。
「果物の香りは、安眠効果があるんだよ」
仙人が、こつこつと杖を突きながら部屋に押し入ってきた。
「おまえ、まだいたのか」
「いるよ。俺の他にも。・・・いろいろ忘れ過ぎだよ、おまえ」
ちいさな友人は、ぴょんと寝台へ飛び乗ると、桃を手に取り、しゃくしゃくとかじりつく。たっぷりの果汁が口から滴り落ち、敷布を汚していく。