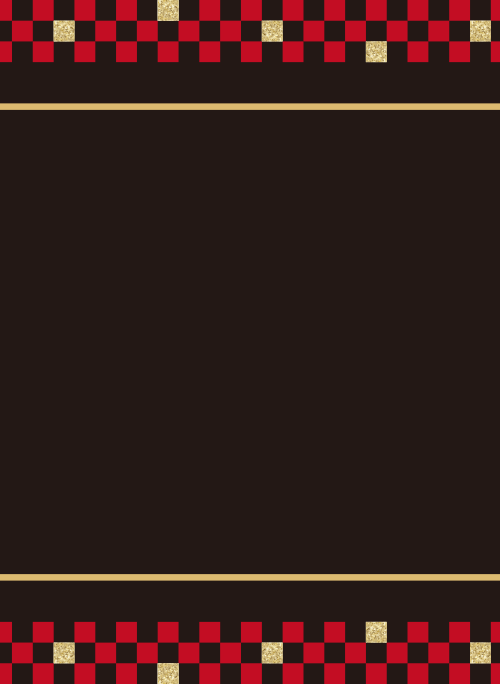「獏さま・・・。どこにいるの・・・?」
和葉の話を聞いた翌朝。
奴婢の娘――譲葉の孫娘は、獏をさがして屋敷中を歩き回っていた。
まだ体は本調子ではない。ふらつく足取りは危なげで、いつ倒れてもおかしくなかった。
侍女から、獏がまだ部屋に帰っていないと知らせを受け、いても立ってもいられなかったのだ。
すると。
長い廊下の向こうから、捜索中の男の白い袍が見えた。
早朝のまばゆい光が窓から差し込む。
だが男の顔に、生気はなかった。
「ばく、さま・・・?」
声をかけようとして、ためらった。
ここに来るまで、娘はあらゆる言葉が脳をよぎった。
なぜ、お祖母様の死を、そこまで悲しまれるのですか?
なぜ、日が昇るまで、ひとりでいたかったのですか?
もしかして、ひょっとして――・・・・・・。
尋ねたいことは、山ほどあって。でもそのどれもが、辛い現実を突きつけるもののような気がしていた。
彼に惹かれ始めている、自分は聞かないほうがいいようなことのような、嫌な予感が。
だから。
呆然と、顔を上げてこちらを見た彼の視線ひとつで、質問はぜんぶ吹き飛んでしまった。
――わたしじゃない。違うひとを見ているような目。
「っ」
娘は胸に手を添え、荒い呼吸を隠そうとした。
感情を殺すのは慣れているはずだった。殴られようと、鞭打たれようと。