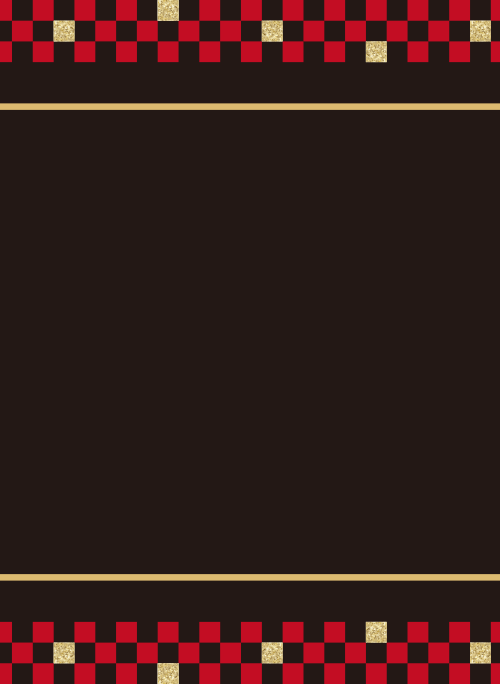あの晩いらい、獏は遠目から彼女を目で追いかけるようになってしまった。
譲葉は日中、舞いの稽古に勤(いそ)しんでいる。
獏は木の枝に腰掛け、無関心を装いながら、それを目で追ってしまうのだ。
(私はなにをやっている・・・)
足元では、譲葉に下心を抱く男どもが鼻息荒く眺めていた。
普段なら、「くだらない」の一言ですます自分だったが、奴らの好奇の目に触れていると思うと、なぜか癇に障った。
木の上から音もなく飛び降りる。すると追っかけはぎょっと腰をぬかし、すごすごと退散していった。
・・・ふと、顔をあげると、譲葉と目が合った。
いつから気づいていたのか。彼女はこちらへ、にこりと笑い返した。
「う」
つい、目をそらしてしまった。・・・・・・重症だ。
(私はいつから、そんな暇人になった!)
獏はバカバカしい、とくだらない思考を切り捨てた。
糸もつながらない女人と接点を持って、なんの特がある。
しかし、心とは不思議なものだ。
禁じられれば、それだけ興味も増す。
獏は時間を見つけては、譲葉のもとへ通い詰めた。
やがて、譲葉にも、変化が見られ始めた。
獏が見当たらないと不安げに目をさまよわせ、見つけると蕾がほころぶように笑うのだ。
ふたりが惹かれ合うのに、時間はかからなかった。
獏は琴を奏で、譲葉はそれに合わせて踊る。天上界でふたりの仲は知らぬものがいないほど、似合いの二人だった。
共に過ごすようになってから、一年がたったころ。
二人は獏の屋敷――夢幻の庭に向かった。
「ユズリハの樹はね、だいだい、先祖の力を受け継いでゆく意味の樹なの」
彼女は言う。
「私の子供も、そのまた子どもたちにも、私や先祖の加護がありますように・・・とね」
「そうか」
獏ははにかんだ。
自然に笑えるようになったのは、まぎれもなく彼女のおかげだ。
譲葉の肩を引き寄せ、
「・・・ならばここに、ユズリハを植えよう」
選んだのは獏の私室からいつでも見られる場所。現世から取り寄せた苗を二人で植えた。
夢などではないと、証明するように。
この木が枯れない限り、彼女との縁(えにし)は途切れないと。
――そう、信じたくて。
苗を植えながら、泥だらけの手がかさなった。
ぱちりと目が合い、ひゅっと呼吸がとまる。
「あ、あの・・・っ」
譲葉は、しどろもどろになりながら、ゆっくりと言った。
「獏。・・・わたし、を」
譲葉は日中、舞いの稽古に勤(いそ)しんでいる。
獏は木の枝に腰掛け、無関心を装いながら、それを目で追ってしまうのだ。
(私はなにをやっている・・・)
足元では、譲葉に下心を抱く男どもが鼻息荒く眺めていた。
普段なら、「くだらない」の一言ですます自分だったが、奴らの好奇の目に触れていると思うと、なぜか癇に障った。
木の上から音もなく飛び降りる。すると追っかけはぎょっと腰をぬかし、すごすごと退散していった。
・・・ふと、顔をあげると、譲葉と目が合った。
いつから気づいていたのか。彼女はこちらへ、にこりと笑い返した。
「う」
つい、目をそらしてしまった。・・・・・・重症だ。
(私はいつから、そんな暇人になった!)
獏はバカバカしい、とくだらない思考を切り捨てた。
糸もつながらない女人と接点を持って、なんの特がある。
しかし、心とは不思議なものだ。
禁じられれば、それだけ興味も増す。
獏は時間を見つけては、譲葉のもとへ通い詰めた。
やがて、譲葉にも、変化が見られ始めた。
獏が見当たらないと不安げに目をさまよわせ、見つけると蕾がほころぶように笑うのだ。
ふたりが惹かれ合うのに、時間はかからなかった。
獏は琴を奏で、譲葉はそれに合わせて踊る。天上界でふたりの仲は知らぬものがいないほど、似合いの二人だった。
共に過ごすようになってから、一年がたったころ。
二人は獏の屋敷――夢幻の庭に向かった。
「ユズリハの樹はね、だいだい、先祖の力を受け継いでゆく意味の樹なの」
彼女は言う。
「私の子供も、そのまた子どもたちにも、私や先祖の加護がありますように・・・とね」
「そうか」
獏ははにかんだ。
自然に笑えるようになったのは、まぎれもなく彼女のおかげだ。
譲葉の肩を引き寄せ、
「・・・ならばここに、ユズリハを植えよう」
選んだのは獏の私室からいつでも見られる場所。現世から取り寄せた苗を二人で植えた。
夢などではないと、証明するように。
この木が枯れない限り、彼女との縁(えにし)は途切れないと。
――そう、信じたくて。
苗を植えながら、泥だらけの手がかさなった。
ぱちりと目が合い、ひゅっと呼吸がとまる。
「あ、あの・・・っ」
譲葉は、しどろもどろになりながら、ゆっくりと言った。
「獏。・・・わたし、を」