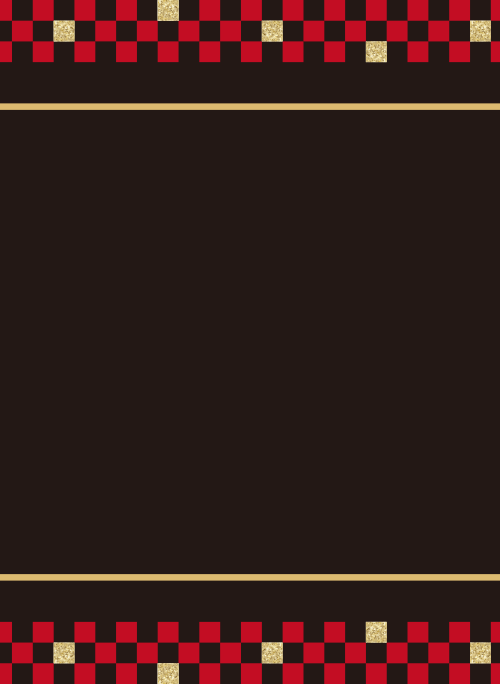ここは娘にあてがった部屋だ。
看病をしながら居眠りをし、懐かしい夢を見てしまったらしい。
上半身だけ預けていた寝台からむくりと起きる。
譲葉の孫娘は、以前より息遣いは落ち着いているが、変わらず高熱が続いていた。
「譲葉の孫、か・・・」
まご。つまり、子供を生んだということ。
五十年たった今となっては、終わったことだが。新たに突きつけられた真実に、ささやかな動揺をしていた。
――心の片隅に譲葉はいて、一日たりとも忘れたことはなかったから。
「う・・・」
ふと、寝台からかすかな吐息の気配がした。譲葉の孫娘が、目を覚ましたのだ。
つとめて、冷静な声で、男は言った。
「目覚めたか。医者の話では、峠は超えたそうだ。・・・水は、いるか?」
娘はうつろな視線を獏へ投げ、こくん、とうなずいた。その仕草でさえ、血筋を感じて胸がきしんだ。
起き上がろうともがき、しかしまだ手足に力がはいらないらしい。
(無理もない。一週間以上眠っていたのだから)
獏は極力、肌に触れないよう、慎重にその背を支えた。触れてしまえば、タガが外れる気がしたのだ。
出逢ってすぐの夜には、もう、もどれない。
娘は支えられながらようやく座ると、ごくごくと水を飲み干した。
「医者を呼んでくる。それまでまだ眠っているといい」
ふたたび横たえられ、娘は不安げな瞳で獏を見上げる。うるんだ瞳は、行かないでと言っているようだった。・・・勘違いかもしれないが。
できればこの場を離れたい。しかし良心が痛んだ獏は、侍女に仙人を呼びに行くよう命じた。
「・・・・・・・・・ばく、さま」
「どうした?」
娘はおぼつかない手つきで、獏の手をさがす。
「――・・・」
本来であれば、これは良くない。自分は、かつて娘の祖母と恋仲だった男だ。譲葉と血がつながっているとわかった以上、なおのこと適切な距離をとるべきだろう。
だが、娘はそれを許してくれなかった。
「手を、にぎってください」
(ひとの気も知らないで)
可愛らしい願い。獏は毒づく。
誰かに甘えることははじめてなのかもしれない。・・・無下にするのは薄情な気がする。
獏は袖をのばし、できるだけ肌に触れないようにすると、娘の小さな手を極力意識しないように努めた。
「あたたかい」
娘は、急に顔を寄せてきた。思わずびくりと体が震えた。運良く、寝ぼけた彼女には悟られなかったようだ。
看病をしながら居眠りをし、懐かしい夢を見てしまったらしい。
上半身だけ預けていた寝台からむくりと起きる。
譲葉の孫娘は、以前より息遣いは落ち着いているが、変わらず高熱が続いていた。
「譲葉の孫、か・・・」
まご。つまり、子供を生んだということ。
五十年たった今となっては、終わったことだが。新たに突きつけられた真実に、ささやかな動揺をしていた。
――心の片隅に譲葉はいて、一日たりとも忘れたことはなかったから。
「う・・・」
ふと、寝台からかすかな吐息の気配がした。譲葉の孫娘が、目を覚ましたのだ。
つとめて、冷静な声で、男は言った。
「目覚めたか。医者の話では、峠は超えたそうだ。・・・水は、いるか?」
娘はうつろな視線を獏へ投げ、こくん、とうなずいた。その仕草でさえ、血筋を感じて胸がきしんだ。
起き上がろうともがき、しかしまだ手足に力がはいらないらしい。
(無理もない。一週間以上眠っていたのだから)
獏は極力、肌に触れないよう、慎重にその背を支えた。触れてしまえば、タガが外れる気がしたのだ。
出逢ってすぐの夜には、もう、もどれない。
娘は支えられながらようやく座ると、ごくごくと水を飲み干した。
「医者を呼んでくる。それまでまだ眠っているといい」
ふたたび横たえられ、娘は不安げな瞳で獏を見上げる。うるんだ瞳は、行かないでと言っているようだった。・・・勘違いかもしれないが。
できればこの場を離れたい。しかし良心が痛んだ獏は、侍女に仙人を呼びに行くよう命じた。
「・・・・・・・・・ばく、さま」
「どうした?」
娘はおぼつかない手つきで、獏の手をさがす。
「――・・・」
本来であれば、これは良くない。自分は、かつて娘の祖母と恋仲だった男だ。譲葉と血がつながっているとわかった以上、なおのこと適切な距離をとるべきだろう。
だが、娘はそれを許してくれなかった。
「手を、にぎってください」
(ひとの気も知らないで)
可愛らしい願い。獏は毒づく。
誰かに甘えることははじめてなのかもしれない。・・・無下にするのは薄情な気がする。
獏は袖をのばし、できるだけ肌に触れないようにすると、娘の小さな手を極力意識しないように努めた。
「あたたかい」
娘は、急に顔を寄せてきた。思わずびくりと体が震えた。運良く、寝ぼけた彼女には悟られなかったようだ。